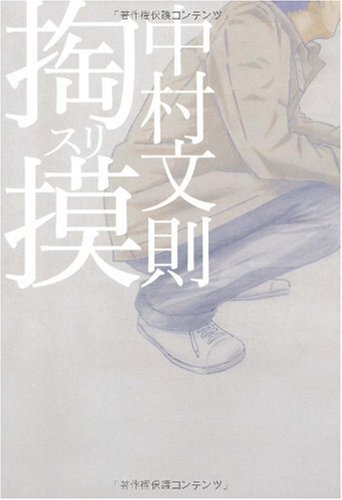
著者の「教団X」は衝撃的な作品だった。私は「教団X」によって著者に興味を持ち、本書を手に取った。
本書は欧米でも翻訳され、著者の文名を大いに高めた一冊だという。
「掏摸」とはスリのこと。いかに相手に気づかれずサイフの中の金品を掏り取るか。数ある罪の中でも手先の器用さが求められる犯罪。それがスリだ。
もし犯罪を芸術になぞらえる事が許されるなら、スリは犯罪の中でも詐欺と並んで芸術の要素が濃厚だと思う。
スリは空き巣に近いと考えることもできるが、空き巣は大抵の場合、場所の条件によって成否が大きく左右される。
さらに、持ち主が被害に気づきやすい。大事になる。
ところが手練れのスリになれば、移動の合間にサイフの中身を抜き取り、持ち主が気づかぬうちに元の場所に戻すこともできる。
相手に盗まれたことすら気づかれぬうちに財布を戻し、しかもサイフの中の全ての金品を奪わずに、少しだけ残しておく。
そうすることで、極端な場合、移動を繰り返す被害者が、移動中のどこかで落としたぐらいにしか思わないことさえある。
被害者に犯罪にあったことさえ気づかせない犯罪こそ、完全犯罪といえるだろう。
そこには、本来、悪が持っている、やむにやまれぬ衝動ではなく、より高尚な何かがある。
それこそが他の犯罪に比べスリを芸術となぞらえた理由だ。
スリ師の一連の手順には、手練れになるまでの本人なりの哲学さえ露になる。
スリを行う上で、何に気をつけ、どういう動機で行うか。それはスリではないとわからないことだ。
むしろ、生き方そのものがスリとなっているのだろう。
だからこそ、著者はスリを取り上げたのだろう。
スリの生態や動機を知らべ、その生きざまを主人公の行動を通して明らかにし、文学として昇華させようとしたのだろう。
本書に描かれたさまざまなスリの生態。それはスリの営みが犯罪である事を踏まえても、犯罪として片付けるだけでは済まない人としての営みの本質が内包されているようにすら思える。
ただし、スリはあくまでも犯罪だ。スリを礼賛することが著者の狙いではない。
スリとはすなわち手口でしかない、いうなれば小手先の芸術。
そこには、何か作家の琴線に触れる職人的な魅力が備わっているのだろう。
本書には主人公の生き方を否定するかのような、さらに本格的な悪が登場する。
その悪の前には主人公の罪など、しょせん生きるためのアリバイに過ぎないとさえ思える。
思うに著者は、悪の本質を描くため、より軽微なスリという犯罪から描きたかったのではないか
著者は本書で悪の本質を追求したかったのだろう。
それを著者は本書に登場する絶対的な悪、つまり木崎の存在として読者に提示される。
絶対的な悪を体現した人物、木崎は、相手に対する一切の忖度をかけない。
そればかりか、主人公を否定すらしない。ただのモノとして、道具として扱う。
木崎の絶対的な悪に対し、主人公には甘さがある。
万引を繰り返す母子に同情をかける主人公。
子供は親の万引の片棒を担がせられている。そして、母はつぎつぎと男を引っ張り込む売春婦だ。
主人公は、彼らの万引の現場に居合わせる。そして彼らの手口が店側にばれていること。次に同じ現場で犯行を行うと、捕まることを母子に忠告する。
そのような主人公の同情を察し、子は主人公のもとに転がり込む。自らの境遇に嫌気がさして。
誰にとっても、人生とはつらく苦しいものだ。
ところが親にとって道具とされる子にとっては、辛い以前に人生とは万引そのものでしかない。何も将来が見えず、何の希望も知らない日々。
主人公のように、スリという犯罪を芸術として楽しむ余裕や視野すらない。より、憐れむべき存在。
だから主人公は子に同情する。そして憐れむ。
ところが絶対的な悪木崎にとっては、主人公が子にかける同情は一片の値打ちすらない。それどころか相手を意のままに操る弱みとして映る。
主人公は母子を人質にされ、木崎の命に従うことを強いられる。
主人公は木崎からスリを要求される。その難易度の高い手口とスリリングな描写は本書のクライマックスでもある。
主人公はどうやって不可能にも思えるスリを成し遂げるのか。
その部分はエンターテインメントに似た読み応えがあって面白い。
だが、本書には別の読みどころもある。それは絶対的な悪、木崎その人が悪の本質を語る場面だ。
「お前がもし悪に染まりたいなら、善を絶対に忘れないことだ。悶え苦しむ女を見ながら、笑うのではつまらない。悶え苦しむ女を見ながら、気の毒に思い、可哀そうに思い、彼女の苦しみや彼女を育てた親などにまで想像力を働かせ、同情の涙を流しながら、もっと苦痛を与えるんだ。」(119ページ)
「俺は人間を無残に殺したすぐ後に、昇ってくる朝日を美しいと思い、その辺の子供の笑顔を見て、なんて可愛いんだと思える。それが孤児なら援助するだろうし、突然殺すこともあるだろう。可哀そうにと思いながら!」(119ページ)
木崎によれば、この世とは「上位にいる人間の些細なことが、下位の人間の致命傷になる。世界の構造だ。」(140ページ)
その考えをつきつめると、最大の悪に行き着く。悪とは人の人生を完全に操ることだと木崎は語る。
木崎は、ある男の一生を例に挙げる。人生のすべての運命や出会いを知らぬ間に操られ続けた男。懸命に生きてきたと本人は信じているのに、すべての幸運も不幸も、出会いや別れさえもすべて上位のある存在にお膳立てされていたことにすぎなかった。それを知った時の男の絶望。
悪とは何をさすのか。
それは他人の人生への介入であり、支配ではないだろうか。
木崎の哲学はそこに行き着く。
自らを上位に立つ人間として位置づけ、絶対的な悪への信念にもとづき、他人を自らを支配する。
木崎の行動の動機はそこにある。その支配がさらに自らを上位に押し上げ、より純粋な悪へと昇華させる。
われわれ小市民が考える悪とは、自分自身を少しでも楽にするための営みに過ぎない。
木崎の考える悪とは、さらに他人の支配も絡める。例えば相手の体を傷つけたり、相手の金品を盗んだり、相手の生命を奪うといった。それこそが悪の一面だが、ただし、それを自覚的に行うのと自分の中の止まない衝動に操られて行うのでは悪の意味が違ってくる。
木崎は自分の信念に基づき、自覚して悪を行使する。だからこそ彼は悪の絶対的な体現者なのだ。
それに比べると、主人公は母子に対し善意の介入を行う。それは善に属する。
そこが主人公が営む悪、すなわちスリと木崎の考える悪の間にある絶対的な差なのだろう。
スリという営みからここまで悪の輪郭を描き出す本書。
私たちの普段の生き方を考える上でも悪は避けては通れない。
味わい深い一冊だ。
‘2019/6/9-2019/6/12

