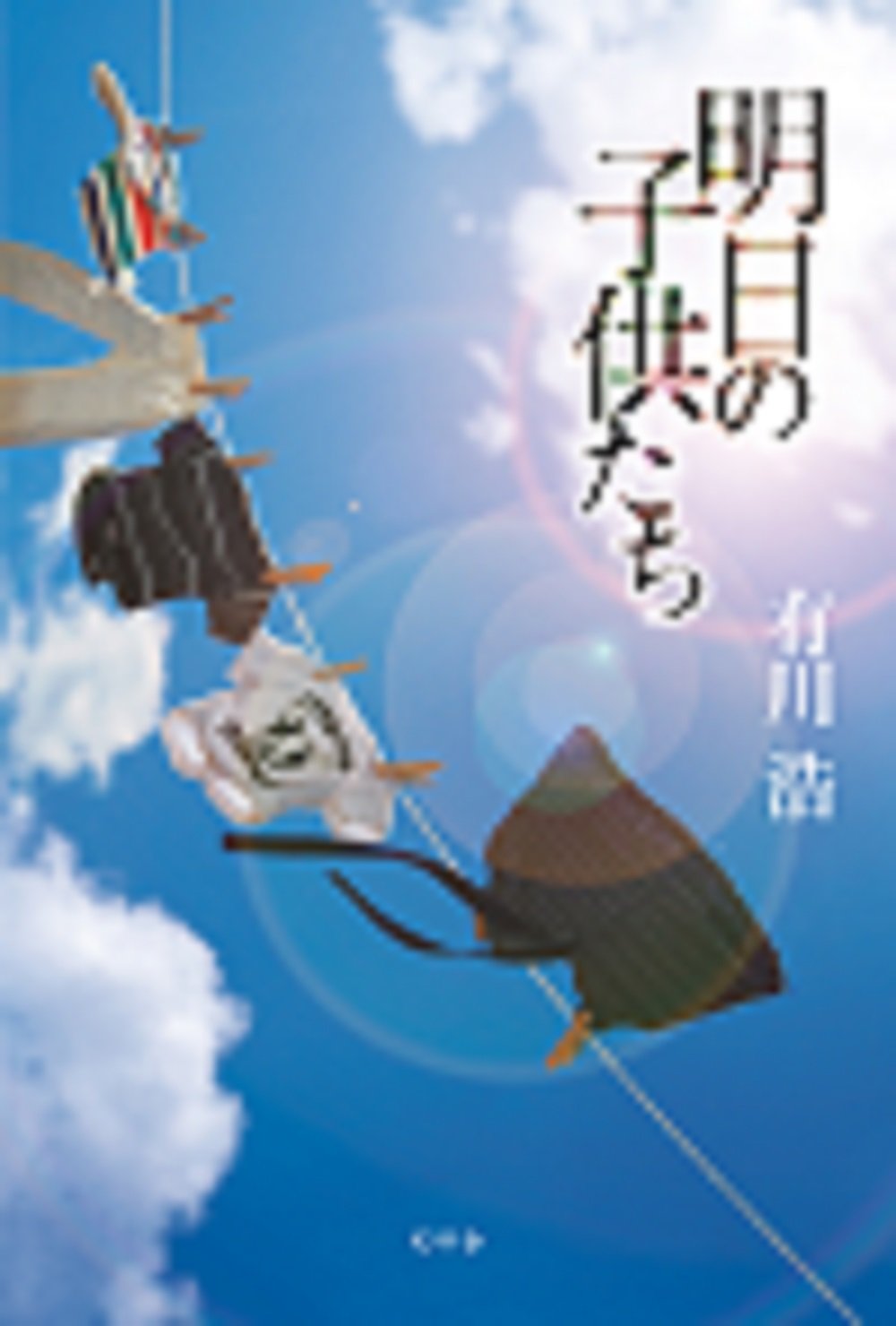
著者は、執筆スタイルが面白い作家だと思う。
高知県庁の観光政策を描いた『県庁おもてなし課』や、航空自衛隊の広報の一日を描いた『空飛ぶ広報室』などは、小説でありながら特定の組織を紹介し、広く報じることに成功している。
そのアプローチはとても面白いし、読んでいるだけで該当する組織に対して親しみが湧く。そのため、自らを紹介したい組織、出版社、作家にとっての三方良しが実現できている。
本書もその流れを踏まえているはずだ。
ある先見の明を持つ現場の方が、広報を兼ねた小説が書ける著者の異能を知り、著者に現場の問題点を広く知らしめて欲しいと依頼を出した。
私が想像する本書の成り立ちはこのような感じだ。
というのも、本書で扱っているのは児童養護施設だ。
児童養護施設のことを私たちはあまりにも知らない。
そこに入所している子供たちを孤児と思ってしまったり、親が仕事でいない間、子供を預かる学童保育と間違ったり、人によってさまざまな誤解を感じる人もいるはずだ。
その誤解を解き、より人々に理解を深めてもらう。本書はそうしたいきさつから書かれたのではないかと思う。
私は、娘たちを学童保育に預けていたし、保護者会の役員にもなったことがある。そのため、学童保育についてはある程度のことはわかるつもりだ。
だが、親が育児放棄し、暴力を振るうような家族が私の身の回りにおらず、孤児院と児童養護施設の違いがわかっていなかった。本書からはさまざまなことを教わった。
甘木市と言う架空の市にある施設「あしたの家」には、さまざまな事情で親と一緒に住めない子供たちが一つ屋根の下で暮らしている。
本書の主人公は一般企業の営業から転職してきた三田村だ。彼より少し先輩の和泉、ベテランの猪俣を中心とし、副施設長の梨田、施設長の福原とともに「あしたの家」の運営を担っている。
「あしたの家」の子供たちは、普段は学校に通う。そして学校から帰ってきた後は、夕食や宿泊を含めた日々の生活を全て「あしたの家」で過ごす。
職員は施設を運営し、子供たちの面倒を見る。
ところが、子供たちの年齢層は小学生から高校生まで幅広い。そうした子供たちが集団で生活する以上、問題は発生する。
職員ができることにも限界があるので、高校生が年少者の面倒を見るなどしてお互いに助け合う体制ができている。
五章に分かれた本書のそれぞれでは、子供たちと職員の苦労と施設の実態が描かれる。
「1、明日の子供たち」
施設に行ったことのない私たちは、無意識に思ってしまわないだろうか。施設の子供のことを「かわいそうな子供」と。
親に見捨てられた子とみなして同情するのは、言う側にとっては全く悪気がない。むしろ善意からの思いであることがほとんどだ。
だが、その言葉は言われた側からすると、とても傷つく。
施設を知らず、施設にいる子供たちのことを本気で考えたことのない私たちは、考えなしにそうした言葉を口にしてしまう。
三田村もまた、そうした言葉を口にしたことで谷村奏子に避けられてしまう。
高校二年生で、施設歴も長い奏子は、世の中についての知識も少しずつ学んでいるとはいえ、そうした同情にとても敏感だ。
「2、迷い道の季節」
施設の子供達が通っているのは普通の公立の小中高だ。
私も公立の小中高に通っていた。もっとも、私はボーッとしていた子供だったので、そうした問題には鈍感だったと思う。だから、周りの友達や他のクラスメイトで親がいなくて施設に通って子のことなど、あまり意識していなかった。
ところが、本書を読んでいると、そうした事情を級友に言いたくない子供たちの気持ちも理解できる。
ひょっとすると、私の友人の中にも言わないだけで施設から通っている子もいたのかもしれない。
本書に登場する奏子の親友の杏里は、かたくなに施設のことを誰にも告げようとしない。
施設の子供が自らの事情を恥じ、施設から通っていることに口を閉ざさせる偏見。私はそうした偏見を持っていないつもりだし、娘たちに偏見を助長するようなことは教えてこなかったと思う。
だが、本当に思い込みを持っていないか、今一度自分に問うてみなければと思った。
「3、昨日を悔やむ」
高校を出た後すぐに大学に進んだ私。両親に感謝するのはもちろんだ。
だが、進学を考えることすら許されない施設の子供たちを慮る視点は今まで持っていなかった。
そもそも、育児放棄された子供たちの学費はどこから出ているのか。
高校までは公的機関からの支援がある。とはいえ、大学以降の進学には多額の学費がいる。奨学金が受給できなければ大学への進学など不可能のはずだ。
だから、「あしたの家」の職員も施設の子供達を進学させることに消極的だ。
進学しても学費が尽きれば、中退する以外の選択肢はなくなる。それが中退という挫折となり、かえって子供を傷つける。だから、高校を卒業した後すぐに就職させようとする。
猪俣がまさにそうした考えの持ち主だ。
でも、生徒たちにとってみれば、それはせっかく芽生えた向学心の芽が摘まれることに等しい。和泉はなんとか進学をさせたいと願うが、仕事を教えてくれた猪俣との間にある意見の相違が埋まりそうにない。
「4、帰れる場所」
施設にいられるのは高校生までだ。その後は施設を出なければならない。高校生までは生活ができるが、施設を出たら自立が求められる。世の中をたった一人で。
それがどれだけ大変なのかは、自分の若い頃を思い出してみてもよくわかる。
サロン・ド・日だまりは、そうした子供の居場所として設立された。卒業した子供たちだけでなく、今施設にいる子供たちも大人もボーッとできる場所。
ここを運営している真山は、そうした場所を作りたくて日だまりを作った。仕事や地位を投げ打って。
その思いは崇高だが、実際の運営は資金的にも大変であるはずだ。
こうした施設を運営しようとする人柄や思いには尊敬の念しかない。本書に登場する真山は無私の心を持った人物として描かれる。
ところが、その施設への公的資金の支出が打ち切られるかもしれない事態が生じる。
その原因が、「あしたの家」の副施設長の梨田によるから穏やかではない。梨田は公聴会で不要論をぶちあげ、施設の子供達にも行くなと禁じている。
子供達の理想と大人の思惑がぶつかる。理想と現実が角を突き合わせる。
そこに三田村が思いを寄せる和泉がかつて思いを寄せていた度会がからんでくる。
著者が得意とする恋愛模様も混ぜながら、本書は最終章へと。
「5、明日の大人たち」
こどもフェスティバルは、施設のことを地域の人たちや行政、または政治家へ訴える格好の場だ。
そこで施設の入所者を代表して奏子が話す。本書のクライマックスだ。
さらに本書の最後には奏子から著者へ、私たちのことを小説に書いて欲しいと訴える手紙の内容が掲載されている。
最後になって本書は急にメタ構造を備え始める。小説の登場人物が作者へ手紙を書く。面白い。
本稿の冒頭にも書いたとおり、著者がそうした広報を請け負って小説にしていること。そのあり方を逆手にとって、このような仕掛けを登場させるのも本書の面白さだ。
本書の末尾には、本書の取材協力として
社会福祉法人 神戸婦人同情会 子供の家
そして、本文に登場する手紙の文面協力として、
笹谷実咲さんの名前が出てくる。
人々の無理解や偏見と対し、施設の実情や運営の大変さを人々に伝えるなど、本書の果たす役割は大きい。
通常のジャーナリズムでは伝えられないことを著者はこれからもわかりやすく伝え続けて欲しいと思う。
‘2019/12/20-2019/12/20

