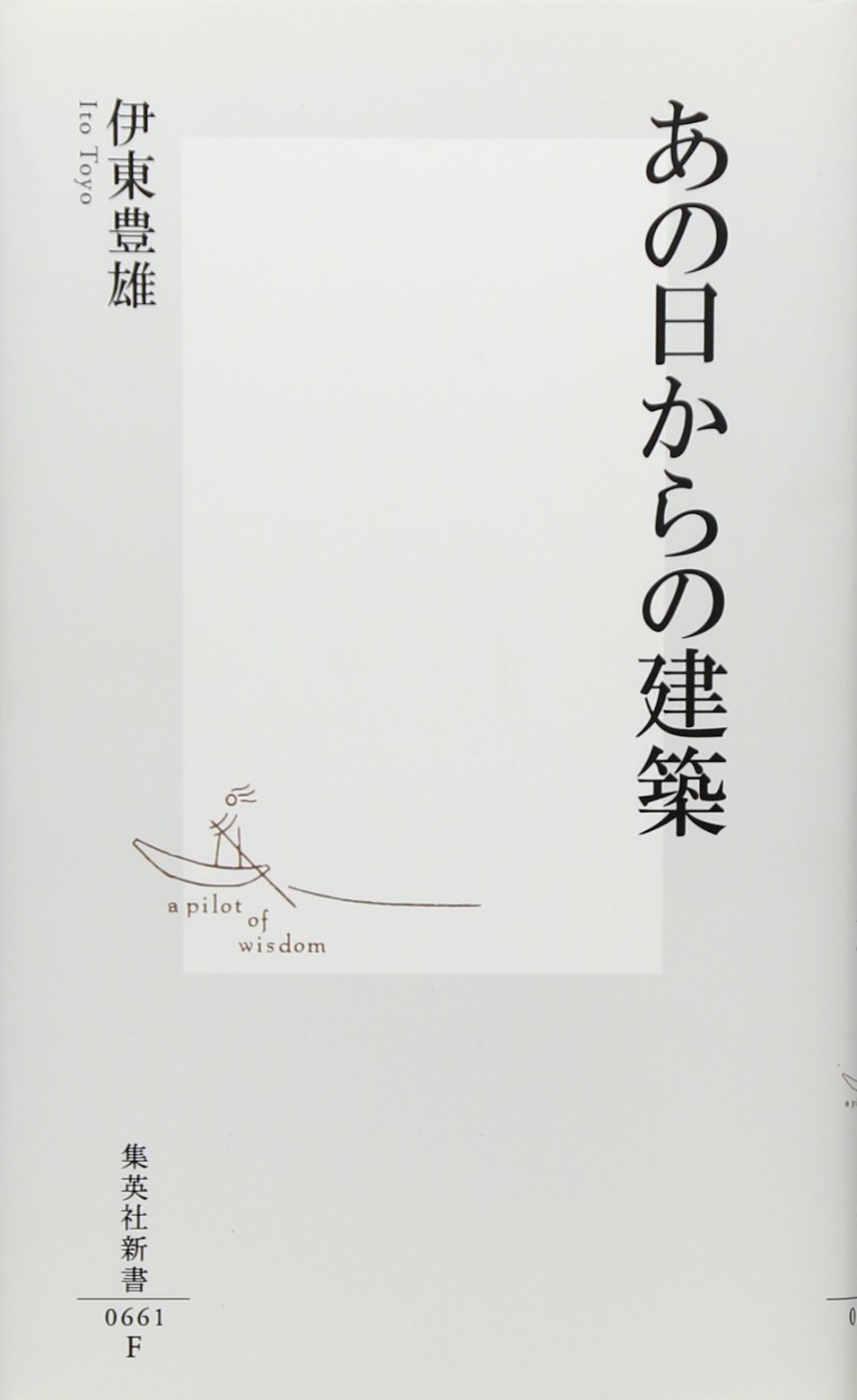
本書もまた、『建物と日本人 移ろいゆく物語』に続いて建築という営みに興味を持って読んだ一冊だ。
丹下健三氏の自伝を読もうと図書館を探したが、見当たらなかったので本書を手に取った。
著者の名前は、建築関連の文章を読むと時折目にしていた。建築界では著名な方に違いない。だから、建築とは何かを知るにはふさわしいと思った。
本書のタイトルにもある「あの日」とは3.11を指す。すなわち東日本大震災。
建築家にとって地震とは己の腕を試される試練だ。
想定した耐震設計が揺れに耐えられなければ建造物は倒壊する。揺れに耐えても津波などが次々と押し寄せる。
倒壊した場合、己の技術の未熟さがさらされる。一方で、災害に耐え抜いた姿が賞賛をもたらすこともある。
著者が手掛けたせんだいメディアテークは、東日本大震災においてわずかな損害を受けただけだったようだ。
著者は東日本大震災を機に建築のあり方や、建築家としての生き方を見直したという。
「日本の社会で、建築家は本当に必要とされているのか」(27P)。
このように自らを省みた著者は、釜石で復興支援プロジェクトに携わる。
建築家はただ建物を設計するだけでよいのか。その問いは建築家である自らの存在意義を揺るがす。
津波で街全体が更地となり、街を一から再構築する必要が生じた際、建物一つを設計すればよいだけの建築家に居場所はあるのだろうか。
そもそも建築とはそこに住まい、通う人々があって成り立つはず。
であれば、街の人々が復興にどう取り組み、それにどう建築家として関与するのかを問わねばなるまい。
設計する。作る。そして住まう。この建築に関わる三つの工程が終われば設計者が関与する余地はなくなる。
つまりその建物がどのように街の中で息づき、活用されるかを設計者が点検する機会がなくなるのだ。
地震によってあらわになった建築家の存在意義。著者の危機意識はそこに発している。
著者は仙台市宮城野区の「みんなの家」にも関わる。
震災後の仮設住宅は行政によって用意された。だが、住民が交流する場所や心を落ち着ける場がない。「みんなの家」はその要望に応じたものだ。
著者は「みんなの家」で住む人と作り手の交流を体感し、建築家としてのこれからのあり方をとらえたことに心を動かされる。
著者はその反省を生かして「伊東建築塾」という私塾を立ち上げる。建築を一般の市民にも開かれたものにしようとする試みだ。
建築家とは現実の社会から遊離しているのではないか、という著者の真摯な反省。その答えがこの私塾として結実する。
本書に満ちているのは、著者の自らへの問いかけや反省だ。
コンセプトがありきで建てられた建築物は、現実に住む人々のことを本当に考えた設計になっているのか。
これは『建物と日本人 移ろいゆく物語』のレビューにも書いたが、私を含めたわが国の人々が建築物に無関心な理由の一つであるに違いない。
続いて著者は、自らの建築家としての歩みを振り返る。
最初は一般の住宅を手掛け、そして徐々に公共の大きな建物へとステップアップした著者。
だが、著者は自らの歩みを振り返り、自らのキャリアに飽き足らない思いを抱く。
著者の歩みは、建築家として一般的なものだろうか。門外漢の私にはよくわからない。
当然ながら、その時々に手掛けた仕事は、その時々の精一杯の力を出しているはずだ。だが、後から思い返すと反省ばかりが目につく。それは私にも理解出来る。
むしろ、著者は、成長してきた自分を見つめなおしたからこそ、この流れの先にさらなる高みを見いだしたのだと思う。
まず社会に飛び込み、その中で苦しんで設計を作り上げるスタイル。それこそが自らのスタイルだったことに気づく。
そのスタイルをベースにし、今の時点で達したレベルとこれからの向上への伸びしろを考える。
そこから導き出された考えとは、その時々のレベルや流行に一喜一憂しないというものだ。
自らの建築家としての意識がどう変わってきたかを、過去を読み解きながら理解する。
社会に飛び込み、その中で住まい方や社会の要請と葛藤する。その姿勢がぶれない限り、今後の成長も見込める。そして、建築家が社会に対してどうやって貢献出来るかの答えが見つかる。
著者はそのような考えにたどり着いた。
著者は公共建築の権威性を壊したいという。
私に限らず、一般の人々が建築に興味を持たない理由。それは、近年、急激に増えた建造物のほとんどが、似たり寄ったりの外観だからではないか。
建築の妙味を知ろうと思えば寺社仏閣などの歴史的建造物か、近代ならばシンボルとなり得る大掛かりな建物しかない。
公共建築である以上、機能が優先される。そこに権威性の衣をまとわせようとしたとき、機能が足かせとなって似たようなデザインに落ち着いてしまう。
機能とはつまり、建築物をどう使うかという機能設計だ。
機能設計については建築家が入り込む余地がない。
コンセプトがありきで建てられた建築物は、現実に住む人々のことを本当に考えた設計になっているのか。この著者の問いがまさに矛盾となってあらわれたのが公共建築だ。
そうした矛盾を著者は権威そのものと受け取った。著者が壊したい権威性とはこのことだろう。
秩序の象徴としてではなく、建築物に違う意図を持たせられないか。
著者はそこで建築の秩序を自然の秩序で置き換える試みを行う。
自然の秩序には直線はない。曲線が主だ。
そこに著者は建築家としての突破口を見いだす。
自然の秩序を建築物で表すには、建築の内部環境を外部環境に近づければよいのではないか。著者はそう考える。
また、著者の公共建築の権威性とは、建築物に対する批評性が社会から遊離したことに問題の根本がある。そう著者は述べている。
著者にとって建築の外観と機能が乖離している問題。それは、建築そのもののあり方に加え、建築の本質が社会の内と外で隔てられていることにあるということだろう。
それは著者が3.11で学んだことにも通じる。地震と津波が建築の内と外を心理的にも物理的にも壊してしまった。
それを再構築する上で、建築を外から区切るものではなく、内と外をつなげられないか。その主張こそが本書の核心だと思う。
今まで触れてこなかった建築家の主張。それを本書で知ったことで、私にとっても建築物を見る目がさらに磨かれた気がする。旅先などで建築の粋を見て回りたい。
‘2019/9/27-2019/9/28

