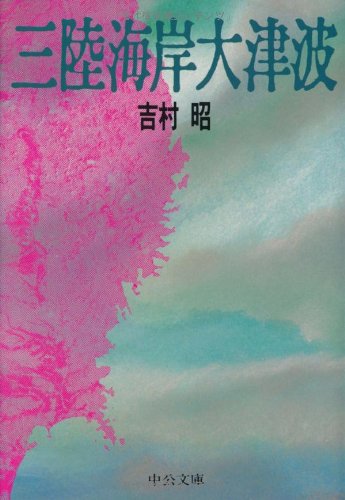
3.11の津波は、日本人に津波の恐ろしさをあまねく知らしめた。ネット上に投稿された数々の津波動画によって。
私自身、それらの動画をみるまでは津波とは文字どおり巨大な波だと勘違いしていた。嬉々としたサーファーたちがパドリングして向かう巨大なパイプラインを指すのだと。しかし3.11で沿岸を襲った津波とは、海が底上げされる津波だ。見るからに狂暴な、ロールを巻いた波ではない。海上は一見すると穏やか。だが、実はもっとも危険なのはこのような津波なのかもしれない。
本書は、3.11が起きるまでに、三陸海岸を襲った代表的な津波三つを取り上げている。すなわち明治29年(1894年)の明治三陸地震の津波、昭和8年(1933年)の昭和三陸地震の津波、最後に昭和35年(1960年)のチリ地震津波である。
著者の記録文学はとても好きだ。時の流れに埋もれそうなエピソードを丹念に拾い、歴史家ではなく小説家視点でわれわれ読者に分かりやすく届けてくれる。記録文学の役割が過小に評価されているように思うのは私だけではあるまい。
だが、著者の筆力をもっても、津波とは難しい題材ではなかったか。
なぜか。それは、時間と時刻だ。
時間とは、過ぎ去った時間のこと。本書が書かれたのは1970年だという。明治三陸津波からは76年の月日がたっている。もはや経験者が存命かどうかすら危ぶまれる年月だ。では、昭和三陸津波はどうだろう。こちらは被害に遭ってから38年。まだ体験談が期待できるはず。
だが、ここで時刻という壁が立ちはだかる。明治も昭和も地震発生時刻は夜中である。津波が三陸沿岸を総ざらいしたのは暗闇の中。つまり、目撃者からは行動の体験は引き出せても、視覚に映った記憶は期待できないのだ。
二階の屋根の向こうに波濤が見えた、海の底が引き潮で数百メートルも現れた、という目撃談は本書に載っている。だが、断片的で迫力にかける。そもそも夜分遅くに津波に襲われた被災者の方々が克明に状況を目撃しているほうがおかしいのだ。
被災者に立ちはだかるのは暗闇だけではない。津波とは一切を非情に流し去る。朝があたりを照らしても、元の風景を思い出すよすがは失われてどこにもない。そして、その思い出すらも時の経過が消し去って行く。荒れ狂う波が残した景色を前に、被災者はただ立ち竦むしかない。後世に残すに値する冷静緻密な絵や文章による描写を求めるのは被災者には酷な話だ。写真があればまだよい。だが、写真撮影すら一般的でない時代だ。
そんなわけで、著者の取材活動にも関わらず、本書は全般的に資料不足が否めない。でも著者は明治、昭和の津波体験者から可能な限り聞き取りを行っている。
視覚情報に期待できない以上、著者は他の感覚からの情報を集める。それが聴覚だ。本書には音についての情報が目立つ。地震発生時に二発響いたとされる砲声とも雷鳴とも聞こえる謎の音。海水が家屋を破壊する音や家にいて聞こえるはずのない水音。目には映らない津波の記憶も、耳の奥にはしっかりと残されている。そういった情報は聞き取りでも残された文献からも拾うことができる。
地震の記録としてよく知られるのは、宏観現象だ。宏観現象とは、前兆として現れた現象のことだ。本書は宏観現象も網羅している。
なかでも秀逸なのは、ヨダという東北弁の語彙の考察だ。ある人は揺れがないのに襲いかかる津波をヨダといい、ある人は揺れの後の津波をヨダという。著者が出した結論は後者である。その様な誤解が生じたのは、本書で三番目に取り上げるチリ地震津波の経験が影響しているのだろう。地球の裏側で起こった地震の津波が2日後に死者を出すほどの津波になるとは誰も思うまい。
そして、そういった波にも甚大な被害を受けること。それこそがリアス式地形を抱える三陸の宿命なのだろう。
だが、宿命を負っているにも関わらず、三陸の人々の全員に防災意識が備わっているかと言えばそうでもない。
著者の聞き取りは、三陸の人々が地震にたいして備えを怠っていたことを暴く。津波を過小評価し過去の地震の被害を軽くみた人や、誤った経験則を当てはめようとして逃げなかった人が津波にはやられている。
今の時代、昔から受け継がれてきた知恵が忘れられているのはよく言われる。しかし、昔の人たちも忘れることについては同じだったのかもしれない。
明治の地震でも更地と化した海沿いから、高台に家屋を移す試みはなされた。しかし、漁師は不便だからという理由でほどなく海沿いに転居する家が後を絶たなかったとか。そしてそれらの家は、後年、沿岸を襲った津波の被害に遭う。
結局、人とは喉元を過ぎれば熱さを忘れる生き物かもしれない。その意味でも著者の記録文学は残っていくべきなのである。
‘2016/6/29-2016/6/29

