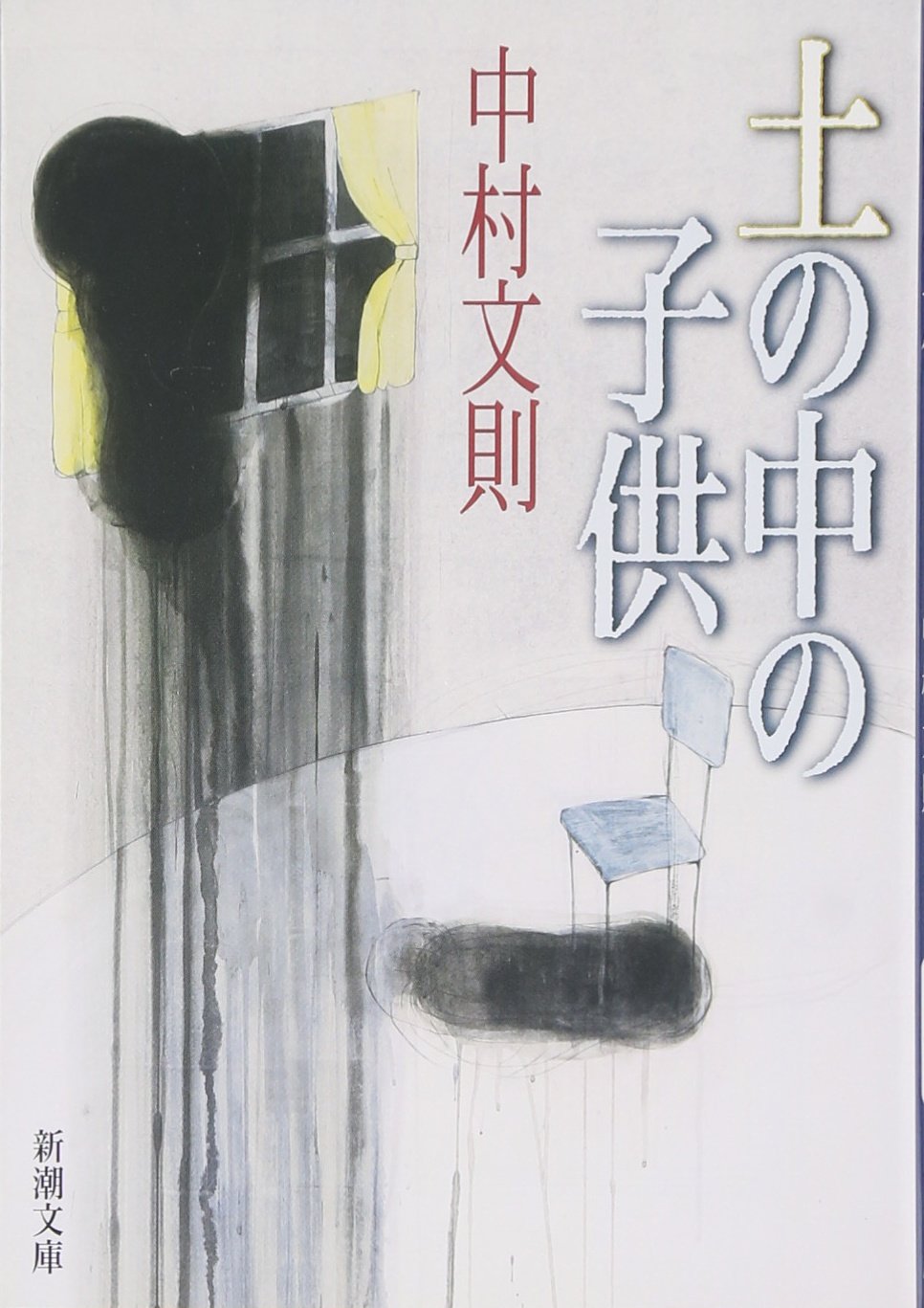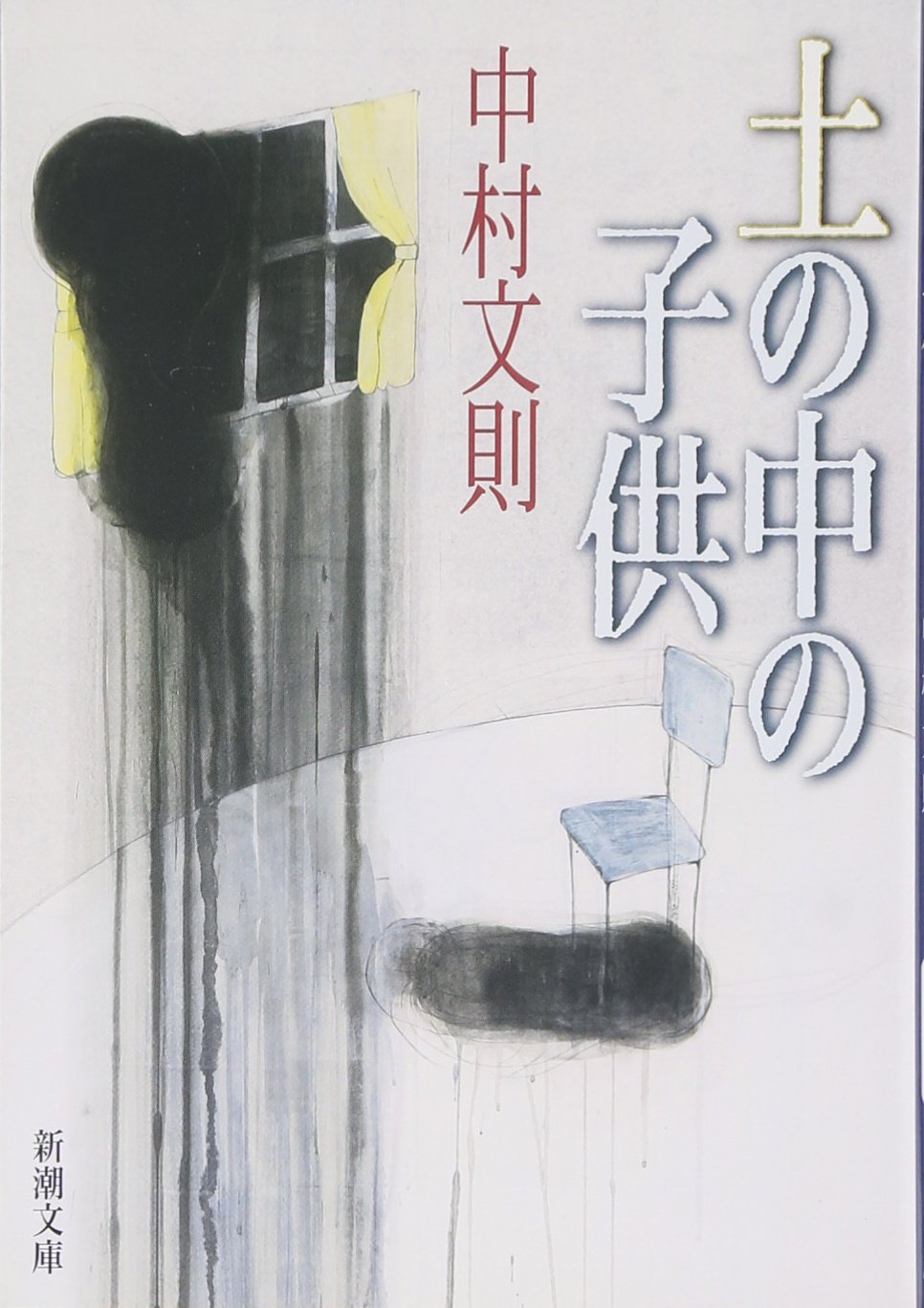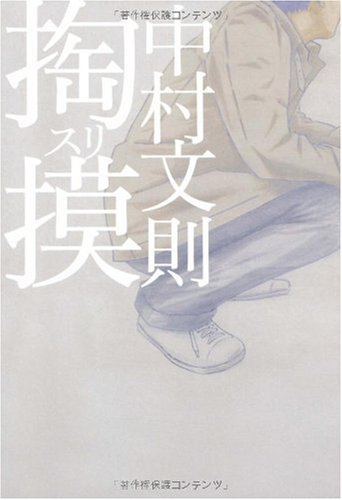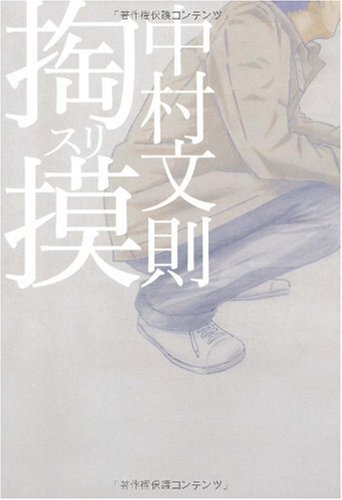著者による『教団X』は凄まじい作品だった。宗教や科学や哲学までを含めた深い考察に満ちており、読書の喜びと小説の妙味を感じさせてくれた。
本書はタイトルこそ『教団X』に似ているが、中身は大きく違っている。本書は政治や統治や支配の本質に切り込んでいる。
「朝、目が覚めると戦争が始まっていた。」で始まる本書は、近未来の仮想的な某国を舞台にしている。
本書は日本語で書かれており、セリフも日本語。そして登場人物の名前も日本人の名前だ。
それなのに本書の舞台は日本ではない。日本に限りなく近い設定だが、日本とは違う別の国「R帝国」についての小説だ。
本書を読み進めると、R帝国に隣り合う国が登場する。それらの国は、中国らしき国、北朝鮮らしき国、韓国らしき国、ロシアらしき国、アメリカらしき国を思わせる描写だ。
だが本書の中ではR帝国が日本ではないように、それらの国は違う名前に置き換えられている。Y宗国、W国、ヨマ教徒、C帝国といった具合に。
一方、本書内にはある小説が登場する。その小説に登場する国の名前は”日本”と示されているからややこしい。
その小説では、日本の沖縄戦が取り上げられている。
なぜ沖縄戦が起きたのか。それは当時の大本営の作戦指導によって、日本の敗戦を少しでも遅らせるための時間稼ぎとして、沖縄が選ばれたからだ。それによって多くの県民が犠牲となった。
沖縄県庁の機能は戦場での県政へと強いられ、全てが軍の指導の下に進められた。その描写を通し、著者は戦いにおいて民意を一切顧みずに戦争に人々を駆りる政治の本質に非道があることを訴えている。
作中の小説では日本を取り上げながら、本書には日本は登場せず、R帝国と呼ぶ仮の存在でしかない。
おそらく著者は、本書で非難する対象を日本であるとじかに示さないことによって、左右からの煩わしい批判をかわそうとしたのかもしれない。
政治やそれをつかさどる政府への著者の態度は不信に満ちている。もちろんそこに今の日本の政治が念頭にあることは言うまでもない。
著者の歴史観は明らかであり、その考えをR帝国として描いたのが本書であると思う。
本書には政府がたくらむ陰謀が横行している様子が書かれる。民が求める統治ではなく、政府の都合を実現するための陰謀に沿った統治。統治がそもそも民にとっては無意味であり、有害であることを訴えたいのだろう。
その考えの背後には、合法的な政権奪取までのプロセスの背後にジェノサイドの意図を隠し持っていたナチスドイツとそれを率いるヒトラーを想定しているはずだ。
こうした本書の背後の考えは普通、陰謀論と位置付けられるのだろう。
だが、私は歴史については、もはや陰謀があったかどうかを証明することが不可能だと思っている。そのため陰謀論にはあまり関わらず、あくまで想像力の楽しみの中で取り扱うように心がけている。
あると信じれば陰謀はあるのだろう。政府がより深い問題から目をそらさせるためにわざと陰謀論を黙認していると言われれば、そうかもしれないとも思う。
本書は、陰謀論を好む向きには好評だろう。だが、私のように陰謀論から一定の距離を置きたいと考える読者には、物足りなく思える。
少なくとも、私にとって著者の『教団X』に比べると本書は共感できなかった。
批判的に本書を読んだが、本書には良い点もある。全体よりもディテールで著者が語る部分に。
「歴史的に、全ての戦争は自衛のためという理由で行われている。小説『ナチ』のヒトラーですら、一連の侵略を自衛のためと言っている。もしあの戦争でナチが勝利していれば、歴史にはそう書かれただろう。
相手に先に攻撃させる。国民を開戦に納得させるための、現代戦争の鉄則の一つ。
あまりにも大胆なこういう行為は、逆に疑われない。なぜなら、まさか自分達の国が、そんなことをするとは思えないから。それを信じてしまえば、自分達の国が、いや、自分達が住むこの世界が、信じられなくなって不安だから。無意識のうちに、不安を消したい思いが人々の中に湧き上がる。その心理を“党“は利用する。
無意識下で動揺している人ほど、こういう「陰謀論」に感情的に反論する。そうやって自分の中の無意識の思いを抑圧し消そうとする。上から目線で大人風に反論し安心する人達もいる。そもそも歴史上、一点の汚点・悪もない先進国など存在しないから、国の行為全てを信じられること自体奇妙だがそういう人はいる。」(239ページ)
私も、ここに書かれた内容と同じ考えを持っている。
先進国のすべてに歴史上の悪行はあると考えているし、そのことに対して感情的に反応する人を見ると冷めた気分になる。
そもそも国とは本来、定義があいまいなものだ。集団が組織となり、それが集まって国となる。同じ民族・人種・言葉・文化を共通項として。国とはそれだけの存在にすぎない。
そのようなあいまいな国を存続させるには、民に対してもある幻想を与える必要がある。
その幻想を統治する根拠を文化や宗教や民族や経済や福祉といったものに置き、最大多数の最大幸福の原理を持ち出して全体の利益を奉る。
そのため、政府とは個人の自由を制限する装置として作動し、全体の利益を追求する。個人とは本質的に相いれない。
人は生きているだけで、他の人に影響を与える生き物だ。生きている以上、その宿命からは逃れようがない。生きているだけで環境は消費され、人口密度が増すのだから。
そうすると行き着くところは個人的な内面の自由だ。
とはいえ、私は陰謀論の信者になろうとは思わない。国による陰謀を信じようと信じまいと、現状は何も変わらないからだ。
自由意志を信じる私の考えでは、政府による統治や統治の介入をなくし、自分の生を全うするためには自分のスキルや考えを研ぎ澄ませていくしかない。
「僕は自分のままで、……自分の信念のままで、大切な記憶を抱えながら生涯を終えます。それが僕の……プライドです」
私は本書とそのように向き合った。
ところが、宗教は内面の自由までも支配下におこうとする。一人もしくは複数の神の下、崇高な目的との縛りで。
本書にもある教祖が登場する。その教義も列挙される。
おそらく、『教団X』にも書かれた宗教と科学の問題に人の抱える課題は集約されていくはずだ。だが、その日が来るのは永遠に近い日数がかかると思う。
「人間は結局素粒子の集合でできている。生物も結局は化学反応に過ぎないとすれば、この戦争も罰も、ただ人間にはそう見えるだけで、実は物理学的なしかるべき流れ、運動に過ぎないと言う風に。…その運動を俯瞰して眺める時、私はそこに、温度のない冷酷さしか感じない。見た目は激痛を伴う戦争であるのに、ただの無意味な素粒子達の流れ、運動である可能性が高いのだ。この奇妙な感覚に耐えるためかのようにね、私もどんどんと人間でなくなっていくように思うのだよ。もし私が戦争で莫大な数の人間を殺し、R帝国を破産させ、これまでの支配層の国々に飛び火させ、それで得た天文学的な資産で今度は貧国を助けるつもりだとしたらどうだ? 私がというより、何かの意志がそのつもりだったとすれば、結果的にお前は将来の善の実現を阻むことになる。」(362ページ)
あとがきに著者が書いているとおり、私たちが持つべき態度は「希望は捨てないように」に尽きる。
‘2020/08/16-2020/08/17