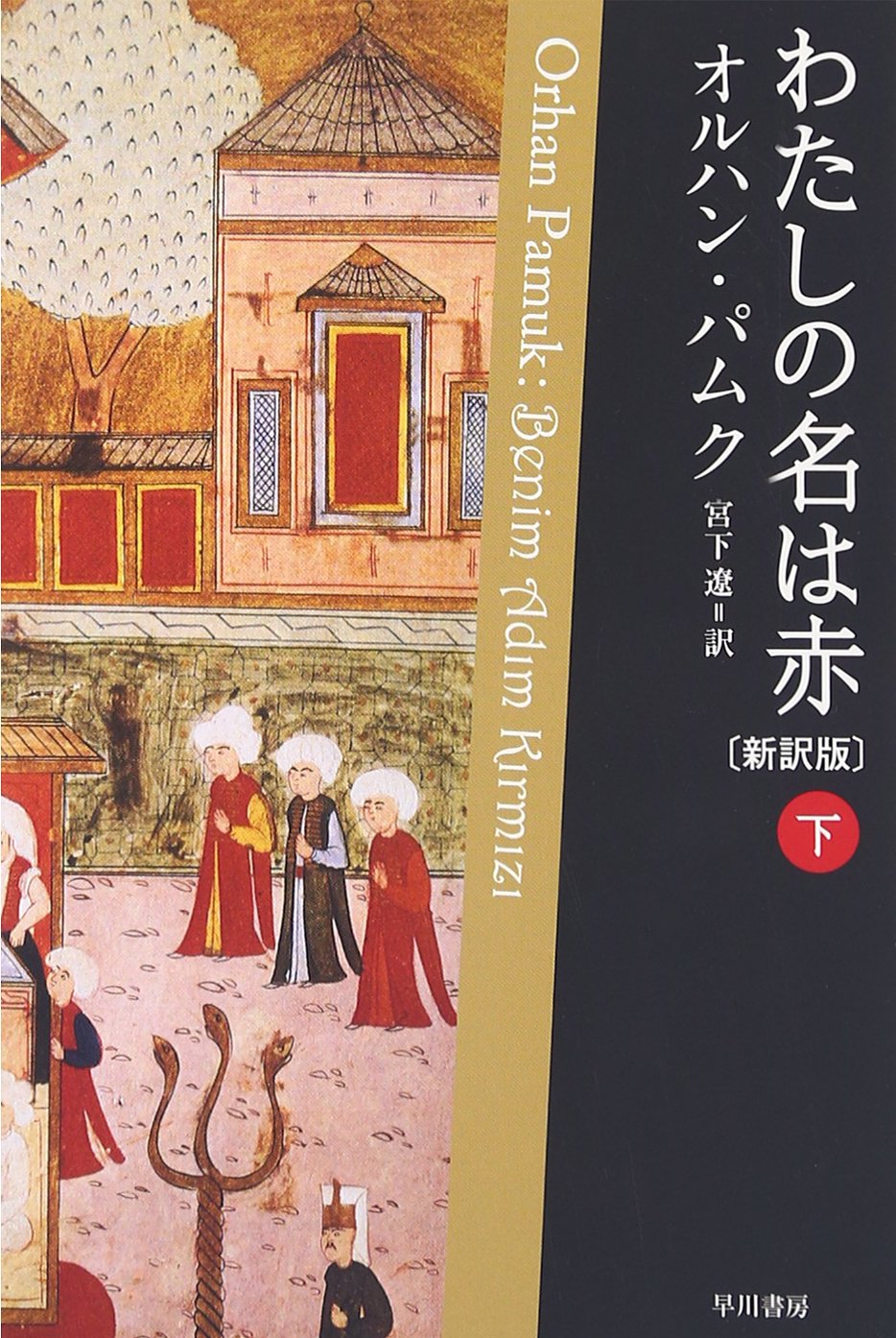
本書のすごさ。それは本書がイスラム文化に押し寄せる西洋文明の脅威、つまり、一つの文化の変動と新旧の世代が入れ替わる痛みを描きながら、それでいてエンターテインメントとしても一級であることだ。
本書は冒頭で細密画師の殺害は誰によるか、という謎を提示する。
通常のミステリーでは、その謎を捜査側から描く。それが常道だ。犯人は誰か、なぜ殺されたのか。ミステリーとは、そうした謎が解かれる過程を楽しむ小説のジャンルだ。
最後に意外な謎が明かされ、読者はそこである種の達成感を味わう。
それとは別に、犯人の側から犯罪を描く倒叙という形式もある。
犯人の視点から犯罪を描くことで、捜査の輪が狭まる様子とそれによって犯人の動きが変化する様子を味わう。
本書が面白いのは、捜査側の視点、犯罪者側の視点に加え、殺された側の殺される瞬間の視点まで描いていることだ。
今まで私は何百冊ものミステリー小説を読んできたが、こうした構成を目にしたのは本書が初めてだと思う。
殺される側の恐怖と理不尽さ。それは、殺人が行われる瞬間の事象をあまねく描くならば、描写の肝となるべきはず。ところが、今までのミステリーは、殺される側の感情の動きを本書ほどに踏み込んで書いていなかったように思う。おそらく、この点こそ、今までのミステリーが踏み込んで描いておくべきだったのかもしれない。
ましてや、本書においては殺される理由が犯行の動機や謎の根幹を占めている。そのため、本書が殺される際の描写もおろそかにせずに書いていることによって、物語の構造がさらに深みを帯びる。そして、本書のテーマがより読者に迫ってくる。
描写が必要なのは、罪を犯す殺人者の側にも当てはまる。
なぜ殺さなければならないのか。犯行を行うには切実な思いがあるはず。
その動機は、本書が掲げる大きなテーマである信仰の本質にも迫っている。
そもそも、イスラムの伝統に即した平面の細密画の視点を、なぜ西洋の遠近法に置き換える必要があるのか、と言う疑問。それは人によっては深刻な、信仰上の信念にも結びつく。そのあたりの動機について、イスラム文化に詳しくない私たちはなかなか理解が難しい。
その動機の深みは、捜査する側にとってはなおさら不可解だ。しょせん、犯罪者の思惑などわからないのだから。
西洋からの絵画技術が流入し、イスラムの伝統が脅かされている時。そのような時期に、信仰上の危機感は誰もが抱いていて不思議ではない。だからこそ、誰が下手人かはわかりにくい。
上巻のレビューに書いたように、本書は殺された側の思い、殺す側の言い分を描写するだけでない。本書は人ではないものの視点からも語られる。そのため、謎は混迷を深めてゆく。だが、本書は混迷する謎を異なる視点で描きながら、章ごとに視点は固定している。また、時間の流れも追いやすい。だから本書は、前衛的な構成や内容になっておらず、読みやすい。読者は複数の視点が目まぐるしく移り変わるが、視点の混乱はないため、理解しながら読み進められるはずだ。
そうした著者による配慮は、本書を純文学の範疇に押し込めず、ミステリーとしても成り立たせながら、扱うテーマの深遠さにおいて本書を現代の第一級の文学作品であらしめている。
ミステリーと純文学の両立は、芸術性の誘惑になびきながら、売り上げを求めなければならない作家にとって常に目標であり続ける。
それが本書においては見事に両方とも成り立っている。それを成し遂げた本書の価値に疑問の余地はない。
本書が取り上げる新旧の文化の相克は、本書の主要なテーマだ。伝統の平面的な細密画と新しい遠近法を駆使した西洋絵画の比較。
その比較において、著者は客観的な視点と主観的な視点を巧みに取り扱うことで、描写に深みを与えている。
上巻の冒頭にはコーランから引用された三つの言葉が掲げられている。そのうちの一つは、こう書かれている。
盲人と正常の目の人とは、同じではない。 コーラン創造者章十九節
コーランが告げるのは、絵描きにとって視点とは何かだ。実に鋭く深い言葉だと思う。画業も極めると目を閉じても描ける。それが細密画師の奥義だ。
本書のあちこちで、コーランの言葉と同じような言葉を人々が語る。それらの言葉が、主観と客観についての違いや、絵を描く営みの本質をついているのは間違いない。
本書はイスラムの伝統である細密画が徐々に廃れ、西洋から来た遠近法の絵画に飲まれていく様子を描いている。21世紀の私たちにとって、どちらの手法が今に残っているのかは明らかだ。遠近法を駆使した絵画が主流になっていることは、もはや歴史的な事実であり動かしようのない事実。
絵画の発展とは、このような新旧の相克によって今に至っている。
上巻の冒頭に引用されたコーランのもう一つの言葉は後一つがある。
東も西も、神のものであり、あなたがたはどこを向こうとも、神の御前にある。 コーラン雌牛章一一五節
これは、モーセやイエス・キリストでさえも預言者とした、イスラム教義の懐の深さを示している。
結局、西洋文明がトルコを席巻しようとも、細密画が忘れ去られようと、すべては神の前にある。そのような大きな視野で物事をとらえるイスラムの器の大きさ。
世俗主義を掲げ、イスラム国でありながら西洋文明を受け入れるトルコ。それはトルコに生きる著者にとっては当たり前に身につけた素養であり、現代のトルコを読み解くにあたっても留意すべき視点なのかもしれない。私たち日本人にとってそのことは押さえておくべきと思われる。
むしろ、その視点は東洋にあって西洋文明を受け入れてきたわが国だから通じるはずだ。
それを理解しているからこそ、トルコは親日国として知られているのかもしれない。異なる文明を受け入れ、取り込んできた文化の在り方が似通っているから。
本書がテーマとする新旧の相克こそ、わが国でも起こっていたのだから。
極東の島国であり、さまざまな文化を受け入れ、消化してきたわが国。鎖国の時代ですら、出島を通して西洋文化は入ってきていた。その背景があったからこそ、明治政府による急激な欧化政策の中でも激烈な拒否が生じなかった原因だと思われる。
だが、わが国でもさまざまな葛藤は当然起こっていたはず。
本書で描かれたような新旧の文化の入れ替わりを、わが国の事例に当てはめてみるのも面白い。
また、もう一つ本書で特筆すべきは、本書が新訳版であることだ。本書は章ごとに語り手が違う。そのため、その口調や文体には細心の注意を払わねばならない。
本書の旧訳版にはあるいはその点で配慮が足りなかったのかもしれない。
実は私は著者の作品を読んだことがある。以前に読んだ『雪』は相当に読み通すのに苦労した記憶がある。それも訳文の固さにてこずって。
本書はとても読みやすいが、もしかしたら旧訳版では読みにくかったのかもしれない。
それも含め、本書はお勧めできる一冊だ。
‘2019/11/24-2019/11/29

