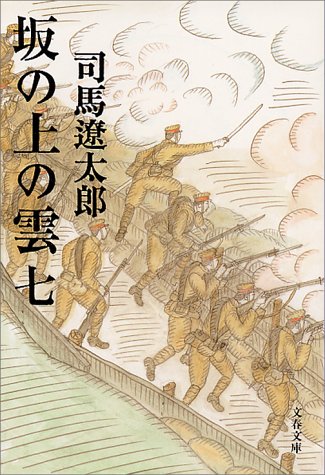
ついに本書は日露戦争の、そして世界史上でも最大の会戦である奉天会戦にたどり着いた。
黒溝台付近の海戦では、臨時に編成された立見尚文中将が率いる鴨緑江軍の活躍とロシアの満州軍の二人の将軍が反目しあった事によって、かろうじて陸軍は戦線を維持できた。
それに対してクロパトキン将軍は奉天で全ての決着を付けようとする。広い満州の野にあって、奉天こそは、陸軍同士が雌雄を決するのにうってつけの場所だ。
東京の大本営が戦後の領土交渉を見据えて送り込んだ遊軍として組織された鴨緑江軍。そうした由来からか、鴨緑江軍は老兵がかなりの割合を占めていたという。奉天会戦の口火はそんな鴨緑江軍によって切られる。
クロパトキン将軍はこの鴨緑江軍を乃木軍と見誤ってしまう。なぜなら、乃木軍は旅順を攻略した後、奉天会戦に合流することが容易に予想できたから。そしてクロパトキン将軍は、乃木軍がどう合流するかを見極めようと必死になって情報を集めていた。
著者は本書の今までの巻を通じ、ロシアの官僚のような思考が日本を有利に導いてきたと指摘してきた。そして、奉天会戦においても、軍人でありながら官僚のような思考にとらわれていたクロパトキン将軍の思考の迷いと、防御に入ろうとする性向が戦局を有利に導いたという。
児玉源太郎の戦略の要諦は、ロシア軍を右に左に揺さぶる事であった。だが、その揺さぶりを行う部隊として想定していたのは鴨緑江軍ではなかった。
大山・児玉の両首脳が想定していたその舞台とは、乃木将軍が率いる第三軍だった。第三軍を日本軍の左翼から回り込ませ、クロパトキン将軍の軍を背後から衝かせる戦術を想定していた。
ところが鴨緑江軍は、日本軍の右翼から第一撃を与えることとなる。
それに激しく動揺したクロパトキンは、ロシア軍の陣形を崩してまで鴨緑江軍に主力を振り向けてしまう。ところがその後に乃木軍が戦場に現れた。そうした偶然が幸いし、ロシア軍はもう一度逆の陣営に注意を向けてしまう。
つまり、大山・児玉の思惑よりもさらに余分にロシア軍は動いてしまう。クロパトキンは結果としてロシア軍をもう半往復も多く動かしてしまう。それは、日本にとってとても有利に働いた。
なぜそれほどまでにクロパトキンは動揺し、日本の術中にはまったのか。それは秋山好古の率いる騎兵部隊が敵陣の深い場所で撹乱を行ったからだ。
騎兵部隊の機動力をフルに活かしたかく乱は、クロパトキンの心に疑念を生じさせた。ところが、当時のロシア軍の置かれた状況は、後世の戦史家が読み解いたところ、ロシア軍に有利な戦況であったという。
日本軍の装備と弾薬と兵員の資源はすでに限界にきており、悠々と構えていさえすれば、ロシア軍は勝てたはずなのだという。
だが、クロパトキンの脳裏の片隅に生まれた恐れは徐々にその割合を大きくした。その結果、日本軍に背後をつかれたり、本国へ帰還するための鉄橋が落とされたりしたら、ロシア軍の受けるダメージは計り知れないとの判断をくださせた。
ロシア軍は奉天会戦で壊滅的な打撃を受けたわけではない。だが、結果として撤退させたことで、日本が勝利したように思わせるチャンスとなった。日本の外交にとっても、諸外国の目からみても。
そして児玉源太郎は、この機を逃さずして、戦争を終わらせられないと決心した。
急いで東京へと舞い戻る児玉源太郎。そして積極的に政府の要人のもとを訪ねては、終戦へと国の総意を導くよう強く具申した。なぜなら諸外国も、仲裁できる立場にあったアメリカも、何より当のロシアですら、戦争が終わったという判断をつけかねていたからだ。
そんな状態だったから、いつになれば終わるのか、誰にもわからない日本への航海を続けるバルチック艦隊を止める要素はなかった。誰もそれを止める者はおらず、ただ、長い航海で士気の緩んだ艦隊が海原を進み続けた。
狭いシンガポール海峡を悠々と行き過ぎたバルチック艦隊は、無防備にも思える航海を続け、後続の第三艦隊を待ちぼうけて仏領インドシナで少しの休みを取る。
インドシナを抜けると、そこから先は日本の近海だ。そこからバルチック艦隊はどういうルートをとるのか。対馬海峡から来るのか、それとも津軽海峡から回り込むのか。それによって艦隊の運用や作戦、待機位置などが大きく変わりうる。
バルチック艦隊が対馬に向かう兆候はいつになっても見えない。作戦を一身に背負う立場にあった秋山真之は、ここにきて憔悴の極みに至る。
そんな参謀をよそに、東郷元帥は対馬経由でしかバルチック艦隊の進路はありえないとの構えを保ち続ける。あくまでも悠揚に構えていた。
そこが東郷平八郎が名将と言われるゆえんだろう。
著者はそんな東郷の器の大きさを描く一方で、その影としての秋山参謀の焦りと苦悩を描く。
その一方で、日露戦争の中で欠かせないエピソードとして、宮古島でバルチック艦隊を見かけた漁民が目撃したとの一報を打つためだけに決死の思いでくり舟を操り、はるかな石垣島へ漕ぎ出した挿話を紹介する。
本書の全体に通じるのは、情報の重要さだ。情報を制するものが世界を制する。
その教訓を壮大な反面教師として後世に残したのが日露戦争の当時のロシアの陸海軍だ。
だが、日本にしても決して情報で有利だったわけではない。日本にしてもバルチック艦隊がどう来るか予想できずにいる中、情報に飢えて渇望した中でつかみ取った勝利だった。
著者は何度も書いている。
日露戦争で得たはずの教訓が四十年の後に活かされず、精神論だけが受け継がれてしまったことが、太平洋戦争の破滅につながったということを。
全く同意する。
その事実から学び取るべきは、今の情報に溺れそうな社会を生き抜くためにも情報は重要だということだ。
‘2018/12/22-2018/12/25


Pingback: 2020年2月のまとめ(個人) | Case Of Akvabit