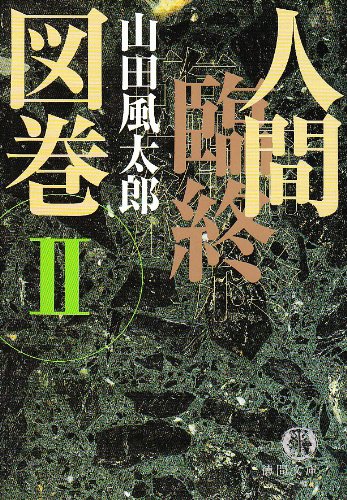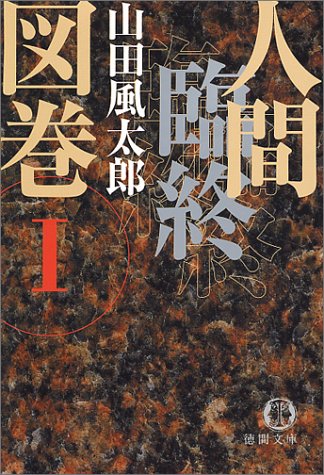魔術的リアリズムの定義を語れ、と問われて、いったい何人が答えられるだろう。ほとんどの方には無理難題に違いない。ラテンアメリカ文学に惹かれ、数十冊は読んできだ私にも同じこと。魔術的リアリズムという言葉は当ブログでも幾度か使ってきたが、しょせんは知ったかぶりにすぎない。だが、寺尾氏による『魔術的リアリズム』は、その定義を明らかにした好著であった。
その中で寺尾氏は、魔術的リアリズムに親しい小説や評論をかなり紹介してくださっている。その中には私の知らない、そもそも和訳がまだで読むことすらままならない作品がいくつも含まれていた。
著者略歴には寺尾氏が訳したラテンアメリカの作家の著作も数冊載っている。それによって知ったのは、寺尾氏が、理論だけでなく実践「翻訳」もする方であること。私は寺尾氏がまだ知らぬラテンアメリカ文学を翻訳してくれることを願う。
そんなところに、本書を見掛けた。著者はラテンアメリカ文学を語る上で必ず名の挙がる作家だ。だが、上述の寺尾氏の著作の中では、著者の作品はあまり取り上げられていない。作風が魔術的リアリズムとは少し違うため、寺尾氏の論旨には必要なかったのだろう。だが、著者の名は幾度も登場する。メキシコの文学シーンを庇護し、魔術的リアリズムを世界的なムーブメントへと育てるのに大きな役割を果たした立役者として。その様な著者の作品を訳したのが寺尾氏であれば、読むしかない。
本書はセルバンテス文化センター鯵書の一冊に連なっている。セルバンテス文化センターとは、麹町にあってスペイン語圏の文化を発信している。私も二度ほど訪れたことがある。セルバンテス文化センターでは、スペイン本国だけでなくスペイン語圏を包括している。つまり、本書のようなメキシコを舞台とした文学も網羅するわけだ。
そういったバックがあるからかは知らないが、本書の内容には気合いが入っている。小説の内容はもちろんだが、内容を補足するための資料が充実しているのだ。
脇役に至るまで登場するあらゆる人物の一覧。メキシコシティの地図。本書に登場したり、名前が言及されるあらゆる人物の略歴。さらには年表。この年表もすごい。本書の舞台である1950年代初頭までさかのぼったメキシコの近代史だけでなく、そこには本書の登場人物たちの人物史も載っている。
なぜここまで丁寧な付録があるかというと、本書を理解するためには少々の知識を必要とするからだ。革命をへて都市化されつつあるメキシコ。農地を手広く経営する土地持ちが没落する一方で、資本家が勃興してマネーゲームに狂奔するメキシコ。そのようなメキシコの昔と今、地方と都市が本書の中で目まぐるしく交錯する。なので、本書を真に理解しようと思えば、付録は欠かせない。もっとも、私は付録をあまり参照しなかった。それは私がメキシコ史を知悉していたから、ではもちろんない。一回目はまず筋を読むことに専念したからだ。なので登場人物達の会話に登場する土地や人物について、理解せぬままに読み進めたことを告白する。
筋書きそのものも、はじめは取っ付きにくい思いように思える。私も物語世界になかなか入り込めないもどかしさを感じながら読み進めた。それは、訳者の訳がまずいからではない。そもそも原書自体がやさしく書かれているわけではないから。
冒頭のイスカ・シエンフエゴスによる、メキシコを総括するかのような壮大な独白から場面は一転、どこかのサロンに集う人々の様子が書かれる。紹介もそこそこに大勢の人物が現れては人となりや地位を仄めかすようなせりふを吐いて去ってゆく。読者はいきなり大勢の登場人物に向き合わされることになる。やわな読者であればここで本書を放り投げてしまいそうだ。本書に付されている付録は、ここで役に立つはずだ。
前半のこのシーンで読者の多くをふるいにかけたあと、著者はそれぞれの登場人物を個別に語り始める。それぞれの個人史は、すなわちメキシコの各地の歴史が語られることに等しい。メキシコの地理や歴史を知らない読者は、物語に置いていかれそうになる。またまた付録と本編を行きつ戻りつするのが望ましい。
実のところ、中盤までの本書は導入部だ。読者にとっては退屈さとの戦いになるかもしれない。
しかし中盤以降、本書はがぜん魅力を放ち始める。本書は、文章の表現や比喩の一つ一つが意表をついた技巧で飾られている。それは、著者と訳者による共作の芸術とさえ言える。前半にも技巧が凝らされた文章でつづられているのだが、いかんせん世界に入り込めない以上は、飾りがかえって邪魔になるだけだ。だが、一度本書の世界観に入り込むことに成功すると、それらの文章が生き生きとし始めるのだ。
文章が輝きを放つにつれ、本書内での登場人物達の立ち位置もあらわになって行く。ここに至ってようやく冒頭のサロンで人々が交わす言葉の意味が明らかになっていく。本書はそのような趣向からなっている。
登場人物たちが迎える運命の流れは、読者にページをめくる手を速めさせる。本書を読み進めていくうちに読者は理解するはずだ。本書がメキシコを時間の流れから書き出そうとする壮大な試みであることに。
革命とその後に続く試行錯誤の日々に翻弄される人々。その変わりゆく営みのあり方はさまざまだ。成り上がり階級の人々が謳歌していた栄華は、恥辱に塗れ、廃虚となる。没落地主の雌伏の日々は、名声の中に迎えられる。人々の境遇や立場は、時代の渦にはもろい。本書の中でもそれらは不安定に乱れ舞う。吉事に一喜し、凶事に一憂する人々。著者のレトリックはそんな様子を余すところなく自在に書いてゆく。閃きが縦横に走り、メキシコの混乱した世相が映像的に描き尽くされる。
だが、それらの描写はあくまでも比喩として多彩なのだ。非現実的な出来事は本書には起こらない。つまり、本書は魔術的リアリズムの系譜に連なる作品ではないのだ。それでいて、本書の構成、描写など、間違いなくラテンアメリカ文学の代表として堂々たるものだと思う。おそらくは、寺尾氏もそれを考えて『魔術的リアリズム』に本書を取り上げなかったと思われる。だが、魔術的リアリズムを抜きにしても、本書はラテンアメリカ文学史に残るべき一冊だ。寺尾氏も我が意を得たりと、本書の翻訳を引き受けたのだと思う。
‘2016/07/17-2016/08/05