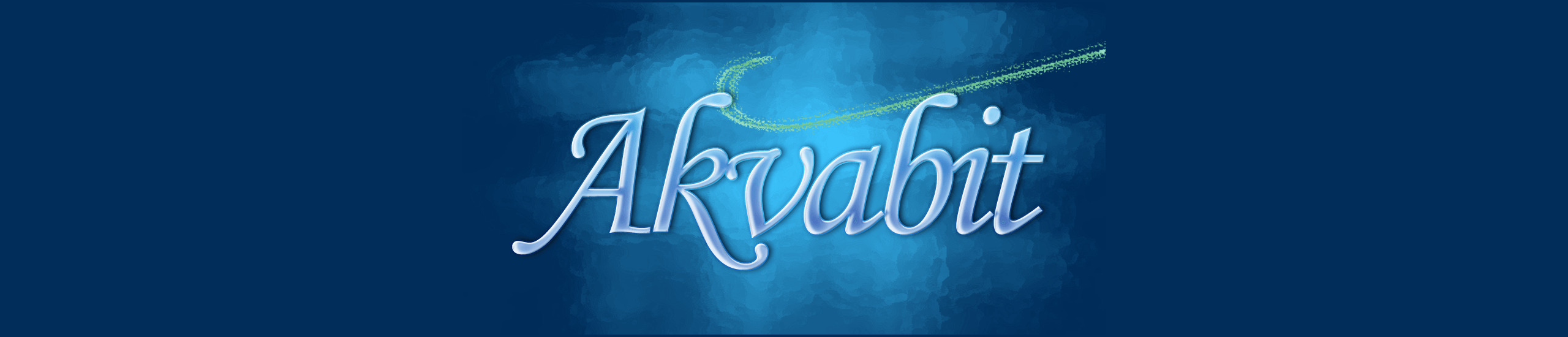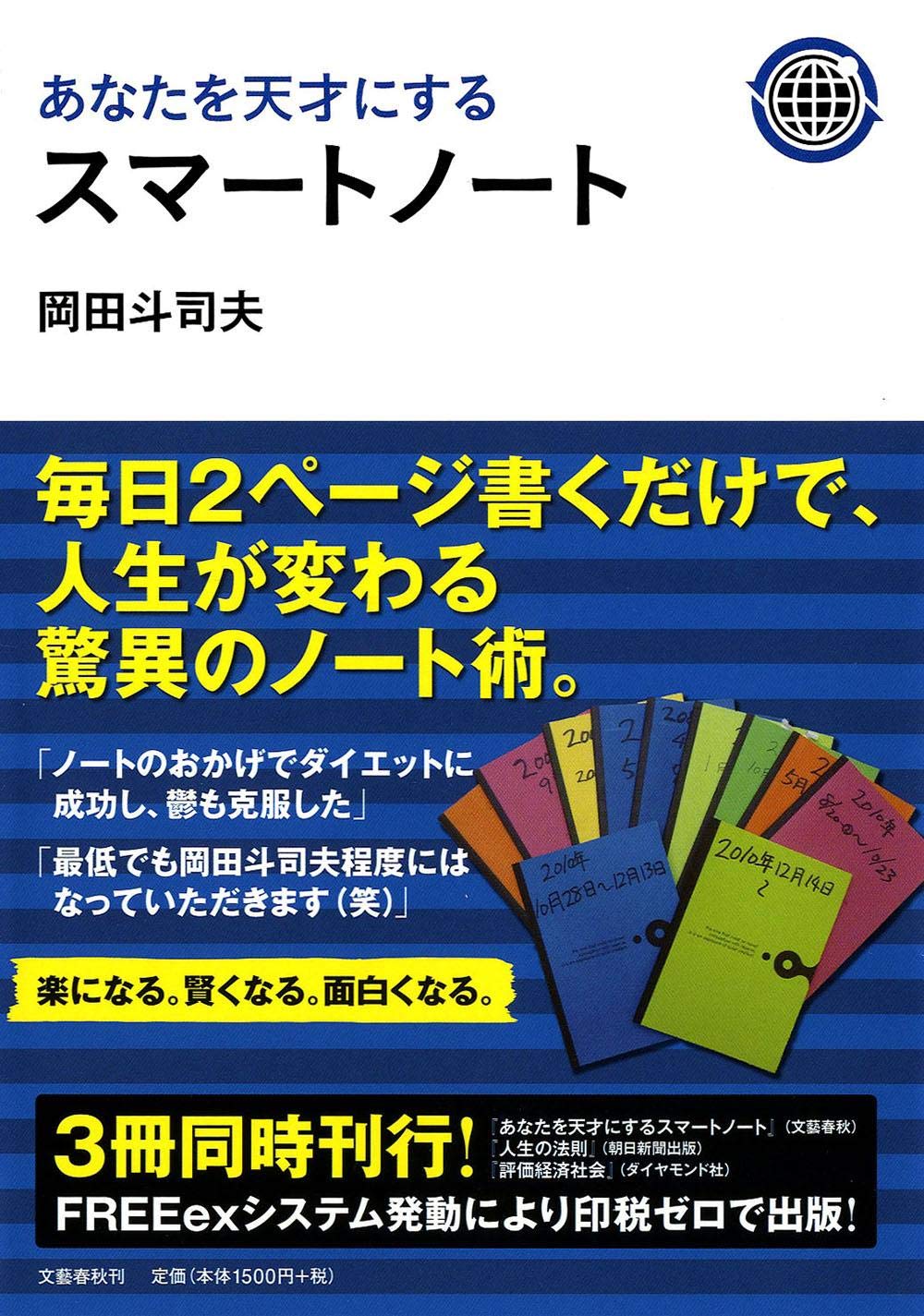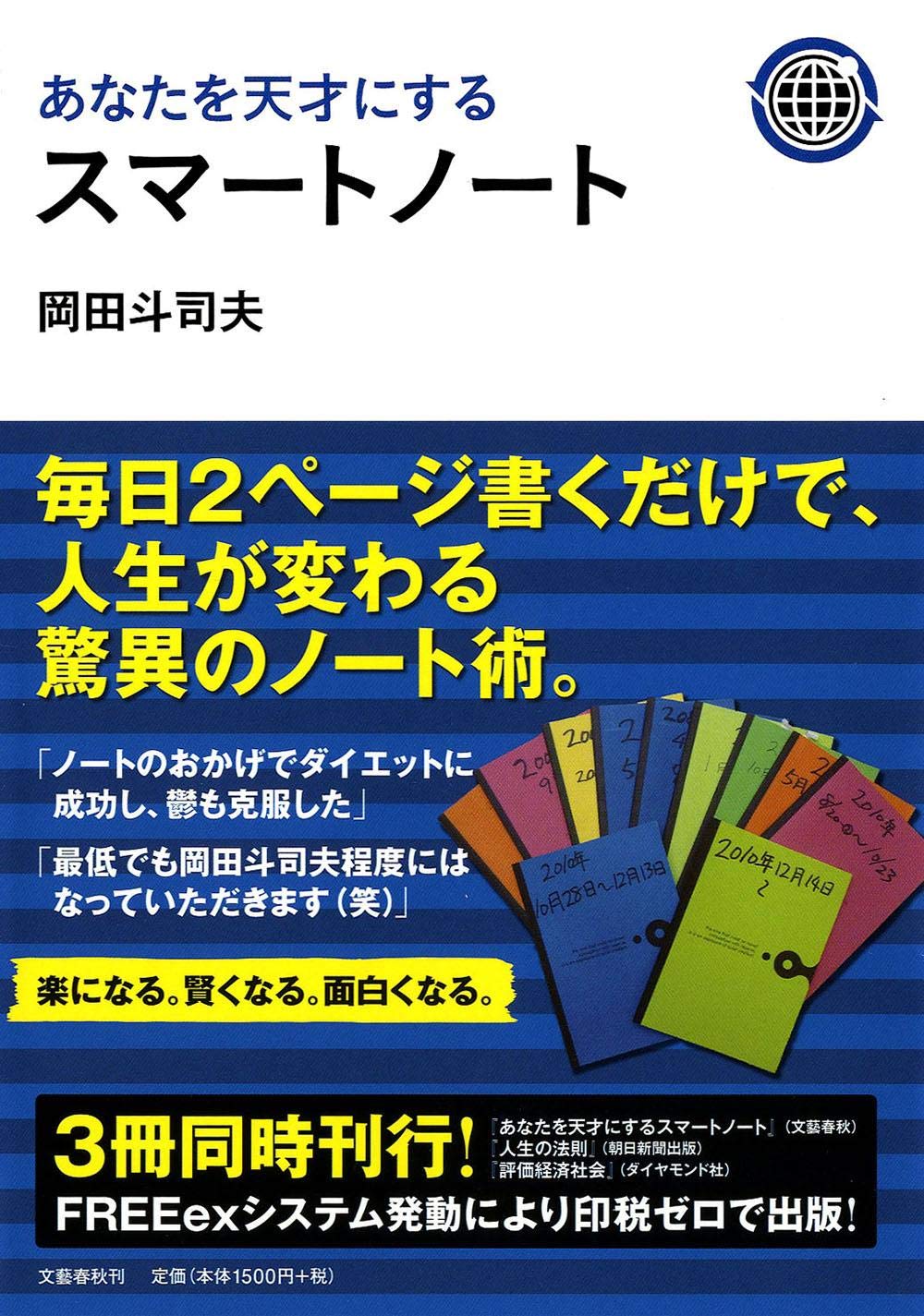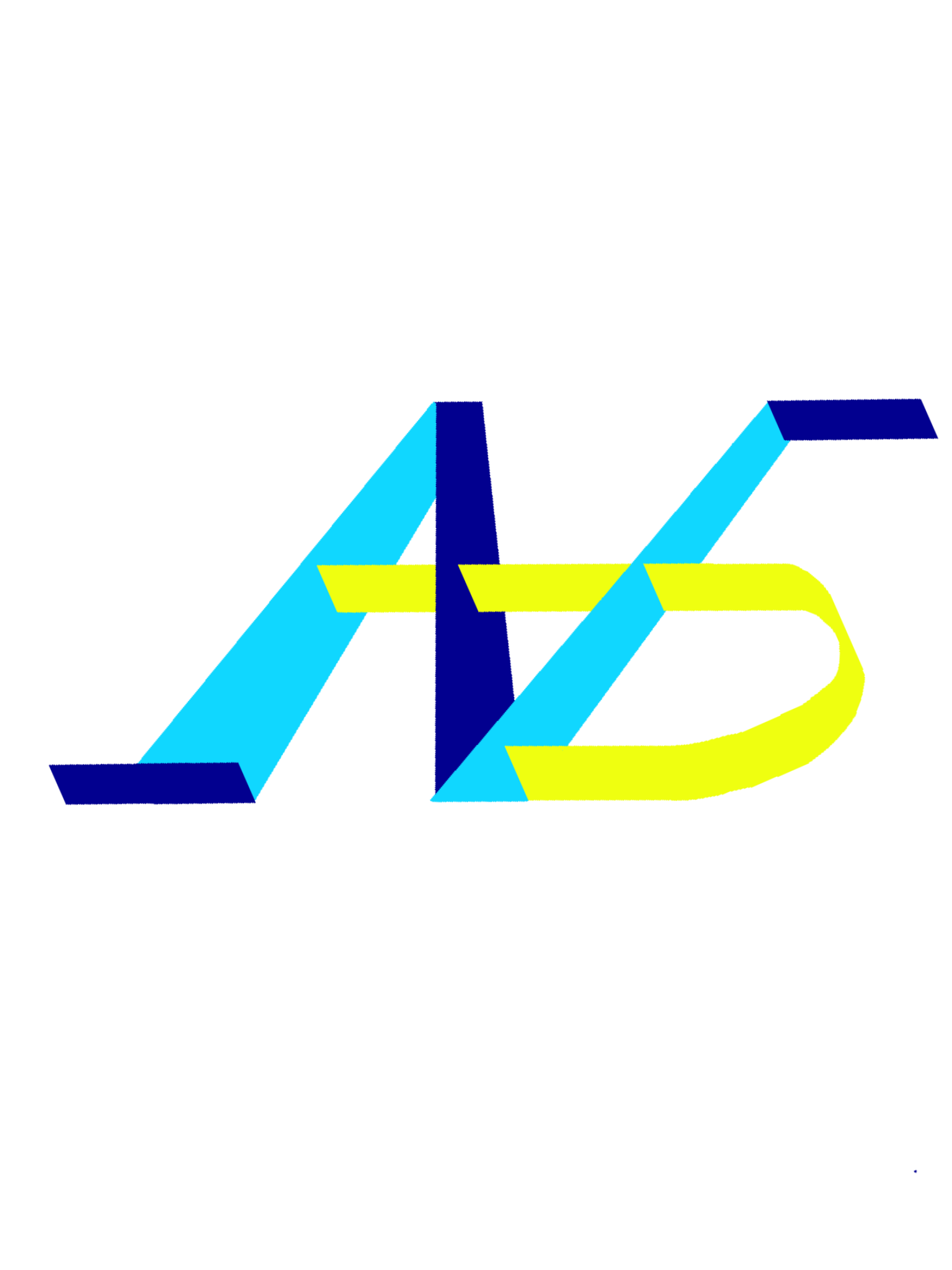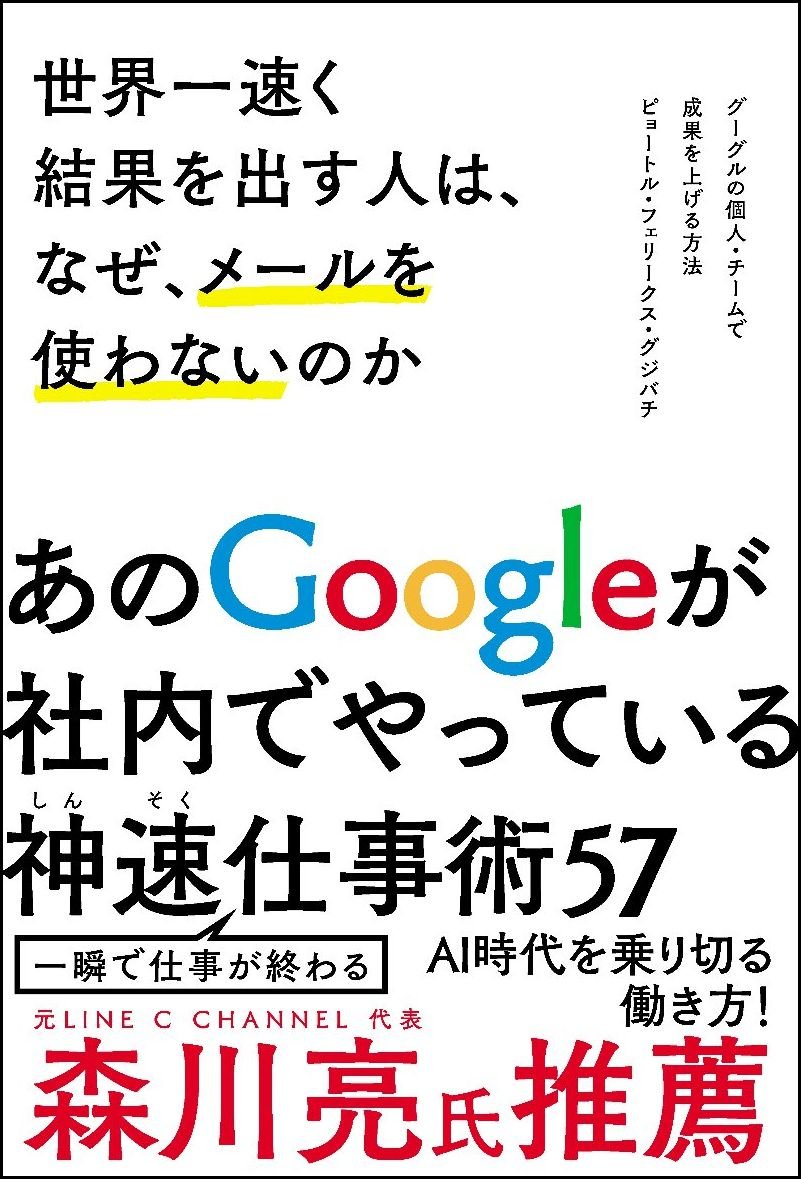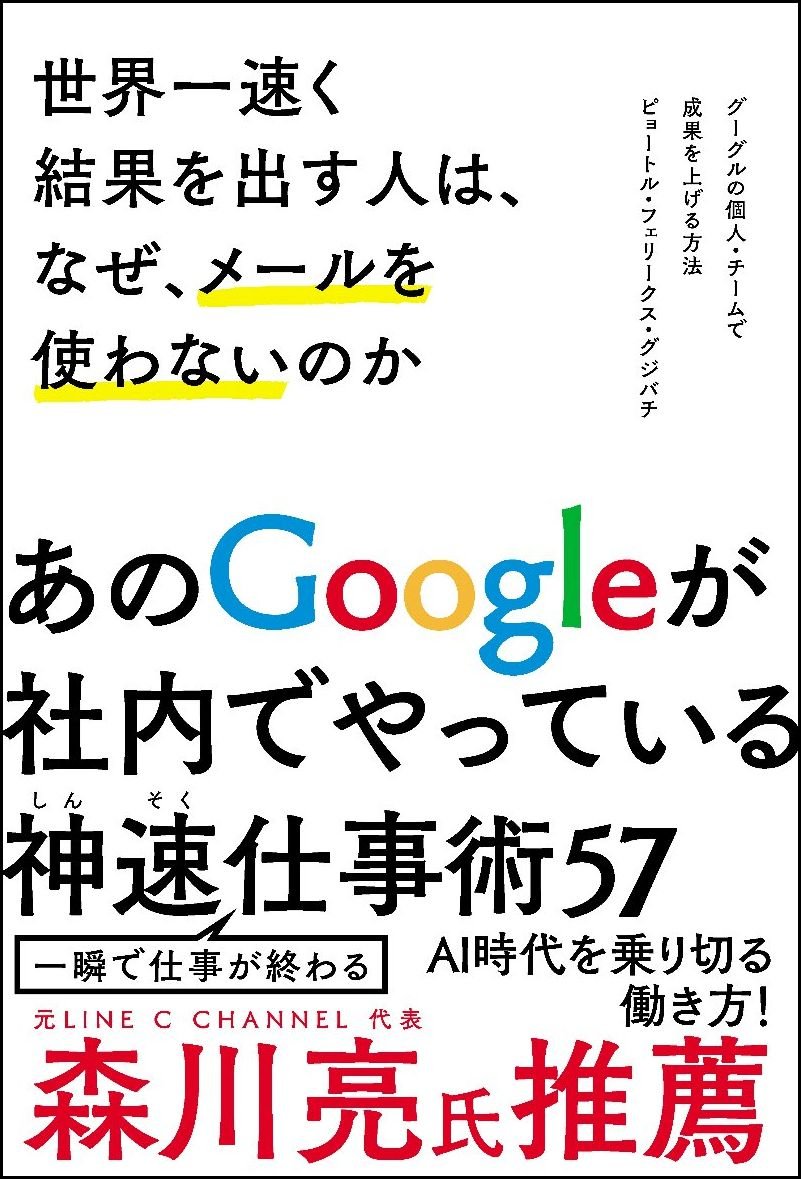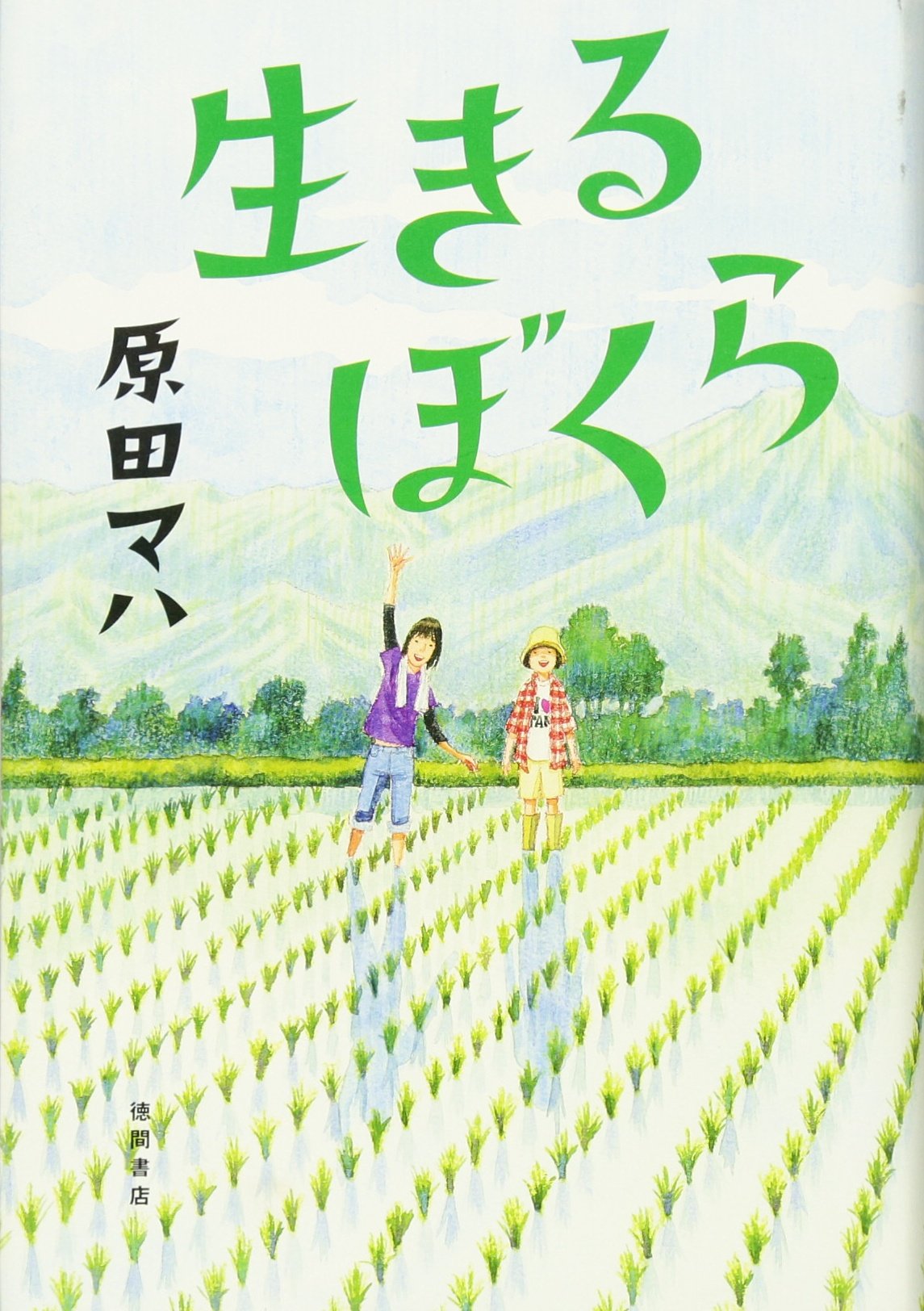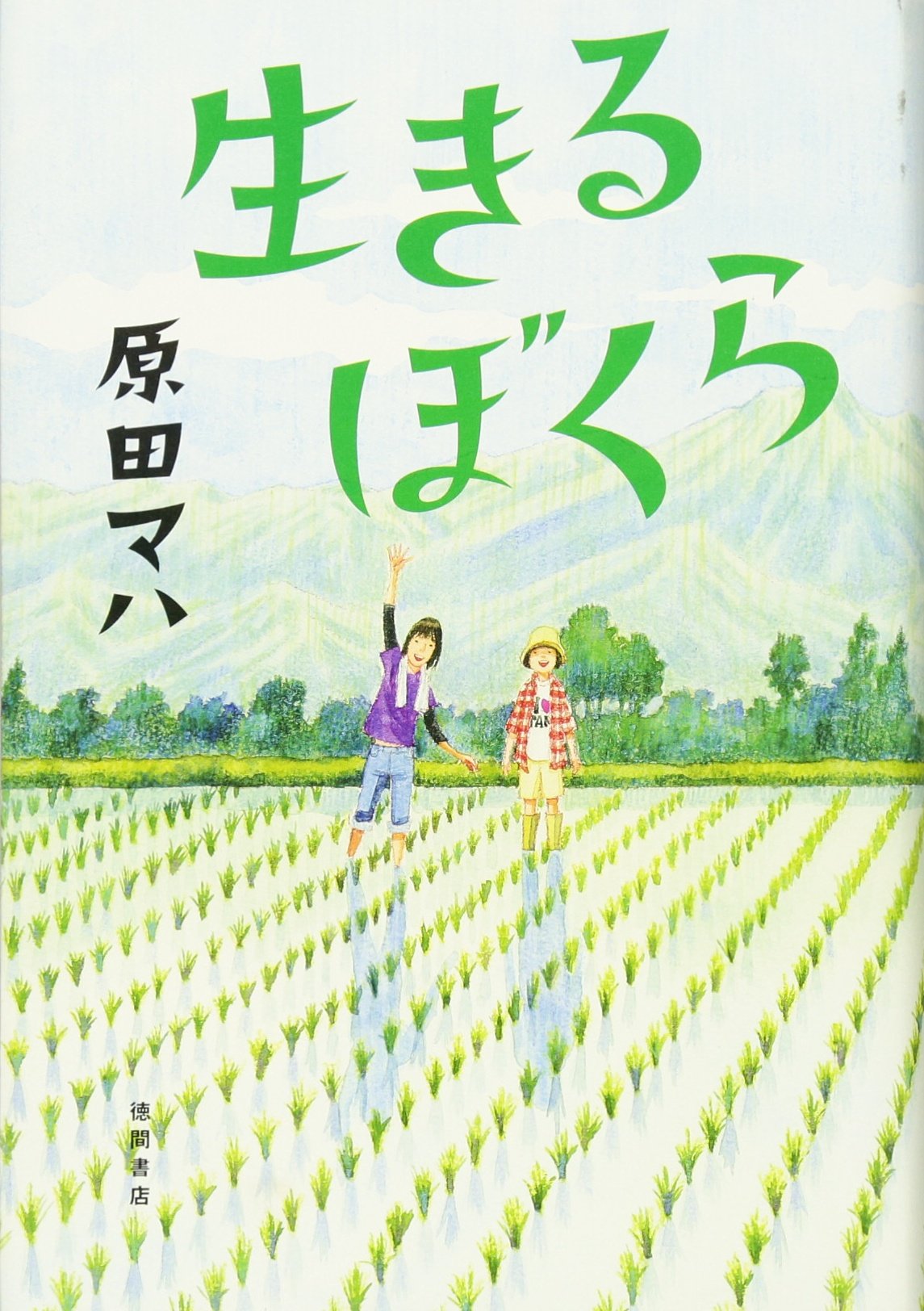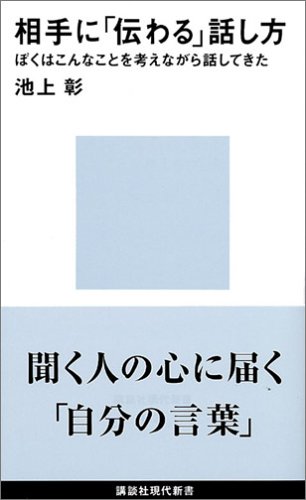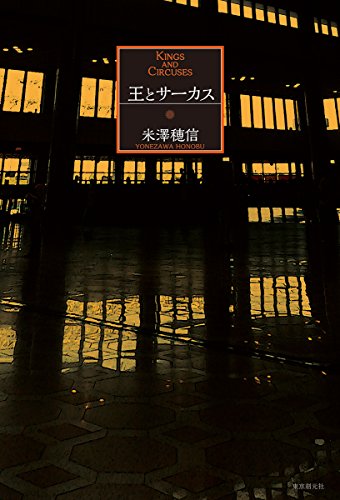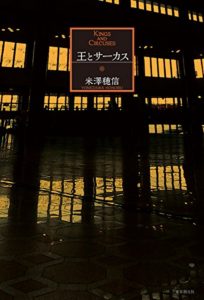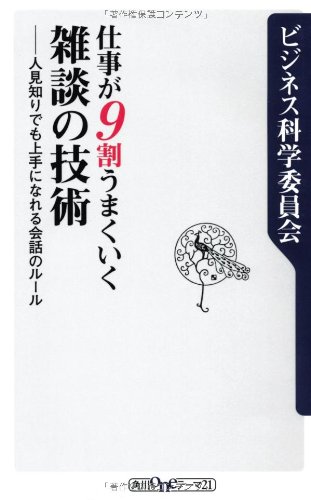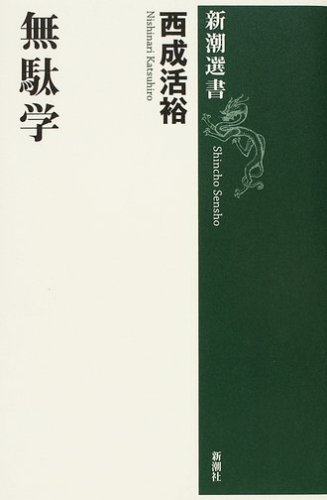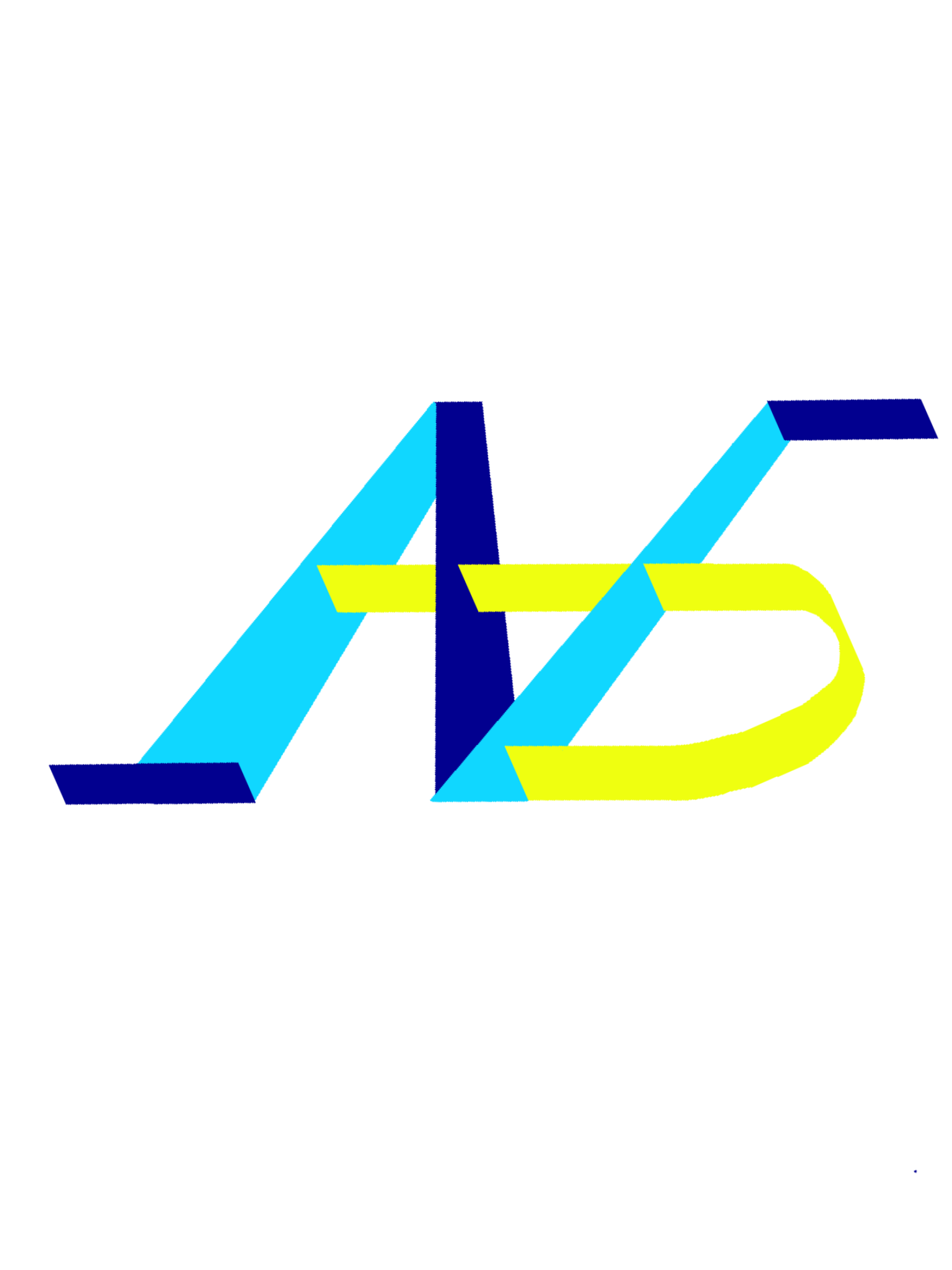「アクアビット航海記」では、個人事業主から法人を設立するまでの歩みを振り返っています。
その中で、私のキャリア上の転機となってきたのは発信ではないかと思います。
技術者の方はアドボケイターやエバンジェリストという言葉を聞いたことがあるでしょうか。かくいう私もkintoneエバンジェリストという肩書をサイボウズさんからいただいています。
なお、余談ですが私はその時までエバンジェリストの言葉すらよく知りませんでした。引き受けたのはよいのですが、何をすればよいのか全く分かりませんでしたので。
しかも当時私がいた常駐先(某大手信販会社基幹刷新プロジェクトのPMO)は猛烈に忙しく、エバンジェリストの事を何もできずにいました。よく私がクビにならなかったと思います。正直、レアキャラと呼ばれていました。クビ候補筆頭だったはずです。お声がけくださった後、辛抱強く育ててくださったサイボウズ社のうっし~さんには感謝しかありません。
さて、そうしたエバンジェリストやアドボケイターという方が行う発信は確かに発信の見本だと思います。スティーブ・ジョブズが鮮やかに行っていたようなプレゼンテーションなんてできるはずがない。発信なんてしょせん雲の上の人たちがやるもの。そう思っていませんか。全くその必要はありません。
それを以下に書いていこうと思います。
意思を伝えることが発信
まず、発信とは技術者であるあなた自身の意思表明です。例えば、到底一人ではやれるはずのない実装を任されたとします。そこで何も意思を示さず、言われるがままにやらされてしまっていては、自分の心身はむしばまれるばかりです。
きっとあなたはこういうはずです。それは無理です。間に合いません、と。多分大丈夫だと思います。これらも立派な発信です。
もしくはエージェントやチームリーダーからこの案件ができるか、という問い合わせがきた際、あなたは自分のスキルを顧みて、こう答えるはずです。「できます」「楽勝です」「無理です」「鬼畜ですか?」「寝ながらできます」。これも立派な発信です。
まずは自分自身のスキルや状況をはっきりと相手に伝える。発信とはまずここから始まるはずです。
仕事している間はしょせん金を稼ぐ手段と割り切り、ポーカーフェイスで羊の皮をかぶって仕事をする人もいるでしょう。そうした方も、プライベートでは自分を友人や親や配偶者にさらけ出しているはずです。発信とはまず意思の伝達から始まります。
私のキャリアでいうと、まずは学生や若い頃の芦屋市でのアルバイト、派遣社員の日々が相当します。
状況をよくしたいと働きかける発信
自分自身の意思を表示するための発信はほとんどの人にとって当たり前の行為です。ですが、次のステップになると少しだけハードルが上がります。
例えば同じチームで気の合うAさんがやっている作業、見ていてとても非効率的。なんとかしたい。
そのような作業を見かねてアドバイスをしたとします。そしてAさんの業務効率は改善されました。これは立派な発信です。
では、特定のAさんにだけアドバイスをするのではなく、チームのミーティングの場で皆に対して発信することはどうでしょう。チームのメンバーは全員がAさんのように気の合うひとだけではありません。同じようにアドバイスしたつもりが、自分の仕事をけなされたと不快に思う人がでてくるかもしれません。ここから難易度が少しずつ上がっていきます。
この時、気を付けるべきは、相手を否定しないことです。否定せず、相手を認めた上で提案します。自分を振り返ってみてください。自分も完璧ではないですよね。未来も予測できないし、Wikipediaをそらんじて相手を驚かすこともできないはずです。人は完璧ではないのに、相手より絶対に正しいことはないはずです。それを踏まえ、相手を立てながら、改善点を伝えます。これも発信です。
むしろ、上に書いたエバンジェリストやアドボケイターとは、こうした発信をより多くの人にしているだけだともいえます。こうしたほうがよいですよ、楽になりますよ、という。
私のキャリアでいうと、スカパーのカスタマーセンターで働いていた頃、Excelの登録件数を集計する仕組みを改善しようと、マクロを使って効率を上げたことが挙げられます。この時、私はチーム内に自ら提案したように記憶しています。
自分の範囲外に働きかける発信
自分の周りの環境を変えられたら、今度はその範囲を少しずつ広げていきましょう。今の世の中にはありがたいことに発信する手段が無数にあります。ブログやSNSといった。こうした手段を使わないのはもったいない話です。
よく炎上を恐れて発信しないという人がいます。ですが、炎上するには理由があります。火のない所に煙は立たぬ、といいますが、やましくなければ炎上しないのです。
もちろん、著名人や芸能人となると別です。その立場を享受しているだけでうらやましがられ、やっかみの対象に選ばれます。そしていわれのない非難と炎上を招きます。ですが、あなたはまだ著名人でもなければ、有名税を払う必要もありません。
世の中には無数のツイートがあり、無数の動画が流れています。その中であなたが炎上するとしたら、よほど運が悪いか、誰かにちょっかいをかけてしまったかのどちらかだと思います。または明らかに世の中の大多数の動きに逆らった発信をするか。
あなたがどれだけ陰謀論を信じているところで、それは大多数ではありません。コロナワクチンや国葬に反対していても同じ。それはあなたの信条や意見として尊重されるべきですが、それを他人に強制すべきではありません。
もし、大多数の意見ではなくても、状況をよくしたいと働きかける発信をしたい場合は、やり方を考えましょう。その場合も上に書いた通り他人を否定しないことです。まず相手の立場と信条を受け入れ、理解した上で具体的な代案を出すとよいでしょう。
コロナワクチンや国葬に反対していても、それを認めさせたいがために相手を否定すると、炎上の当事者に祭り上げられます。ようはそうした悪目立ちをせずに発信すればよいのです。
私のキャリアにとっては、インターネット黎明期にBBSやメールマガジン、またはICQなどで見知らぬ人と会話していた時期にあたります。私も相手をけなしてしまう失敗をしましたし、自分のされて嫌な思いを味わいました。
人々を巻き込む発信
プレゼンの達人と呼ばれる人々は、プレゼンの結果に拍手をもらえたり、学びになりましたと言ってもらえたりすることをゴールとしていません。
エバンジェリストやアドボケイターも含め、そうした方々は相手が実際に行動に移った時をもってゴールとします。つまり、相手を巻き込んだ時です。
これはなかなか難しい問題です。そもそもプレゼンの成果を知る由はありません。無表情で反応の薄い人があとで行動を起こすこともあれば、コクコクとうなづいていた方が夜の懇親会で昼間の記憶を飛ばすこともあるからです。
どうすれば人を巻き込めるか。それは私にも答えがありません。熱意をこめ、抑揚をつけ、相手の目を見る。そうした技術はいくらでもネットや本にのっています。私も自分のプレゼンがどこまで人を巻き込めているか、まったく手探りのまま登壇しています。
ただ、言えるのは、自分がこうなりたい、こういうあり方が望ましいという信念を誰も傷つけず、それでいて確信を込めて語ることです。
当然、語るにあたっては裏付けとなる実績が要ります。その実績は結果を積み重ねていくしかありません。私も商談で依頼されたことをやった経験がなくてもやれますとハッタリを利かせることもあります。ですが、それらはネットを調べればわかることです。苦しんでも、寝ずに不休でも、やり遂げねば実績はたまりません。
私のキャリアにとっては、kintoneでいくつかの案件をこなし、エバンジェリストに任命され、法人成りを果たしたあたりまで私が人を巻き込むことはできていなかったはずです。
発信すると自分が楽になれます
自分がそうだからわかるのですが、このように順をおって発信することは、かならずあなたのキャリアを助けます。
別にエバンジェリストになる必要はありません。例えば会社勤めであっても、自分の意思を伝え、チーム・会社をよくしたいと発信することは重要です。そしてそれが社外にまで広まった時、転職やヘッドハンティングの対象に選ばれることもあるでしょう。または副業で人を巻き込む仕事をする際に、もしくは近所付き合いの際にイベントを誘う際にも役に立つことでしょう。
結局、発信とは自分を楽にするためにあるのです。発信をためらい、発信を億劫がると、受け身の人生になってしまいます。発信とは自分の人生を能動的に生きるための営みなのですから。
発信すれば、結果はあとからついてきます。結果とは例えば会社内の地位であったり、良き配偶者との出会いだったり。または私のように運よくエバンジェリストとしてお声がかかるかもしれません。もちろん収入にも跳ね返ってきます。
発信とは、誰のためでもありません。自分のためにやるのです。
最初のうちは、発信しても何の反応もないでしょう。でも、反応など気にしてはいけません。いいねがつかなくても、誰かの目に触れる。恥ずかしがらずに発信することは、あなた自身の知見を高め、より熱の入った洗練された内容に磨き上げられていくはずです。3年ぐらい、地道に発信しましょう。やがて、少しずつ反応が増えてゆくはずです。
そうなればこっちのものです。
発信しても否定されないコミュニティがあります
いかがでしょうか。もし、発信という営みに興味が出てきたら、全国津々浦々、どこかでやっている勉強会に出てみることをお勧めします。手練れのエバンジェリストもいれば、まだ発信をし始めた方もいます。
私たちもそうした方を決してけなしません。否定しません。それはもっともやってはいけないことです。私たちはまず誰の発言でも受け入れます。そしてもし改善が必要なら穏やかにそれを伝えます。
実際、私も何度もダメ出しを穏やかに頂いてきましたし、それを受けて自分なりに改善を重ねてきました。もちろん、私などまだまだです。すごい発信者は何人もいますから。私はただ、それを目指して努力するだけです。自分の望む人生に。自分にとって心地よい生き方のために。
まとめ
ここで書いたことがどなたかのご参考になれば幸いです。