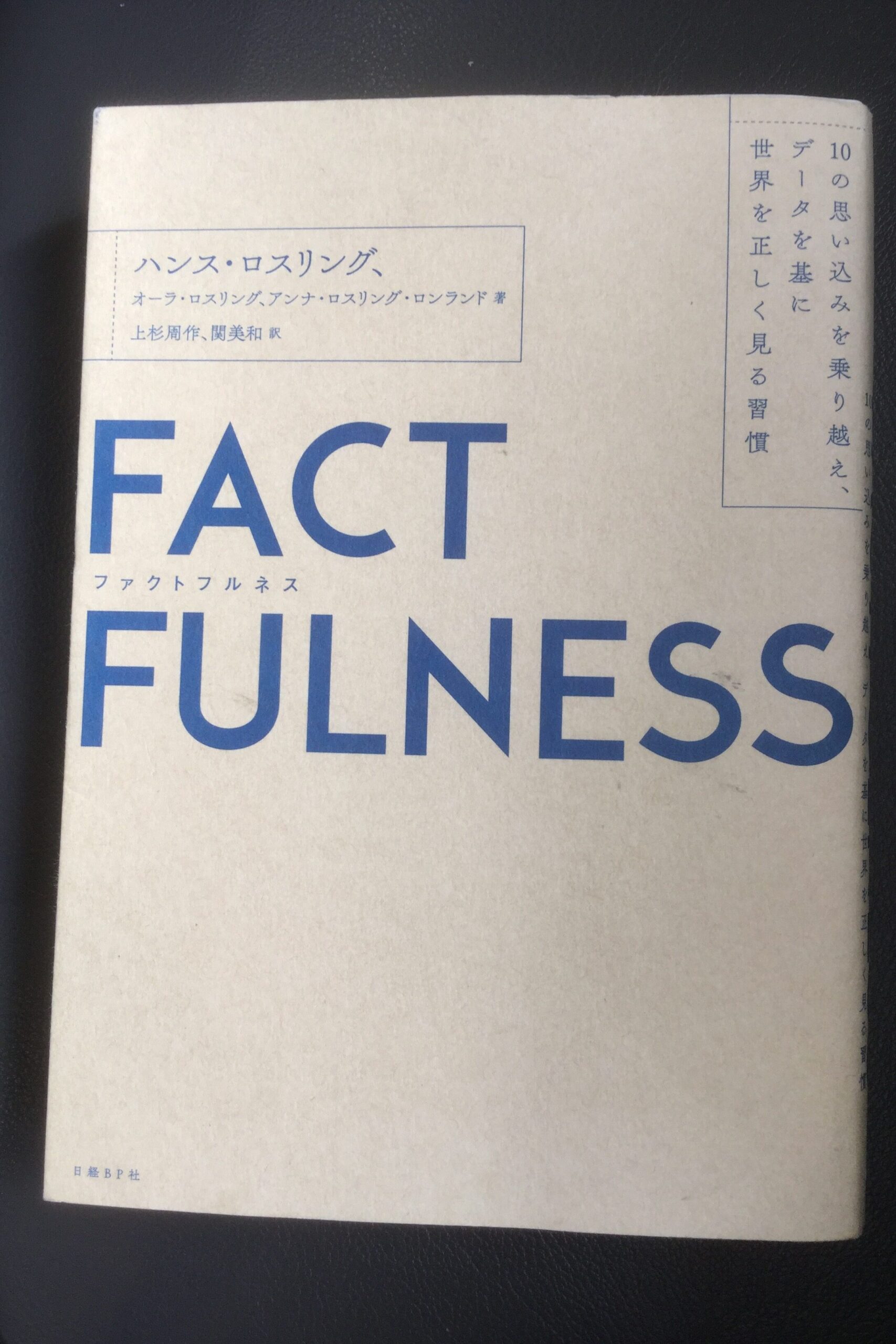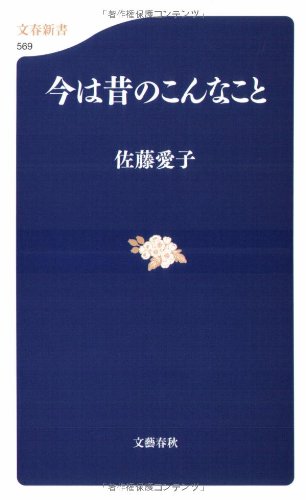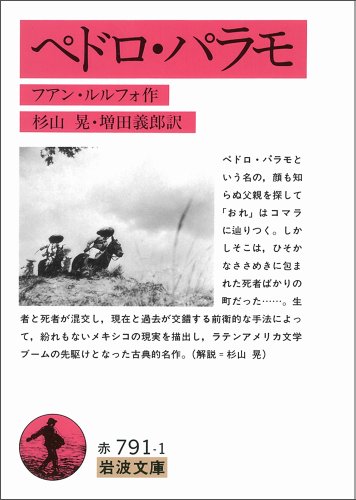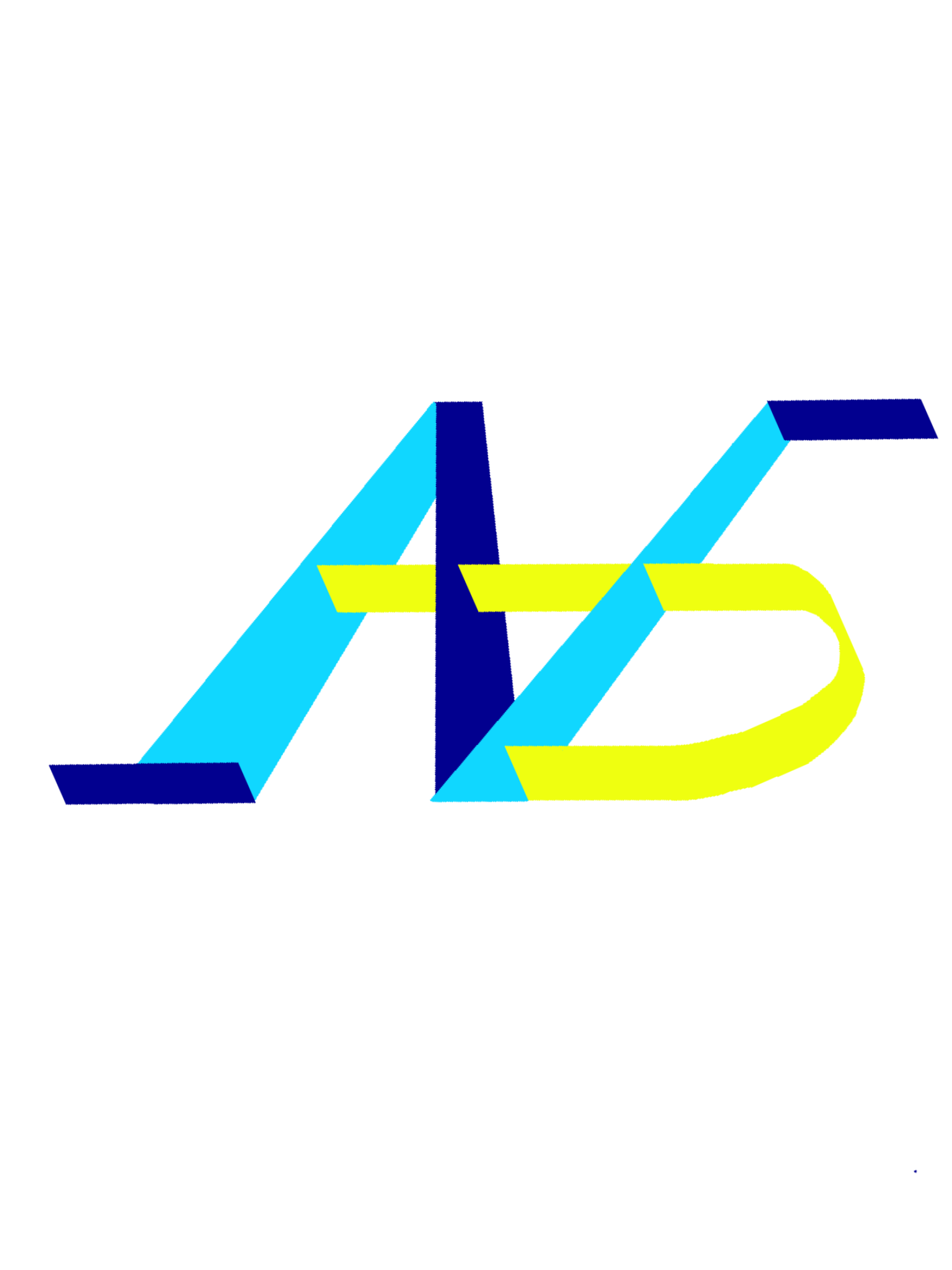私が書店でSFの新刊本を、しかもハードカバーで購入するのは初めてかもしれない。
本書はその中でお勧めされていたので購入した。
とてもよりすぐりの九編が続く本書は、二度読んだほうが良さそうだ。
特に、一度目を読むタイミングが集中できない環境にあった場合は。
私も本稿を書くにあたってざっと斜め読みした。
すると、本書の奥深さをより理解できた。
「商人と錬金術師の門」
本編を一言で表すとタイムワープものだ。
だが、その舞台は新鮮だ。アラビアン・ナイトの千夜一夜物語を思わせるような、バグダッドとカイロを舞台にした時空の旅。
とある小道具屋に立ち寄った主人公は、時間をさかのぼることができる不思議な門を店主のバシャラートに見せられる。右から入ると未来へ、左から潜ると過去へ進める。
この機構は論理的に現代物理学の範疇で可能らしい。
この門に関する複数のエピソードがバシャラートから語られ、それに魅入られた主人公は自らも旅を決意する。
ここで語っているのは、未来も過去も同じ人の運命という概念だ。今までのタイムワープもので定番になっていた設定は、過去を変えると未来が変わり、変わったことで新たな時間の線が続く。行為によって新たな時間線ができることによってストーリーの可能性が広がる。だから、登場人物は過去にさかのぼって未来を変えようとする。
だが、本編では未来は過去の延長にある。つまり、従来のタイムワープものの設定に乗っかっていない。それが逆に新鮮で印象に残る。
卵が先か、鶏が先か。わからない。だが、人は結局、宿命に縛られる。ある視点ではそのような閉塞感を感じる一編だ。
だが、その閉塞感は、自分の努力を否定するものではない。それもまた、人生を描く一つの視点だ。それが本編の余韻となっている。
「息吹」
並行宇宙。そして平衡状態になると終わるとされる宇宙。二つの「へいこう」をテーマにしているのが本編だ。
本編は、地球とはどこか別の場所、または時代が舞台だ。未知の存在の生命体、もしくは機械体が自らの存在する宇宙の終わりを予感する物語だ。
空気の流れが平衡状態になりつつあることにより、生命を駆動する動力が失われる。それを回避し、食い止めようと努力する語り手は人ではない。それどころか、現代のこの星の存在ですらない。
限られた紙数であるにもかかわらず、平衡に向かう宇宙のマクロと、自らを解剖する語り手のミクロな描写を平行で書くあたりが良かった。一つの短編の中でマクロとミクロを同時に書き記す離れ業。それが本編の凄さである。
「予期される未来」
わずかな紙数の本編。
未来を予測できる機械が行き渡ったことで、自由意志を否定されたと自らで動くことをやめた人々。そのようなディストピアの世界を描いている。
本編は、一年ちょっと先の未来からメッセージを送ってきた存在が語り手となっている。その存在は、決定論を受け入れた上で、嘘と自己欺瞞で乗り切れとアドバイスを送る。その冷徹な現実認識を決定論として認めなければならない。強烈なメッセージだ。
「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」
本編を読んでいると、AIBOやファービー、またはたまごっちなどの育てゲームを思い出す。どれも数年でブームを終えている。
本編にはディジエントという人工知能を有したペットのような存在が登場する。それらは動物の代替のペットとして人々に受け入れられた。だが、育てるのは難しく、飼い主の手を煩わせる。人々は飼いならせなくなったティジェントを手放し、運営する会社は廃業する。
たが、一部の人々は、手元に残されたディジエントを育てようと努力する。同じ保護者同士でコミュニティを作り、ディジエントとの共生やディジエントの自立に向けて模索する。本編はディジエントの保護者である主人公の葛藤が描かれる。ディジエントを世の中に適応させるにはどうすればよいか。
保護者がディジエントに気をもむ様子は、通常の子育てやペットの飼い主とは違う。まるで障害を抱えた子供を持つ親のようにも思える。通常の子育てと違った難しさが、本書に人間やペットと違う何かを育てることの困難さを予言している。
ディジエントに法人格を持たせることや、ディジエント同士のセックスなど微妙な問題にまで話を膨らませている。
私たちもそのうち、高度なAIと共生することもあるだろう。その時、倫理的・感情的な問題とどう折り合うのだろう。予言に満ちた一編だ。
「デイシー式全自動ナニー」
20世紀初頭に発明されたとする当時の産物のナニー(ベビーシッター)。当時にあって新奇な技術が人々から見放されていく様子を研究論文の体裁をとって描いているのが本編だ。
全自動の存在に人の成長を委ねることのリスク。本編は、現代から考えると昔の技術を扱っている。だが、ここで書かれているのは間違いなく未来の技術信仰への疑問だ。
私たちは今、人工知能に人類のあらゆる判断を委ねようとしている。そこから考えられる著者のメッセージは明白だ。
「偽りのない事実、偽りのない気持ち」
本編は人の生活のあらゆる面を記録するライフログがテーマだ。
私もライフログについては本のレビューを書いたこともあるし、自分なりの考えをブログにアップしたこともある。
人々は、自らの記憶があやふやであることに救われている。あやふやな記憶によって、人間関係はあいまいに成り立っている。そのあいまいさがある時は人を救い、ある時は人を悩ませる。
リメンという機械によって、ライフログが当たり前になった未来。人々は、リメンによって自分の過ちに気づく。本編の登場人物である親子の関係と二人の間にある記憶の食い違いが強制的に正されていく。
本編が優れているのは、もう一つ別の物語を並行で描いていることだ。ティブ族と言うどこかの部族が、口承で伝えられてきた部族の歴史が、文字や紙によってなり変わられていく痛みを書いている。古い文化から新しい文化へ。そこで起こる文化の変容。それは人類が新たなツールを発明してきた度に引き受けてきた痛みそのものだ。痛みとは、自分が誤っていたと気づくこと。自分が正しくなかったことではなく。
「大いなる沈黙」
本書の末尾には、著者自身による創作ノートのようなものが付されている。それによると本編は、もともと映像作品を補足するスクリプトとして表示していたテキストだったと言う。それを短編小説として独自に抜き出したものが本編だ。
フェルミのパラドックスとは、なぜ宇宙が静かなのかと言う謎への答えだ。宇宙に進出する前に絶滅してしまう種族が多いため、宇宙はこれだけ静かとのパラドックスだ。
「オムファロス」
進化論と考古学。
アメリカではいまだに、この世は創造主によって創造されたことを信じる人がいると言う。それもたくさん。
彼らにとっては人類こそが宇宙で唯一の存在なのだろう。彼らが仮定した創造主とは、私たちにとって絶対的な上位の存在だ。それは同時に、私たち自身が絶対的な存在だと仮定した前提がある。もちろん、この広大な宇宙の中で太陽系などほんの一握りですらない。チリよりも細かいミクロの存在だ。全体の中で人類の位置を客観的に示すことこそ、本編の目的だとも言える。
「不安は自由のめまい」
プリズムと言う機械を起動する。その時点から時間軸は二つに分岐する。分岐した側の世界と量子レベルで通信ができるようになった世界。本編はそのような設定だ。
別の可能性の自分と通信ができる。このような斬新なアイディアによって書かれた本編はとても興味深い。周りを見渡して自分の人生に後悔がない人などいるだろうか。自分が失ったであろう可能性と話す。それはある人によっては麻薬にも等しい効果がある。常に後悔の中に生きる人間の弱さとそこにつけ込む技術。考えさせられる。
‘2020/06/08-2020/06/13