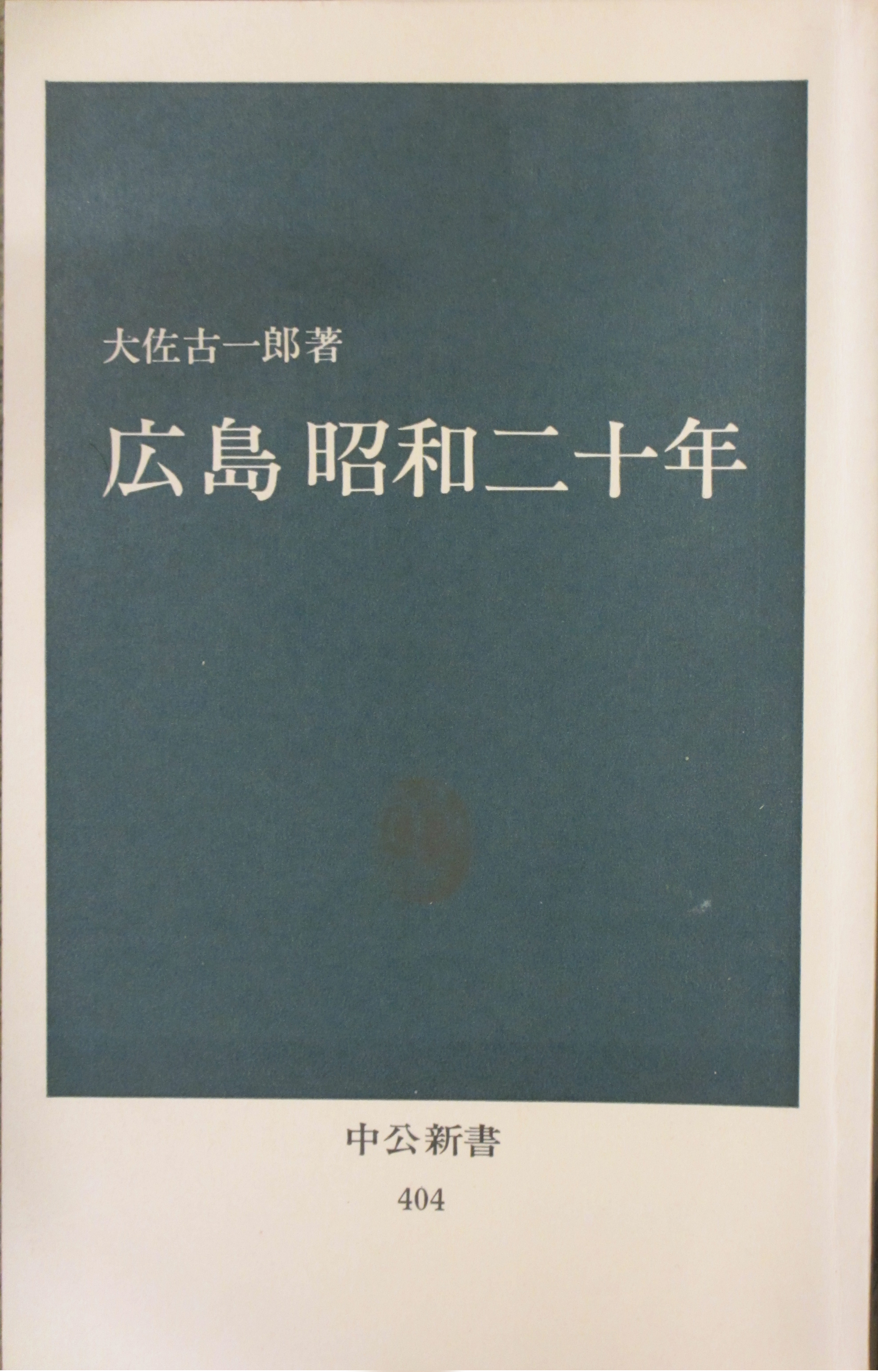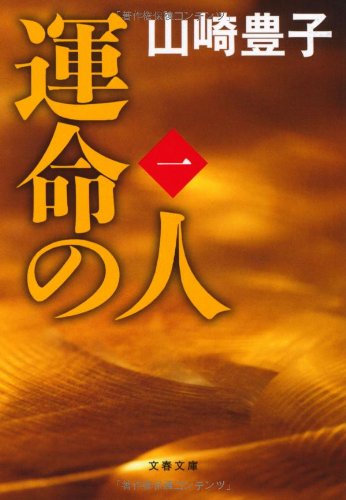本書は、三編の短編からなっている。
どれもがスピード感に満ちており、一気に読める。
「ハル、ハル、ハル」
「この物語はきみが読んできた全部の物語の続編だ」という一文で始まる本編。
“全ての物語の続編”というキーワード。これが本編を一言で言い表している。
全ての物語とは、出版された小説に限らない。あらゆるブログやツイッターやウォールやストーリーも含む。物語は何も発表されている必要はない。人々の脳内に流れる思考すら全ての物語に含められるべきだからだ。
この発想は面白い。
物語とは本来、自由であるはず。物語と物語は自由につながってよいし、ある物語が別の物語の続編であるべきと決めつける根拠もない。
場所や空間が別であってもいい。物語をつむぐ作者の性別、人種、民族、時代、宗教は問わない。どの物語にも人類に共通の思考が流れている限り、それが続編でないと考える理由は、どこにもない。
本編のように旅する三人組のお話であっても、読者である私の人生に関係のない登場人物が出てこようとも、それはどこかで私=読者のつづる物語とつながっているはず。
十三歳。男。十六歳。女。四十一歳。男。本編の三人の登場人物だ。
私に近いのは四十一歳の男だろう。彼と私に似ているところは性別と年齢ぐらい。
彼はリストラに遭い、妻子にも逃げられ、今はタクシー運転手をしている。そんな設定だ。
そんな彼が偶然拾ったのが、子供のような年齢の若い男女。二人はなぜか拾った拳銃を持っており、それで男を脅してきた。どこか遠くに行け、と。
三人の名前のどこかにハルがつくため、奇妙な連帯感でつながった三人は、あてもなく犬吠埼を目指す。ちょうど、人生について投げやりになっていた年長のハルは、若い二人の勢いにあてられ、誰かの続編の物語を生き始める。
そう考えてみると、そもそも私たちの人生も誰かの人生の続編と言えないだろうか。それは生殖によってつながった生物的なつながりという意味ではない。時代や場所や文化は違えど、一人の人生という物語を生きることは、誰かの人生の続きを生きることにほかならない。同じ惑星で生きている限り、人がつむぐ物語は誰かの物語に多かれ少なかれ関連しているのだから。
私たちは本編に出てくるハルたちの物語をどう読むべきだろうか。自分の人生に関係ないとして退けてよいだろうか。作り話だと知らぬふりをすれば良いだろうか。
どれも違う。
彼らの行動は自分たちのひ孫が起こす未来かもしれないし、並行している可能性の現実の中で自分がしでかす暴挙なのかもしれない。
「そして物語に終わりはない。全部の物語の続編にだって。この場面のあとにも場面はずっとずっと続いて。時間は後ろに流れ続けて」(71P)
私たちの人生にも、本来の終わりはない。意識のある生物があり続ける限り。
終わりが来るとすれば、56億7千万年あとに地球が消え去るか、あらゆる原子が一点に終息したビッグクランチの時点だろう。
だが、そんな無意味なことを考えても仕方がない。それより、誰もが誰もの人生の続編を生きていると考えたほうが、生きやすくはないか。著者が本編で提案した物語の意味とは、そういうことだと思う。
「スローモーション」
一人の少女の日記だったはずなのに、それがどんどんと意味を変えていく本編。
さまざまな少女の文体がめまぐるしく変わり生まれてゆく文章は、少女の移ろいやすい意識のあり方そのものだ。
自分と他者。世間と仲間。外見と内面。
少女の意識にとってそれらを区別することは無意味だ。
全てが少女の中で混在し、同じレベルで入れ代わり立ち代わり意識の表層に現れる。
そんな鮮やかな文章の移り変わりを堪能できる。
そして本編はある出来事をきっかけに、少女が過去をつづっていたはずの文章が、現在進行する時間の流れに沿い始める。
それもまた、現実を自我の中に消化しながら生きる少女の意識にとっては、矛盾がなく存在する自分なのだ。
さらに少女の日記はレポートとしての文章から報道としての性格を帯び始める。
その移り変わりは、今の世に氾濫するSNSのあり方を表しているように思える。
人の意識が無数に公開され、自分で自分の感想を報道して飽きない今の世相を。
著者がそれを見越して描いていたとすれば本編のすごさは実感できる。
小説としての可能性も感じさせながら、今の世を切り取って批評する一編だ。
「8ドッグス」
本編のタイトルを日本語に訳すと八犬。
ここから想像できるのは「南総里見八犬伝」だ。
言うまでもなく江戸時代に書かれた日本文学史上に残る作品だ。
仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の文字が書かれた玉を持つ八人が、さまざまな冒険をへて里見家の下に参ずる物語だ。
その有名な物語を背景に奏でつつ、著者が語るのはある男の内面だ。
彼女であるねねを思いつつ、律義に生きる彼の思考の流れはどこか危うさをはらんでいる。
ねねのためといいながら彼が行う行動。それは、八犬伝をもじった刺青を自らに彫るなど、どこか狂気の色を帯びている。
徐々に暴走してゆく狂気は、ねねを見張るところまで突き進んでいく。
そしてそこで知った事実が彼の狂気にさらなる拍車をかけてゆく。
ここで出てくるのは皮膚だ。彼は皮膚に仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の文字を丸で囲って彫り込む。それらの文字は社会で生きる規範となるべき意味を持っている。
だが、それらの文字が皮膚に彫り込まれることで、現実と自我を隔てる境目は破れ、彼の狂気が現実の社会に害を及ぼしていく。
狂気の流れがこれらの文字を通して皮膚へ。それを文学としてメッセージに込めたことがすごい。
‘2020/01/29-2020/01/29