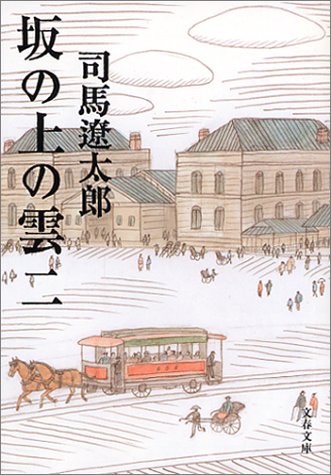
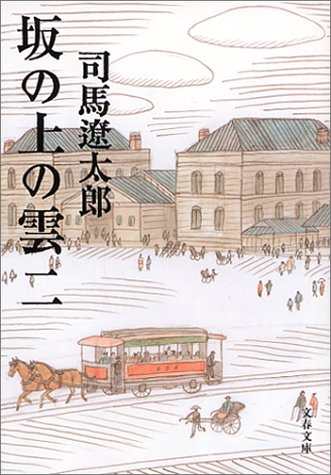
本書では日清戦争から米西戦争にかけての時期を描いている。その時期、日本と世界の国際関係は大いに揺れていた。
子規は喀血した身を癒やすため愛媛で静養したのち、小康状態になったので東京に戻った。だが、松山藩の奨学金給付機関である常盤会を追放されてしまう。
それは、短歌・俳句にうつつをぬかす子規への風当たりが限界を超えたから。
そんな子規の境遇を救ったのが、子規が生涯、恩人として感謝し続けた陸羯南だ。
羯南は子規を自分の新聞社「日本」の社員として雇い入れ、生活の道を用意する。それだけではなく、自らの家の隣に家まで用意してやる。
その恩を得て、子規は俳諧の革新に邁進する。
本書には随所で子規の主張が出てくる。そこではどのように子規が俳諧と短歌の問題を認識し、どう変えようとしたのかがとても分かりやすく紹介されている。
著者は日清戦争がなぜ起きたのかについて分析を重ねる。
日清戦争の勃発に至るまでにはさまざまな理由はある。だが、結局は朝鮮の地政が原因で日中の勢力の奪い合いが起こったというのが著者の見る原因だ。
そこに日本も清国も朝鮮も悪い国はない。ただ時代の流れがそういう対立を産んだとしかいえない。その歴史を著者はさまざまな視点から分析する。
本書には一人の外交官が登場する。小村寿太郎。
日露戦争の幕引きとなるポーツマス条約の全権として、本書の全編に何度か登場する人物だ。
彼の向こう気の強さと努力の跡が本書では描かれる。
そして日本の中国駐在公使代理として着任した小村寿太郎の立場と、朝鮮をめぐる日本と清の綱引きを描く。さらには虎視眈々と朝鮮を狙うロシアの野望を絡めつつ、著者は歴史を進めて行く。
そうした人々の思惑を載せた歴史の必然は、ある時点で一つの方向へと集約され、戦いの火蓋は切られる。
秋山兄弟はそれぞれ陸と海で任務を遂行する。そして本書を通して重要な役割を果たす東郷平八郎は浪速艦長として役割を果たす。
そうした軍人たちに比べ、伊藤博文の消極的な様子はどうだろう。
伊藤博文は、初代の朝鮮統監であり、後年ハルビンで暗殺されたことから、国外からは日本の対外進出を先導した人物のように思われている。だが、実は国際関係には相当に慎重な人物だったことが本書で分かる。
日清戦争の直接のきっかけとなった朝鮮への出兵も、伊藤博文が反対するだろうから、と川上操六参謀次長が独断で人数を増員して進めたのが実際だという。
日清戦争の戦局は、終始、日本の有利に進む。
清国の誇る北洋艦隊は軍隊の訓練度が足りず、操艦一つをとっても日本とは歴然とした差がある。
また、全ての指図が現場の指揮官では判断できず、その都度、北京に伺いを立ててからではないと実行できない。
両国の士気の差は戦う前から明らかであり、そんな中で行われた黄海海戦では日本は圧勝する。そして陸軍は朝鮮半島を進む。さらに旅順要塞はわずか一日で陥ちる。
こうした描写からは、戦争の悲壮さが見えてこない。それは清国の兵に何が何でも国を守るとの気概が見えないからだと著者は喝破する。同時に著者は、満州族を頭にいただく漢民族の愛国意識の欠如を指摘する。だからこそ、日清戦争の期間中、日本と清国の間には膨大な惨禍もおきなければ、激闘も起こらなかったのだろう。
そうした呑気な戦局を遊山気分で見にいこうとしたのが、当時、結核の予後で鬱々とした子規だ。彼はなんとか外の世界を見ようと、特派員の名目で清国の戦場へと向かおうとする。
彼が向かおうとしたタイミングは幸いと言うべきか、ほぼ戦争の帰趨が定まり、戦火も治まりつつある時期だ。
ところが彼は、陸羯南をはじめとした人々が体調を理由に反対したにも関わらず、渡航を強行したことでついに倒れる。それ以降、子規が病床から出ることはなかった。脊椎カリエスという宿痾に侵されたことによって。
そうした子規の行動は、見方によっては呑気に映る。だが、その行動は別の視点からみれば、明治の世にあって激しく自分の生を生きようとした子規の心意気と積極的にとらえることも可能だ。
威海衛の戦いでは海軍が圧勝し、日清戦争は幕を閉じる。それを見届けて真之はアメリカにゆき、米西戦争を観戦する。
そこで彼が得た知見は後年の日露戦争で存分に生かされる。
その知見とは、例えば、港に敵艦隊を閉じ込めるため、わざと船を港の入り口に沈める作戦を見たことだ。
また、米西戦争の観戦レポートの出来栄えがあまりに見事で、それが真之を上層部に取り立てられるきっかけになる。
そうしているうちに、事態は独仏露による三国干渉へと至る。
三国干渉とは、日本が清国から賠償で受け取った遼東半島を清国へと返却するよう求めた事件だ。そこには当然、ロシアの満州・朝鮮への野心がむき出しになっている。そのシーンで著者は、ロシアのヴィッテの嘆きを紹介する。
ヴィッテ曰く、ロシアの没落は三国干渉によって始まったとのことだ。ヴィッテ自身の持論によれば、ロシアはそこまで極東への野心を持ってはならないとのこと。だが、その思いはロシア皇帝ニコライ二世やその取り巻きには理解されず、それが嘆きとして残ったという。
なぜ、ロシアが極東に目を向け始めたのか。
そうした地理の条件からの説明を含め、著者は近世以降のロシアの歴史を説き起こしてゆく。そして、今に至るまでのロシアの状況を的確に彫りだしてゆく。
それによれば、西洋の進歩に乗り遅れた劣等感がロシアにはあった。当時のロシアは、社会に制度が整っていないこと。官僚主義が強いこと。そして、政府の専制の度合いが他国に比べて厳しいこと。さらに、不凍港を求めるあまり、極東へ進出したいというあからさまな野心が見えていること。最後に、ニコライ二世が、訪日時に津田三蔵巡査によって殺されかけたことから、日本を野蛮な猿として軽んじていたこと、などを語っていく。
そうして、日本とロシアの間に戦いの予感が漂っていく。そんな緊迫した中、意外なことにロシアは日本との戦いを予想していなかったという。それはロシアにとってみれば、日本の国力があまりにも小さいため、どれだけロシアが極東に圧力をかけようとも、日本がロシアに戦争を挑むはずがない、と高をくくっていたからだ。もちろん、歴史が語るとおり、日本は世界中の予想を跳ね返してロシアに戦いを挑むわけだが。
当時の日本がどれだけ世界の中で認識されていなかったか。そしてどれだけ侮られていたか。それなのに、日本にとってはどれだけロシアの圧力が国の存亡をかけたものととらえられていたか。風雲は急を告げる中、著者は次の巻へと読者をいざなう。
‘2018/12/7-2018/12/11



