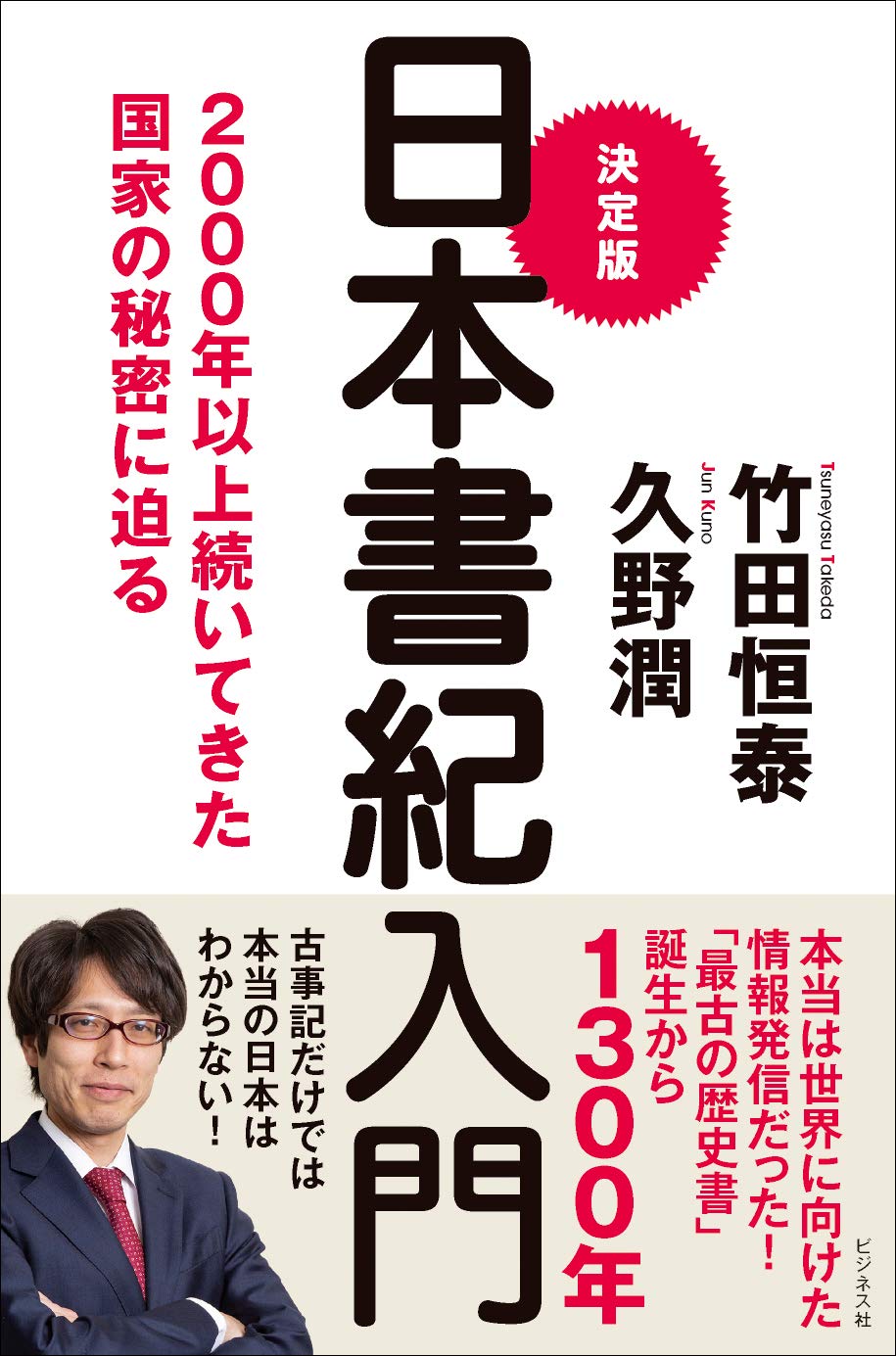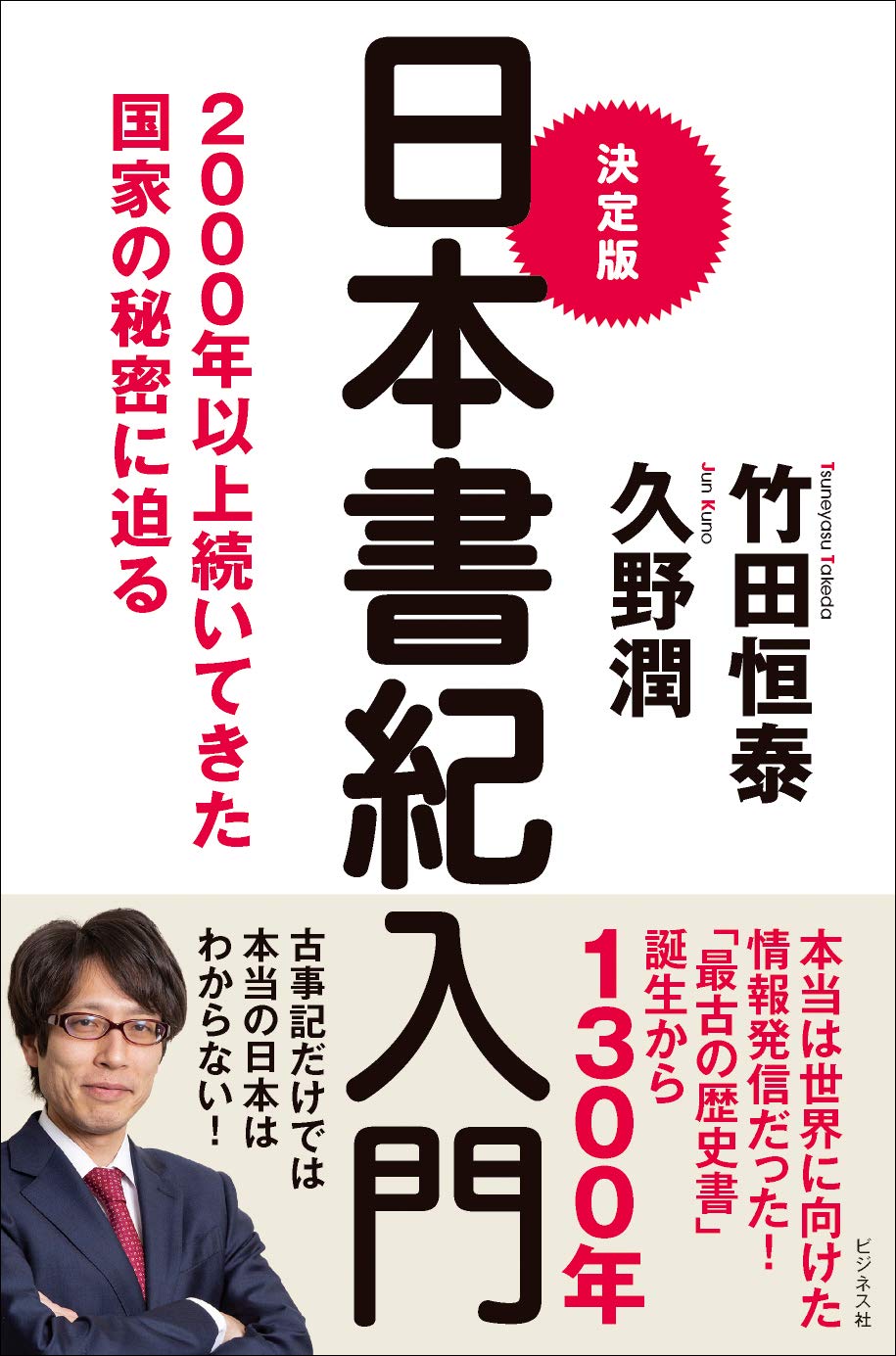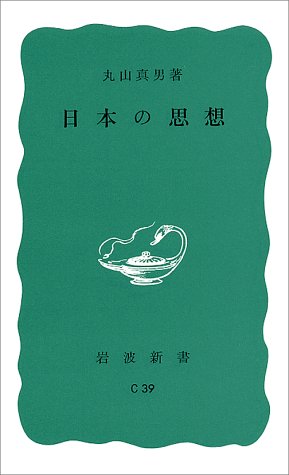毎年この時期になると、昭和史に関する本を読むようにしている。
その中でも著者については、そのバランスのとれた史観を信頼している。
当ブログでも著者の作品は何回もとり上げてきた。
ただ、著者は昭和史を概観するテーマでいくつも本を出している。私もそのいくつ下には目を通している。概要を論じる本からは、さすがにこれ以上斬新な知見には出会えないように思う。私はそう思い、本書の新鮮さについてはあまり期待せずに読み始めた。
本書は、昭和史を概観しながら、時代の仕組みや流れを数学の図形になぞらえ、その構造がなぜ生まれたのか、その構造のどこがいびつだったのかを解き明かす試みだ。
つまり、文章だけだと理解しにくい日本の近代史と社会の構造を、数学の図形という媒体を使って、読者にわかりやすく示そうとする狙いがある。
図形を媒体として取り扱うことによって、読者は脳内に論旨をイメージしやすくなる。そして、著者を含めた数多くの識者が今まで語ってきた昭和の歪みがなぜ生じたのかの理解が促される。
図形に変換する試みは、私たちが事象を理解するためには有用だと思う。
そもそも、私たちは文章を読むと同時に頭の中でいろんな手段を用いて理解する。人によっては無意識に図形を思い浮かべ、それに文章から得たイメージを投影したほうが理解しやすいこともあるだろう。本書はそのイメージを最初から文章内に記すことによって、読者の理解を促そうという狙いがある。
私たちは昭和の教訓から、何を読み取ればいいのか。それを図形を通して頭に刻み込むことで、現代にも活かすことができるはずだ。
例えば第一章は、三角錐を使っている。
著者は昭和史を三期に分け、それぞれの時期の特色を三角錐の側面の三辺に当てはめる。
その三角錐の一面には戦前が、もう一面は占領期、残りの一面は高度経済成長の日本が当てはめられる。そして、それぞれの面を代表する政治家として、戦前は東條英機、占領期は吉田茂、高度経済成長期に田中角栄を置く。
ここに挙げられた三人に共通する要素は何か。
それは、アメリカとの関係が経歴の多くを占めていることだ。東條英機はアメリカと戦い、吉田茂は占領国であるアメリカとの折衝に奔走し、田中角栄はアメリカが絡んだロッキード事件の当事者。
三角錐である以上、底面を形作る三角形も忘れてはならない。ここにアメリカもしくは天皇を置くことで、昭和と言う激動の時代の共通項として浮かび上がってくる。
図形で考えてみると確かに面白い。
三角錐の底辺に共通項を置くことで、読者は昭和史の特徴がより具体的に理解できるのだ。
本書の狙いが見えてきた。
続いて著者は正方形を取り上げる。
具体的には、ファシズムが国民への圧迫を行う手法を、四つの柱に置き換える。
四つの柱がそれぞれ情報の一元化(大本営発表)、教育の国家主義化(軍人勅諭・戦陣訓)、弾圧立法の制定と拡大解釈(戦時下の時限立法)、官民あげての暴力(懲罰招集)に擬せられ、正方形をなすと仮定する。
その四つの辺によって国民を囲い、ファシズムに都合の良い統治を行う。
反ファシズムとは正方形の一辺を破る行為であり、それに対するファシズムを行う側は、正方形を小さく縮めて国民を圧してゆく。
当然のことながら、檻の中に飼われたい国民などいるはずもない。正方形の怖さを著者は訴える。今の右傾化する世相を憂いつつ。
続いては直線だ。
著者はイギリスの歴史家・評論家のポール・ジョンソンの評を引用する。著者が引用したそのさらに一部を引用する。
「発展を線的にとらえる意識はほとんど西洋的といってよく、点から点へ全速力で移動する。日本人は時間とその切迫性を意識しているが、これは西洋以外の文化ではほとんど例を見ないもので、このため日本の社会では活力が重視される」
著者は戦前の軍国化の流れと、池田勇人内閣による所得倍増政策と、戦後初のマイナス成長までの間を、一直線に邁進した日本として例える。まさに的を射た比喩だと思う。
続いては三角形の重心だ。
三角形を構成する三点は、天皇、統帥権、統治権になぞらえられている。
このバランスが軍の暴走によって大きく崩れたのが戦前の日本とすれば、三角形を持ち出した著者の意図は明確だ。三点の動きによっていびつになる様子が理解できるからだ。
統帥権の名のもとに天皇を利用し、なおかつ統治権を無視して暴走したのが戦前の軍部であり、軍部の動きが著者の描く三角形の形を大きく崩してゆく。
天皇を三角形の頂点にし、左下の一点だったはずの頂点が上に移動し、天皇をも差し置いて高みに登ろうとしたのが戦前のわが国。著者はそもそも三角形の上の頂点が天皇ではなく統帥権にすり替わっていたのではないか、とすらいう。不敬罪が適用されるべき対象とは、あるいは戦前の軍部なのかもしれない。
続いて著者が取り上げるのは、三段跳びだ。ここにきて数学とは離れ、スポーツの概念が登場する。
ところが、著者は戦前の若手将校の超量が飛躍していく様を三段跳びと称し、増長に増長を重ねる動きを当てはめる。
そろそろ図形のネタが尽きてきたようにも思えるが、著者はさらに虚数の概念まで持ち出す。
そもそもの思想の根幹が虚があり、それゆえに数字を乗じようと掛けようと足そうと、何物も生まれない軍部の若手将校に痛烈な皮肉を浴びせている。三段跳びも踏み板が虚無であれば飛べないのだ。
続いては球。
完全無欠の球は、坂道を転がり始めると加速度がつく。これは物理学の初歩の初歩だ。
ここで言う加速度とは、魂の速度が無限に増える事象を示す。ちょうど戦争へ向けたわが国のように。著者のいう球は日本が突入していく戦争と破滅の道の上を走る。
著者は、「昭和という時代を詳細に見ていると、意外なほどに社会に波乱が少ない。」(85p)と言う。つまり、著者に言わせれば昭和とは、完全な球のような状態だったという。だからこそいちど弾みがついた球は誰にも止めようがなく、ひたすら破滅の淵に向かって突き進んでいったのだろう。
では、球に勢いをつけるためには、どういう成果があれば良いだろうか。それは派手な緒戦の大戦果だ。真珠湾攻撃はまさにそうして望まれた。
その決断は、わずか重職にある数人が知っていたにすぎない。この大戦果によって、国のムードは一気に最高潮になり普段は理性的なはずの文士ですら、われを忘れて喜びを連呼する。
その球の内部には、何があったのか。実は何もなかった。ただ目的もなく戦争を終わらせる見通しすらないまま、何かに向かって行動しようとしていた見栄だけがあった。
転げ落ちた球はどこかでぶつかり、大きく破壊される。まさにかつての日本がそうだったように。
S字曲線。
著者が次に持ち出すS字曲線は、言論を対象とする。
S字曲線と言えば、関数のややこしい式でおなじみだ。
縦横の座標軸で区切られた四つの領域を曲がりくねったS字曲線はうねる。そして時代の表と裏を進む。戦前のオモテから戦後のウラへと。戦前のウラから戦後のオモテへと。
敗戦をきっかけにがらりと変わったわが国の思想界。著者はそれを、オモテの言論とウラの言論と言い表す。
戦後になって太平洋戦争と呼ばれるようになったが、敗戦までは大東亜戦争と称していた。その言い方の違いは、国が、戦争の大義と言い方のレトリックに過ぎない。
著者は最近、右傾化が進むわが国を歴史修正主義という言葉を使って批判する。そうした思想の論じられ方一つで、歴史の表と裏が繰り返されると言いたいかのようだ。S字曲線のように。
著者が続いて取り上げるのは座標軸だ。
座標軸とは、戦争に参加した人々が自らの戦争体験を表す場合、どのような階級、どこの組織に所属していたかによって分布を見る際の基準となる。多くの人々によって多様な戦争の体験が語られているか。それを著者は分布図を使って分析する。
例えば、後方から戦術を立案する高級将校による体験記の記述の場合、そうした現場を知らない人々が語る言葉には、実際の戦争の姿が描かれていないと批判する。
それに比べ、最前線で戦った戦士の手記が世に出ることは驚くほど少ないと著者は指摘する。
そうした不公平さも、分布図に表すと一目瞭然だ。
続いて自然数。
ここでいう自然数とは正の整数の中で、1と素数と合成数からなる数だ。
1は自分自身しか約数がない。素数は自分と1以外に約数のない数だ。合成数は約数が3つ以上からなる数だ。
つまり数を構成する要素がどれだけあるかによって、その対象を分析しようという試みだ。
多彩な要素が組み合わさった複雑な要素、つまり約数が多くあればあるほど、その要素となった数の要素は色濃く現れる。例えば、素数のように約数が少ない関係は、二国間の国民間の友好的交流がない状態と例える。逆に合成数が多い場合、二国間の国民間には、さまざまな場面での交流がある状態と例える。
多彩な交流があればあるほど、二国間の友好度は盤石なものとみなせる。
だが、素数のように要素となる数が少なければ少ないほど、政府間の交渉が決裂した途端、他に交流をつなぎ留めるものもなくなる。つまり、国交断絶状態だ。
かつての日本とアメリカの関係は、戦争の直前には素数に近い状態になっていた。今の日本と中国、日本と韓国、日本と北朝鮮の関係もそう。
この分析は、なかなか面白いと思った。
本書のほかでは見かけたことのない考えだ。ここに至って、著者の試みる国際関係や歴史を数学の概念で表す試みは、成功したと言える。
最終章は、平面座標。
ここで著者は、昭和天皇の戦争責任を題材に取り、天皇が法律的・政治的・歴史的・道義的・社会的に、どのフェーズにおいて責任があるかをマトリックスにして分析する。
責任のフェーズとは、臣民の生命を危機に陥れた、臣民に犠牲を強いた、終戦、敗戦、継戦、開戦のそれぞれを指す。
著者のこの分析は、著者の他の本でも見かけたことがある。
| 昭和天皇が考えていたと思われる戦争責任 |
|
法律的 |
政治的 |
歴史的 |
道義的 |
社会的 |
| 臣民の生命を危機に陥れた |
△ |
△ |
━ |
○ |
○ |
| 臣民に犠牲を強いた |
△ |
△ |
━ |
○ |
○ |
| 終戦 |
△ |
△ |
○ |
○ |
△ |
| 敗戦 |
△ |
△ |
○ |
△ |
△ |
| 継戦 |
△ |
△ |
○ |
○ |
△ |
| 開戦 |
△ |
△ |
○ |
△ |
△ |
| 昭和天皇が考えていたと思われる戦争責任(保阪案) |
|
法律的 |
政治的 |
歴史的 |
道義的 |
社会的 |
| 臣民の生命を危機に陥れた |
○ |
○ |
━ |
○ |
○ |
| 臣民に犠牲を強いた |
○ |
○ |
━ |
○ |
○ |
| 終戦 |
△ |
○ |
━ |
○ |
○ |
| 敗戦 |
△ |
○ |
━ |
○ |
○ |
| 継戦 |
△ |
○ |
━ |
○ |
○ |
| 開戦 |
○ |
○ |
━ |
○ |
○ |
上記の表の通り、著者は昭和天皇に相当多くの戦争の責任があった、と考えている。
ただし、この図を見る限りでは厳しく思えるが、当初は戦争に反対していた天皇の心情はこの章の中で、著者は十分に汲み取っているのではないか。
私は個人的には昭和天皇には戦争責任はあると思う立場だ。それはもちろん直接的にではなく、道義的にだ。
もちろん、昭和天皇自身が戦争を回避したがっていた事や、消極的な立場だったことは、あまたの資料からも明らかだろう。
そこから考えると、私が思う天皇の政治責任は天皇自身が考えていたようなマトリックス、つまり上の図に近い。
読者一人一人が自らの考えを分析し、整理できるのも、本書の良さだと言える。
‘2019/9/1-2019/9/4