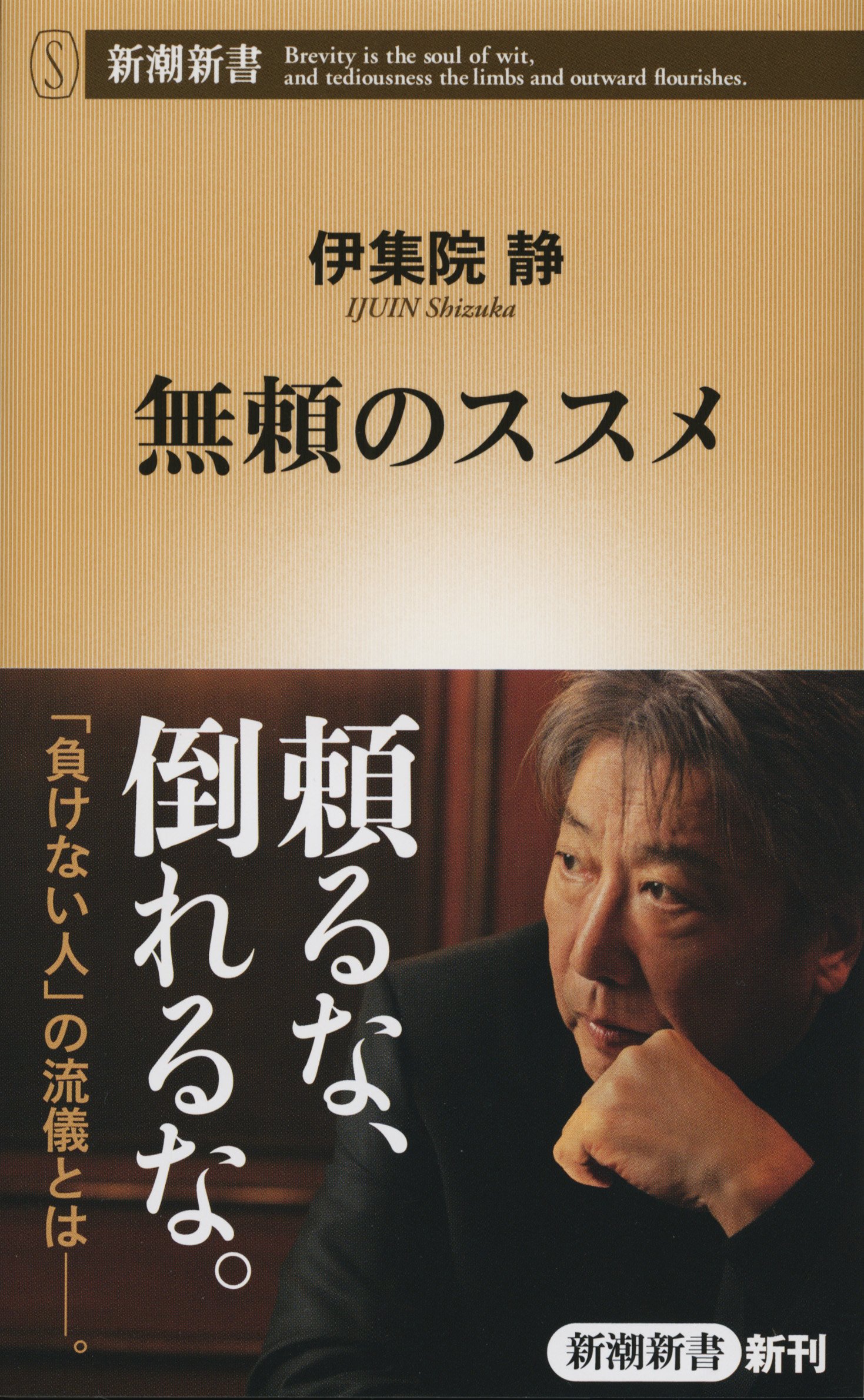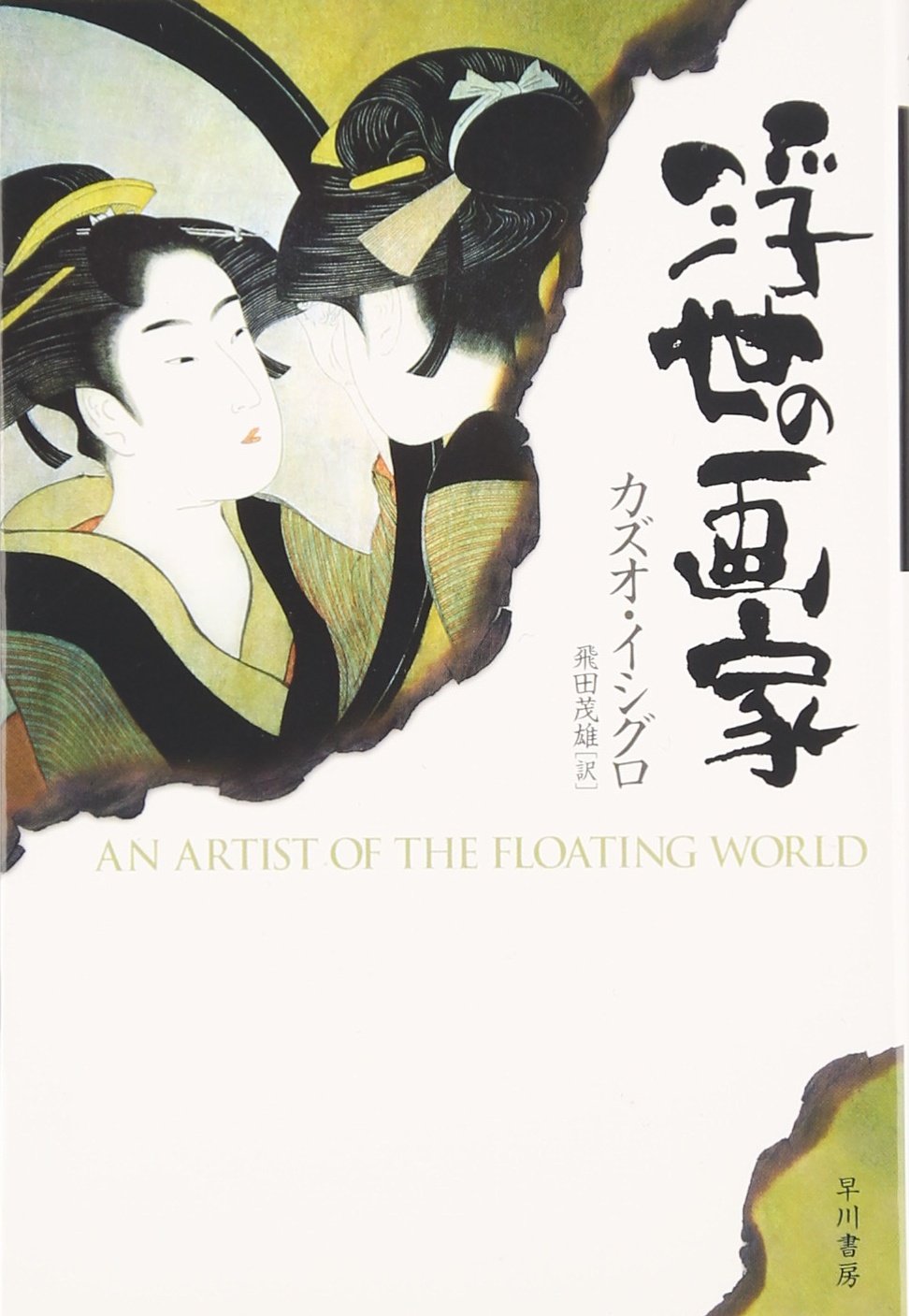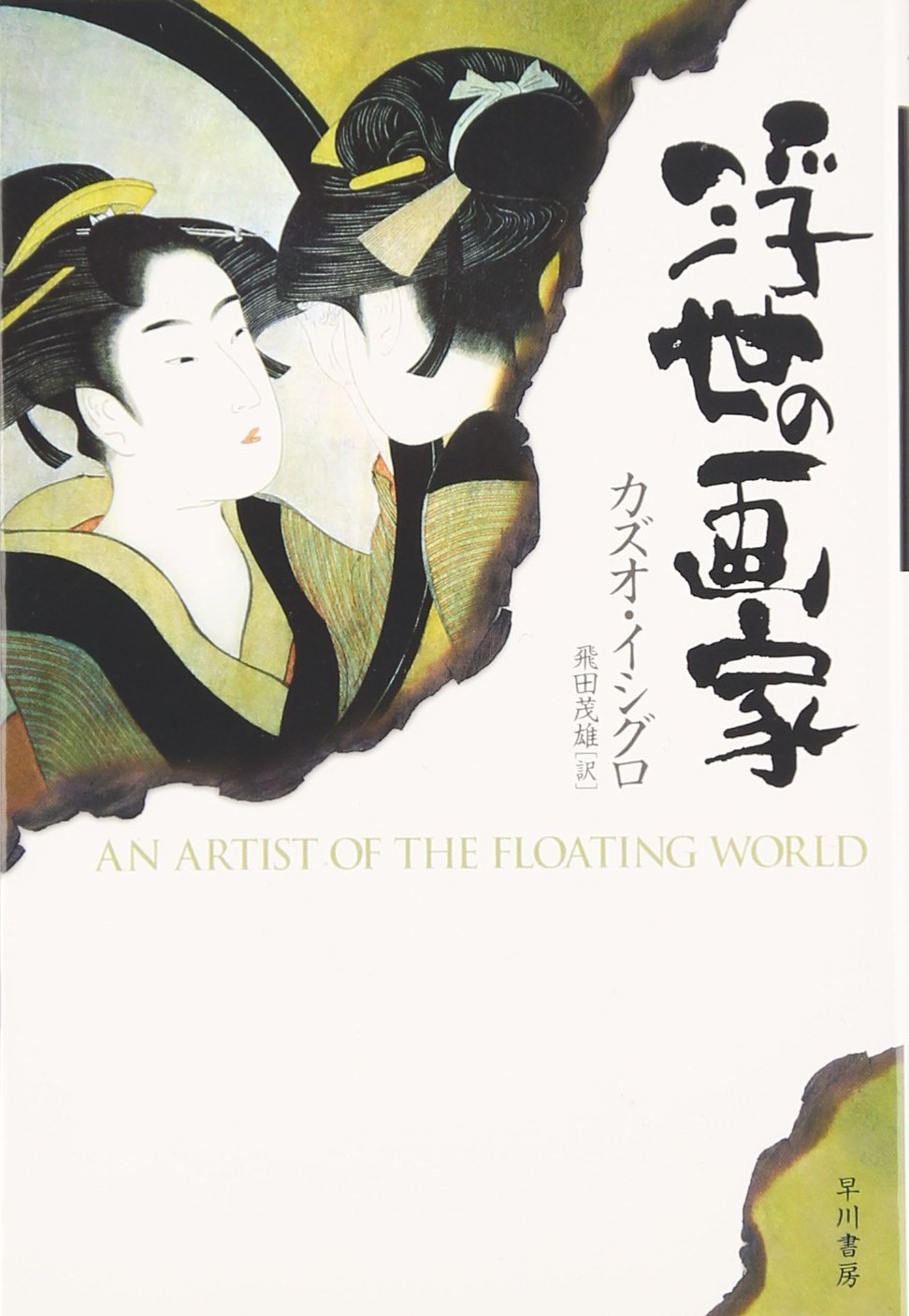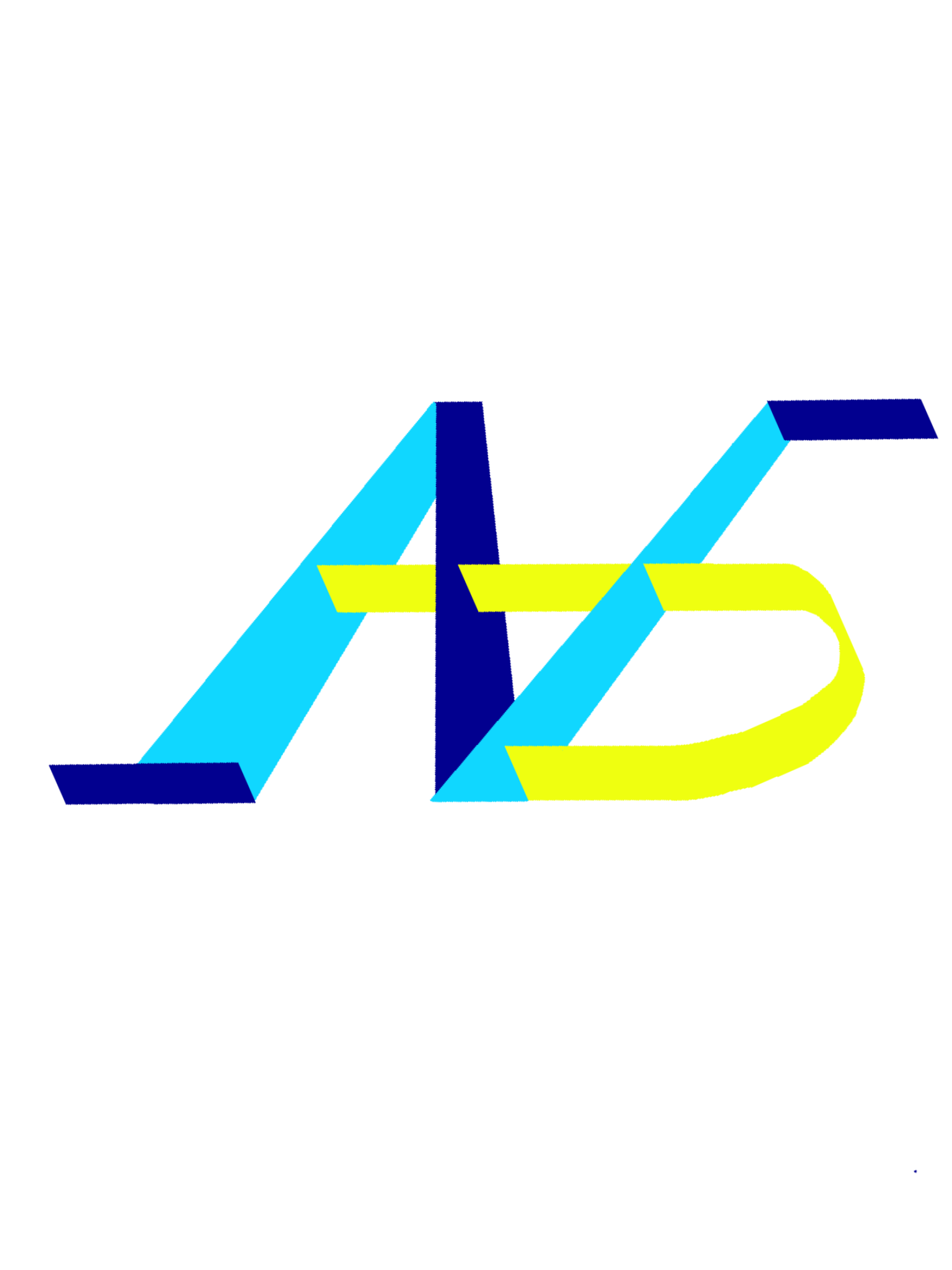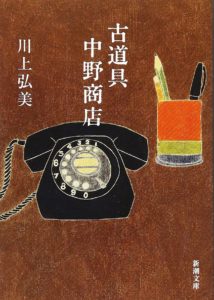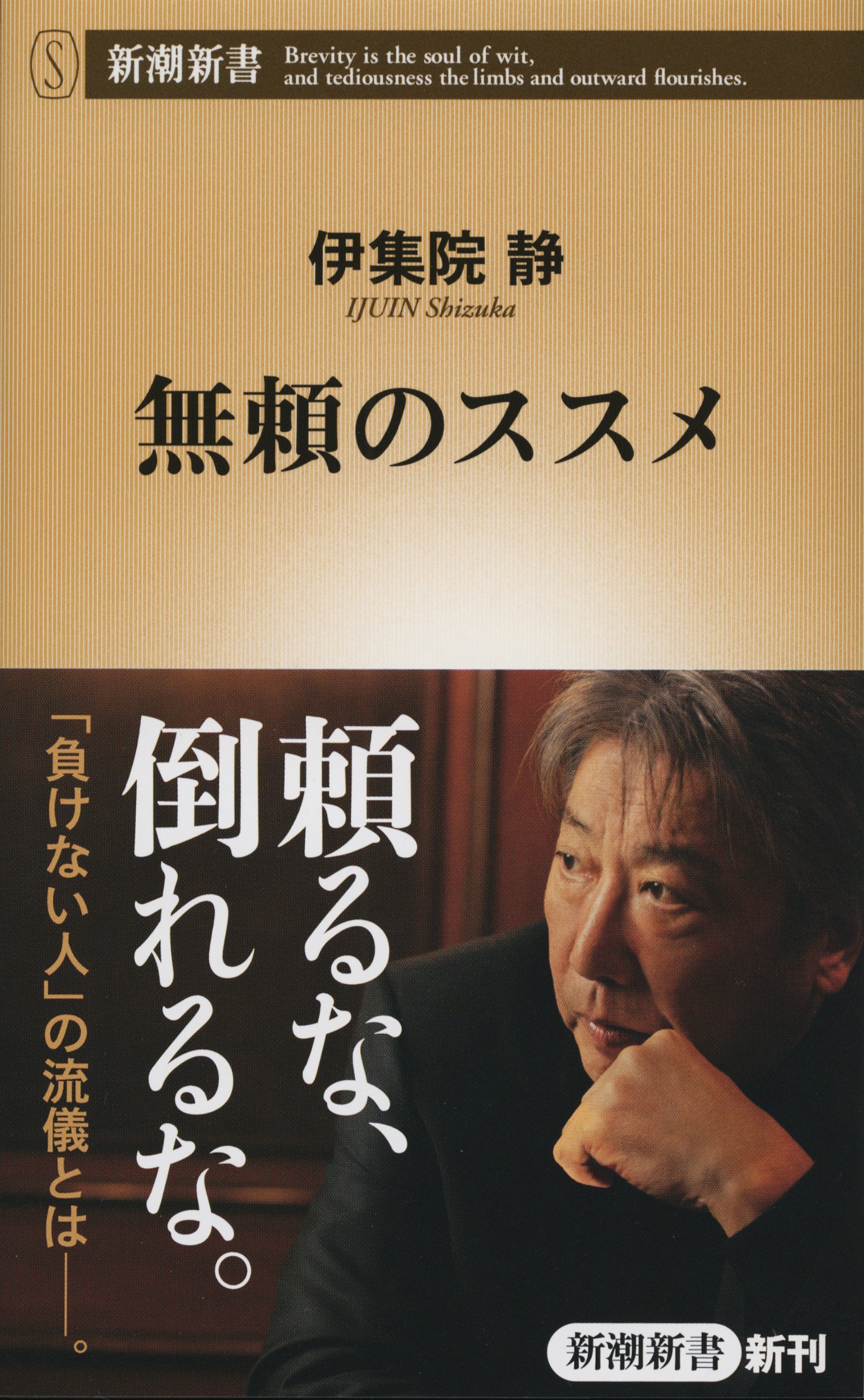
私は独り。一人で生まれ、独りで死んでいく。
頭で考えれば、このことは理解できるし受け入れられる。だが、孤独でいることに耐えられる人はそう多くない。
独りでいることを受け入れるのは簡単ではない。
群れなければ。仲間といなければ。
新型コロナウイルスの蔓延は、そうした風潮に待ったをかけた。
独りで家にこもることが良しとされ、群れて酒を飲むことが悪とされた。
コロナウイルスのまん延は、独りで生きる価値観を世に問うた。
孤独とは誰にも頼らないこと。つまり無頼だ。
無頼。その言葉にはあまり良いイメージがない。それは、無頼派という言葉が原因だと思われる。
かつて、無頼派と呼ばれた作家が何人もいた。その代表的な存在として挙げられるのは、太宰治と坂口安吾の二人だろう。
女性関係に奔放で、日常から酒やドラッグにおぼれる。この二人の死因は自殺と脳出血だが、実際は酒とドラッグで命を落としたようなものだ。
既存の価値観に頼らず、自分の生きたいように生きる。これが無頼派の狭い意味だろう。
本書のタイトルは、無頼のススメだ。
著者は、広い意味で無頼派として見なされているそうだ。ただ、私にとって無頼派のイメージは上に挙げた二人が体現している。正直、著者を無頼派の作家としては考えていなかった。
だが、そもそも作家とは、この現代において無頼の職業である事と言える。
ほとんどの人が組織に頼る現在、組織に頼らない生き方と言う意味では作家を無頼派と呼ぶことはありだろう。
今の世の中、組織に頼らなければやっていけない。それが常識だ。だが、本当に組織に頼ってばかりで良いのだろうか。
組織だけではない。
そもそも、既存の価値観や世の中にまかり通る常識に寄りかかって生きているだけでよいのだろうか。
著者は、本書においてそうした常識に一石を投じている。
人生の先達として、あらゆる常識に頼らず、自分の生き方を確立させる。著者が言いたいのはこれだろう。
著者はそもそも出自からしてマイノリティーだ。
在日韓国人として生を受け、厳しい広告業界、しかも新たな価値を創造しながら、売り上げにつなげる広告代理店の中で生き抜いてきた人だ。さらには作家としても大成し、ミュージシャンのプロデュースにまで幅を広げている。著者が既存の価値観に頼っていれば、これだけの実績は作れなかったはず。
そんな著者の語る内容には重みがある。
「正義なんてきちんと通らない。
正しいことの半分も人目にはふれない。
それが世の中というものだろうと私は思います。」(19ページ)
正義を振りかざすには、それが真理であるとの絶対の確信が必要。
価値観がこれほどまでに多様化している中、そして人によってそれぞれの立場や信条、視点がある中、絶対的な正義など掲げられるわけがない。
また、著者は別の章では「情報より情緒を身につけよ」という。
この言葉は、情報がこれほどまでに氾濫し、情報の真贋を見抜きにくくなった今の指針となる。他方で情緒とは、その人が生涯をかけて身に付けていくべきものだ。そして、生きざまの表れでもある。だからこそ、著者は情緒を重視する。私も全く同感だ。
ノウハウもやり方もネットからいくらでも手に入る世の中。であれば、そうした情報に一喜一憂する必要はない。ましてや振り回されるのは馬鹿らしい。
情報の中から自分が必要なものを見極め、それに没頭すること。全く同感だ。
そのためには、自分自身の時間をきちんと持ち、その中で自分が孤独であることを真に知ることだ。
著者は本書の中で無頼の流儀についても語っている。
「「酒場で騒ぐな」と言うのは、酒場で大勢で騒ぐ人は、他人とつるんでヒマつぶしをしているだけだからです。」(64ページ)
「人をびっくりさせるようなことをしてはいけない。」(65ページ)
「人前での土下座、まして号泣するなんて話にもならない。」(65ページ)
「「先頭に立つな」というのも、好んで先頭に立っている時点ですでに誰かとつるんでいるから。他人が後からついてくるかどうかなんて、どうでもいいだろう。」(65ページ)
老後の安定への望みも著者はきっぱりと拒む。年金や投資、貯蓄。それよりも物乞いせず、先に進む事を主張している。
「「私には頼るものなし、自分の正体は駄目な怠け者」」(96ページ)
そう自覚すれば他人からの視線も気にならない。そして、独立独歩の生き方を全うできる。冒頭で著者が言っている事だ。
そもそも著者は、他人に期待しない。自分にも期待しない。
人間は何をするかわからない生き物だと言い切っている。
「実際、「いい人」と呼ばれる人たちのほうが、よっぽど大きな害をなすことがあるのが世の中です。」(107ページ)
著者は死生観についても語っている。
「自分が初めて「孤」であると知った場所へと帰っていくこと。」(130ページ)
「なぜ死なないか。
それは自分はまだ戦っているからです。生きているかぎり、戦いとは「最後まで立っている」ことだから、まだ倒れない。」(131ページ)
本書は一つ一つの章が心に染みる。
若い頃はどうしても人目が気になる。体面も気にかけてしまう。
年月が過ぎ、ようやく私も経営者となった。娘たちは自立していき、自分を守るのは自分であることを知る年齢となった。
これからの人生、「孤」を自分の中で築き上げていかねばならないと思っている。
努力、才能、そして運が左右するのがそれぞれの人生。それを胸に刻み、生きていきたい。
著者は運をつかむ大切さもいう。時代と巡り合うことも運。
私の場合は技術者としてクラウドの進化の時代に巡りあえた。それに職を賭けられた運に巡り合えたと思う。
だが、著者は技術そのものについても疑いを持つ。
「技術とは、人間が信じるほどのものではなくて、実は曖昧で無責任なものではないか。
技術革新と進歩には夢があるように聞こえるけれど、技術を盲信するのは人間として堕落しているということではないか。私は、人類みんなが横並びで進んでいくような技術の追求は、いつか大きな失敗をもたらすような気がしてなりません。」(174ページ)
私もまだまだ。人間としても技術者としても未熟な存在だ。多分、ジタバタしながら一生を生き、そして最後に死ぬ。
そのためにも、何物にも頼らず生きる。その心持だけ常に持ちたいものだ。とても良い一冊だと思う。
2020/9/1-2020/9/1