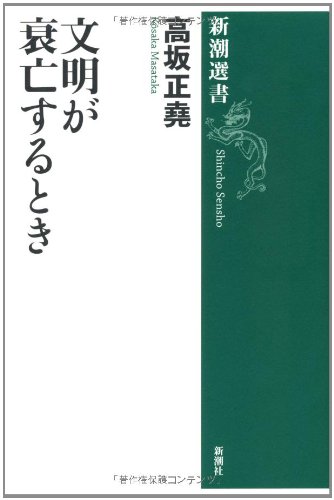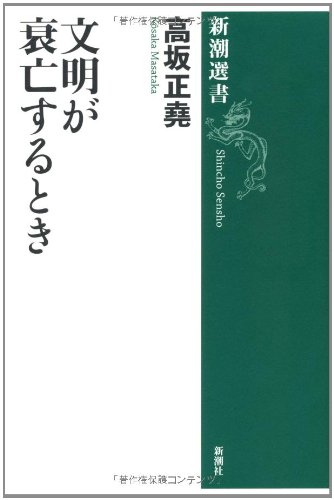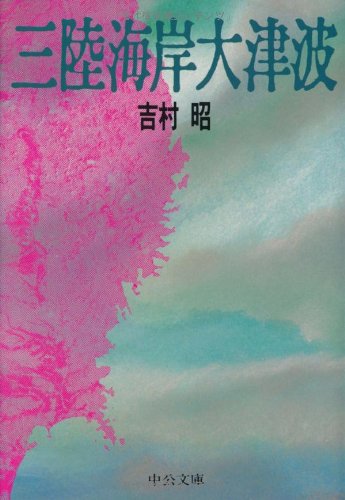今日は76回目の終戦記念日です。
おととしにこのような記事をアップしました。今年も思うところがあり、振り返ってみようと思います。
なぜそう思ったか。それは今日、昭和館を訪れ、靖国神社に参拝したからです。
今年は初めて終戦記念日に靖国神社に参拝しました。その前には近くにある昭和館を訪れました。こちらも初訪問です。
さらにここ最近に読んでいる本や、レビューに取り上げた書物から受けた感化もありました。そうした出来事が私を投稿へと駆り立てました。
つい先日、東京オリンピックが行われました。ですが、昨今の世相は新型コロナウィルスの地球規模の蔓延や地球温暖化がもたらした天災の頻発、さらなる天災の予感などではなはだ不透明になっています。本来、オリンピックは世界を一つにするはず。ですが排外主義の台頭なども含め、再び世界が分裂する兆しすら見えています。
なぜ太平洋戦争に突入してしまったのか。私たちはその反省をどう生かしていけばいいのか。
戦争を再び繰り返してはならないのは当たり前。それを前提として、自分なりに考えてみました。
太平洋戦争を語る際に必ずついて回るのは、1929年のウォール街の株価大暴落に端を発する昭和恐慌であり、第一次世界大戦の戦後処理の失敗から生まれたナチスの台頭です。
当時のわが国は恐慌からの打開を中国大陸に求めました。それが中国からの視点では、満州事変から始まる一連の侵略の始まりだったことは言うまでもありません。
しかも中国への侵略がアメリカの国益を損なうと判断され、ABCD包囲網からハル・ノートの内容へと追い込まれたことも。ハル・ノートが勧告した内容が満州事変の前に状況を戻すことであり、それを受け入れられなかった指導層が戦争を決断したことも知られたことです。
結局、どちらが悪いと言うよりも、恐慌に端を発した資源獲得競争の中で生じた国際関係の矛盾が、戦争につながった。それは確かです。真珠湾攻撃を事前にアメリカ側が知っていたことは確かでしょうし、在米領事館の失態で宣戦布告交付が遅れたとしても。
一年くらいなら暴れてみせると言った山本五十六司令長官の半ばバクチのような策が当たり、太平洋戦争の序盤の大戦果につながったことも周知の通りです。
私は、そこまでのいきさつは、仕方がないと思っています。では、これからの私たちは敗戦の何を教訓にすれば良いのでしょうか。
私は三つを挙げられると思っています。
まず、一つ目は戦を始める前に、やめ時をきちんと決めておかなかったこと。
二つ目はトップがそれまでの出来事を覆す決断力を欠いていたこと。
さらに三つ目として、兵隊の統率の問題もあると考えています。
山本司令長官が、開戦前に一年と決めていたのなら何があろうと一年でやめるべきだったはずです。それをミッドウェイ海戦で敗戦した後もずるずると続けてしまったのが失敗でした。この時に軍部や新聞社の作る世論に惑わされず終戦の決断を速やかにしておけば。悔いが残ります。
また、日露戦争の際には国際法を遵守し、捕虜の扱いについても板東収容所のように模範となる姿勢をとれた日本軍が、日中戦争にあたっては軍紀が大きく崩れたことも悔やまれます。
経済の打開を求めて中国に進軍したのであれば、絶対に略奪行為に走ってはならばかったはず。侵略された側から三光作戦と呼ばれるきっかけを与えたら大義が崩れてしまいます。それも悔やんでも悔やみきれない失敗です。
そうした教訓をどう生かすか。
実は考えてみると、これらは今の私に完全に当てはまる教訓なのです。
経営者として広げた業務の撤退は考えているか。失敗が見えた時に色気を出さず決断ができるか。また、従業員に対してきちんと統制がとれているか。教育をきちんと行えているか。
私が仮に当時の指導者だったとして考えても同じです。戦の終わりを考えて始められただろうか。軍の圧力を押しのけて終わらせる決断ができただろうか。何百万にも上る軍の統率ができただろうか。私には全く自信がありません。
ただ、自分で作った会社は別です。自分で作って会社である以上、自らの目の届く範囲である今のうちにそれらができるように励まなければと思うのです。
ただ、その思索の過程で、わが国の未来をどうすべきかも少しだけ見えた気がしました。
まず前提として、わが国の地理の条件から考えても武力で大陸に攻め込んでも絶対に負けます。これは白村江の戦いや、豊臣秀吉による文禄・慶長の役や、今回の太平洋戦争の敗戦を見ても明らかです。
であれば、ウチに篭るか、ソトに武力以外の手段で打って出るかのどちらかです。
前者の場合、江戸時代のように自給自足の社会を築けば何とかなるのかもしれません。適正な人口を、しかもピラミッド形を保ったままであれば。多分、日本人が得意な組織の力も生かせます。
ただし、よほど頭脳を使わないと資源に乏しいわが国では頭打ちが予想されます。おそらく、群れ社会になってしまうことで、内向きの論理に支配され、イノベーションは起こせないでしょうね。世界に対して存在感を示せないでしょうし。
ソトに出る場合、日本人らしい勤勉さや頭脳を駆使して海外にノウハウを輸出できると思います。
日本語しか使えない私が言うのはふさわしくないでしょうけど、私はこちらが今後の進む道だと思っています。今までに日本人が培われてきた適応力はダテではないからです。あらゆる文明を受け入れ、それを自分のものにしてきたわが国。実はそれってすごいことだと思うのです。
日本人は、組織の軛を外れて個人で戦った時、実は能力を発揮できる。そう思いませんか。今回のオリンピックでも見られたように、スポーツ選手に現れています。
ただ、そのためには起業家マインドが必要になるでしょう。組織への忠誠を養うのではなく、自立心や自発の心を養いたいものです。ただし、日本人の今までの良さを保った上で。
固定観念に縛られるのは本来のわが国にとって得意なやり方でないとすら思えます。
私は、今後の日本の進む道は、武力や組織に頼らず個人の力で世に出るしかないと思います。言語の壁などITツールが補ってくれます。
昭和館で日本の復興の軌跡を見るにつけ、もう、この先に人口増と技術発展が重なるタイミングに恵まれることはないと思いました。
そのかわり、復興を成し遂げたことに日本人の個人の可能性を感じました。
それに向けて微力ながらできることがないかを試したい。そう思いました。
任重くして道遠きを念い
総力を将来の建設に傾け
道義を篤くし 志操を堅くし
誓って国体の精華を発揚し世界の進運に後れざらんことを期すべし