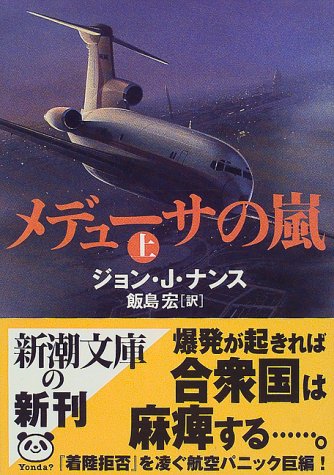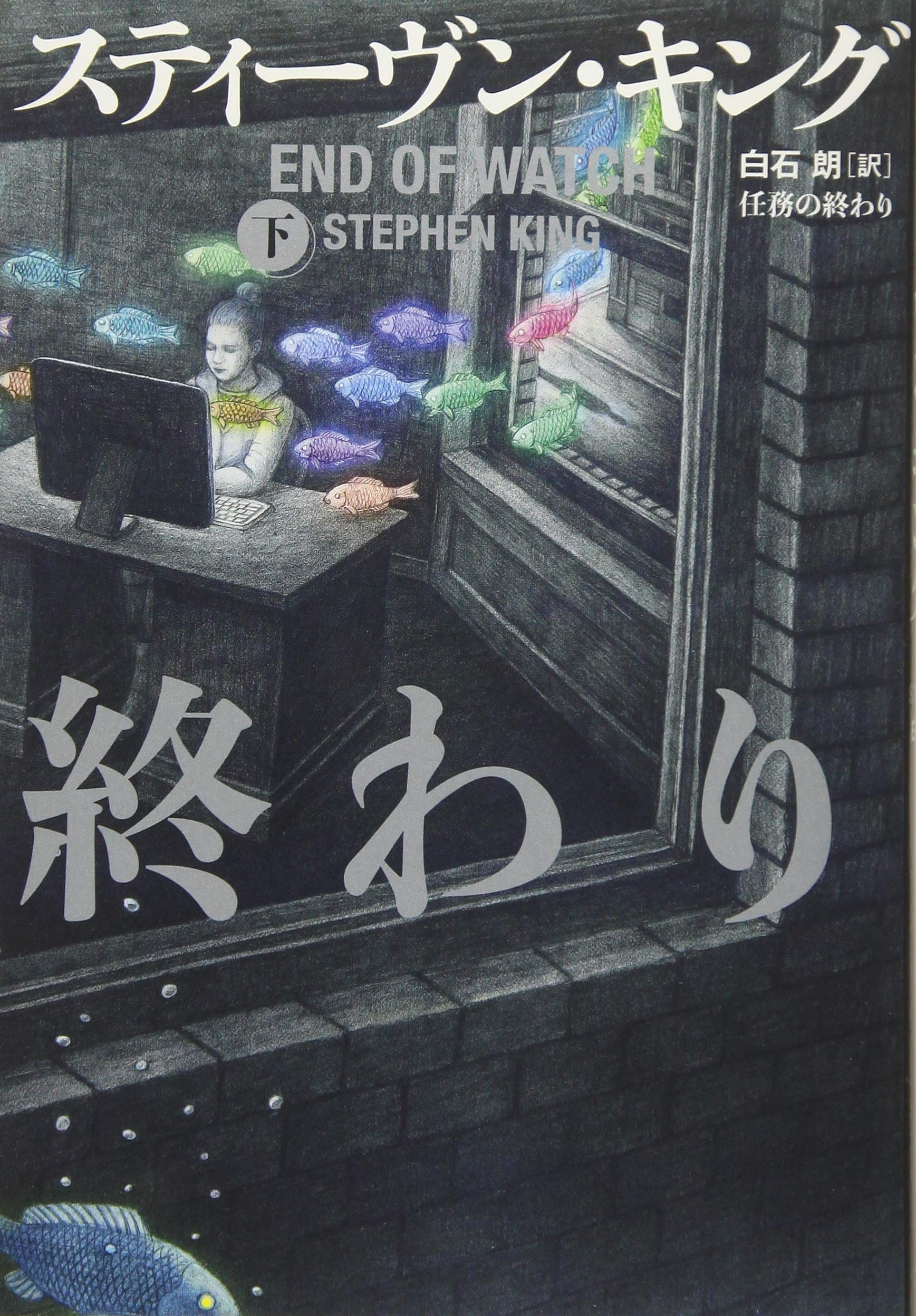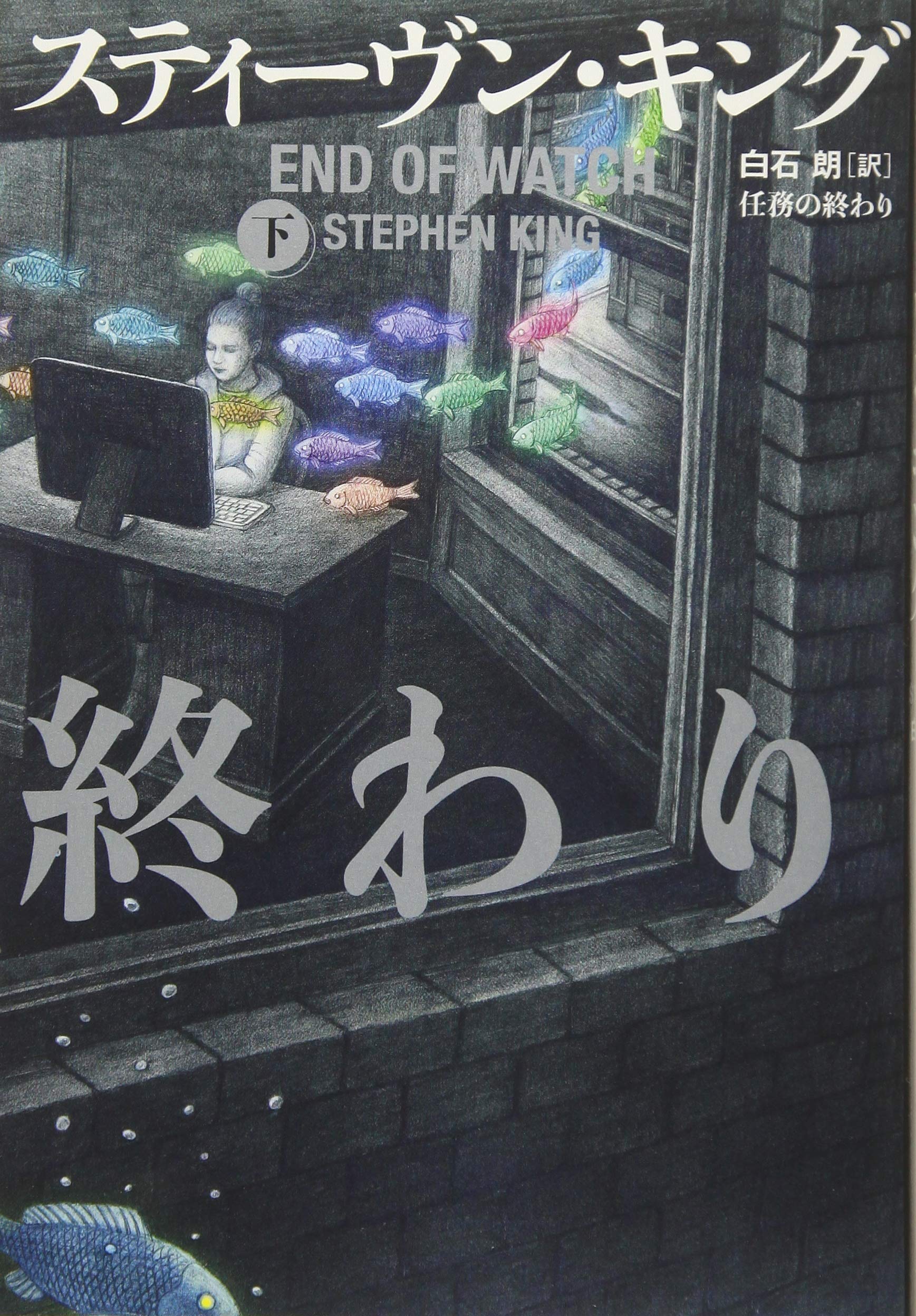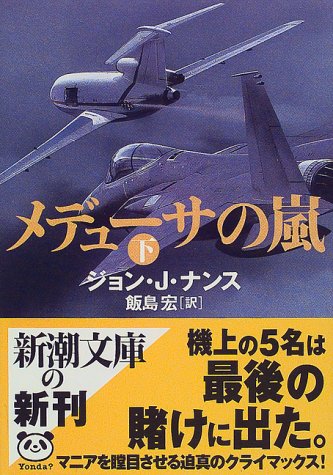
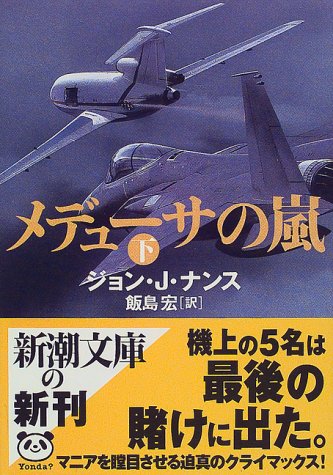
下巻では、着陸する空港を求めてあちこちを飛び回るスコットの苦闘が描かれる。
メデューサが野放しになっている事実は、アメリカ中が知ることとなった。ペンタゴンやCIAも、とんでもない兵器が空にある事態を把握する。一方で、アメリカを危機に陥れた犯罪者がすでに亡くなったロジャーズではなくヴィヴィアンによってなされたと考え、捜査するFBIも。
さまざまな思惑を持つ人々がそれぞれの立場で事態を掌握しようとするため、なかなかうまくいかない。
もっともやっかいなのは、メデューサを無傷で確保したいとの軍の一部の思惑だ。
まだどの国も開発に成功していないメデューサウェーブが今、合衆国の上空にある。それは軍にとって願ってもないチャンスだ。この兵器を可能な限り無傷で入手し、内部を解析することによって、アメリカによる世界の覇権はより一層強固なものとなる。
アメリカに無限の力がもたらされるメデューサは、軍が確保しなければならない。
そう確信した一部の軍人は、兵器を遺棄したいと願うスコットを欺き、スコットの飛行機を軍の飛行場に着陸させようと画策する。
ところがスコットのそばには、兵器の実際の開発者であるロジャーズの妻ヴィヴィアンがいる。かつてロジャーズと一緒に研究職に就いていたヴィヴィアンにとって、ロジャーズの能力はよく知っている。この兵器を完成させてもおかしくないことも。
ロジャーズがやると決めたら必ず実行する。軍がいかに知恵をめぐらそうとも、安全に解体することなど不可能。メデューサは軍が生半可に扱えるような代物ではない。そして、処置を誤ったが最後、アメリカ中の電子機器は使い物にならなくなり、アメリカは二度と立ち上がれないほどのダメージを被る。
ヴィヴィアンからそのような事を聞いたスコットは、アメリカを救わねばという使命につき動かされる。そして、策をめぐらせながら機を飛ばし続ける。スコットエアも自分自身もそしてクルーも最後まであきらめることなく、どうやればメデューサを安全に処分するかを考えながら。
そのスコットからみて、軍のおかしな動きは怪しむに十分だった。軍が自らを欺きメデューサを手中に収めようとしているのではないか、と。その疑いが確信に高まり、いったんは着陸した空港から、軍の制止を振り切って再び離陸への道を選ぶ。
物語を盛り上げるため、このような余計な画策をする役割の人物は必要だ。軍人としての動機がもっともなだけに、スコットを再び空へと送り出す展開も無理やりな感じは受けない。
軍の用意した飛行場が頼りにならないとなれば、もうスコットにとれる道はすくない。時間は少ない。そこで彼がどういう決断を下すのか。
超巨大台風とメデューサ。熱核爆弾としての側面も持つメデューサが爆発すれば、電磁波だけでなく、自身も一瞬にして塵と化す。
そのような極限状況にあって、ある人はパニックに陥り、ある人は判断力を失う。だが、ヒーローでなくとも、集中力を高められる人もいる。本書のスコットのように。
もともと航空機のパイロットは高度な知識と集中力を擁する仕事だという。
本書のような事態に巻き込まれたとしても、スコットが毅然と対処できることはある意味理にかなっている。空軍のもと戦闘機載りの経歴ならなおさら。
おそらく著者も自身や仲間のパイロットの姿をみていたはず。その素養は承知していたため、本書のような設定も著者には荒唐無稽とは考えていなかったのだろう。
飛行機とはただでさえ、一瞬の操作ミスが命の危機に直結する。
だから、もともとサスペンスの題材としては適している。
そして著者にパイロットとしての知識があったならば、飛行機を題材とした本書のようなサスペンスは面白いはずだ。
実際、本書を読む間は手に汗を握るような展開が連続する。本書のように極上の緊張感を楽しめるのは、読者としての喜びだ。
ただ、本書には物足りない点もあった。
正直にいうと、本書の登場人物にはもう少し深みがあっても良かったと思う。
たとえばスコットがなぜ一人で貨物便を扱うスコットエアを創業したのか。上巻の冒頭でそのあたりのいきさつには多少は触れられる。だが、あまりスコットが貨物会社を創業した動機には挫折があまり感じられなかった。
さらに、重要な役回りを演じるドクやジェリーの人物ももう少し深く掘り下げてもよかったのではないだろうか。
そしてリンダにも同じ物足りなさがつきまとう。なぜ南極からの観測データを焦って積み込まねばならないのか。そこに環境学者としての彼女が抱いていた地球温暖化の危機感を書き込めば、より彼女の強引な行為の理由が理解できたはず。
結局、本書で一番無茶な企てを仕掛けたロジャーズと、その企みにまんまとはめられたヴィヴィアンの元夫婦が、人物の中でもっとも深みがあったように思うのは私だけだろうか。
彼らの闇の暗さと、たくらみや巻き込まれた事件はもっとも現実に考えにくい役回りだったにもかかわらず。
だが、そうした欠点など取るに足りないと思えるぐらい、本書は航空機とそれを舞台にしたサスペンスの書き方に長けていたと思う。
あえて人物の書き方に注文を付けたのも、それだけ本書のサスペンスとしての構成がしっかりしていたからだ。
このあたりのバランスをどうすればよかったのかは、結果論に過ぎない。
一つだけいえるのは、本書が極上のサスペンスだったこと。それを読めて楽しめたことぐらいだ。
本書は余韻の描き方もとてもよかった。この終わり方によって、沸騰していた物語に締めくくりが付けられたように思える。
‘2019/6/19-2019/6/19