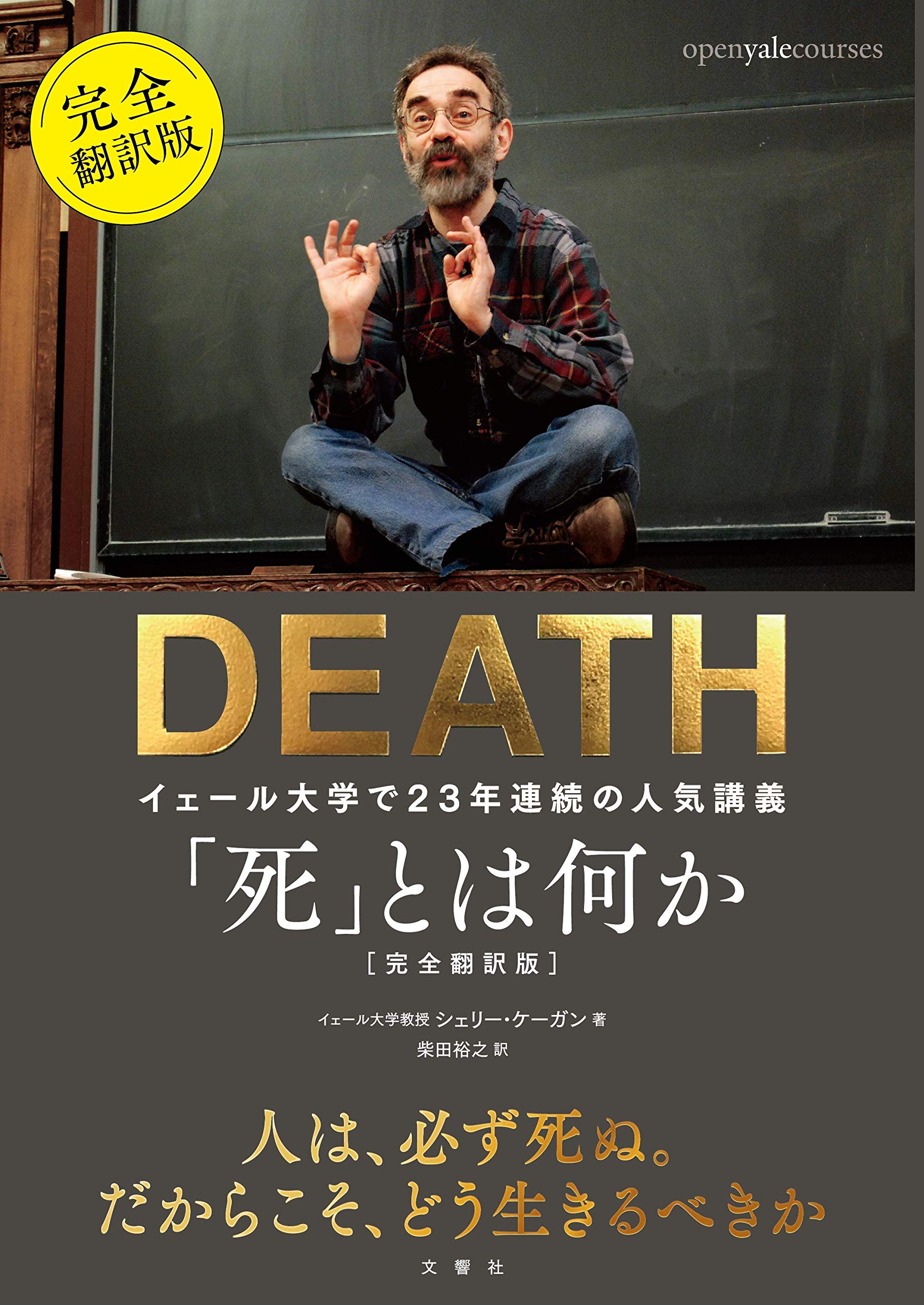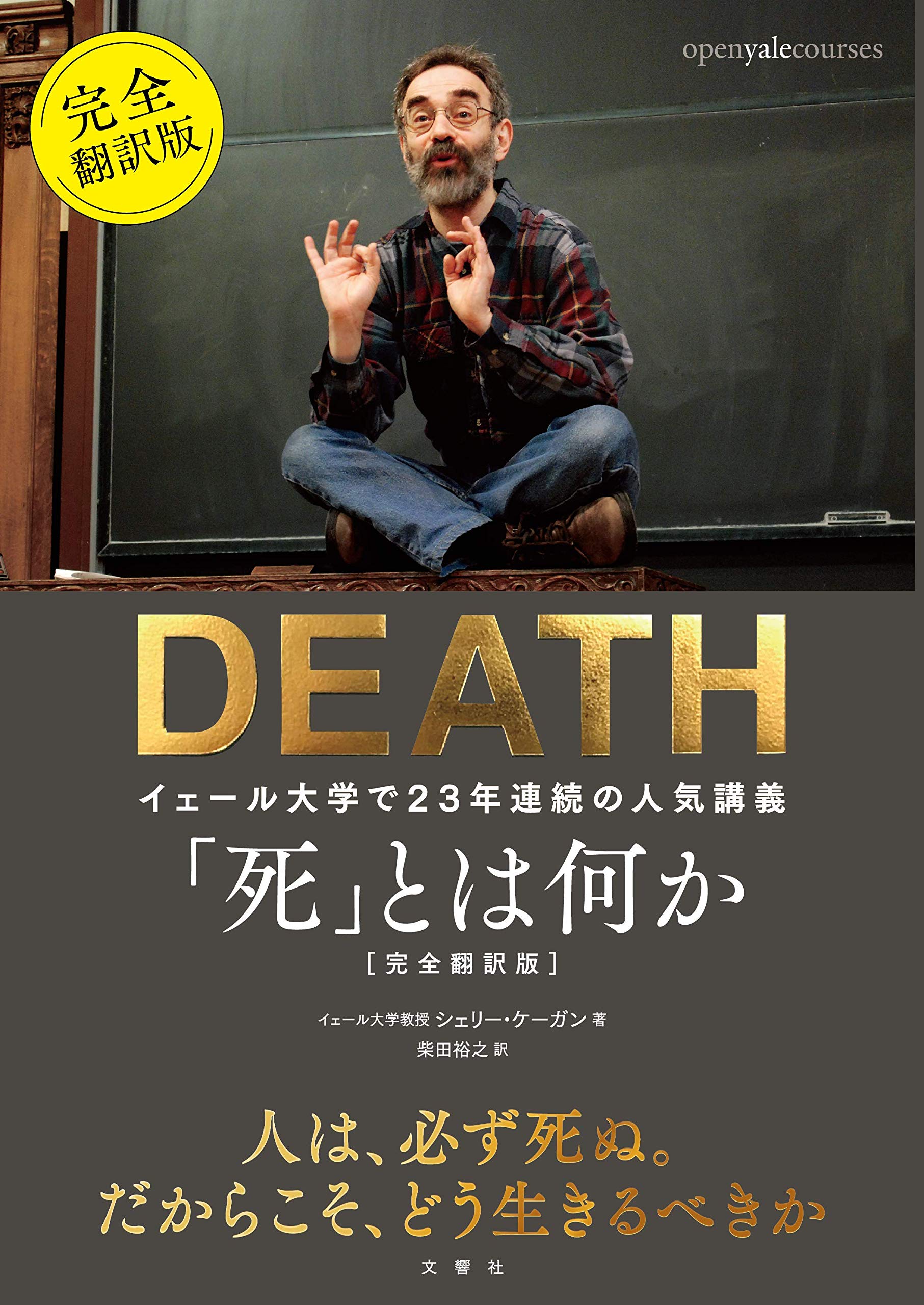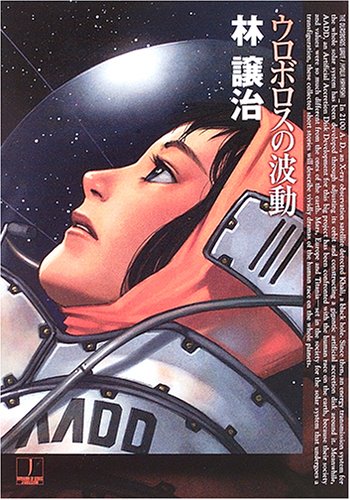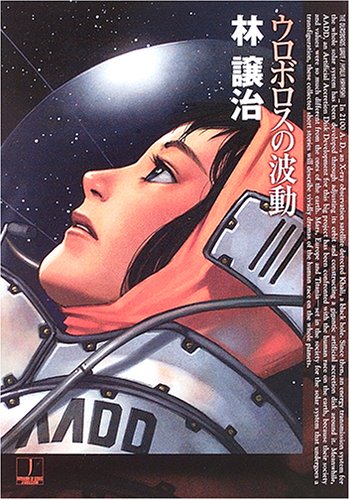本書はミステリというよりも、医学的なテーマについて考えさせられる小説だ。
ここでいう医学的なテーマとは、脳死とは何か、果たして人間の意識とは何かを意味する。本書にはそれらのテーマが取り上げられている。
人の意識とは何か。この問題に対して容易に答えを出すのは難しい。
今、考えていること自体が意識なのか。考えていることを指の動きまで伝達するまでの全ての営みが意識なのか。この意識とは、私の自由意志であるとみなしてもよいのか。
脳波を調べると、情報の伝達からそれに基づいた選択が行われるよりも前に脳のどこかで反応が生じるという。つまり、私たちが判断を行っているという意識よりも上位の何かが命令を発している論議さえまことしやかに交わされている。
そもそも、私たちの意思とはあらかじめプログラムされた命令の発動でしかないという説すらある。
そうした意識について人々が思索できるのも、私たちが今まさに活動し、外界に向けてアウトプットをしているからだ。私が笑ったり声を出したり動いたりするからこそ、私以外の人は私に意識があると判断する。
では、不慮の事故で外界に反応しなくなった場合、意識はないとみなしてよいのか。
生存に必要な生体反応や生理反応は生じるが、まったく外界に向けて反応がない場合、その人は生きているといえるのか。
ここに挙げた問題は容易には答えが出せない。
現代の医学でも、こうした問題については脳波やその他の反応を確認して意識の有無、つまりは脳死の有無を判断するしかないのが現状だ。本当に脳が死んでいるのか生きているのかは、あくまで脳波などの客観的な要素でしか判断できないのだ。
では、客観的に脳波があっても、外部への反応が確認できない場合、脳死と判断することは可能なのだろうか。
それが自分の子どもであれば、なおさらそのような判断を下すことは困難だ。呼吸はしているし、ただ寝てだけのように思えるわが子に死の宣告を下す。そして、死に至らしめる。
それは子を持つ親にとってあまりにも過酷な判断である。不可能といっても過言ではない。
はたして、親は眠ったままのわが子に脳死の判断を下せるのか。また、下すべきなのか。
著者はそれらの問いを登場人物に突き付ける。もちろん、読者にも。
本書の中で脳死になるのは瑞穂だ。播磨和昌と薫子の間に生まれた娘だ。
この二人が瑞穂に起こったアクシデントを聞かされたのは、和昌の浮気が原因で離婚の話し合いをしている時だった。
プールでおぼれて脳死状態になった瑞穂をいったんはあきらめ、臓器移植の意思表示をした二人。だが、最終的にその意思を示す直前で瑞穂の手から反応が返ってきたことで、二人は延命に望みをつなぐ。
和昌が経営する会社では、ちょうど人間に接続したデバイスを脳から動作させる研究が進展していた。
その研究が娘の意識を取り戻すための助けになるなら、そして妻が望みを持ち続けられるなら、と離婚を取りやめた和昌は、娘の体を機械で操作する研究に手を染め始める。
その和昌による研究は進展し、研究の成果によって薫子は瑞穂を生きている時と変わらないように動かせるまでになる。
起きることのないわが娘を、さも生きているかのようにふるまわせる薫子は、次第に周囲から疎んじられるようになる。
狂気すら感じられるわが子への愛は、どのような結末を迎えるのか。そんな興味に読者は引っ張られていく。
法的には生かされているだけの脳死状態の人。
私たちは脳死という問題についてあまりにも無知だ。医者が脳死判定を下す基準は何か。脳死状態の人が再び意識を取り戻すことはありえるのか。脳死状態の人の法的な地位はどうなるのか。意識はなくとも肉体は成長する場合、その人の年齢や教育はどう考えるべきなのか。
また、脳死状態にある人の臓器を移植したい場合、誰の意思が必要なのか。その時に必要な手続きは何なのか。
当事者にならない限り、私たちはそうした問題に対してあまりにも無知だ。
私は常々、今の世の中の全ての出来事に対して当事者であり続けることは不可能だと思っている。
当事者でない限り、深くその問題にコミットはできない。そして、説得力のある意見を述べることもできない。だから私はあまり他人の問題に言及しないし、ましてや非難もしない。
さらにいうと、当事者でもない政治家や官僚があらゆる問題を決める仕組みはもはや存族不能だと考えている。
日々の暮らしに起こりうる可能性の高い出来事についてすら、いざ事故が起きてみないと当事者にはなれないのが現実だから。
本書を読むと、まさに脳死の問題とは、当事者にならなければ深く考えることもできない事実を突きつけられる。
では、死に対してはどうだろう。または、意識に対しては。
これらについても当事者にならなければ深く考えることはできないのだろうか。
ここで冒頭の問いに回帰してゆくのだ。
果たして意識とは何だろうか。
そう考えたとき、本書から得られる教訓は当事者意識の問題だけでないことに気づかされる。
私たちは普段、自らの意識を意識して生きているのか、という問いだ。つまり、私たちは自分の意識について当事者意識を持っているのだろうか。
冒頭に書いたような問いを繰り返す時に気づく。私たちは普段、自らの意識を意識して生きていないことに。
例えば呼吸だ。無意識に吸って吐いての動作を繰り返す呼吸を私たちが意識して行うことはない。
だが、ヨガ行者や優れたスポーツ選手は呼吸を意識し、コントロールすることによって超人的な能力を発揮するという。
また、大ブームになった『鬼滅の刃』にも全集中の呼吸がキーワードになっている。
呼吸だけでなく、歩き方や話し方、思考の流れを意識する。そうすることで、私たちは普段の力よりも高い次元に移り行くことができる。
脳死の問題について私たちが当事者になる機会はないし、そうならないことが望ましい。
だからといって、本書から得られることはある。
本書は、そうした意識の大切さと意識に対して目を向けることに気づかせてくれる小説だといえる。
2020/12/12-2020/12/15