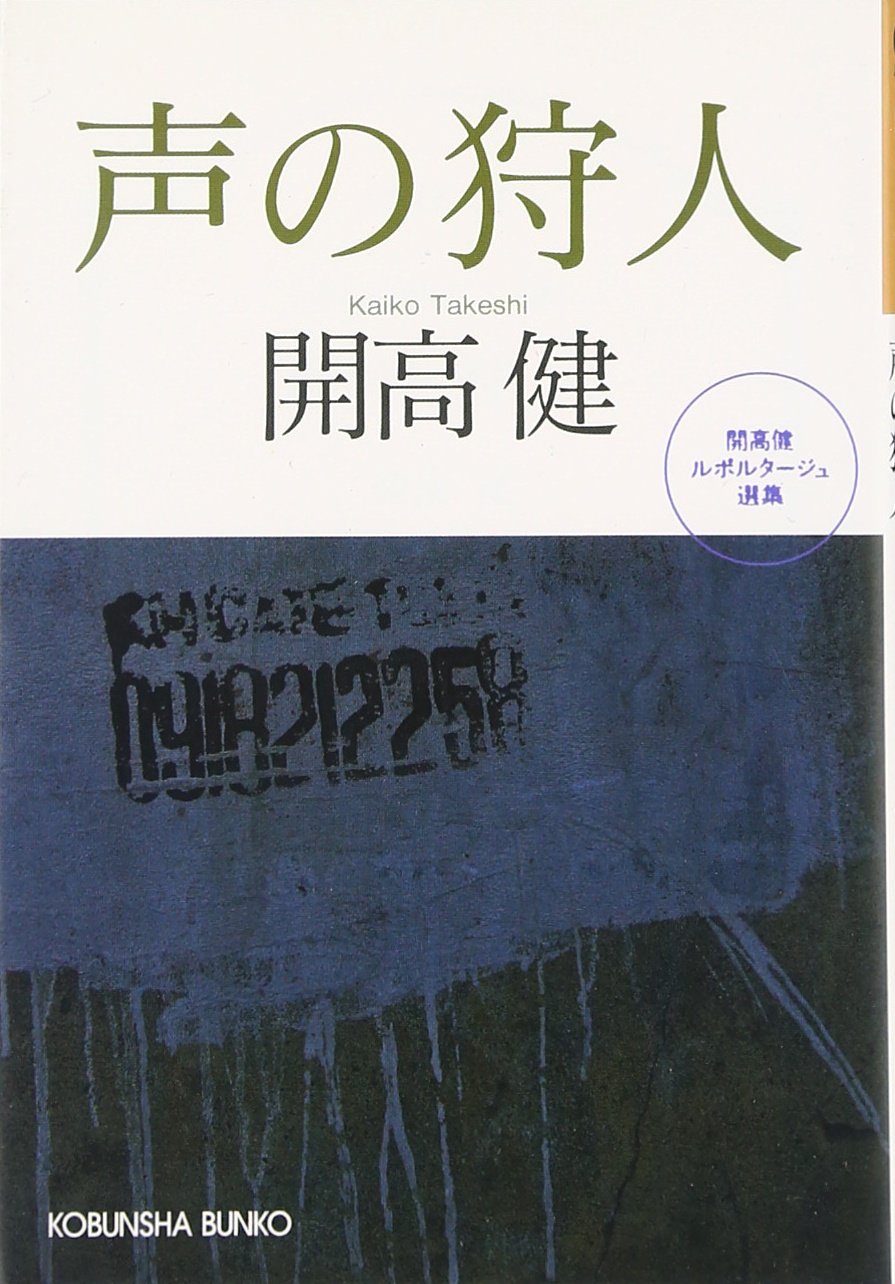
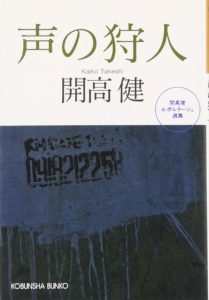
著者を称して「行動する作家」と呼ぶ。
二、三年前、茅ヶ崎にある開高健記念館に訪れた際、行動する作家の片鱗に触れ、著者に興味を持った。
著者は釣りやグルメの印象が強い。それはおそらく、作家として円熟期に入ったのちの著者がメディアに出る際、そうした側面が前面に出されたからだろう。
だが、行動する作家、とは旅する作家と同義ではない。
作家として活動し始めた頃、著者はより硬派な行動を実践していた。
戦場で敵に囲まれあわや全滅の憂き目をみたり、東西陣営の前線で世界の矛盾を体感したり。あるいはアイヒマン裁判を傍聴してで戦争の本質に懊悩したり。
著者は、身の危険をいとわずに、世界の現実に向き合う。
書物から得た観念をこねくり回すことはしない。
自らは安全な場所にいながら、悠々と批判する事をよしとしない。
著者の行動する作家の称号は、行動するがゆえに付けられたものなのだ。
そうした著者の姿勢に、今さらながら新鮮なものを感じた。
そして惹かれた。
安全な場所から身を守られつつ、ブログをかける身分である自分を自覚しつつ。
いくら惹かれようとも、著者と同じように戦場の前線に赴くことになり得ない事を予感しつつ。
没後30年を迎え、著者の文学的な業績は過去に遠ざかりつつある。
ましてや、著者の行動する作家としての側面はさらに忘れられつつある。
だが、冷戦後の世界が再び動き出そうとする今だからこそ、冷戦の終結を見届けるかのように逝った行動する作家としての姿勢は見直されるべきと思うのだ。
冷戦が終わったといっても、世界の矛盾はそのままに残されている。
ソ連が崩壊し、ベルリンの壁が崩され、東西ドイツや南北ベトナムが統一された以外は何も変わっていない。
朝鮮は南北に分断されたままであり、強大な国にのし上がった中国を統治するのは今もなお共産党だ。
ロシア連邦も再び強大な国家に復帰する機会を虎視眈々と狙っている。
そもそも、イスラム世界とキリスト世界の間が相互で理解し合うのがいつの日だろう。パレスチナ国家をアラブの国々が心から承認する日はくるのだろう。ドイツで息を吹き返しつつあるネオナチはナチス・ドイツの振る舞いを拒絶するのだろうか。
誰にも分からない。
それどころか、アメリカは世界の警察であることに及び腰となっている。日韓の間では関係が悪化している。EUですらイギリスの離脱騒ぎや、各国の財政悪化などで手一杯だ。
世界がまた混迷に向かっている。
冷戦後、いっときは平穏に見えたかのような世界は実は休みの時期に過ぎなかったのではないか。実は何も解決しておらず、世界の矛盾は内で力を蓄えていたのではないか。
その暗い予感は、わが国の活力が失われ、硬直している今だからこそ、切実に迫ってくる。
次に世界が混乱した時、日本は果たして立ち向かえるのだろうか、という恐れが脳裏から去らない。
本書は著者が旅先でたひりつくような東西の矛盾がぶつかり合う現場や、アイヒマン裁判を傍聴して感じたこと、などを密に描いたルポルタージュ集だ。
「一族再会」では、死海の過酷な自然から、この土地の絶望的な矛盾に思いをはせる。
古来、流浪の運命を余儀なくされたユダヤ民族は、苛烈な迫害も乗り越え、二千数百年の時をへて建国する。
生き残ることが至上命令と結束した民族は強い。
自殺者がすくないのも、そもそも自殺よりも差し迫った悩みが国民を覆っているから。
著者の筆はそうした本質に迫ってゆく。
「裁きは終わりぬ」では、アイヒマン裁判を傍聴した著者が、600万人の殺人について、官僚主義の仮面をかぶって逃避し続けるアイヒマンに、著者は深刻に悩み抜く。政治や道徳の敗北。哲学や倫理の不在。
アイヒマンを皮切りに、ナチスの戦犯のうち何人かはニュルンベルクで判決を受けた。だが、ヒトラーをはじめとした首脳は裁きの場にすら現れなかった。
一体、何が裁かれ、何が見過ごされたのか。
著者はアイヒマンを絞首刑にせず生かしておくべきだったと訴える。
顔に鉤十字の焼き印を押した生かしておけば、裁きの本質にせまれた、とでもいうかのように。
「誇りと偏見」は、ソ連へ旅の中で著者が感じ取ろうとした、核による終末の予感だ。
東西がいつでも相手を滅ぼしうる核兵器を蓄えてる現実。
その現実の火蓋を切るのは閉鎖されたソ連なのか。そんな兆しを著者は街の空気から嗅ぎ取ろうとする。
ステレオタイプな社会主義の印象に目をくらまされないためにも、著者は街を歩き、自分の目で体感する。
今になって思うと、ソ連からは核兵器の代わりの放射能が降ってきたわけだが、そうした滅びの終末観が著者のルポからは感じられる。
「ソヴェトその日その日」は、終末のソ連ではなく、より文化的な側面を見極めようとした著者の作家としての好奇心がのぞく。
共産主義の教条のくびきが解けようとしているのではないか。暗く陰惨なスターリンの時代はフルシチョフの時代をへて過去となり、新たなスラヴの文化の華が開くのではないか。
著者の願いは、アメリカが主導する文化にNOを突きつけたいこと、というのはわかる。
だが、数十年後の今、スラヴ文化が世界を席巻する兆しはまだ見えていない。
「ベルリン、東から西へ」でも、著者の文化を比較する視点は鋭さを増す。
東から西へと通過する旅路は、まさに東西文化に比較にうってつけ。今にも東側を侵そうとする西の文化。
その衝突点があからさまに国の境目の証となってあらわれる。
それでいながらドイツの文化と民族は同じであること。著者はここで国境とはなんだろうか、と問いかける。
文化を愛する著者ゆえに、不幸な断絶が目につくのだろうか。
「声の狩人」は、ソ連を横断してパリに着いた著者が、花の都とは程遠いパリに寒々しさを覚える。
アルジェリア問題は激しさを増し、米州機構反対デモが殺伐とした雰囲気をパリに与えていた。
実は自由を謳歌するはずのパリこそが、最も矛盾の渦巻く場所だったという、著者の醒めた観察が余韻を与える。
結局著者は、あらゆる幻想を拒んでいた人だったのだろう。
「核兵器 人間 文学」は、大江健三郎氏、そして著者とともに東欧を訪問した田中 良氏による文だ。
三人でフランスのジャン・ポール・サルトルに質問を投げかける様が描かれる。
ジャン・ポール・サルトルは、のちにノーベル文学賞を受賞するも、辞退した硬骨の人物として知られる。
ただ、当代一の碩学であり、時代の矛盾を人一番察していたサルトルに二人に作家が投げかける質問とその答えは、どこか食い違っている感が拭えない。
この点にこそ、東西の矛盾が最も表れているのかもしれない。
「サルトルとの四十分」は、そのサルトルとの会談を振り返った著者にる感想だ。
パリに来るまでソ連を訪れ、その中で左翼陣営の夢見た世界とは程遠い現実を見た著者と、西洋文化を体現するフランスの文化のシンボルでもあるサルトルとの会談は、著者に埋めようもない断絶を感じさせたらしい。
日本から見た共産主義と、フランスから見た共産主義の何が違うのか。
それが西洋人の文化から生まれたかどうかの差なのだろうか。
著者の戸惑いは今の私たちにもわずかに理解できる。
「あとがき」でも著者の戸惑いは続く。
本書に記された著者の見た現実が、時代の流れの速さに着いていけず、過去の出来事になってしまったこと。
その事実に著者は卒直に戸惑いを隠さない。
そうした著者の人物を、解説の重里徹也氏は描く。
「開高がしきりにのめりこんでいくのは、こういう、現実と理想の狭間に生まれる襞のようなものに対してである」(239ページ)
ルポルタージュとは、そうした営みに違いない。
‘2018/11/1-2018/11/2







