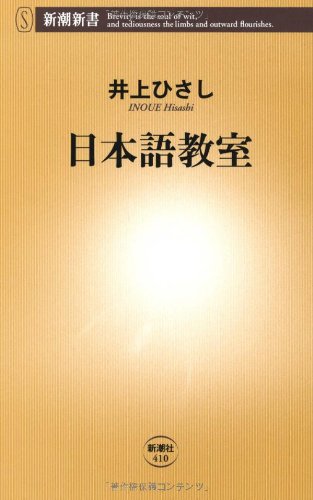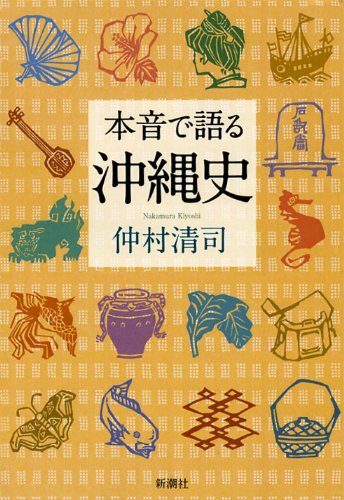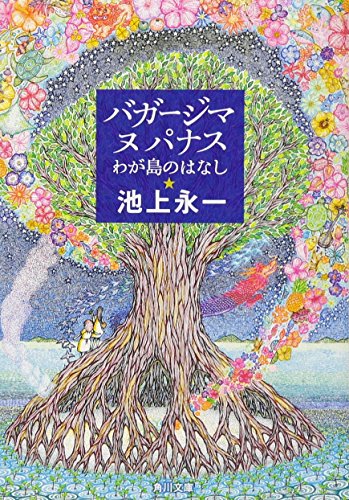旅が好きな私。日本各地の神社にもよく訪れる。
神社を訪れた際、そこに掲げられた由緒書は必ず読むようにしている。
ところが、その内容が全く覚えられない。特に御祭神となるとさっぱりだ。
神代文字に当てた漢字の連なりも、神の名前も、神社を出るとすぐに忘れてしまう。
翌日になるとほとんど覚えていない。
そんな調子だから、いまだに古事記の内容を語れない。
何度も入門書や岩波文庫にチャレンジをしているのだが、内容が覚えられないのだ。
結局、私が覚えている事は、子供向けの本に出るような有名な挿話をなぞるだけになってしまう。
いつも、旅に出て神社を訪れる度に、何とかして古事記を覚え、理解しなければ、と思っていた。
そんなところに、妻がこのような本を買ってきた。タイトルからしてクダけている。
クダけ過ぎている。
スサノオはマザコンのヤンキーだし、アマテラスは引きこもりでしかもロリ巫女。因幡の白ウサギはバニーガールで、海幸山幸はねらー(5ちゃんねるの住人)だ。
文体もそう。砕けている。
私はあまりライトノベルを読んでいないが、ライトノベルの読後感は、多分こんな感じなのだろう。
折り目正しく端正な日本語とは無縁の文体。
ネット・スラングを操り、SNSを使いこなす神々。
かなりはっちゃけている。今の若者風に。
それがイマドキ。
でも、イマドキだからいいのだ。
暴れ狂うスサノオも、古事記に書かれる姿は何やらしかつめらしく武張っている。威厳ある神の姿。
だが、暴れ狂う姿は、成人式で傍若無人の所業に狂うヤンキーと変わらない。しかも母のアマテラスへの甘えを持っているからたちが悪い。
スサノオにサジを投げ、天の岩戸に隠れたアマテラスも、見方を変えれば、ドアを閉め切った引きこもりと変わらない。
文化、文明、言葉。そうしたものが古めかしいと、権威を帯びてしまう。
そして、古典としてある種の侵しがたい対象へと化ける。
だが、同じ時代を生きた神々が見た身内とは、案外、今の私たちがSNSに一喜一憂し、仕事にレジャーに家庭に勤しむ姿とそう変わらないように思える。
「いまどきの若いものは」と愚痴る文句が古代の遺跡から見つかった、と言う話はよく聞く。
このエピソードは、今も昔もそう変わらない事実を私たちに教えてくれる。
結局昔も同じなら、日本人の祖先を描いた古事記も同じではないか。
神々の行いを全て神聖なものと見なし、全てに深淵なる意味を結びつける場合ではない。
そうした行いは、見る神から見れば、単なる甘えた駄々っ子の振る舞いと変わらない。そう気づいた著者は偉い。
神々とはいえ、今の人間とそう変わらないのでは。そう見直して書き直すと本書が生まれ変わるのだろう。
古事記と名がついていても、やっている事は、今の私たちの行いとそう変わらない。
なら、いっそのこと今風の文体や言葉に変えてしまえ。
そうして、全編が今風な文体と言葉で置き換えられた古事記が本書だ。
本書の内容は古事記の内容とそう変わらない。
ただし、その内容やセリフが大幅にデフォルメされ、脚色されている。
そのため、圧倒的に読み進められる。
まず、あの古めかしい言葉だけで古事記を遠ざけていた向きには、本書はとっつきやすいはずだ。
上に書いた通り、古事記といっても難しいことはなく、ただ神々の日々を少し大げさに描いただけのこと。
それが本書のようにイマドキに変えられると、より親しみが湧くだろう。
ただ、古事記の内容は簡潔だ。
そして登場する神の心象も詳しく描かれることはない。
著者はそれを埋めようと、イマドキのガジェットで埋め尽くす。
それによって現代の若者には親しみが湧くだろう。
だが、ガジェットも行きすぎると、肝心のシナリオを邪魔してしまう。
ライトノベルを読み慣れていないからだろうか。
イマドキの表現に目移りして、肝心の筋書きが頭に入って来にくかった。
それは著者のせいでなく、そうしたイマドキの表現に印象付けられた私のせいなのだが。
これはライトノベルを読み慣れた読者にとって、どうなんだろう。
慣れ親しんだ表現なので、帰って筋書きは頭に入ったのだろうか。
若者が古事記に関心を持ってもらえるなら、私一人が惑わされても大したことではないのだが。
古事記とは、日本創世神話だ。
ナショナリズムを今さら称揚するつもりはないが、古事記に込められている物語の豊かさは、注目しても良いはずだ。
ましてやそれが1700ー2000年の昔から語り継がれて来た。
これだけ豊穣な物語。大陸やユダヤの影響があったとしても荒唐無稽とはいいきれないが、それが昔の日本で編まれたことは事実だから。
だから日本はすごい、とかは考えなくても良い。
けれど、日本人であることを卑下する必要もないと思う。
そうした物語の伝統が今もなお息づいていることを、本書を読んだイマドキの方が感じ取ってくれればと思う。
本書は著者が東北芸術工科大学文芸学部に在籍している間、授業の課題から産まれたそうだ。自由で良いと思う。
温故知新というが、若い人たちが古い書物に新しい光を与えてくれることはよいことだ。
‘2018/10/28-2018/10/29