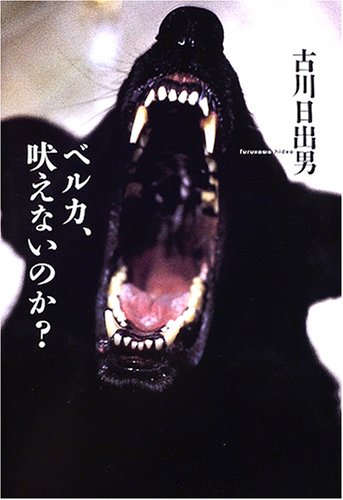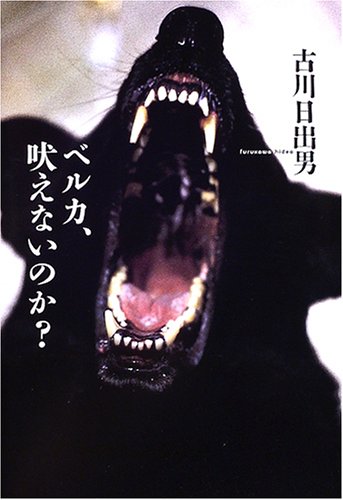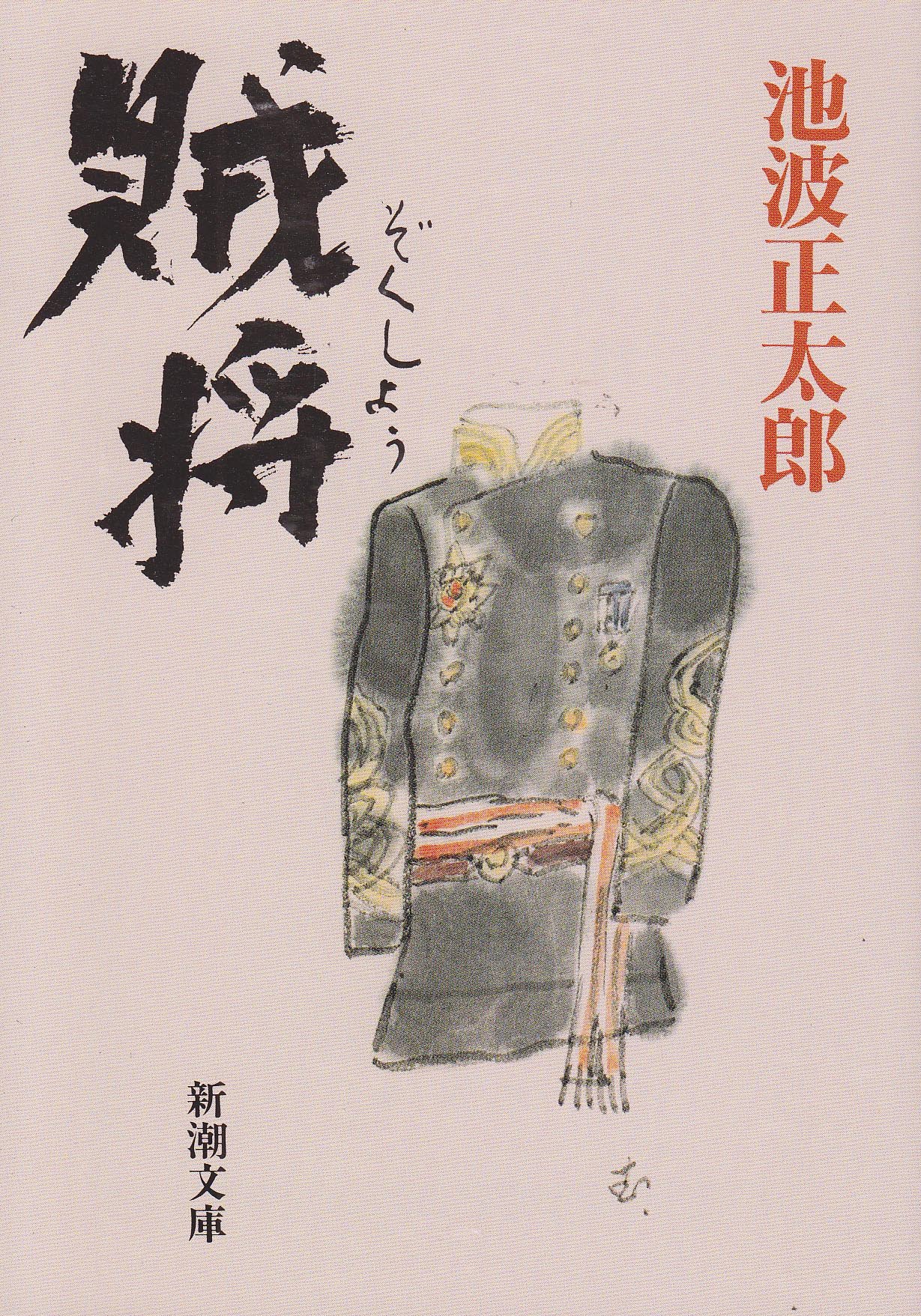
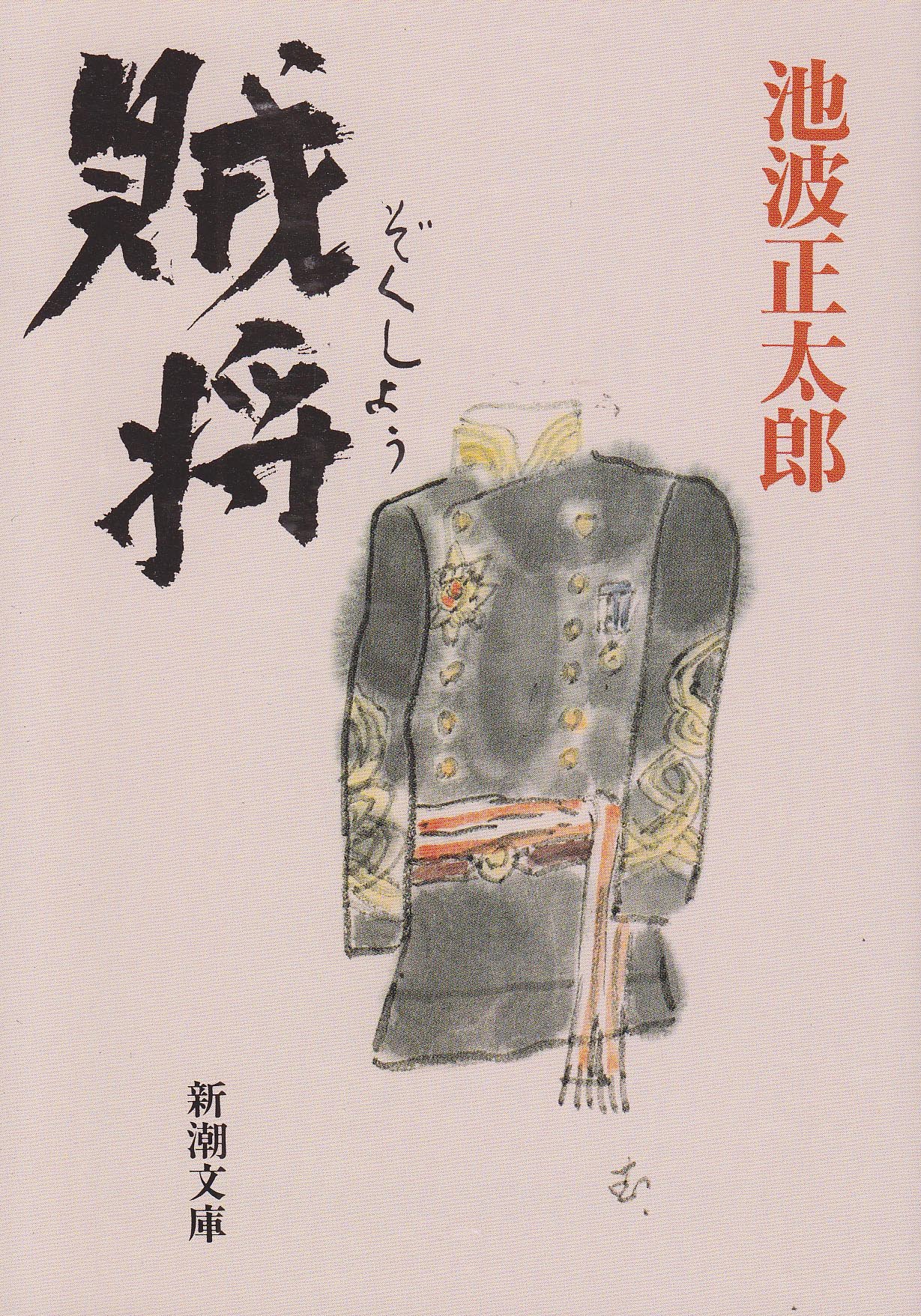
『人斬り半次郎』に書かれた桐野利秋の生涯。本書はその前身となった短編『賊将』が収められた短編集だ。
本書は著者が直木賞をとる直前に出され、まさに脂ののった時期の一冊だ。
多作で知られる著者だが、著者のキャリアの早期に出された本書にも流麗な筆さばきが感じられる。
とはいうものの、速筆で知られていた著者も本書を書くにはかなりの苦労があったらしい。
私たち一般人にとっては、時代小説が書けるだけでも大したものだ。おそらく私たちは書くだけで難儀するだろう。今を書くことすら大変なのに、価値や文化の異なる当時を描きつつ、小説としての面白さを実現しなければならないからだ。特に、時代小説は、登場人物をその時代の人物として描かねばならない。その違いを描きながら、読者には時代小説を読む楽しみを提供しなければならない。時代小説作家とは、実はすごい人たちだと思う。
読者は時代小説を読むことで、現代に生きる上で当たり前だと思っていた常識が、実は時代によって変わることを知る。現代の価値とは、現代に沿うものでしかない。それを読者に教えることこそが時代小説の役割ではないだろうか。
「応仁の乱」
本編は応仁の乱を描いている。
応仁の乱を一言で語るのは難しい。
もし応仁の乱を一言で済ませろと言われれば、山名宗全と細川勝元の争いとなるのだろう。だが、応仁の乱を語るにはそれでは足りない。
応仁の乱によってわが国は乱世の気運がみなぎり、下克上を良しとする戦国時代の幕を開けた。
その責任を当時の足利幕府八代将軍である足利義政にだけ負わせるのは気の毒だ。
後世に悪妻と伝えられる日野富子との夫婦関係や、二人の間に生まれた義尚が、還俗させ義視と名乗らせた弟の立場を変えてしまったこと。日野富子の出自である公家や朝廷との関係も複雑だったこと。加えて、有力な守護大名が各地で政略を蓄えており、気の休まる暇もなかったこと。どれも義政にとって難題だったはずだ。
後世の印象では無能と見られがちの義政。だが、本人にはやる気もあった。愚鈍でもなかった。だが、受け継いだ幕府の仕組みが盤石ではなかったことが不運だった。
そもそも、足利幕府の始まりが盤石でなかった。初代将軍の足利尊氏は圧倒的な力を背景に征夷大将軍に就いたわけではなかった。建武の乱から観応の擾乱に至るまで戦乱は絶えず、天皇家すら南北朝に分かれて争っていた。
ようやく三代将軍の義満によって権力を集中させることができたが、義政の父である六代将軍義教が嘉吉の乱で白昼に殺されてからは、将軍の権威は弱まってしまった。義政の代は、各守護大名の協力のもとでないと幕府の権力の維持は難しくなっていた。
複雑な守護大名間の勢力争いや、夫婦間の関係などを細やかに描いた本書は、義政の葛藤と苦悩を描くとともに、応仁の乱へ歴史が導かれていった事情を詳らかにしていてとてもわかりやすい。
応仁の乱の背景を知るには本編は適していると思う。
「刺客」
こちらは、江戸時代の松代藩における権力争いを描いている。
松代藩といえば、真田家だ。著者の代表作の一つに「真田太平記」がある。
著書の著作リストを見る限り、松代藩を舞台とした作品は多そうだ。
本編は、松代藩の権力争いの中、翻弄されていく娘の無念と、刺客として任務を果たす男の運命を描いている。
現代に比べると、当時は相手の生を尊重することはあまりなかった。本編にもその習慣の低さが描かれている。
ただし、本編のような人と人の争いは今の世でもありえる。実は、今の世にも同じような悲劇が隠れているのではないか。
「黒雲峠」
仇討ちも現代の私たちにはなじみのない習慣だ。
だが、当時は幕府や藩に届けを出せば肉親の敵を成敗することは認められていた。忠義を奨励することになるため、幕府の統治にも都合がよかったからだ。
仇討ちとは個人的な思いの強い行いだ。そして、それは命にも関わる。
だからこそ、真剣にもなる。濃密な関係の中、人の本章が顕わになる。
現代の私たちは、当時の人々が仇討ちにかける思いと同じだけの何かを持っているだろうか。そう思わせてくれる一編だ。
「秘図」
人は謹厳なだけでは生きていかれないものだ。
本編は、そのような人間の本性を描いており、本書の中でも印象深い一編だ。
若い頃に放蕩の道に迷いかけ、名を変えて生まれ変わった徳山五兵衛。
今では藩の火付盗賊改として、厳格な捜査と取り調べによって人々に一目置かれていた。
だが毎夜、妻子が寝静まった後、自室で五兵衛が精根を傾けるのは、絵描き。それも男と女の交わる姿を描いた秘図。つまり春画だ。
やめようにもやめられぬまま、死を自覚した五兵衛。自分の数十年にわたるこのような別の姿を人々にさらすわけにはいかない。
妻にも自分の亡き後は絶対に手文庫を処分するようにと言い残す。
自負に満ち、誇りの高い武士も楽ではなかったのだろう。
今の世も終活と称し、ハードディスクの中身をいかにして処分するか、という問題がある。またはSNSにアップした内容の取扱いなど。まったく、江戸時代も今の世も、人の心のあり方はそう変わらない。これもまた時代小説から得られる面白さだ。
「賊将」
本書の表題になっている本編は、人斬り半次郎が、陸軍少将桐野利秋になってからの物語だ。
西郷どんを慕うあまり、征韓論で不利になったことに悲憤し、西郷隆盛と共に薩摩に下野する桐野利秋。
薩摩を立ち上がらせよう、西郷どんの意見を政府に認めさせようと奔走したのも桐野利秋。西南戦争に向けてもっとも急進論を唱えた一人が桐野利秋だった。
幕末には名うての志士として活動した人斬り半次郎は、結果的に官軍の側の人として栄達した。だが、すぐに運命に操られるままに逆賊の汚名を被る。
その結果、西南戦争では賊将として突き進み、戦死する。その様子を描いた本編は、人間の運命の数奇さとはかなさだ。
後日、著者が桐野利秋の志士の時代を長編にしたて直したくなったのもよくわかる。
「将軍」
明治に生き、明治に準じた乃木希典将軍も、自分に与えられた天運と時代の流れに翻弄された人物だ。
西南戦争で軍旗を奪われた事を恥と感じ、軍人と生きてきた乃木将軍。
さらに日露戦争における旅順攻略戦でも莫大な戦費を使い、あまたの兵士の命を散らした。自分の恥をすすぐためには息子たちを戦地で失ってもまだ足りないかというように。
明治天皇の死に殉じて死を選んだ乃木将軍の姿は、明治がまだ近代ではなく歴史の中にあったことを教えてくれる。
2020/10/6-2020/10/10