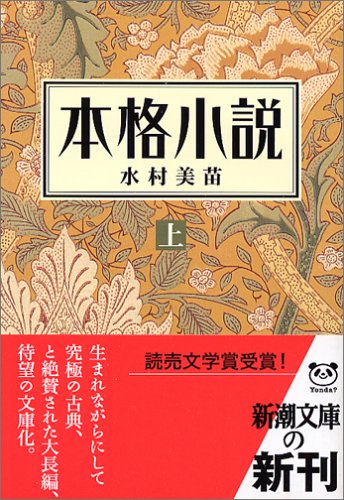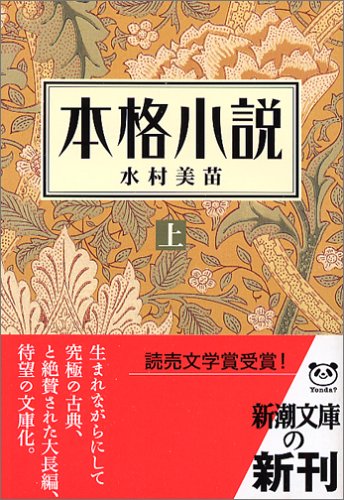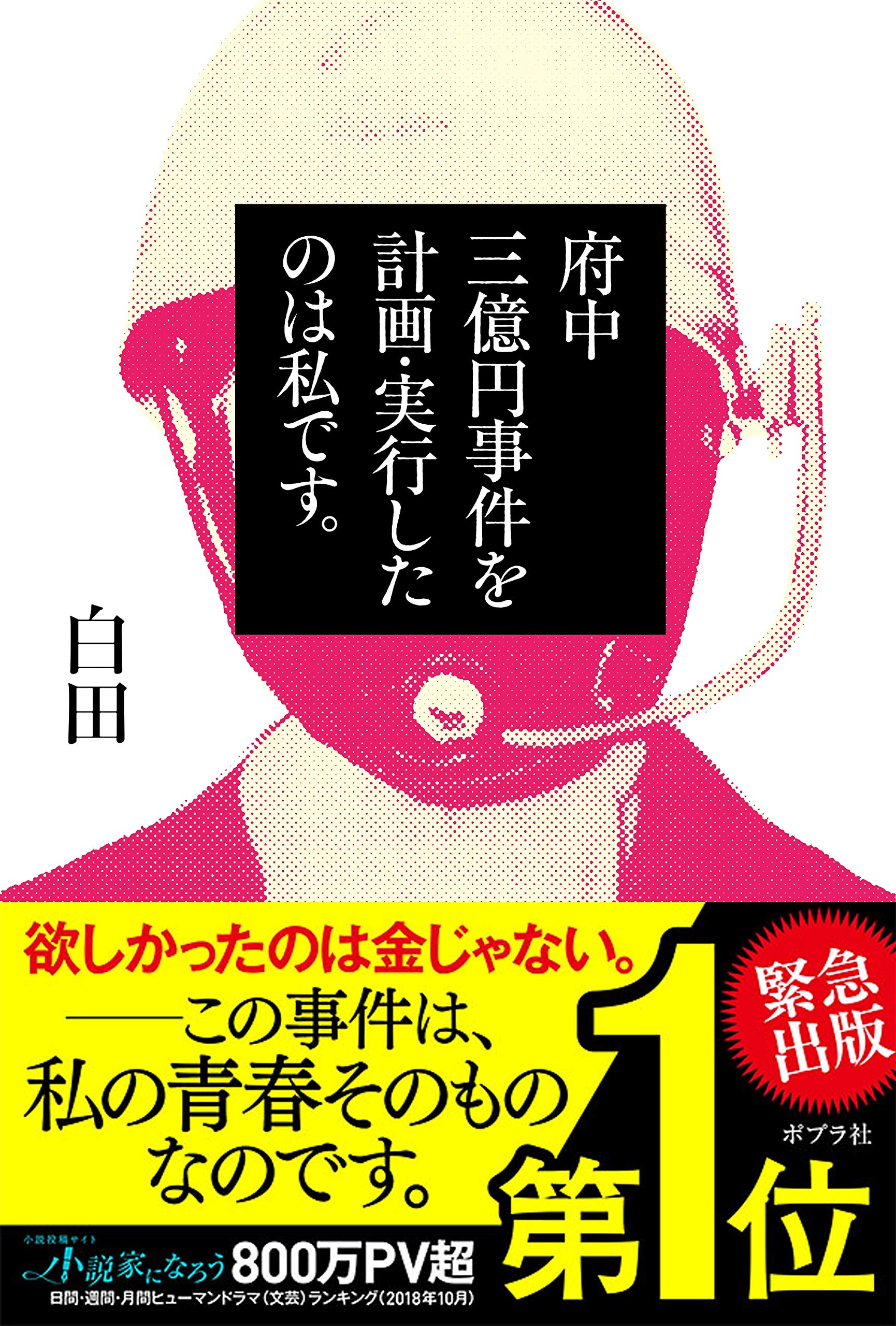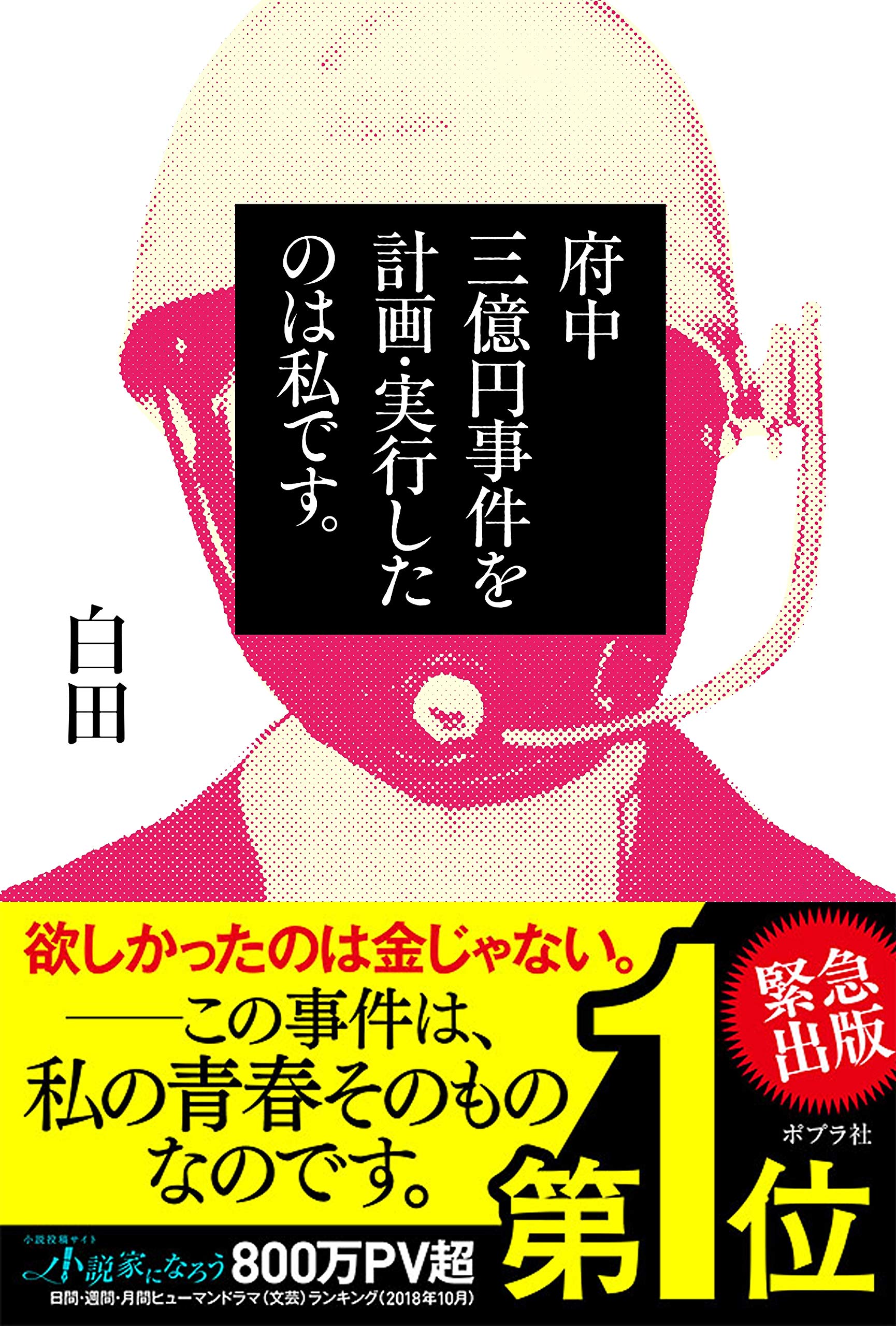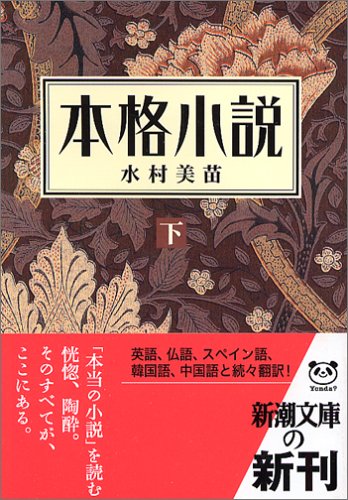
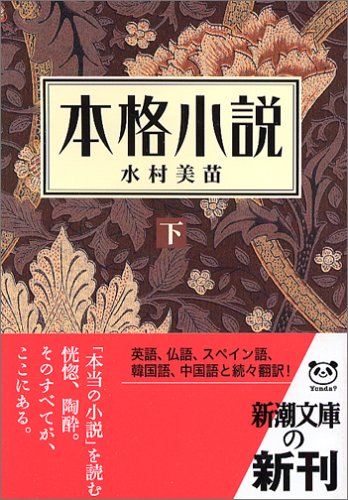
上巻からの続きで、下巻は本編から始まる。長い長い前書きではない。
冨美子からハイ・ティーに誘われた祐介は今にも崩れそうな古い別荘に招かれる。重光と三枝、宇多川という表札のかかった古びた洋館。かつて軽井沢が別荘地として旧家を集めていた時期の名残だ。
その洋館で祐介は、冨美子からタローにまつわる長い話を聞かされる。
冨美子の語りに引き込まれていく祐介。
重光家と三枝家、宇多川家は、小田急の千歳船橋駅付近で戦前から裕福な暮らしを送っていた。成城学園に子女を通わせるなど、優雅な毎日。冨美子もそこに家政婦のような立場で雇われた。
では、タローこと東太郎はどのような立場だったのか。
宇多川家がかつて雇っていた車夫は、敷地の一角に居宅を与えられていた。その車夫から、甥の一家が大陸から引き上げてくるから一緒に住まわせてほしと懇願され、同居する事になったのが東家。
大陸からの引き上げ者の息子として、居候のような立場だった太郎。その経済の差は歴然としており、同じ敷地内でも生活や文化などあらゆる違いがあった。
三枝家の娘として何不自由なく育っていたよう子にとっては家格など関係ない。同じ年頃の友達として、太郎とよう子は一緒に遊ぶようになっていた。
幼い頃より、よう子と遊んで過ごす日々の中で、少しずつ太郎はよう子に思慕を抱くようになる。
だが、東家にとって三枝家ははるか上の家格。周りから見ても、当人たちにとっても不釣り合いなことは明らか。
昭和の高度成長の真っただ中とはいえ、摂津藩の家老だった重光家や大正期に商売で成り上がった三枝家は、まだ古い価値観に引きずられている。
有形無形の壁を前にした太郎はよう子との結婚を諦める。そして、単身アメリカへ飛ぶ。
やがて富を重ね、大金持ちになって日本に戻ってきた太郎。そこにはもはや自分の居場所はない。よう子は重光家の御曹司雅之と結婚し、三枝家と重光家は隣の家同士の関係から、親戚になる。
太郎は日本で過ごすことを諦める。が、つかず離れずこの両家の周辺に姿を見せる。冨美子がさまざまな人生の経験をへてもなお、この両家とつながっているように。
やがて、この両家も時代の荒波をかぶり、その栄華の日々に少しずつ影が生じる。
少しずつ衰退に向かっていく三枝家と重光家の周囲に太郎の気配がちらつく。つかず離れずよう子を見守るかのように。
家の格によって恋を引き離された二人の運命。それが描かれるのが本書だ。日本は経済で成長し、古い価値観は置き去られていく。この両家のように。
わが国の歴史が何度も繰り返してきた盛者必衰のことわり。それに振り回される男女の関係のはかなさ。
上巻ては特異な構成に面食らった読者は、下巻では冨美子の語る本編に引き込まれているはずだ。「嵐が丘」を昭和の日本に置き換えた本書の結末がどうなるかと固唾を飲みながら。
ここまで読むと、本書が著者の創作なのか、それとも序や長い長い前書きで著者が何度も強調するようにほんとうの話なのかはどうでも良くなる。
本書の本編は、祐介が冨美子か聞いた太郎とよう子の物語だ。だが、そこで語られた言葉が全ての一語一句を再現したはずはない。そこかしこに著者の筆は入っている。
だから本当のことをベースにした物語と言う考え方が正しいだろう。
本書の終わりはとても物悲しい。
私が『嵐が丘』を読んだのは20代の前半の頃なので、あまり筋書きも余韻も覚えていない。
が、本書の終わり方はおそらく『嵐が丘』のそれを思わせるものなのだろう。
本書の舞台となる時代は、戦後のわが国だ。
一方の『嵐が丘』は18世紀の終わりから19世紀初頭のイングランドが舞台だ。
その二つの時代と国だけでも大きな隔たりがあるが、戦後日本の移り変わりは、まだ旧家の価値観を留めており、物語としての本書の設定を成り立たせている。
たが今はどうだろう。世の中の動きはグローバルとなり、仕組みもさらに複雑になっている。つまり、本書や『嵐が丘』のテーマとなった価値や信条の大きな断絶が成り立たなくなりつつある。
いや、断絶がなくなったわけではない。むしろ、世の中が複雑になった分、断絶の数は増えているはずだ。
だが、読者の大多数が等しく感じるほどの巨大な断絶はだんだんとなくなっていくように思う。
もちろん、人間と人間の間にある断絶は細かく残り続けるだろう。だが、それを大きなテーマとしてあらゆる読者の心に訴求することにはもはや無理が生じている気がする。
本格小説に限らず、これからの小説に大きなテーマを設定することは難しくなるのではないか。
あるとすれば人間と人間ではなく、人間と別のものではないか。例えば人工知能とか異星人とか。
だが、そのテーマを設定した小説は、SF小説の範疇に含まれてしまう。
人と人の織りなすさまざまなドラマを本格小説と定義するなら、これからの世の中にあって、本格小説とは何を目指すべきなのだろう。
本書のテーマや展開に感銘を受ければ受けるほど、本格小説、ひいては小説の行く末を考えてしまう。
著者の立てたテーマは、本書を飛び越えてこれから人類が直面する課題を教えてくれる。
2020/11/5-2020/11/7