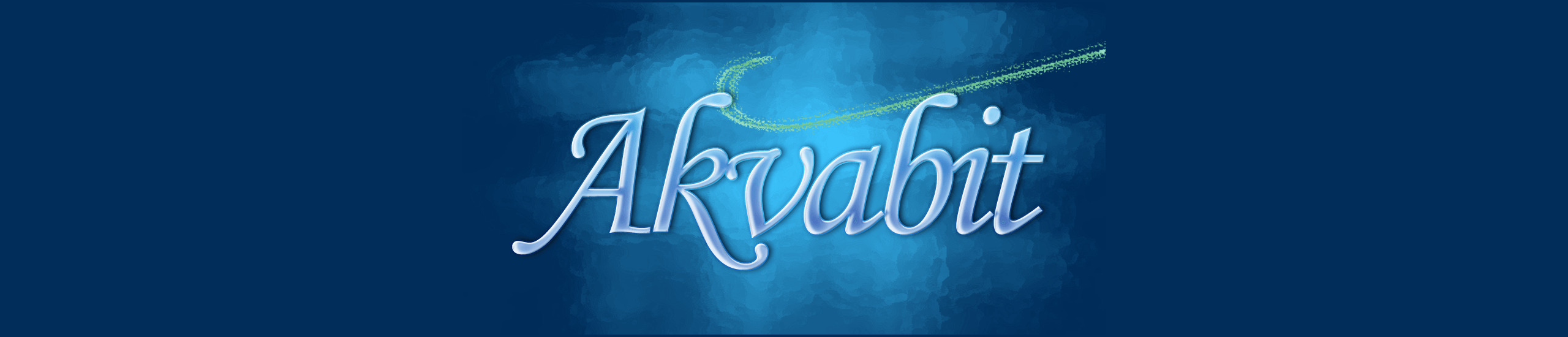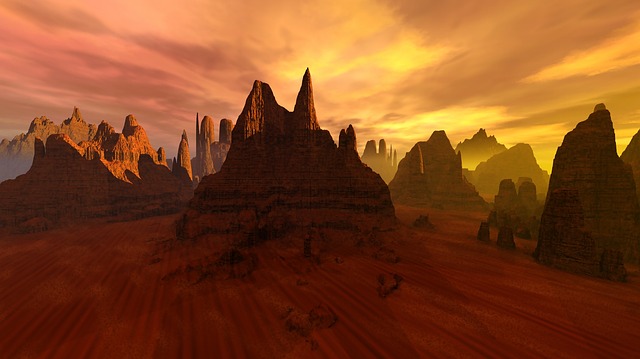あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。
弊社の起業までの航海記を書いていきます。以下の文は2018/3/8にアップした当時の文章が喪われたので、一部を修正しています。
衝動的にホームページの作成に取り掛かる

今の私には、いくつもホームページを立ち上げた経験があります。
単にウェブサーバーにファイルをアップロードするだけではありません。サーバー用マシンを購入するところからはじめ、Linuxのディストリビューションのインストールから、Apache、MySQL、PHPをインストールするところまで。
社内ネットワークを敷設しましたし、サーバーの中を開けてメモリーの増設も経験しています。その他にもいろいろと経験を積んできています。
当たり前ですが、そんな私にも初めてホームページを作った時がありました。
真っさらな状態からHTMLの〈head〉タグや〈body〉タグの勉強を始めた瞬間が。今回はその時のことを思い出してみたいと思います。
本連載の主旨である起業への道筋を語るには不可欠のはずなので。
前回の連載で娘の誕生に立ち合った経緯を書きました。その時の感動は、私の内部に記録したい、表現したいという欲を呼び起こしました。娘の誕生の感動をホームページで表現しなければ。そんな衝動に駆られ、私は矢も盾もたまらずホームページ作成に取りかかります。
娘の誕生が12/28だったので、仕事も正月休みに重なっていたことが幸いしました。
私の知る限り、その当時はブラウザーを使ったウェブアプリは一般的ではありませんでした。もちろん、スカパーのカスタマーセンターの中でも私の知る範囲では使われていなかったはずです。というのも、ブラウザーといえばInternet ExplorerかNetscape Navigatorの二択だった時代。ブラウザーとはシステムのためのものではなく、あくまでもビジネスの広告媒体、つまりホームページの表示用のソフトでした。つまり、私も含めた大多数の人にとってブラウザーとは誰かがアップしたページを見るだけの場所でした。
もちろん、私の知識もその程度。ですから、技術的にも大したページは作れません。ページも静的なHTMLだけで作りました。CGIどころかJavaScriptも皆無。CSSすら適用しなかったように記憶しています。フォントサイズはCSSで指定せず、フォントタグの中の要素値として指定するのが一般的でした。
ホームページの設置場所もどこに置けば適切なのか分からず、ドメインについての知識もありません。そこで、当時加入していたインターネット接続プロバイダー(DTI)の加入者用スペースを利用しました。そこにFTP接続用のソフト(FFFTP)で接続し、HTMLで組み上げたファイルと画像をアップロードします。そうすると、プロバイダーから割り当てられたURLでページが閲覧できました。
独学でホームページ作成を学ぶ
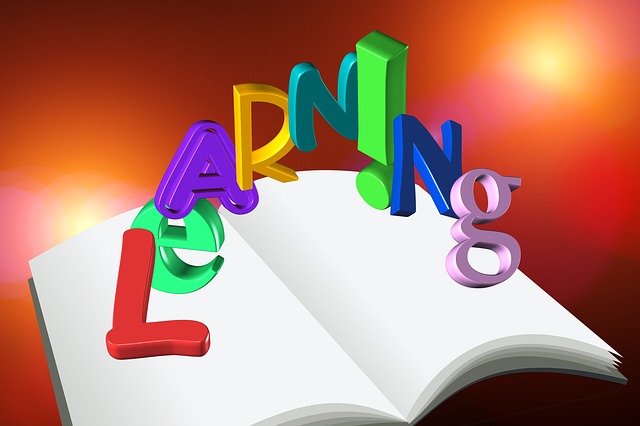
私は一からホームページの作り方やアップロードのやり方を調べました。どのようにすればホームページがアップロードできるのか。ページが表示できるのか。確か「とほほのWWW入門」には多大なお世話になったはずです。
その結果、娘が生まれた次の日あたりにはホームページをアップすることができました。確か、取りかかってから半日程度だったはずです。ちょうどその時、娘の誕生を応援するため、私の母も東京に来ていました。出来上がったばかりのホームページをうちの母に見てもらいました。
今の私の感覚からすると単に〈html〉や〈img〉タグを組み合わせただけのページに半日はかかりすぎです。でも、それも無理はありません。
私にホームページのいろはを教えてくれる先生はおらず、サーバーやネットワークの概念から独りで学ぶ必要がありました。学びつつ作業する。ですから半日でアップできたのはむしろ早かったともいえます。
この時、独学でホームページの仕組みを学んだことは、私のその後に有益でした。もちろん起業の上でも。
冒頭にも書いたように、今の私はホームページの仕組みについてさまざまな経験を積んできています。それらの知識はほぼ独学で学びました。
芦屋市役所で学んだマクロの初歩も、スカパーで集計の仕組みを改良したのも独学。そしてホームページ作成も。
もちろん、芦屋市役所でお世話になったSさんや「集計チーム」で私にアクセスを教えてくれたOさんのように、その時々で私の手本となる方はいました。それでも私は独学で学んだのだとと思っています。
言うまでもなく、独学は学習効率から考えるととても非生産的です。本来は褒められることでも自慢することでもありません。ですが私にとっては独学とは自分の力で得た知識なのです。それは私に自信を与えてくれています。
その経験は尊く、自分の力で手に職を身につけた実感。これは自信となりました。私の起業の本質は独学にあると思っています。
連載の第十九回で妻と出会ったきっかけが電子掲示板であることは書きました。そしてその当時の私が電子掲示板やICQを使って英語で海外の方とコミュニケーションをとっていたことも書きました。しかし、当時の私はただブラウザーを利用するだけでした。裏にどれだけ複雑なロジックが使われているかも意識することもなく。
そんな私がホームページをアップする作業を経験したことで、私にとってブラウザーの位置づけが変わりました。単にホームページを見てコミュニケーションするためのソフトから、コンテンツをアップし自分を表現する場所へ。ホームページを独力でアップしたことにより、私は自分を表現するための手段を手に入れました。
ホームページ作成で起業の発想はなかった

ブラウザーで何かを表現する。この時、私が表現したのは娘の誕生の感動です。
その時ホームページに掲載した十数枚の画像の中には、娘が生まれた瞬間をとらえた際どい画も含まれていました。それも含めてホームページとは表現なのだと思います。
そして、ホームページをアップすることによって、私は表現とはこれほどまでにやりがいのある営みなのかという感触を得ました。
この時、私がもう少しホームページの可能性を真面目にとらえていたら、関西にいる時に抱いていたクリエイティブな職に就きたいとの望みはもっと早くに叶っていたのでしょう。それどころか、ホームページを使った起業さえ成し遂げていたかもしれません。
ただし、それは今だからいえる話。当時の私はそのような発想を全く持っていませんでした。
その頃の私はあいかわらず旺盛に本を読みまくっていました。そして、何かで私自らの生の証しを立てたいと夢想していました。でも、残念ながら、それは夢想でしかなかった。当時の私はあまりにも未熟でした。
しかし未熟であるが故に伸び盛りでもありました。私が自分の伸びしろを持て余し、自分の能力の可能性に戸惑っていました。自分の可能性を感じながら、何に向かって具体的な努力をすれば良いのか、全く理解していませんでした。
今から考えれば、その時の私には強大なチャンスが目の前に転がっていたにもかかわらず。
私の心の中にビジネスで身を立てる発想は皆無でした。
私がビジネスに興味を持てなかった理由。
それは妻の妊娠と娘の出産を控えた親の心情にかかわりがありました。娘には自分が親として教えられることの全てを伝えたい。良き父、良き夫でありたい。そんな理想の家庭像、理想の自分像に私が縛られていたのです。
その幻想は私の眼にはとても魅力的に映りました。クリエイティブな職を目指す余地を奪うほどに。
何にもまして日々の生活が十分なほどクリエイティブだったのですから。娘の誕生、結婚の日常、そして広大な家での生活。仕事も含めて全てが新鮮でした。
そのクリエイティブな状態は、娘が生まれる二年前の自分を比較すると隔世の感すらあります。二年前の私はブラック企業で追い詰められ、何も考えられなくなるまで消耗していました。それから二年。正社員となり、妻をいつくしみ、娘の誕生にまで立ち会えました。しかも持ち家まで構えていられる。
そんな風に恵まれた自分が、その当時の境遇に満足し、上を目指そうと思えなかったのも仕方ないと思えます。その時の私は、クリエイティブな職を目指すだけのモチベーションを持ちようがなかったのです。自分の境遇の変化に追随するだけで精いっぱいだったのでしょう。
ところが、世間的にはステータスであるはずの持ち家が、私を苦しめはじめるのです。
次回からは持ち家の処分について語っていこうと思います。ゆるく永くお願いいたします。