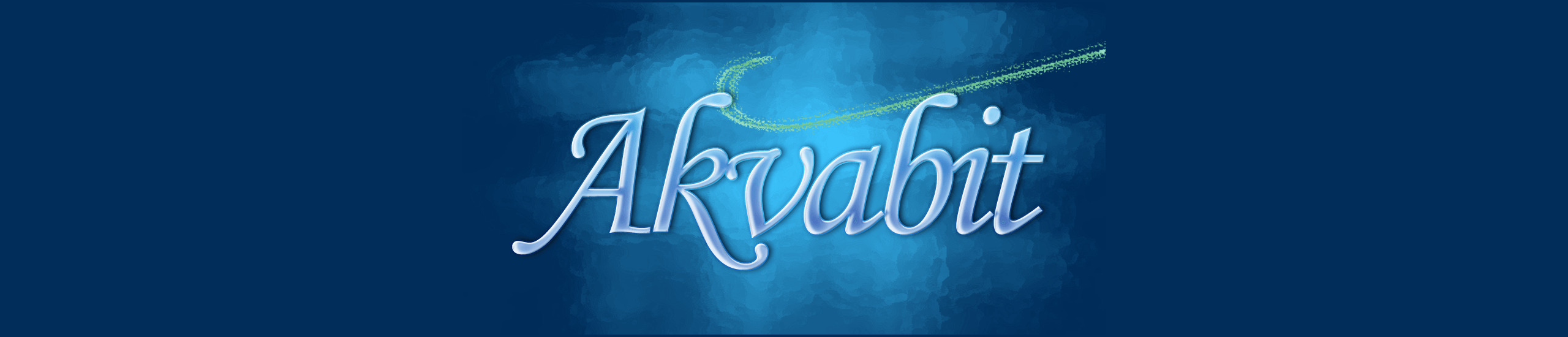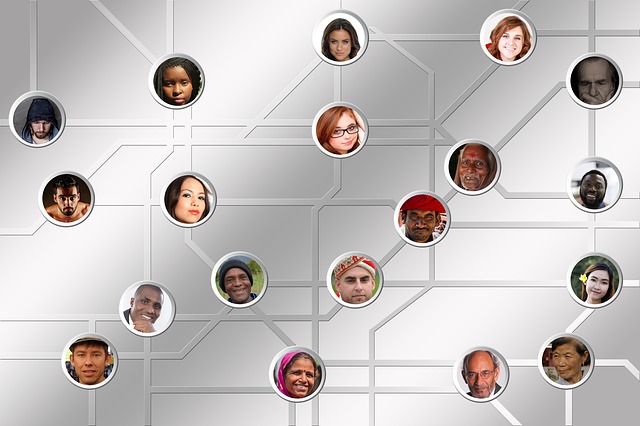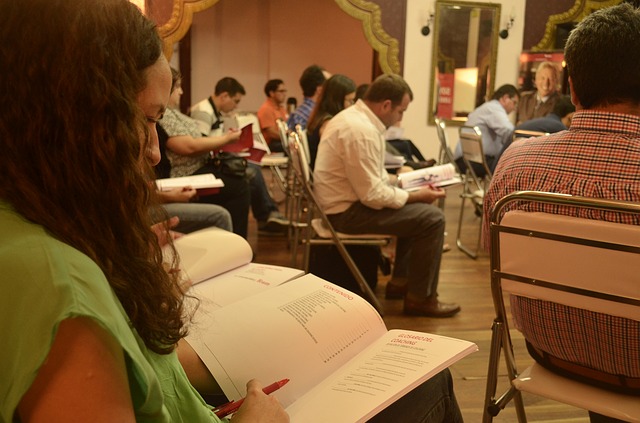
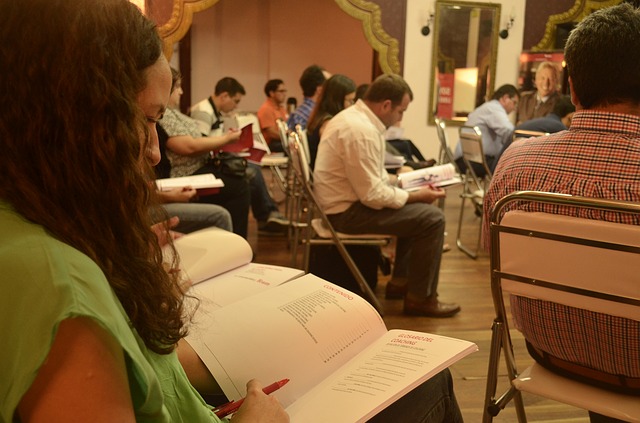
あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。前回にも書きましたが、弊社の起業物語をこちらに転載させて頂くことになりました。第二回~第六回までは起業をポジティブにとらえた視点での利点を述べました。前々回、前回に続き、今回も起業のデメリットを語っています。前回、起業前であれば、利害関係が友人との関係にモロに響くことはあまりない、と書きました。ところが、“起業”してからは、その辺りがガラッと変わります。今回はここから続けたいと思います。なお、以下の文は2017/10/13にアップした当時の文章そのままです。
“起業”すると新たな知り合いは増えますが、責任を背負っての付き合いになります。
個人事業であれ、法人であれ、組織のトップである以上、組織の不始末は代表の責任です。責任を分散させ、曖昧にすることは許されなくなります。組織はかばってくれないのです。よく、経営者は孤独だ、という言葉を聞きます。それは責任者である以上、甘んじて引き受けなければなりません。
では、“起業”すると新たな友人を作れないのでしょうか。私の個人的な経験ではそうではありません。むしろ、人と知り合いになれる可能性はより増えます。
“起業”すると、広告塔としての役割を担わねばなりません。トップセールスマンとしての自覚が求められるのです。ということは、外に出かける機会も増えます。セミナーや異業種交流会、パーティーなど。そのような場所に集うのはあなただけではありません。“起業”した方々が同じような目論見で集ってきます。そこでは、“起業”した方だけでなく、“起業”を目指している、または“起業”しつつある人々にも出会えることでしょう。要するに価値観の似通った方が集まるのです。そこで知り合いを作ることはそれほど難しくありません。むしろ、利害の対立がなければ、一生の友人に出会える可能性もあると思います。
ところが、そういった方々は組織のトップであることが多い。従って、利害が対立した時にはお互いが矢面に立たねばなりません。お互いが組織の責任を背負う立場である以上、いざ利害が対立すればたもとを分かたねばならないこともあります。利害が関係構築の邪魔をしたり、仲を引き裂いたりもします。“起業”した皆さんはそれがわかっています。そして、利害を絡めないようなうまい付き合いの方法を模索していきます。ですから、“起業”すると大人の付き合いに長けていかざるをえません。あまりお互いの内部に深く立ち入らず、当たり障りのない話題に終始するような。もっともこれは組織の中で生きていく処世術でもあるため、大人であれば多かれ少なかれ身に着けるスキルなのかもしれませんが。
友人との起業について。

また、信頼できる友人と共同で“起業”する、という事例もよく聞きます。でも、私に言わせるとそれも賛否の分かれるところです。なぜならば、もとからある友人との仲など関係なく、ビジネスである以上は利害が割り込んでくるからです。仮にその友人との関係が、利害とは関係ないところで結ばれた場合はなおさらです。ビジネスの冷徹な利害に直面して、なおも続く友情であればよいのです。が、下手すればせっかく結んだ友情関係だって壊れてしまうかもしれません。
「安心」と「信頼」について。

前回、組織と個人を対比させる際に「安心」と「信頼」という二つのキーワードを示しました。それはどういうことでしょうか。このキーワードは社会心理学者の山岸俊男氏が提唱しています。「安心」とは組織の中の論理です。組織の中でその人物が受け入れられてゆく過程で、組織はその人物を「安心」できる人物として認めます。つまり、組織に属していることは、自らが「安心」できる人物と外部に示すことでもあるのです。一方、組織から外に出て独立することは、「安心」という組織のセーフティネットから出ることと等しい。個人の立場で外に出る時、私たちは自らが「信頼」できる人間であることを示さねばなりません。組織の提供する「安心」のかわりに「信頼」が求められるのです。
新たに知己となった方とお会いするとき、われわれは無意識に「安心」と「信頼」の基準で判断している。それが山岸氏の提唱する主旨です。同じ組織に属しているか、組織の肩書を背負った方であれば「安心」できます。ところがお会いした方が個人事業を営んでいるか見知らぬ会社の代表者であった場合は「安心」はできません。そのかわりに私たちはお会いした方が「信頼」できるかどうかを見極めねばならないのです。利害が衝突するリスクを引き受けてもお付き合いできるかどうか。
学生時代のトモダチには、「安心」も「信頼」もありません。ただ気の合うトモダチなのです。ところが、社会にでると「安心」を基準に仲間が作り上げられます。そして、“起業”すると「信頼」をベースに友人を構築していくのです。ですから、“起業”してから新たに組織を構築する行ないの中には、自らが「安心」できる組織を作りたい希望が含まれている。そんな仮説も可能です。そう考えると、仕事を広げるための体制作りには「信頼」から「安心」への回帰願望があるとみなしても許されるかもしれません。利害が衝突する「信頼」から「安心」へと。
安心から信頼へ。“起業”する前とした後では、あなたが身につけなければならない観念には違いが生じるのです。それこそが私が実感した友人との関係の違いではないかと思います。利害のない中で心を許し合うトモダチ。安心を背負って交際する仲間。そして信頼を武器に付き合ってゆく友人。私の本音は、その区別を取っ払いたいと思っています。「安心」でき「信頼」でき、さらにそこを超えて心を許し合え、本音で付き合える友人。そんな友人を“起業”してからも作っていければ。私は常にそう願っています。
この点をデメリットとみるか、「信頼」を身に着けるチャンスとみるか。それは皆さん次第だと思います。
次回も引き続き、起業のデメリットを語っていこうとおもいます。ゆるく永くお願いします。