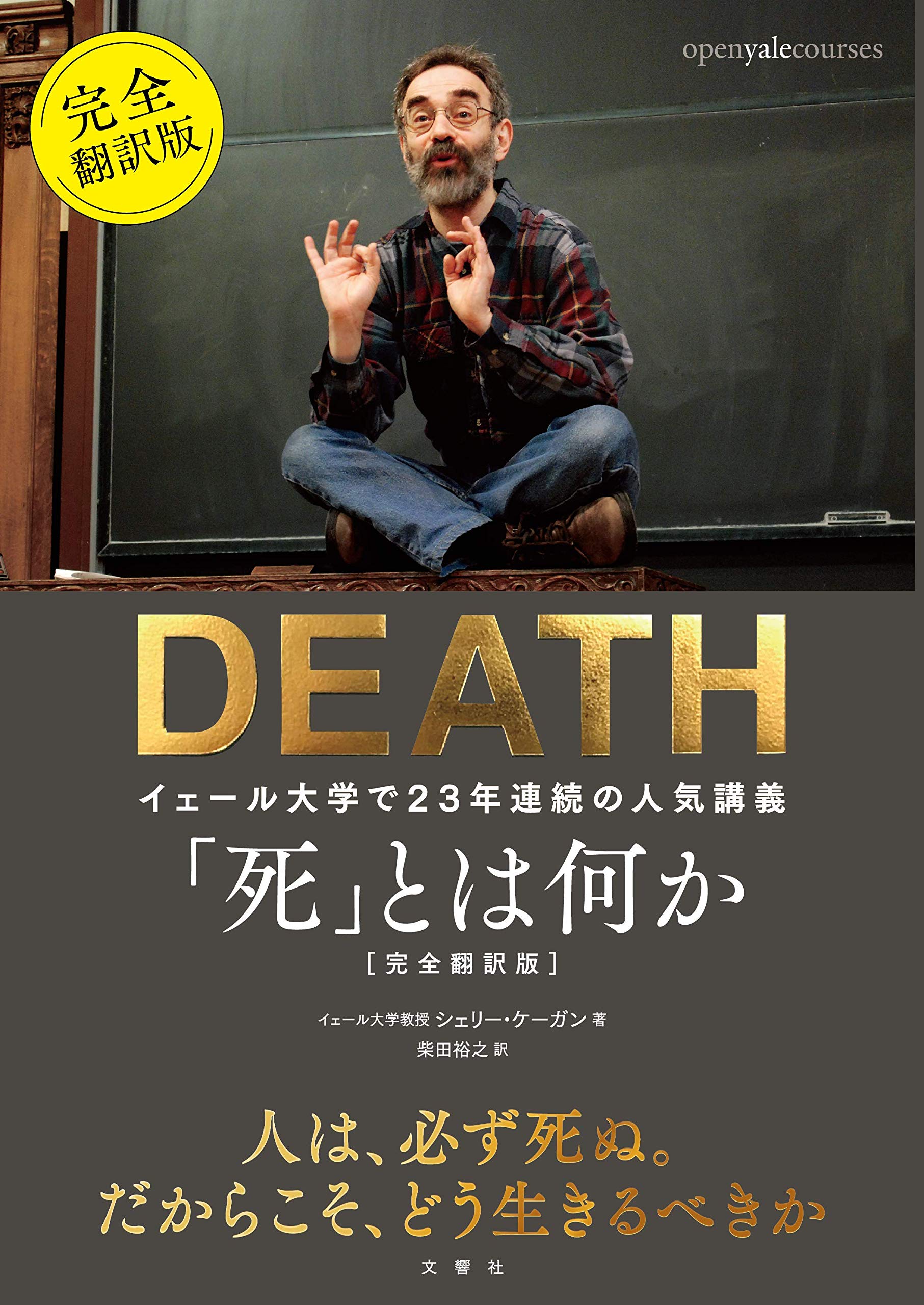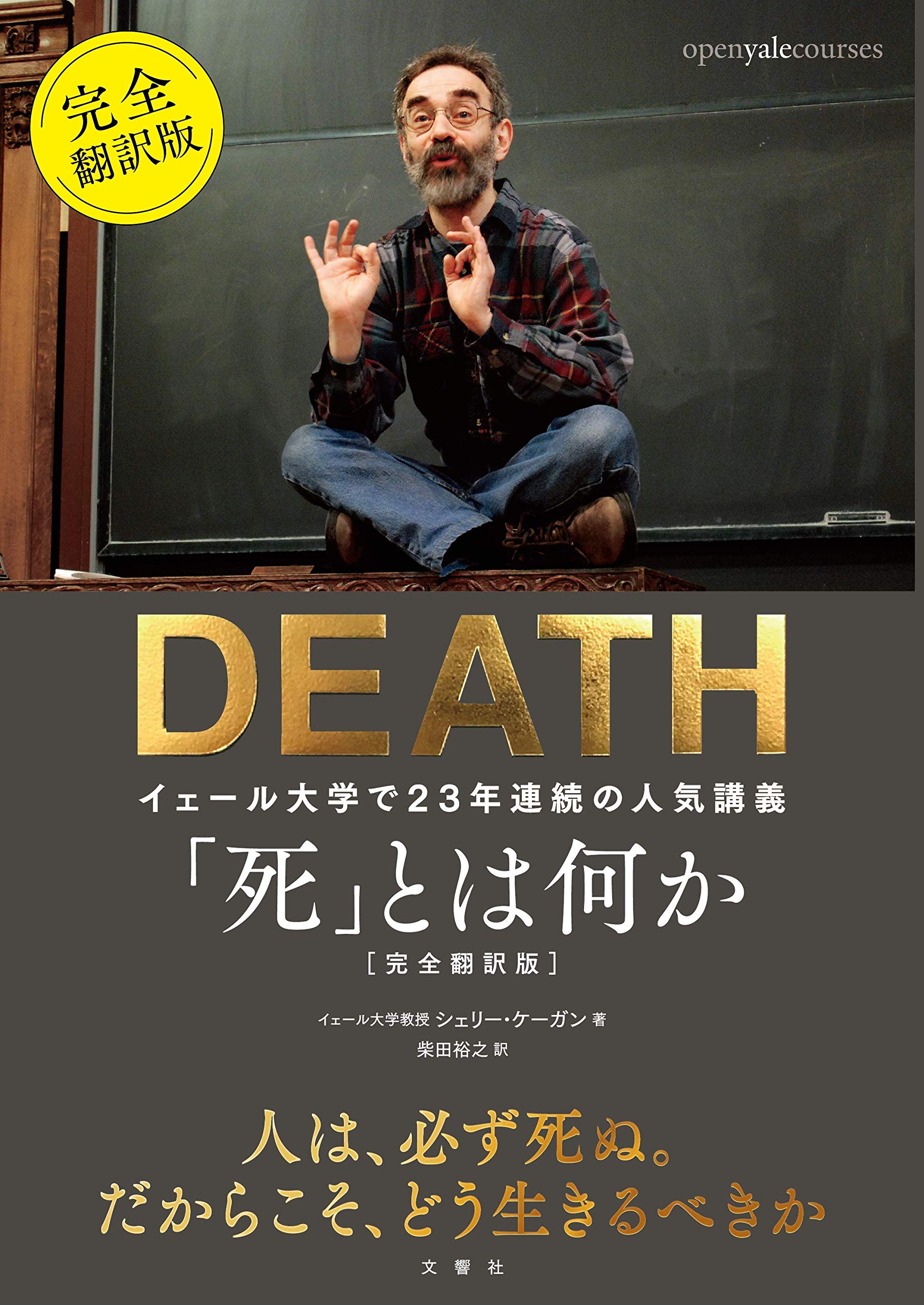
本書はその重厚な分厚さと、壇上にあぐらをかいて語る著者の風貌が目につく。本屋や書評でも見かけ、読みたいと思っていた。
そこで47歳の誕生日の自分へのプレゼントとして妻に買ってもらった。
47歳。あと3年で50歳を迎える。いわゆるアラフィフだ。人生の後半戦であり、その後にやってくる死が意識の端にのぼり始める。
永遠に続くはずと思い込んでいた日々。そのはるか先に暗闇、つまり無が口を開けている。無が私たちの前途を黒く塗りつぶす光景は、想像の難しい領域だ。だが、誰にも必ずその終わりは来る。それに備えておかなければ。
本書のテーマである「死」は、私にとって知っておかねばならないテーマだった。
本書はイエール大学で23年間続いたという講義の内容をもとにしている。
とはいえ、本書は死についての本質を明快に語ってくれるわけではない。世に多くある哲学書と同じく、本書は死の概念の周囲を歩き回りながら、さまざまな視点と切り口から死の本質を覗き込もうとしている。
死は著者の慧眼を持ってしても一言で言い表せる類の概念ではない。そのため、本書は決して読みやすいとは言えない。
だが、ありとあらゆる切り口と視点から死と生を語る本書は、私たちにその概念を考えるきっかけを与えてくれる。
自己の同一性や時間の概念。魂の存在や死後の世界。そして自殺は倫理的に正しいのかについての考察。
以前もどこかで書いたように思うが、子供の頃の私は死を恐れていた。
死んだらどうなるのか。自分が死んだ後、世の中は何も変わらず続くのに、世界でたった一つの自我は無に消える。そのことが耐え難く恐ろしく、心の底から死に慄いていた。
頭では、ほぼ全ての人間が自我を持っていることは分かっている。だが、自分の主観から見た世界は、他人の客観から見た世界の間には絶対的な違いがある。唯一無二の自我。それがどうにも理解できないでいた。
それから40年以上が経過した今、私は日々の仕事の忙しさを乗りこなすのに精一杯だ。死や虚無を恐れる暇がない。
私にとって仕事とは、死の恐怖を忘れるために人類が発明した営みだと思っている。
でなければ仕事のための仕事や、管理のための管理がまかり通っている理由がない。
だが、無我夢中で仕事と戦っていた時期に終わりが見え、ある程度乗りこなせるようになってきた。子育ても娘の卒業が見えた今、関わる必要が薄れてきた。
そうなると、次に考えるのは自分の死にざまだ。後半生では、死に向かうだけの自分の生きかたを考えなければ。
だが、今の私には死それ自体や、死の後に来るはずの虚無よりも恐ろている事がある。それは、残りの時間に自分がやりたいことがやれない未練だ。死の瞬間、私は自分のしたいことができずに死んでいく無念を全霊で悲しむだろう。
そうした迷いの数々を振り切りたくて、本書を手に取った。
著者はまず自らの死生観を明らかにする。そこで明言するのは、死後の魂を否定することだ。来世や輪廻、天国を否定する著者の口調に一切の迷いはない。死ねばそれで終わり。救いもなければ、やり直す機会もない。そもそも著者にとって死は悪いものですらない。
死は悪くない。その考えは果たしてどこから来るのか。死とはいったい何にとって悪いのだろうか。死を残念がるのは、死する主体、つまり魂なのか。その時に死ぬのは肉体だけで、魂は別と主張する人もいる。
では、肉体と魂は別々の存在なのだろうか。肉体が死んでも魂が別ならば、死を恐れる必要がない。魂があるなら死後の世界も生まれ変わりもあるだろう。天国すら存在するかもしれない。
だが、それを実証する術は私たちにはない。著者は魂の不在を主張する。だが、ないことを証明できない以上、魂が存在しないとも断言しない。
魂や意識は今の科学でも説明ができない。物質主義に寄った立場を隠そうとしない著者も、魂の存在については両者が引き分けと言っている。
著者は物質主義を貫くが、性急に結論を出さない。デカルトやプラトンの見解を援用し、詳細に彼らの哲学を検討し、本当に魂は存在しないのかについての綿密な論考を重ねてゆく。
私たちが魂を信じる理由は、自己の一貫性があるからだ。夜に寝て朝に起きた時、前の日の私と今の私は同一人物だ。私たちはそれを当たり前のこととして受け入れている。だが本来、それは証明ができない。同一に見えるのは外見だけ。もし精神に変調をきたした場合、前の日と次の日の自分は同じなのだろうか。それを証明する手段はない。だが、私たちはその同一性を当たり前のようにして日々を生きている。
著者はこの同一性を魂ではなく人格だと説く。記憶、肉体、魂で歯なく人格。
著者は人格こそが人の本質であることをほのめかす。この自己同一性があるからこそ、私たちは自分の人格を信じる。同一性が大切なことは、時間と空間を隔てても保持できることからも分かる。肉体と魂は別ではく、肉体の一機能である脳機能の発現こそ人格。
ここまで、本書の400ページ弱が費やされている。まだ半分だ。死とはまず何の主体に対しての死なのか。それをきちんと定義しておく。それが著者のアプローチだ。
ここまで論を深めた上で、著者はようやく死とは何かについて語る。意識の不在が死であるなら、睡眠もまた死と言えるはずだ。だが、睡眠が死とは違うことは誰もがわかっている。
そもそも本人にとって悪い事とは何か。悪い事と意識が認識して初めて、それが悪い事になる。意識とは生きている。悪い事を認識するには生きていることが必要だ。
では、意識が虚無である死のなかで、死は本人にとって悪い事なのだろうか。
さらに、意識のない状態が悪ならば、生まれてくる前の状態は本人にとってどういう状態なのか。生とは無限の時間の中で一瞬だけの間の話なのだろうか。
死が人間にとって悪くないとすれば、生きている間は人にとってどのような状態なのか。それが永遠に続く、いわゆる不死の状態は人にとって果たしてあるべき姿なのか。それは悪いことではないのか。
上に出てきた自己同一性の問題も不死が必要なのかについて考える題材になる。不死の体現者となった時、人は何百年、何万年と生きるだろう。その時、膨大な時を隔ててもその人は果たして同じ人物と言えるのだろうか。
10,000年前の自分が考えていたことを完全に覚えていない場合、自分は10,000年前の自分と同じ人物と言えるだろうか。
不死も同じ理由だ。しかも、不死と言っても常に成長を続けることはできない。どこかで衰えや飽きに苛ませられる。その時、不死は人にとって良いことではなくなる。むしろ、身の毛のよだつと言う表現まで使って著者は不死を拒否する。
そのように突き詰めて考えると、死は悪いことでない。
その上で著者は人生の価値、人生の良し悪しが何かについて述べる。
結局、人は死によってその生を中断させられる。来世も転生もなく。限られているからこそ、生を輝かせようとする。
著者は本書において明確な生の本質を語らない。むしろ、著者自身も自らの考えをまとめながら死を考えているように思う。
だが、著者による回りくどくも精緻な分析は、私たちが普段、考えずにやり過ごしている己の生を考えさせてくれる。本書から明確な死の定義を求めようとしても無駄だ。
だが、宗教が形骸化し、元となった仏典や経典が顧みられなくなった今、現代の人が死を考え直さねばならない現実を本書は教えてくれる。
正直に言うと、私は本書を読んでもなお、膨大な時間を求めている。数万年の生を。だが、いざ不死が自分の身に訪れた時、一億年もの間、衰えや飽きを知らずに生きていけるだろうか。
それを考えるためにも折に触れ、本書を読みなおしてみようと思う。
2020/9/2-2020/9/25