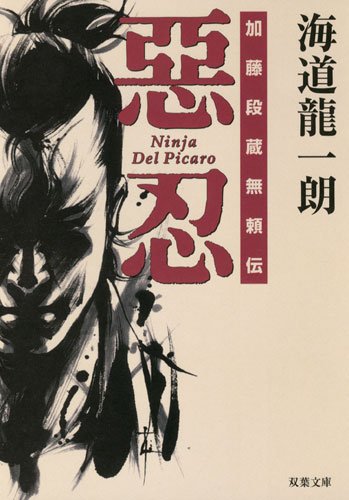
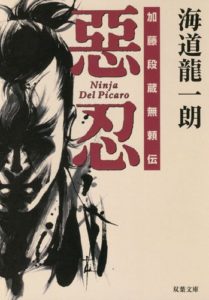
著者は戦闘シーンの書き方が抜群にうまいと思う。川中島合戦を描いた『天祐、我にあり』は戦闘シーンのダイナミズムを間近に感じられる力作だった。
本書は戦闘をより個人的な行いとして描いた作品だ。忍。忍とは人目を忍んで仕事をし遂げるのが極意。本書でも忍びの非道な生きざまはしっかりと描かれている。飛び加藤、鳶の加藤といえば、私も名を知っている有名な忍びだ。確か『花の慶次』にも出てきたはず。加藤段蔵が活躍したのは戦国群雄が割拠し、まだ覇者が誰かすらも定まらぬ時期。つまり、織田信長が頭角を現す前の時期だ。
そのような時期だからこそ、伊賀も自由に自治権を行使し、自由で放埓でありながら、生き延びるには厳しい国であることができた。そして、加藤段蔵のように伊賀ですら窮屈なはみ出し者が存分に活躍できたのかもしれない。伊賀に育ちながら伊賀に歯向かい、自由な一匹狼として忍びの世界で悪名をとどろかせる。痛快ではないか。その生きざまには迷いがない。ただ悪を貫くことに徹している。全ては己の人生のため、己が生き抜くため。武でも忍びでも一流ならば、人を惑わす達者な弁舌もだてではない。
加賀一向宗の実顕を相手にし、越後の長尾景虎を相手に堂々と引かず、朝倉の武将、富田景政を通じて朝倉宗滴に取り入り、甲賀の座無左を欺いて己が手下に使い、伊賀の弁天姉妹と怪しく絡みながら、児雷也を手下に術を掛ける。その一方で千賀地服部や雑賀衆、軒轅などの忍びの軍団とも戦う。本書には伝説の忍びともいわれる加藤段蔵の姿が生き生きと描かれている。まさにエンターテインメントとして楽しんで読める一冊だ。
上にも書いた通り、加藤段蔵が活躍したのは、戦国がもっとも戦国だったころだ。その頃を描いた小説を読むことが最近は多い。それは、人物が諸国を自由に往来し、自由に戦えたからだろうか。登場する人物が生き生きと振る舞っているのだ。それに反し、信長が天下布武を宣してからは、クローズアップされるのはトップの大名である武将たち。忍びや武芸者が活動する余地がどんどん狭まってしまう。要は窮屈なのだ。せいぜい、宮本武蔵のような風来坊の武芸者にしか許されない生き方なのだろうか。私は、組織に属することを潔しとしない人間だ。なので、なおさら、加藤段蔵のような一匹狼に心ひかれてしまうのかもしれない。加藤段蔵のような人間がのびのびと活躍できた頃、戦国が割拠していた頃の物語が面白い。
私にそう思わせるほど、加藤段蔵も、周囲の人物も魅力的だ。登場人物のそれぞれがきっちりと書き分けられているし、魅力的に描かれている。著者の筆の冴えだ。忍びの術を駆使しての戦闘シーンは、声や闘気などの擬音を漢字一文字に凝縮する工夫がとても効果を上げている。それが躍動感を与え、展開にスピーディーなリズムを加えている。忍びとはなんと魅惑に満ちた存在か。最近、和田竜氏による『忍びの国』が映画化された。私はその原作を読んだ(レビュー)。多彩な忍びの技が繰り出され、伊賀を縦横に駆け抜ける内容に、忍術の魅力をあらためて知った。忍びを題材にとった小説など講談もので使い古されたと思いきや、まだまだ書きようによっては魅力的な題材ではないか、ということを『忍びの国』から教えられた。だが、忍びの非情さが描けているか、という観点から読むと、本書のほうが『忍びの国』より上回っていたように思う。それは、本書のテンポや文体が、迅速こそ命の忍びに合っているからだと思う。
私は歴史小説を何冊も読んできたし、名作と思えるものにも数多く触れてきた。だが、細部の描写のうまさは著者が一番ではないかと思うぐらい、著者の細部の描写が気に入っている。こればかりは作家が持って生まれたセンスとしか言いようがない。
ただ、後半にいたり、弁天姉妹が登場し、彼女たちが段蔵にちょっかいをかけ始めるあたりから、少々筆が急ぎすぎてしまったような気がしてならない。前半の濃密な展開が素晴らしかっただけに、少しバランスが欠けたのが残念だ。そのあたりから、段蔵の描写からもすごみが消えたような気がするのは私だけだろうか。弁舌の巧みさは、眼光の鋭さと無類の武芸の強さとのバランスがあってこそ。後半はそのバランスが弁舌に傾きすぎていたような気がする。
さらにいうと、本書の終わり方にも少し不満がある。続編の存在を存分に匂わせつつ、物語が唐突とも言えるほどに終わるからだ。果たして最初から続編を見越して書かれていたのかどうか。それは私にはわからない。本書から6年後に『修羅 = El diablo de la lucha 加藤段蔵無頼伝』が発行されており、本書の続編が書かれたのは確か。ただ、それならばもう少し本書の終わらせ方にも工夫があってもよかったはず。細部の描写が優れているだけに、全体の構成がチグハグだったのが惜しい。著者の他の作品もそう。構成がアンバランスなのだ。
そうした不満はあれど、本書の細部には神が宿っている。この描写の妙を楽しむためにも、続編はぜひ手に取ってみるつもりだ。たとえ構成のバランスが崩れていたとしても、細部の描写で私を魅了させてくれるに違いない。そして私を忍びの世界へといざなってくれるはずだ。
‘2017/10/2-2017/10/4


