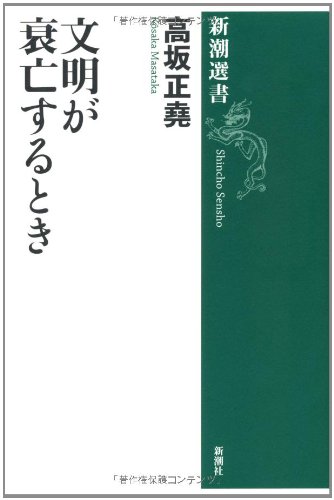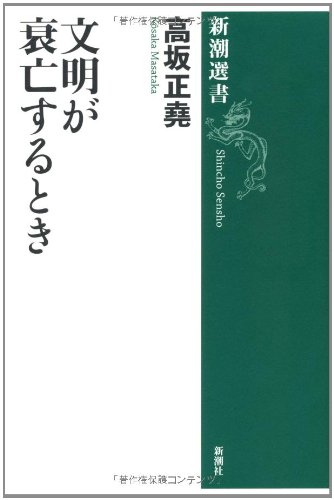わが国をめぐる問題を挙げろ、と問われて答えをいくつ思い浮かべられるだろうか。私はすぐに十以上は用意できると思う。
では、その問題の中ですぐに解決策が見いだしやすく、しかも今のわが国に悪い影響を及ぼしている問題を一つ挙げろと言われればどうだろう。
その場合、私は東京への一極集中を挙げる。
本書にも書かれている通り、都心への一極集中は地方から人を一掃し、消滅の危機に追いやっている。
そして、都心の機能は3.11の時に如実に現れたとおり、飽和の極みにある。このまま問題を放置しておけば悪い事態に陥るのは確実。
だが、一極集中への解決策は他の問題(国防、少子化、移民、地震、感染症、温暖化、宇宙からの災厄、人工知能、遺伝子)に比べるとまだ対策のしようがあると思う。少子化をのぞいた他の問題は日本だけでは難しいが、一極集中は国内でどうにかできる問題だからだ。
本書は、このまま手をこまねいていると896の都市が亡くなると危機感をはっきり表明している。そして、それに対してさまざまな打つ手を提示している。
元岩手県知事で総務大臣も務めた著者が提示する現状認識と処方箋は明確だ。白い表紙がおなじみの中公新書で、赤一色の本書の装丁は目立つ。内容もあいまって本書はベストセラーになったという。
だが、こうした危機が迫っているにもかかわらず、国が一極集中へ本腰を入れて対応しているとはとても思えない。それどころかマスコミもこの問題については口を閉ざしているように思える。
おそらく出版・マスコミ業界がもっとも一極集中の恩恵を受け、また、促進してきた当人だからだろう。
だが、新聞離れ、テレビ離れが叫ばれている今、もう既存のビジネスモデルに未来はないと思う。
インターネットは情報の価値を拡散し、都市でも都会でも情報が等しく受け取れるようにしてしまった。
今や、情報に関しては都会の優位性はなくなっている。あえて言うなら、ネットワーク越しよりも対面で会った時のほうが受け取れる情報は多いぐらいだろうか。
なぜ人は都会に出てきてしまうのか。
その理由は、従来から言われていた仕事があるかどうか、に尽きるのではないか。
戦前や戦後、農村から出稼ぎと称して多勢の人々が都会へと出てきた。それが戦後の高度経済成長につながった。そうした成功の体験を今も引きずっているのが日本ではないだろうか。
ネットワークがない時代、情報は都会が独占していた。都会にはチャンスがあり、金が流れていた。だから人々は集まってきた。都会だと仕事につける。地方にはないやりがいが都会にはある。そうした幻想がわが国をいまだに縛っている。
かつての私もそうだった。
兵庫の西宮に住んでいた私は、私が求めていた編集者には大阪ではなれないと思い、東京に出てきた。
もちろん、理由はそれだけではない。
当時、付き合っていた今の妻が東京に住んでいて、しかも歯科大学の病院に勤務していたため、動けなかったという理由もある。
私の場合、東京に出た理由はそれだけだ。東京に対する憧れはなかった。
家から自転車を漕いで1時間で大阪の梅田に行けた。そもそもファッションやビジネスに興味がなかった。
もし妻が仙台に住んでいて、私が望む仕事があれば仙台にだって向かっていたかもしれない。
そういう過去をもっている私だから、今の若者が地方から都会へと向かう理由も分かる。
当時の私と同じような動機だろうと察する。漠然とした都会に対する憧れで東京に出てきて、そして消耗してゆくのだろう。
その理由や幻滅はよくわかる。なので、私は今の若者たちを非難しようとは思わない。
それどころか、そうした若者に対して地方に仕事先が就職先が用意されていれば、都会に来なくてもよいのではないか、と提案したい。
今や、私が上京した頃と違い、ネットワークが日本の全土を覆っている。
仮に地方から都会に出てきたとしても、仕事が終わればスマホとにらめっこしているのであれば、都会に住む意味はないはずだ。稼げる仕事の有り無しの違いにすぎないので。
そして今、職種にもよるが、地方で仕事は可能だ。
私の仕事は情報系だが、ネット会議で大抵のことはケリがつく。仕事の発注から受注、納品までを一度も顧客と会わずに済ませたことも何度もある。
本稿をアップする二週間前には奈良の下北山村に行き、二泊三日でワーケーション体験をした。
コワーキングスペース「Shimokitayama Biyori」のWi-Fi環境が良かったのか、AWSのオンラインカンファレンスに参加し、東京で行われた顧客との会議にもオンラインで参加できた。
また、この体験で、田舎の暮らしはお金がかからないことも知った。そもそもお金を使う場所がないのだ。
都会には刺激的なものが多すぎる。そして、その刺激が仮にネット上のコンテンツで満たせるのであれば、地方でもそれは享受できる。
個人の性格にもよるが、私の場合、二週間に一度、東京や大阪に出られればそれで十分。それであれば地方でも働けるし暮らしていけるめどはついた。
だが、その体験をもってしても、本書の内容を読むにつけ危機感が募る。
本書には今後の人口予測と消滅可能性のある896の市町村のリストも付されている。
そこには当然、下北山村も含まれている。しかもこのリストによれば2010年の下北山村の人口は1000人を超えているが、先日訪れた時点ではWikipediaの情報では800人を割っていた。
日中でもほとんど車が通らない下北山村のメインストリートを思い出すにつけ、「消滅」の二文字が切実に迫ってくる。
本書では国による国家戦略の必要も記されている。
だが、今の国会ではモリ・カケ問題や桜を見る会やその他の大臣の失言の糾弾にばかり時間が空費されている。
そのような足をすくわれるようなことをしでかす与党にも失望させられるし、そうした問題をあげつらうばかりの野党にも期待が持てない。
党利党略や利益誘導より、国家の大計に取り組み、足元をしっかり固めて喫緊の課題に注力してほしいと思う。
マスコミももっともっとこの問題には発言してほしい。旅情を誘う番組もいいが、一極集中の問題の危機感を報道しないと何が報道機関か、と思う。
少子化の問題も本書は一章を割いて取り上げている。そして、都会の生きにくさが子作りの妨げになっていることは確実だ。
保育園落ちた日本死ね!!! のブログが反響を巻き起こしたことは記憶に新しい。これもまた、都会の生きづらさの顕著な例だと思う。
子育てをしながら働ける環境を。企業においてもそうした対策が求められていることは自明のことだ。
もし自社の利益を追求するモチベーションを自社の百年後の存続にあると考えているならば、少子化を甘く見るとそもそも会社のサービスの売り先が消え去っていますよ、と忠告したい。
本書にはさまざまな処方箋が載っている。それらの一つ一つはもっとも。
だが、実際に効果を上げうるかどうかはやってみてはじめて分かる点が多い。
だから二の足を踏むのではなく、今のうちに取り組まなねば間に合わないのだ。
本書には各地に人口流出のダムとなる地を作る対策を挙げている。
たとえば下北山村を例に挙げると、村の若者が外に出るのを防ぐのは難しいかもしれない。だが、その流出先が東京ではなく、熊野市や尾鷲市であれば下北山村にはすぐ戻れる。
そうしたダムになりうる都市を各地に育てていくべき、という提言には賛成だ。
ある程度の経済規模さえ確保してもらえれば、都会の人が地方で転職する際にもハードルは少ない。
本書では、そうしたモデルケースとして北海道を取り上げている。
今、日本で最も過疎化が進んだ地域と言えば北海道だろう。
私もあの原野の雰囲気は好きだが、それが将来の日本全土の景色と言われれば、言葉を失ってしまう。
北海道の中でも札幌だけがダムになりうるのではなく、函館、帯広、旭川、釧路といった都市をダムとして、それ以上の流出を食い止める。本書にはその事例が詳しく載っている。
それでは地域がどのようにして雇用を創出していけばよいか。
この課題は当然、考えられなければならない。今までにも議論は出し尽くされてきている。
本書には地域が活きる6モデルとして、産業誘致型、ベッドタウン型、学園都市型、コンパクトシティ型、公共財主導型、産業開発型が挙げられている。
どれもが可能性があるモデルだと思うが、地域によってどれを選ぶかは、地域の特性にもよるだろう。
本書は最後に増田氏と識者による三つの対談が載っている。
最初は藻谷浩介氏との対談。藻谷氏はかつて私もブログで取り上げた『里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く』の編者でもある。(a href=”https://www.akvabit.jp/%E9%87%8C%E5%B1%B1%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%AE%89%E5%BF%83%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%80%8D%E3%81%A7%E5%8B%95%E3%81%8F/” target=”_blank”>レビュー)
二人の結論もやはり今のままでは地方ばかりか日本も破綻するというもの。
さらにお二人は提言として東京に本社を置く必要の意味を問うている。アメリカではニューヨークに本社を置く企業は四分の一だが、日本の場合、七割が東京にあるという。
二つ目の対談は、小泉進次郎氏、須田善明氏と行っている。
小泉氏は政治家として著名だが、須田氏は宮城県女川町の町長であり、東日本大震災で被害にあった町の復興を担当している。
本稿をアップする今、小泉氏の株はかなり下がってしまった。だが、小泉氏が一極集中を問題として認識していることはこの対談でも述べられている。そして今も持ってくれているはずだと期待している。
結局、一極集中の解消を国家戦略として策定し、それを確実に遂行していかなければこの問題は解決しないと思う。
その戦略とは東京オリンピックや大阪万博ではない。地方を主役にしたイベントを誘致するといったことでもない。
たとえば、本社の機能を六大都市以外の都市に移した企業に対しては税務上の優遇措置を与えるとかの策でもあるし、いつの間にか誰も言及しなくなった遷都の問題を真剣に議論することでもある。
三つ目の対談は、慶応義塾大教授の樋口美雄氏と行っている。
6モデルに即した地方の生き残り策を提言しているが、それらを推進するためのリーダーの存在が指摘されている。
まったくその通りだと思う。本当であれば、地方から選出されたはずの国会議員が担うべきことだが、国政や党政を優先させることに汲々としている。
本書を読んで思うのは、考えるよりも実行の必要性だ。
もちろんそれは私や弊社にも当てはまる。
東京に登記し、東京に住んでいる私。働き方を変えることで朝夕の通勤ラッシュを一人分だけ解消させることができた。
ここ数年、地方でも講演する機会も増えてきた。ワーケーション体験に参加し、地方で働き、暮らす可能性も確信できた。
働き方改革を掲げるサイボウズ社のkintoneを担ぐことで、地方の方とのご縁は増えてきた。
そうした実践ができる立場にある弊社と私。だが、それが実体ある生活として地方に還元できているとはとてもいえない。
下北山村へ伺う契機となった紀伊半島はたらくくらすプロジェクトはカヤックLivingさんをはじめとした複数の企業が共同している。そうした取り組みがすでになされている今、私も弊社に協力できることはあるはず。
これから私や弊社に何ができるのか。これからも動いていかねばなるまい。
‘2018/11/13-2018/11/16