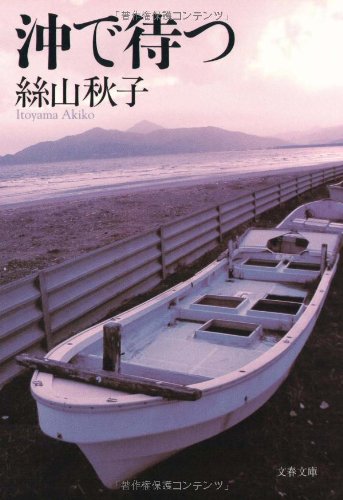
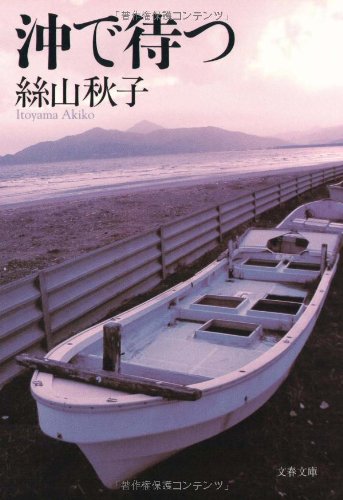
私は芥川賞の受賞作をよく読む。芥川賞の受賞作は薄めの文春文庫に二話められていることが多い。一話は受賞作で、もう一編は同じぐらいの量の短編というように。ところが本書には三編が収められている。しかも行間はたっぷりとられ、フォントも大き目に。それはつまり、各編が短いということだ。著者の作品を読むのは初めてだが、短めの話を得意とされているのだろうか。
著者についても本書についても予備知識がゼロで読み始めた。ところが始めの二編はサクサク読める。著者の経験に題材を採ったと思われる二編は、状況も展開もとっぴではない。誰にでも訪れそうな日常のイベント。そんな普通のイベントに向き合った主人公の日々が読者の心のみぞおちをくくっと押す。
「勤労感謝の日」はお見合いの話だ。アラフォーの主人公恭子のもとにお見合い話が舞い込む。見合いなんて、さして珍しい話でもない。だが、冒頭で勤労感謝の日に毒づく恭子の内面が露になるにつれ、恭子が無職である事が徐々に明らかになる。そんな恭子に残されたのは逃げ道としての結婚だ。
ところが見合いの席に現れた野辺山という男は恭子をがっかりさせる。風采、態度、言動のすべてが冴えないのだ。野辺山の全部に反感をもつあまり、見合いの席を中座してしまう恭子。恭子からは結婚の逃げ道すら遠のいてしまう。気の置けない後輩を渋谷に呼びつけて呑みなおす。が、この後輩も空気の読めない女なので、カイコはサナギまでが美しいけど成虫になると醜くなるというなどとやくたいもない話を婚期を逃しつつある恭子に語り、さらには彼氏と行く旅行の話までのたまう。家に帰っても恭子には見合いに同席した母から今日の逃げ出した振る舞いを愚痴られる。いたたまれず一人でなじみの店を訪れて愚痴を聞いてもらおうと思っても、折あしく生理が来てしまう。女である事の負の面だけが重く心に沈む。
でも、なじみの店でふっと心の重荷を下ろしてはじめて、恭子は今日が勤労感謝の日であることに気づく。勤労って、仕事のことだけじゃなく、生きることもまた勤労。そんな人生の中にぽっと浮かんだ救いにも似た終わりかたが印象的だ。本編は芥川賞の候補にも挙がった。
「沖で待つ」は、主人公と太っちゃんの交流を描いた一編だ。同期入社の男女。恋愛でもなくただの顔見知りでもない不思議な関係。会社で新卒された同期とはじっくり考えると不思議な関係だ。共学のクラスメイトよりも交流が生じる。同僚とはある種特有の結びつきが生まれるのかもしれない。新卒で入社していない私にはわからないが。
新卒で会社に入らなかった私は、同期など一人もいない。一度だけ中途で入った会社では、10人ほど同時に入社した。彼らはたぶん、同期と呼べるのだろう。けど、入社から3カ月以内に私も含めてほぼ全滅した。社内ではあまりにも追いまくられたため、写真すら撮っていない。一度ぐらい一緒にカラオケに行った程度か。今では顔も忘れてしまった彼/彼女らを同期と呼ぶのは無理がある気がする。そんな私だから本書に描かれた及川さんと太っちゃんの関係はうらやましい。
会社にはいろんな出来事が起こる。例えばクレーム対応、営業、出張、転勤など。会社に入ればどれもが避けようのないイベントだ。本編にはそれらがつぶさに描かれる。そんな中で二人の関係は付かず離れず続く。そしてある日、不慮の事故で太っちゃんは死んでしまう。
そこからが本書の独特の展開に入る。生前の二人が交わした約束。それはどちらかが先に死んだら片方の家にあるパソコンのハードディスクを使用不能にするというもの。ハードディスクの形を棺桶と表現し、中の円盤を死の象徴にたとえるあたりに作家の感性を感じる。
本編は2005年の芥川賞受賞作だ。その頃からわが国でもSNSがはやり始めた。私たちが死んだとき、ブログやSNSにアップしたデータはどこにゆくのか。今の私たちはその機能がFacebookに備わっているのを知っている。だが当時なこのような発想は目新しかったように思う。この点に着目した著者の視点を評価したい。
信頼できる関係とは何か。同じ性別だから、一つ屋根の下に住む家族だから信頼できるのか。そうでもない。同じ会社に勤めていれば、利害を同じくするから信頼できるのか。そうでもない。人と人とが心を許し合うことが、どれだけ難しいか。だが、人は一人では生きられない。自分が死んだ後始末を託せるだれかは必ず持っておいたほうがいい。例えばパソコンの中の個人情報を託せる誰かに。人の信頼関係を無機質なハードディスクに見立てたことが本編の優れた点だ。
「みなみのしまのぶんたろう」は、全編がひらがなとカタカナのみで構成されている。本編を読みながら、私の脳裏に去来したのは、筒井康隆氏の「大いなる助走」だ。「大いなる助走」は文学賞選考にまつわるドタバタが描かれている。何度も落選させられた作家が選考委員に復讐するラストは筒井氏の真骨頂が味わえる。本編の主人公「ぶんたろう」は大臣の経験者で作家との設定だ。となれば「ぶんたろう」に擬されているのは石原慎太郎氏のほかはありえない。
ふとした失策で南の島の原発に流された「ぶんたろう」の日々が描かれている。かなとカナだけの内容は、童話的な語りを装っているが、内容はほぼ完全に慎太郎氏を揶揄している。そうとしか読めない。
著者が「沖で待つ」で芥川賞を受賞するまでに三たび芥川賞の候補者となった。直木賞にも一度候補に挙がっている。その中で著者が石原慎太郎氏に対して含むところでもあったのだろうか。芥川・直木賞の選評を紹介するサイトもみたが、そこには石原慎太郎氏による著者の作品への選評と批判が載っていた。が、そこまでひどい選評には思えなかった。ここまで著者に書かせた石原慎太郎氏への感情がなんだったのか、私にはわからない。でも、「みなみのしまのぶんたろう」を書かせた著者の思いの強さはなんだか伝わって来る。
‘2017/04/11-2017/04/11


