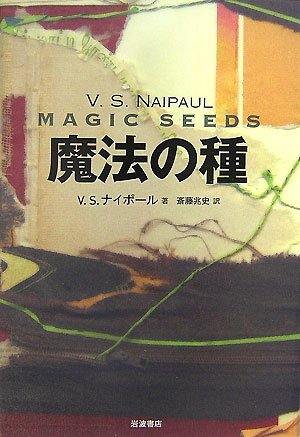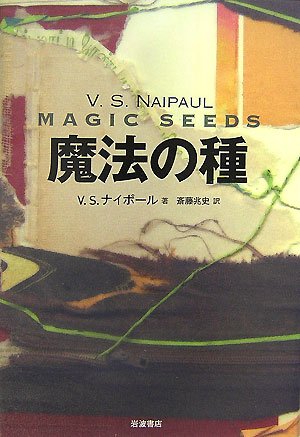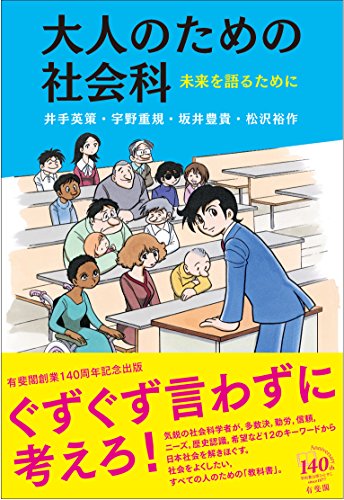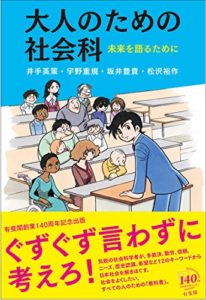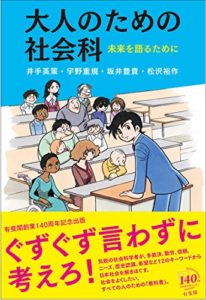
技術書を買いに来た本屋で、もう一冊経営に関する本を買い求めようとした私。ところがどうしてもビジネス書よりも人文科学書に目が移ってしまう。そして平積みになっている本書を見つけた。もともと新刊本はあまり買わない私。だがそれだけに買った本には愛着がわく。成り行きで手に入れた本書は収穫だった。刺激を受けただけでなく、新たな知見も得られた。
そもそも私が社会学に特化した本を読むのは初めてだと思う。私が大学で学んだのは商学部だったし。もちろん学際的な視野を身につけるため、他の分野の本も読んだ。経済学、経営学、会計学はもちろん、文学、史学、心理学、政治学あたりまで。経営者になってからは実務の法律知識にも目を通すため、法学にも手を出した。だが、社会学については私の記憶では系統だった本を読んだことがなかった。
私が通っていた大学には社会学部もあった。それなのに社会学が何を学ぶ学問なのか、さっぱり知らなかった。そもそも、社会学が指し示す「社会」が何か分かっていなかった。世間知らずの学生の悲しさといえばよいか。だが、本書を読んで社会学の一端に触れられた気がする。何しろタイトルに社会学と銘打たれているぐらいだから。タイトルに社会学を含んでいるものの、本書の取り上げる範囲は社会学だけに限らない。政治や経済、心理学も含めての社会学だ。つまり、本書でいう社会とは、私たちが生きるこの社会を指している。未熟な学生時代には社会が何かがわからなかった私だが、今はだいぶ分かるようになった。そして、本書がいう「社会」が、われわれが生活を送る上で欠かせない社会であることも分かる。生活に即した社会であり、より良い人生を送るために欠かせない社会。本書は実の社会を取り上げているため、好意的に本書を読めた。
本書がなぜ社会についての本だと思えたのか。それは多分、本書の視線が未来を見すえているからではないだろうか。未来を見なければ今の日本に必要な視座はわからない。本書のいう社会学は、未来を含めた社会学だ。過去だけでもないし、現在のみでもない。未来を見ている。だから現在の日本の課題も明らかにできる。今の日本の課題を社会学を通して的確に把握することにより、本書は、社会学が日本のこれからを考える上で有効な学問であることを示している。
本書は以下のような構成になっている。各章に振られた簡潔な単語は、本書が視野に入れるべきと判断した課題だ。それは社会学が扱える範囲だ、と宣言した課題でもある。それを四つの部でさらに大きく区分けしている。
第Ⅰ部 歴史のなかの「いま」
第1章「GDP」
第2章「勤労」
第3章「時代」
第Ⅱ部 <私たち>のゆらぎ
第4章「多数決」
第5章「運動」
第6章「私」
第Ⅲ部 社会を支えるもの
第7章「公正」
第8章「信頼」
第9章「ニーズ」
第Ⅳ部 未来を語るために
第10章「歴史認識」
第11章「公」
第12章「希望」
例えばGDP。GDPといえばGross Domestic Product、つまり国内総生産のこと。経済指標の一種だから、経済学に属する言葉と思われがち。だが、著者によると、社会学の文脈からもGDPは考察に値する概念だという。GDPとは社会の良さを表しているのか、という問いにおいて。というのも、GDPが計上するのは全ての生産物の付加価値なので、マイナスからの復旧もGDPに計上されるからだ。例えば病気の治療費、災害の復旧工事など。だが、それらは社会の良さを上向かせていない。また、国によっては違法な犯罪から生まれた生産物もGDPに計上しているという。例えば銃器や麻薬、密輸品など。それらが社会の良くしないことは、論じるまでもない。そして、シェア・エコノミーの広がりも、GDPの上昇に寄与しない。
そうした点から考えると、社会にとっての良さを測る指標はGDPの他にあるはず。そこで国連開発計画はHDIという指標を提案している。また、ブータン王国は国民総幸福量という指標を発表し、GDPやGNPが重んじられる風潮に一石を投じている。さらには、指標値をどうやって計上するかもさまざまな手法がある。例えばそれぞれの指標を足し算で求める場合(功利主義基準)、掛け算で求める場合(ナッシュ基準)、最小値で求める場合(マクシミン基準)で求める場合、それぞれで同じ指標でも結果に差は生じる。つまり、GDPとは経済学の文脈でみれば有効であっても、社会学からみれば不十分なのだ。第1章「GDP」からすでに本書は社会学の意義を存分に主張する。
第2章「勤労」も、経済学や法学の範疇で扱われることが多い。経済学では古典経済学で勤労の概念が扱われているし、法学では憲法27条にも勤労の義務が謳われておりおなじみだ。ところが本書は社会学の観点で勤労を語る。日本国憲法では、真面目に労働に勤しむことを国民の義務と定めている。それは言い換えれば、義務を果たさない国民に対し、国が生活を保証する義務がないことに近い、と著者は言う。そこから考えると、実は日本とはかなりの自己責任社会なのだ。その視点は社会学ならではのもの。新鮮だ。日本国が国民に対して提供する無償のサービスも、外交、安全保障、教育の三つだけ。これは先進国の中でも少ない部類だそうだ。
本章で示された観点は、さらに引き延ばして考えてもよい。例えばベーシックインカムが日本で根付くのかという議論にも適用できるだろう。今まで民の手で生活をまかなって来た日本人にベーシック・インカムの考えが行き渡るのかという論点で。あと、日本人がなぜこれほどまでに企業に忠誠を尽くすのか、という議論にも使える。国が生活の面倒を見てくれないから企業がその替わりを担って来た歴史も踏まえると、企業への忠誠は今後も根強く残り続けるはず。
続いての第3章は「時代」と題されている。ここには、史学はもちろんのこと、政治学、経済学が含まれる。ここでは時代区分をどう分けるかに焦点を当てられている。時代区分とは古代、中世、近世、近代と時代を区分して考える手法だ。だが、この区分は切り取り方によって変わる。例えば政治体制によって絶対王政や貴族制、立憲民主主義で分けられる。社会体制の変遷によっても区分できる。農奴制や封建制。また、経済体制でも考えられる。狩猟、遊牧、農業、商業の段階によって。もちろん、資本主義や社会主義といったイデオロギーの観点でも区分できるはず。
重要なのは、そもそも区分の仕方自体が、時代によって変化するという指摘だ。あらゆる価値は絶対でない。当たり前だが、日々の生活ではついそのことを忘れてしまう。これは常に肝に銘じておかねばならないことだ。鎌倉、室町、安土桃山ときて江戸、という区分けは私たちにとって常識だ。ところが時代がもっと先を行けば、その区分も変わるだろう。私たちにとっては激動だった明治、大正、昭和すら、未来では違う区分名で括られているかも。
次の第4章「多数決」からは、第二部「<私たち>のゆらぎ」に入る。今の社会が本当に理想的な姿なのか。それを問い続けることに社会学の意義はある。そして人類の歴史とは理想的な社会を求めた日々だ。理想の社会を求め、揺らぎ続けた過ちと失敗。その積み重ねこそが人類の歴史だと言い換えてもよい。社会のあり方をどうやって良くするか。それは、人々がどうやって意思を決定するかを考え続け、試みて来た歴史に等しい。だが、理想的なやり方はいまだ見つかっていない。もちろんいくつかはある。その一つが多数決だ。一見すると多数決による意思決定は合理的に思える。だが、内情を知れば知るほど理想的な解決策だとは思えなくなる。
多数決が理想的な意思決定手段なのかどうかは、今までに何度も行われた選挙の度に議論されてきた。たとえば三択の場合、第三位に投票された票数によって、第一位と第二位が入れ替わることがある。それを改善するため、再び一位と二位で投票を行う決選投票と呼ぶ方法がある。また、有権者が一人一票を投じるのではなく、候補者にランクを付け、その点数によって当選者を選ぶボルダルールと呼ばれる方法もある。単純な多数決で選ばれた結果と決選投票で選ばれた結果とボルダルールで選ばれた結果が違うことは、本章でも簡単な例として理解できる。また、評価の対象によっても結果は変わる。総合評価とそれぞれの政策ごとで投票する場合も、結果に差は生じることが例に示される。それをオストロゴルスキーの逆理という。とても興味深い一例だと思う。
私がパンと膝を打ったのは、コンピューターの父であるフォン・ノイマンの多数決原理が紹介されている箇所を読んだときだ。ノイマンは電子回路にはエラーが起こると考えた。だから複数の回路の処理結果の中で多数決をとり、導かれた結果に基づき後続の処理を進めた。つまり、ロジックの権化であるコンピューターの動作原理にも、あいまいな多数決の論理が含まれている。これはとても参考になる知見だと思う。
曖昧だから、多数決で意思が決定が確定される危険も先人たちは認識してきた。たとえば我が国では、基本的人権に関する法案の制定は憲法で禁じられている。それは、多数決のあいまいさをよく認識した叡智のたまものだろう。そもそも我が国の憲法自体が、改定するための手続きをかなり厳しくしている。それがあまりにも厳しいため、現内閣が意図する憲法改正も、まずそこから着手しようと考えている節があるくらいだ。結局、私たちは多数決原理が必ずしも最善ではないことを念頭に置きながら、日々の決断を下すしかないのだろう。
つづいて著者は、「運動」と名付けられた第5章で、選挙によらず社会を変える方法について記す。運動とは、主張を通すため集団で集まることを指す。選挙で選ばれた代議士が、立法に関わり、それが法律となって国民の生活を縛る。その道以外にも、運動によって立法に基づいたさまざまな政策を変えさせることもできる。憲法第21条にも集会の自由として謳われている。著者は江戸時代の百姓一揆から、明治時代の負債農民騒擾、2015年の安保反対デモを例にあげ、時代や集団によって変わり得る「正統性」を議論する。この「正統性」が揺らぐため、ある時代では正義だった主張が今は違ってくる。本章には”SEALDs”も登場する。いっとき話題となった学生による安保反対の運動だ。著者はSEALDsの主張の是非を問わず、あくまでも中立に運動の現実を論じる。だが、そもそも”SEALDs”の主張が正当性があるものなのかどうかは問われなければなるまい。”SEALDs”は終わりを迎えたが、終わったことを彼らの主張に正当性がなかったからと決め付けるのも良くないと思う。今の世の中は多様性を重んじる方向に向かっている。正当性が求めにくい社会にもなっている。”SEALDs”に限らず、運動に正当性を与えることが難しい時代だ。運動を成り立たせること自体が困難な時代。
続いての第6章「私」では、「社会問題の個人化」がテーマだ。それを説きおこすため、著者は前提から話を進める。その前提とは、多数決と運動が、世の中に個人の主張を反映するため、必ずしも最適なやり方ではないという実情だ。そのため、個人の意思を発揮できにくい無力感が、今の若者に漂っていると指摘する。”SEALDs”も活動を終え、選挙権が20歳から18歳に引き下げられた後も、その無力感は変わらない。むしろ若者に関していえば年齢が上がるにつれ政治に対する無力感が濃くなるらしい、という調査結果もあるらしい。それは、集団から個人へと利害の対象が変わってきたためだと著者は喝破する。確かに、歴史の流れを眺めると争いの多くは、集団の利害が絡んでいた。百姓一揆もそうだし、フランス革命もそう。だが、今は多様化の時代。集団で共通の利害を持ちにくくなっている。集団で活動する”SEALDs”はむしろ珍しい存在なのかも。集団よりも一人の個人が抱える状況によって利害は大きく揺れる。それを著者は「社会問題の個人化」と言い表している。「社会問題の個人化」は、SNSが今の世でこれだけ支持されている理由でもあるのではないか。私にとってSNSを通した自己顕示のあり方とは、常に関心の高い話題だ。そして「社会問題の個人化」を頭に入れ、SNSを眺めるとそのことに合点がいく。匿名の発信に逃げてしまう理由も。
個人の自由には孤独と責任が伴う。エーリッヒ・フロムの『自由からの逃走』の一節だ。フロムは問う。ナチス・ドイツになぜあれほどのドイツ国民がなびいたのか、と。それは個人が与えられた自由を負担として扱いかね、強大なリーダーシップに自由をゆだねたことにある。フロムはそう分析した。自由を持て余す個人。リスクや冒険を苦痛に感じ、自由を与えられるぐらいなら、束縛を望む人もいてもおかしくない。ところが世の中の流れは、個人に自由を与える方向に進んでいる。会社も多様化を許容しつつ、成長に向けて社員をまとめなければならない。その時、個人はどうやって自分に与えられた自由を扱うか。それを持て余しているのが大多数だと著者はいう。その問題はこれからも人類の歴史に付いて回ることだろう。今よりも個人の自由には孤独と責任が伴うことが増えていくはず。
最後に著者は東浩紀氏が提唱する「一般意思2.0」を紹介する。「一般意思2.0」とは、今の民意のありかがネット空間の言論の中にこそ見いだせる、という仮説だ。もしそうだとすると、今はまさに黎明期にあたるはず。当ブログも私なりの意見発表の場であり、自己顕示の場になっている。私の書いた文も、一般意思の一つとして生き残り得るならば、マスターベーションで終わらないだろう。一般意志の一端として、何かしら書く意味が生じる。望むところだ。
第7章「公正」からは「第3部社会をささえるもの」として、価値観について取り上げる。「公正」とは何をもって判断すれば公正なのか。それはもちろん、おのおのの受け止め方によって変わる。では、客観的に見た「公正」は存在しないのだろうか。著者はここで『バビロニアン・タルムード』とアリストテレスが説いた公正の概念を紹介する。二つの概念から導かれた公正の割合は同じ例題を扱っていてもかなりの隔たりがある。特にタルムードの公正から導かれた結果は、今の私たちの感覚からするとかなり奇妙に思える。だが、本章で解説されるタルムードの公正は、それで理にかなっていることが分かる。つまり「公正」とは採用する計算の方法や文化の共通認識に応じて変わるのだ。
これは例えば議決の票数についても当てはまる。一人当たりの票数を所持する株数に応じて与えるべきか、それともあくまで一人一票に限るのか、という議論だ。また、課税の考え方にも公正の考えは適用される。一人当たりの税額を一律にするのか、所得に応じて累進的に課税額を変えるのか、全ての所得を比例で考えるのか。それによって課税額は変わる。公正とは私たちの生活にモロに直結するのだ。そればかりか、もともと私たちは公正についても、ある傾向で捉えているらしい。「公正に扱われたい」という感情として。それを著者は、最後通告ゲームという経済実験で立証されていることを紹介する。最後通告ゲームで示された結果は私にとってかなり参考となった。なぜなら私は値付けがうまくないからだ。どうも低い額を見積もってしまう。相手にとっては有利な、こちらには不利な額を。値付けを低くする傾向にある人は、幸福感が高い=セロトニン値が高いという実験結果もあるらしい。本当だろうか。
第8章「信頼」で示された内容も私にはとても参考になった。日本人は他人を信頼する率が他の先進国にくらべて低い。それは日本が信頼社会でなく安心社会だから、という山岸俊男氏の論を知ったのは、この章からだ。ある個人が信頼できるかどうかは、その個人がその組織にどれだけ長く属しているか。それは長く受け入れられていること、つまりその人物が安心できる人物であるかどうかの尺度だ。それが日本にでは特に強いと山岸氏は説いている。逆に言えばそれは、組織を飛び出した人間が、周りからは安心を得られないため、個人的に信頼してもらうよう努力するしかないことを意味する。だが信頼の考えが日本には根付いていないため、日本で信頼を勝ち得るためのハードルは高い。そして独立・起業に対する難易度も高い。私はこの論にとても刺激を受けた。昨年、とあるブログでも起業のための一章の中でこの論を紹介した。
信頼の概念は他の学問ではあまり取り上げられていないようだ。そのため社会学で信頼を取り扱うようだ。本章ではさまざまな学者の論を紹介する。その中で多かったのは信頼がないと仕事も生まれない、つまり資本主義の発展には信頼の有無が大いに関係するという指摘だ。これはAirBNBやUberといったシェア・エコノミーの発展にも欠かせない。また、私のような独立した者にとっては、仕事の取り方やネットワークの構築の仕方、また、組織の構築にあたってとても重要な考えだ。山岸氏の本はきちんと読まねばなるまい。本稿を書いたことをきっかけにあらためて探してみたいと思う。
第9章「ニーズ」も重要な章だ。なぜ弱者を助けなければならないか、の問いから始まる本章は、社会そのものの存在意義を説いている。なぜ社会が成立するのか。それは人が一人で生きるには自然は過酷だから。だから集団で生活する。それが生き延びるためには最善な方法である。この考えは歴史学でも人類学でも登場する。そして人が生きていく上ではさまざまな必要(ニーズ)に迫られる。
そのニーズは人によっても、時代によっても、属する集団や場所によっても違う。集団に求められる共通のニーズを見いだすのは難しい。そして、そのニーズがどうやって満たされるのかを測ることも難しい。それを人類は貨幣の発明や、税の義務を課すことで解決してきた。一律で集め、なるべく公正になるように分配したのだ。だが、公正が難しいことは、今までの章で解説されてきた通りだ。
そこで個の利益よりも集団の利益を考えることで、人々は社会を維持しようと試みた。弱者をいたわらなければ、自分がその立場になった時に不利になる。「情けは人のためならず」だ。皆のために税を払ったほうが、結果的に自分にとって利益が大きくなる。もっとも、それは理屈ではわかっていても、それを実践することはなかなかできない。
最低の位置にいる人だけに最低限度の保証をするのか、全員に向けて厚みのある保証を施すのがよいか。あるいはその間のどこかか。それは大きな政府、小さな政府という政治学の領域で論じられる問題だし、ベーシック・インカムの導入については経済学の範疇でもある。ただ、それらは全て社会のあり方を考えると同じ分野に属するのだ。ここまで読んで来ると、社会学とは学問が個別化してきたため、カバーしきれなくなった人々の社会を繋ぎ止めるための学問であることが見えてきた。
第10章「歴史認識」からは「未来を語るために」というテーマが論じられる。未来を語るにはまず過去の歴史をきちんと認識しなければならない。それは歴史学が常に考えているはずのテーマだ。だが、第二次大戦の間のわが国民の行いは、70年以上たった今でも論争の対象となっている。南京事件や従軍慰安婦、その他の虐殺や731部隊の人体実験。それらが事実としてどうだったのかを正しく認識することが重要なのはいうまでもない。だが、実際のところは、イデオロギーの対立の道具や、国際政治のカードとして使われているのも確かだ。
著者も従軍慰安婦問題のいきさつや論争を紹介し、このように結論付けている。「しかし、それが人々のあいだに深刻な亀裂をもたらさないようにするためには、まず出来事レベルでの認識を共有し、解釈レベルでの対立が一定の範囲内に収まるようにする努力が必要なのです。」(187-188P)
まだまだこの問題が収まるには長い時間が必要だろう。だが、もしもう一度同じ過ちを起こさないためにやるべきなのは、アーカイブズの運用を始めることだ。本章の前半でもさまざまな公文書(アーカイブス)を保管する施設が紹介されている。いったい、私たちはあらゆる物を捨ててしまいすぎる。かつては軍機に触れるため、今は断捨離やシンプル・ライフの名の下、貴重な資料となるはずの書類が顧みられず捨てられ続けている。日本は土地が狭いとの制限があるかもしれないが、日本もアーカイブズの考えを身に着けねばならないと思う。私はそう思い、以前から自分の人生をライフログの形で貯め続けている。もっともそれを私が見返すことはあまりないし、将来の人々に役立つのかは心もとないのだけれど。
第11章「公」では、プライベートとパブリックの対比を取り上げる。日本では公共性に相当する言葉がないのと同じく、英語でも公共性を表わす言葉がないらしい。公と私の区別は、大人になれば否が応でも意識せざるをえない。私の場合は、公私を区切らないようにしている。だが、この考えは少数派だろう。日本人は公私をとにかく分けたがる傾向があるようだ。
本章はそのあたりを詳しく見ている。さらに、社会が人口の縮減期にはいると、公共性が生まれる傾向にあることも指摘する。それは今までの歴史からも明らかなようだ。そして、これからの日本の人口は必ず縮減する。今までのイケイケな高度経済成長期では軽んじられてきたが、将来は公共性が求められるはず、と占う。公共性の発露はどういう具体性を持って現れるのか。本章では二つの団体の事例を取り上げている。常陸大宮市の医療法人博仁会と、福山市のNPO法人地域の絆だ。そこで挙げられる職員への育児休暇などの制度を手厚くする施策や、地域の高齢者に対するケアの実践は公共性の一つのあり方だろう。他にも高知県の限界集落で自然発生した助け合いのエコシステムの事例も挙げられている。
私の知る会社ではサイボウズ社がまさにそうした取り組みで知られている。そして事業の一つとして社会への還元を掲げる会社も少しずつ増えつつある。公共との連携は、以前から私も考えていることだ。具体的には自治会との連携だが、まだまだ採算の面ではめどがつかない。そもそも非営利団体に潤沢な予算がない以上、こちらも身銭を切らなければならない。それが実情だ。そこをどう進めるかは試行錯誤中だ。企業のCSRという言葉が市民権を得ている今でも、取り組みが実を結び始めるには時間があるかかるはず。本章はそれを理論的に支えるために、もう少し読み込んでおきたいと思う。
第12章「希望」は、まとめとなる章だ。今、未来がみえない。私たちの誰もがそう感じている。人工知能の脅威や地球環境の激変を指摘する論者もいる。日本の場合、未来に向けた不確定要素が少ないため、諸外国よりも対処のやりようがあると説く論者もいる。
本章では、希望と幸福に焦点を当てている。幸福とは現時点で感じる心の状態。希望とは未来の時間を含んでいる。つまり、今ではなく常に未来に目を向ける。「まだーない」ものを考える。それが希望だと本章は説く。今はまだなくとも未来にはあるかもしれない。それこそが希望。もちろん、ただ待っていても希望は叶わない。未来を変えるには正しい方向への努力がいる。だが、今の出来事が未来に影響するのであれば、今、正しい向きへ何かを成せば未来は必ず変わるはず。希望とはそうしたものだ。
本稿を書くため、あらためて本書をつまみ読みした。あらためて、本書から得る物はまだまだ多いと感じる。社会学とはどういう学問かがわかっただけでなく、ビジネスや生き方の観点でも役立つ情報が多かった。本書は社会学が何かを知らない方にこそお勧めしたい。
‘2017/09/19-2017/09/29