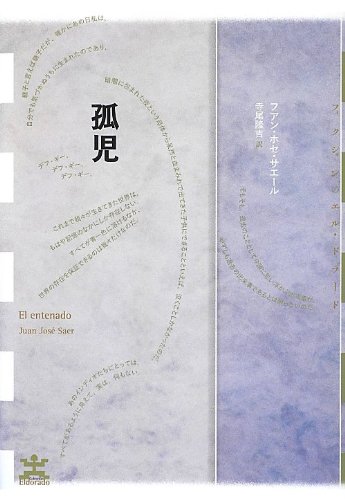著者の作品を読むのはこれで三作目だ。著者は「震災列島」「死都日本」の二冊で、宮崎・鹿児島と濃尾平野を壊滅させている。
本書で壊滅させられるのは、富士山のふもとに控える山中湖村や御殿場市、裾野市のいったいど。
令和の今、富士山が噴火するとどうなるか。おそらく日本は言葉では表せない状態に陥ることだろう。壊滅的。
実際、江戸時代の宝永の大噴火では、富士山から吹き上げられた火山灰が江戸に積もったという。
ところが、今の東京の人々は噴火のリスクをとても楽観的に考えているように思う。なぜなら、江戸の街に降った火山灰は人体に直接の影響を与えず、後世に噴火の恐ろしさが伝えられていないからだ。
だが、現代は江戸時代とは違っている。現代は情報の時代だ。
あらゆる経済活動が情報機器の扱うデータに頼っている。
人々の日常すら、見えないデータの流通がなくては滞ってしまう時代。江戸時代とは社会的な状況が違っているのだ。
それらの情報機器が火山灰の襲来にどこまで耐えうるのか。残念ながら厳しい結果となるだろう。
火山灰の細かな粒子が機器の内部に入り込み、予期せぬ誤動作を起こす。そうなった時、首都の機能はどこまでダメージを受け、人々の生活にはどれほどの影響が生じるのか。
それだけならまだいい。
もし富士山から噴き出た火砕流が御殿場や三島や沼津まで流れた時、街はどうなってしまうのか。
その時、日本の大動脈は切断される。その時、日本の経済はどれほどの痛手を被るのか。
誰にもわからない。
確かに試算はされている。とはいえ、それらはあくまでも試算に過ぎない。
情報社会の恩恵を謳歌している今の日本は、まだ首都圏直下型地震も富士山大噴火も経験したことがないのだから。誰にもその被害は想像できない。
著者は「震災列島」「死都日本」の二冊で、日本の地質上の宿命を描いている。
各プレートがせめぎ合い、マントルが摩擦する上に浮かぶ日本。地震と火山との共存が古代から当たり前だった。
日本が享受している繁栄とは、実はあやうい地盤の上に乗っている。それを認めるのはつらいが事実だ。
それが今までの日本の災害史が示してきた教訓なのだ。
本書の冒頭には上下二段で富士山周辺の地図が掲げられている。
上段では神縄・国府津-松田断層帯の断層が図示されている。下段では富士山が噴火した際、火砕流が及ぶ範囲が図示されている。
神縄・国府津-松田断層帯は、伊豆半島の上部を巡って富士山頂を通り、富士山の西側で富士川河口断層帯となって海へと延びている。
その形は伊豆半島の生い立ちが、もともと太平洋の南の彼方に位置していた古代に起因している。
伊豆半島はかつて島だった。そして日本列島へ北上し、日本列島に衝突した。その衝撃が丹沢山地や富士山や箱根の景観を作り上げた。
皮肉なことに、その衝突によって富士山は日本列島のシンボルにふさわしい姿となり、観光資源を生み出した。そして古くから日本列島に住まう人々に富士山は崇められてきた。
かつては二つの峰を持つ「ふち(二霊)山」として。
時には怒り狂い、人々に自然の圧倒的な力を見せつける。その姿はまさに神。
本書が面白いのは、地質学の最新成果を盛り込みながら、一方で人々にとっての神とはなにか、どうして生まれたのかという考察が豊富に加えられていることだ。
その解釈はとても興味深い。
著者がめぐらす考察の範囲は日本神話にとどまらない。
たとえばソドムとゴモラで知られる旧約聖書の挿話も本書には登場する。シナイ山とアララト山の関係も。
地球の変動が人類の深層記憶として刻まれ、それらが各地で神話として語り継がれてきた。
太古の人類にとって、火山の噴火とは人知が圧倒的な及ばぬ力を感じさせる一大イベントだったことだろう。
火山こそが神と等しかった。神は怒らせると噴火や地震としておごり高ぶる人類に鉄槌を下す。
その一方で噴火は人類に火を教えた。熱を加えることで肉は食べやすくなり、食物は殺菌できるようになる。人々の健康は増進し、寿命を延ばした。
世代間の伝承が進むようになり、人間は文明を持つまでの進化を遂げた。それらもすべて神、つまり火山が人類にもたらした恩恵だ。
ホモ・サピエンスが生まれたのはアフリカの大地溝帯であることはよく知られている。そしてその地は火山地帯でもある。
著者は本書の主要な登場人物である山野承一郎の口を通して火山=神説を語る。
類人猿が人類へと進化したきっかけには火山の噴火があった。この説にはとても興奮させられた。
長きにわたって伝えられてきた火山の恩恵と恐ろしさ。それは人類に神への畏敬を生み、人々は神によって導かれ、種として成熟を遂げた。
本書は冒頭で徐福伝説を登場させ、富士山のふもとに徐福の墓を置く。もちろんそれは著者の創作だろう。
秦の始皇帝から命ぜられ、蓬莱山に不老不死の薬を探しに来た徐福。彼が富士山を発見し、それを神の象徴として感じたという想像。それはロマンチックな心を目覚めさせる。
本書では富士山が噴火する。その圧倒的な描写は本書の一つのクライマックスだ。
だが著者が書きたかったのは、その破壊の側面ではないはずだ。上にも書いた通り、著者は火山が人類に恩恵を与えてきたことを記してきたからだ。
では、富士山が本書で描かれる通りに噴火したら、日本列島に住む私たちにはどのような恩恵をもたらされるのだろうか。
私は、その恩恵とは東京への一極集中を終わらせることにあると思う。富士山の噴火をきっかけに首都圏の機能が壊滅的なダメージを受ける。それをきっかけに日本列島の各地に分散した日本人。それが未来ではないか。
そういえばかつて日本沈没を描いた小松左京氏も、分散した日本人に希望を見いだしていた。私もそう思っている。
4-06-213705-4
‘2020/01/27-2020/01/28