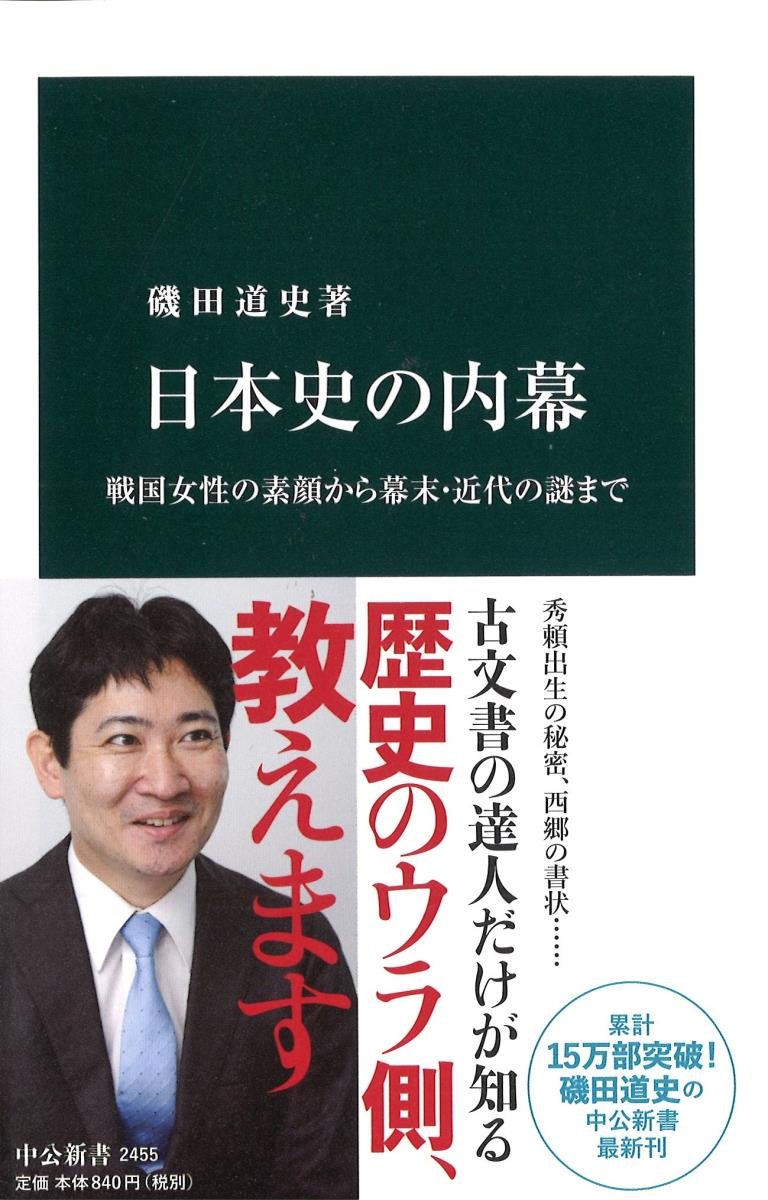
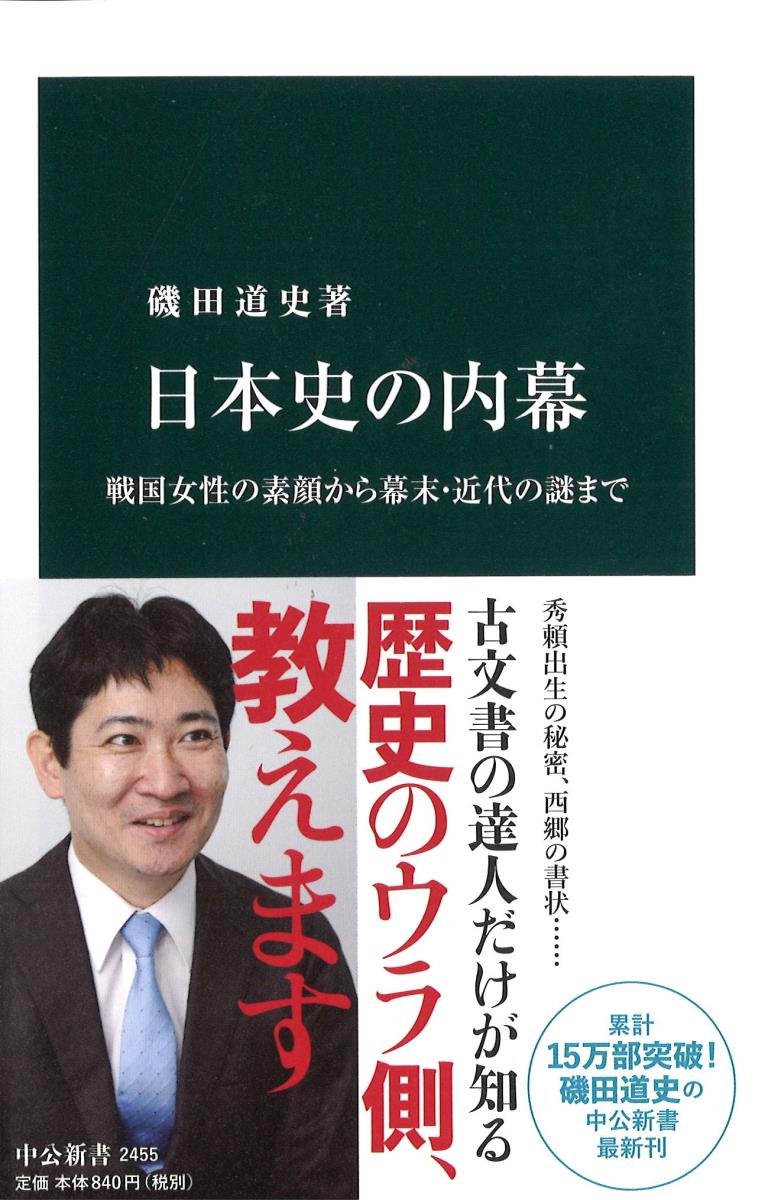
著者のお顔はここ数年、テレビでよくお見かけする。
テレビを見ない私でも見かけるくらいだから、結構よく出ているのだろう。
そこで著者は歴史の専門家として登場している。
著者の役割は、テレビの視聴者に対して歴史を解説することだろう。だが、ディスプレイの向こうの著者は、役割をこなすだけの存在にとどまらず、歴史が大好きな自分自身を存分に楽しんでいるように見える。著者自身が少年のように目を輝かせ、歴史の面白さを夢中で話す姿には親しみすら覚える。
本書は、筋金入りの歴史愛好家であり、歴史をなりわいにしている著者による歴史の面白さをエッセイのように語る一冊だ。
歴史のうんちく本と言えば、歴史上の謎や、思わぬ歴史のつながりを解きほぐす本が多い。それらの本に比べると、本書は該博な著者の知識を反映してか、独特の視点が目立つ。
著者はフィールドプレーヤーなのだろう。書斎の中から歴史を語るのではなく、街に出て歴史を語る。古本屋からの出物の連絡に嬉々として買いに出たり、街角の古本屋で見かけた古文書に胸をときめかせたり、旧家からの鑑定依頼に歴史のロマンを感じたり。
古文書が読める著者に対する依頼は多く、それが時間の積み重ねによって埋もれた史実に新たな光を当てる。
著者は、あまり専門色を打ち出していないように思える。例えば古代史、平安時代、戦国時代、江戸時代など、多くの歴史学者は専門とする時代を持っている。だが、著者からはあまりそのような印象を受けない。
きっと著者はあらゆる時代に対して関心を持っているのだろう。持ちすぎるあり、専門分野を絞れないのか、あえて絞らない姿勢を貫いているように思える。
私も実はその点にとても共感を覚える。私も何かに嗜好を絞るのは好きではない。
歴史だけでなく、あらゆることに興味を持ってしまう私。であるが故に、私は研究者に適していない。二人の祖父がともに学者であるにもかかわらず。
本書から感じる著者の姿勢は、分野を絞ることの苦手な私と同じような匂いを感じる。
そのため、一般の読者は本書から散漫な印象を受けるかもしれない。
もちろん、それだと書物として商売になりにくい。そのため、本書もある程度は章立てにしてある。第二章は「家康の出世街道」として徳川家康の事績に関することが書かれている。第三章では「戦国女性の素顔」と題し、井伊直虎やその他の著名な戦国時代に生きた女性たちを取り上げている。第四章では「この国を支える文化の話」であり、第五章は「幕末維新の裏側」と題されている。
このように、各章にはある程度まとまったテーマが集められている。
だが、本書の全体を見ると、取り上げられている時代こそ戦国時代以降が中心とはいえ、テーマはばらけており、それが散漫な印象となっている。おそらく著者や編集者はこれでもなんとかギリギリに収めたのだろう。本来の著者の興味範囲はもっと広いはずだ。
そうなると本書の意図はどこにあるのだろうか。
まず言えるのは、なるべく広い範囲、そして多様なテーマに即した歴史の話題を取り上げることで、歴史の裏側の面白さや奥深さを紹介することにあるはずだ。つまり、著者がテレビ番組に出ている目的と本書の編集方針はほぼ一致している。
本書を読んでもう一点気づいたのは、著者のアンテナの感度だ。
街の古書店で見かけた資料から即座にその価値を見いだし、自らの興味と研究テーマにつなげる。それには、古文書を読む能力が欠かせない。
一般の人々は古文書を眺めてもそこに何が書かれているか分からず、その価値を見逃してしまう。だが、著者はそこに書かれた内容と該博な歴史上の知識を結び付け、その文書に記された内容の真贋を見通す。
著者は若い頃から古文書に興味を持ち、努力の末に古文書を読む能力を身に付けたそうだ。そのことがまえがきに書かれている。
私も歴史は好きだ。だが、私は古文書を読めない。著者のような知識もない。そのため、著者と同じものを見たとしても、見逃していることは多いはずだ。
この古文書を読み解く能力。これは歴史家としてはおそらく必須の能力であろう。また、そこが学者と市井の歴史好きの違いなのだろう。
これは私がいる情報処理業界に例えると、ソースコードが読めれば大体その内容がわかることにも等しい。また、データベースの定義ファイルを読めば、データベースが何の情報やプロセスに役立つのか、大体の推測がつくことにも通じる。それが私の仕事上で身に付けた能力である。
著者の場合は古文書がそれにあたる。古文書を読めるかどうかが、趣味と仕事を大きく分ける分岐点になっている気がする。
上に挙げた本書に書かれているメッセージとは、
・歴史の奥深さや面白さを紹介すること。
・古文書を読むことで歴史が一層面白くなること。
その他にもう一つ大きな意図がある。
それは、単なる趣味と仕事として歴史を取り扱う境目だ。その境目こそ、古文書を読めるかどうか、ではないだろうか。
趣味で歴史を取り扱うのはもちろん結構なことだ。とてもロマンがあるし面白い。
一方、仕事として歴史を取り扱う場合は、必ず原典に当たらなければならない。原典とはすなわち古文書を読む事である。古文書を読まずに二次資料から歴史を解釈し、歴史を語ることの危うさ。まえがきでも著者はそのことをほのめかしている。
そう考えると、一見親しみやすく、興味をそそるように描かれている本書には、著者の警句がちりばめられていることに気づく。
私もここ数年、できることなら古文書を読めるようになりたいと思っている。だが、なかなか仕事が忙しく踏み切れない。
引退する日が来たら、古文書の読み方を学び、単なる趣味の段階から、もう一段階上に進んでみたいと思う。
2020/10/10-2020/10/10





