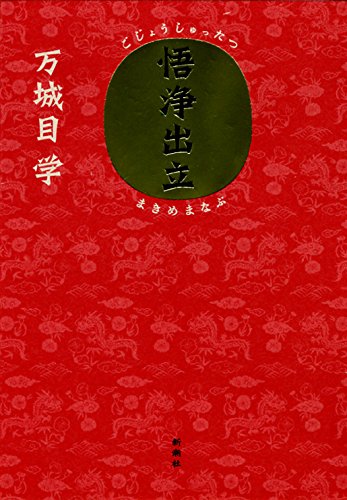
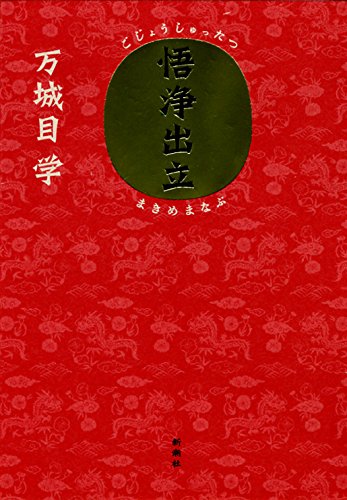
本書によって著者は正統な作家の仲間入りを果たしたのではないか。
のっけからこう書いたはよいが、正統な作家とは曖昧な呼び方だ。そして誤解を招きかねない。何をもって正統な作家と呼べばよいのか。そもそも正統な作家など存在するのか。正当な作家とは、あえていうなら奇をてらわない小説を書く作家とでもいえばよいかもしれない。では本書はどうなのか、といえばまさに奇をてらわない小説なのだ。そう言って差し支えないほど本書の語り口や筋書きには正統な一本の芯が通っている。
今まで私は著者が世に問うてきた著作のほとんど読んできた。そして作品ごとに凝らされた奇想天外なプロットに親しんできた。その奇想は著者の作風である。そして私が著者の新作に期待する理由でもある。ところが本書の内容はいたって正統だ。それは私を落胆させるどころか驚かせ、そして喜ばせた。
文体には今までの著者の作風がにじんでいる。だが、その文体から紡ぎだされる物語は簡潔であり、起承転結の形を備えている。驚くほど真っ当な内容だ。そして正統な歴史小説や時代小説作家が書くような品格に満ちている。例えば井上靖のような。または中島敦のような。
著者の持ち味を損なわず、本書のような作品を生み出したことを、著者の新たなステージとして喜びたいと思う。
本書に収められた五編は、いずれも中国の古典小説や故事に題材を採っている。「悟浄出立」は西遊記。「趙雲西行」は三国志演義。「虞姫寂静」は史記の項羽伝。「法家孤憤」は史記に収められた荊軻の挿話。「父司馬遷」は司馬遷の挿話。
それぞれは単に有名小説を範としただけの内容ではない。著者による独自の解釈と、そこに由来する独自の翻案が施されている。それらは本書に優れた短編小説から読者が得られる人生の糧を与えている。
「悟浄出立」は沙悟浄の視点で描かれる。沙悟浄は知っての通り河童の妖怪だ。三蔵法師を師父と崇め、孫悟空と猪八戒と共に天竺へと旅している。活発で短気だが滅法強い孫悟空に、対極的な怠け癖を持つ猪八戒。個性的な二人の間で沙悟浄は傍観者の立場を堅持し、目立たぬ従者のように個性の薄い妖怪であることを意識している。ただ従者としてついて歩くだけの存在。そのことを自覚しているがそれを積極的に直そうともしない。
そんな沙悟浄は、怠け癖の極致にある猪八戒がかつて無敵の天蓬元帥として尊敬されていたことを知る。なにが彼をそこまで堕落させたのか。沙悟浄は問わず語りに猪八戒から聞き出してみる。それに対して猪八戒から返ってきた答えが沙悟浄に自覚をもたらす。猪八戒はかつて天蓬元帥だった頃、天神地仙とは完成された存在であることを当たり前と思い込んでいた。ところが過ちがもとで天から追放された人間界では、すでに完成されていることではなく、完成に至るまでの過程に尊さがあることを知る。猪八戒の怠け癖やぐうたらな態度も全ては過程を存分に味わうための姿。
そんな猪八戒の人生観に感化された沙悟浄は、自ら進んで完成までの経過を歩みたいと思う。そして従者であることをやめ、一団を先導する一歩を踏み出す。それはまさに「出立」である。
「趙雲西航」は、趙雲が主人公だ。趙雲といえば三国志の蜀の五虎将軍の一人としてあまりにも有名だ。蜀を建国したのは劉備。だが、劉備率いる軍勢は魏の曹操や呉の孫権と比べて基盤が未熟で国力も定まっていない流浪の時期が長かった。劉備玄徳の人徳の下、関羽や張飛と共に各地を転戦する中、諸葛亮孔明という稀有の人物を軍師に迎え、運が開ける。諸葛亮の献策により、劉備の軍勢は蜀の地に活路を見いだす。本編は蜀へと向かって長江を遡上する舟の上が舞台だ。
慣れぬ舟の上で船酔いに苦しむ趙雲は、自らの心が晴れぬことを気にしていた。それは間も無く50に手が届く自らの年齢によるものか、それとも心が弱くなったからか。冷静沈着を旨とする趙雲子龍の心からは迷いが去らない。
先行していた諸葛亮孔明より招きを受け、陸に上がった趙雲は、陸に上がったにもかかわらず、気が一向に晴れない心をいぶかしく思う。なぜなのか。理由は模糊としてつかみ取れない。
そんな趙雲の心の曇りが晴れるきっかけは、諸葛亮孔明が発した言葉によって得られた。諸葛亮が言外ににおわせたそれは、郷愁。趙雲は中原でも北東にある沛県の出身だ。そこから各地を転戦し、今は中原でも真逆の南西にある蜀へ向かいつつある。名声はそれなりに得てきたが、逐電してきた故郷にはいまだ錦が飾れずにいる。それが今でも残念に思っていた。そしてこのまま蜀の地に向かうことは、故郷の母と永遠に別れることを意味する。天下に轟かせた自らの名声も、親不孝をなした自らの両親に届かなければ何の意味があろうか。そんな真面目な英雄の迷いと孝心からくる悔いが描かれる。これまた味わい深い一篇だ。私のような故郷から出てきた者にとってはなおさら。
「虞姫寂静」は、虞美人草の由来ともなった虞姫と項羽の関係を描いている。虞姫は項羽の寵愛を一身に受けていた。だが項羽は劉邦に敗れて形勢不利となり、ついには垓下において四面楚歌の故事で知られるとおり劉邦軍に包囲されてしまう。
自らの死期を悟った項羽は、虞姫を逃がすために暇を申しつける。項羽と共に最期を遂げたいと泣いて願う虞姫に対し、項羽は虞の名を召し上げる。そうすることで、虞姫を項羽の所有物でなくし、自由にしようとする。意味が解らず呆然とする彼女の前に表れたのは范賈。項羽の軍師として有名な范増の甥に当たる人物だ。そもそも虞姫を項羽に娶わせたのも范増だ。その甥の范賈が虞姫に対し、なぜ項羽がここまで虞姫を寵愛したのか理由を明かす。
その理由とは、虞姫が項羽の殺された正妃に瓜二つだったから。誰よりも項羽に愛されていた自らの驕りに恥じ入り、その愚かさに絶望する虞姫。やがて死地に赴こうとする項羽の前に再び現れた虞姫は渾身の舞を披露し、再び項羽から信頼と虞の名を取り戻すと、その場で自死し果てる。虞美人草の逸話の陰にこのような女の誇りが隠れていたなど、私は著者が詳らかにするまでは想像すらできなかった。これまた愛の業を堪能できる一篇だ。
「法家孤憤」は、荊軻の話だ。荊軻とは秦の始皇帝の暗殺に後一歩のところまで迫った男。燕の高官に短期間で上り詰め、正規の使者として始皇帝の下に近づく機会を得る。だが、後ほんのわずかなところで暗殺に失敗する。
だが、本編が主題とするのは暗殺失敗の様子ではない。しかも主人公は荊軻ですらない。荊軻と同じ読みを持つ京科が主人公だ。同じ読みであるため官吏の試験で一緒になった二人。しかも試験官の間違いから京科だけが官吏に受かってしまう。望みを絶たれた荊軻は京科に法家の竹簡を託すといずこともなく姿を消してしまう。
数年後、暗殺者として姿を現した荊軻は、始皇帝暗殺の挙に出る。そして失敗する。一方、荊軻より劣っていたはずの京科は官吏として実務経験を積み、今や秦が歩もうとする法治国家の担い手の一員だ。京科は、かつて己に法家の竹簡を託した荊軻は法家の徒ではなく、己こそが正統な法家の徒であることを宣言する。
歴史とはその時代を生きた人の織りなすドラマだ。そこに主義を実現するための手段の優劣はなく、個人と組織の相克もない。そこにあるのは、歴史が後世の読者に諭す人として生きる道の複雑さと滋味だけだ。
「父司馬遷」。これは末尾を飾る一編である。そして印象的な一編だ。あえて漢の武帝に逆らい、匈奴に囚われの身となった友人の李陵をかばったことで宮刑に処された司馬遷。宮刑とは、宦官と同じく男を男でなくする刑だ。腐刑ともいわれ、当時の男子にとっては死にも勝る屈辱だった。本編の主人公は司馬遷の娘だ。兄たちや母が宮刑を受けた父から遠ざかる中、彼女は父に近づく。そして生きる意味を失いかけていた父に対して「士は、己を知る者のため、死す」と啖呵を切る。娘から投げられた厳しい言葉は、司馬遷を絶望から救いだす。今なお中国の史書として不朽の名声を得ている史記が知られるようになったきっかけは、司馬遷の娘の子供が当時の帝に祖父の遺した書を伝えてことによるという。
娘が父の心を救う。それは封建的な考えが支配的だった当時では考えにくい。だが、それをあえて成し、父の心を奮い立たせた娘の行いこそ父を思いやる強さがある。そんなことを味わいながら読みたい一編だ。
五編のどれもが正統で味わい深い。まさに本書は著者にとって転機となる一冊だと思う。
‘2017/03/16-2017/03/16



