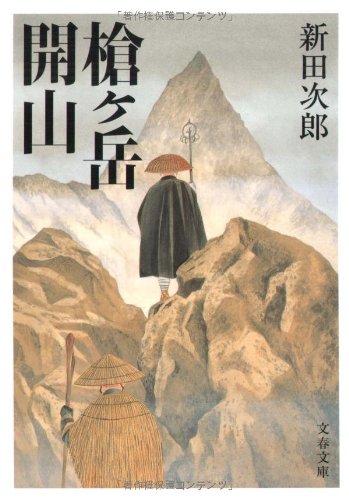

日本の仏教をこう言って揶揄することがある。「葬式仏教」と。
平安から鎌倉に至るまで、日本の宗教界をリードしてきたのは紛れもなく仏教であった。しかし、戦国の世からこのかた、仏教は利益を誘導するだけの武装集団に堕してしまった。その反動からか、江戸幕府からは寺院諸法度の名で締め付けを受けることになる。その締め付けがますます仏教を萎縮させることになった。その結果、仏教は檀家制度にしがみつき「葬式仏教」化することになったのだと思う。
では本当に江戸時代の仏教は停滞していたのか。江戸時代に畏敬すべき僧侶はいなかったのか。もちろんそんなことはない。例えば本書の主人公播隆は特筆すべき人物の一人だろう。播隆の成した代表的な事跡こそが、本書の題にもなっている「槍ヶ岳開山」である。
開山とは、人の登らぬ山に先鞭を付けるということだ。人々が麓から仰ぎ見るだけの山。その山頂に足跡を残す。そして、そこに人々が信仰で登れるようにする。つまり、山岳信仰の復興だ。山岳信仰こそは、行き詰っていた江戸仏教が見いだした目標だったのだろう。そして現世の衆生にも分かりやすい頂点。それこそが山だったのだ。登山を僧や修験者といった宗教家だけのものにせず、一般の衆生に開放したこと。それこそが播隆の功績だといえる。
だが、播隆が行ったのは修行としての登山だ。修行とは己自身と対峙し、仏と対話する営み。純粋に個人的な、内面の世界を鍛える営みだ。それを、いかにして小説的に表現するか。ここに著者の苦心があったと思われる。
本書には、越中八尾の玉生屋の番頭岩松が、後年の播隆となって行く姿が描かれている。だが、その過程には、史実の播隆から離れた著者による脚色の跡がある。wikipediaには播隆の出家は19の時と書かれているらしい。wikipediaを信ずるとなると、19で出家した人間が番頭のはずがない。ただ、どちらを信ずるにせよ、槍ヶ岳を開いたのが播隆であることに変わりはないはず。
播隆に槍ヶ岳を登らせるため、著者はおはまを創造する。越中一揆において、おはまは岩松が突き出した槍に絶命する。仲の睦まじいおしどり夫婦だった二人だが、夫に殺された瞬間、おはまは夫をとがめながら絶命する。一揆の当事者として成り行きで農民側に加担することになった岩松は、越中から逃げて放浪の旅に出る。おはまが最後に己に向けた視線に常に胸を灼かれながら。
一揆で親を亡くした少年徳助を守るという名分のもと、旅を続ける岩松は椿宗和尚のもとに身を寄せることになる。そこで僧として生きることを決意した二人は、大坂の天王寺にある宝泉寺の見仏上人に修行に出される。そして見仏上人の下で岩仏という僧名を得、修行に明け暮れる。次いで京都の一念寺の蝎誉和尚の下に移り、そこで播隆という僧名を与えられることになる。八年の修行の後、播隆は椿宗和尚の元に戻る。
八年のあいだ、俗世から、おはまの視線から逃れるため、修行に没頭した播隆。皮肉にも修行に逃れようとしたことが播隆に威厳を備えさせてゆく。俗世の浮かれた気分から脱し、信心にすがり孤高の世界に足を踏み入れつつある播隆。だが、一方で播隆を俗世につなぎとめようとする人物も現れる。その人物とは弥三郎。彼はつかず離れず播隆の周りに出没する。一揆の時から播隆 に縁のある弥三郎は、播隆におはまの事を思い出させ、その罪の意識で播隆の心を乱し、女までめとわせようとする。播隆 と弥三郎の関わりは、本書のテーマにもつながる。本書のテーマとは、宗教世界と俗世の関わりだ。
だが、僧の世界にも積極的に俗世と関わり、そこに仏教者として奉仕することで仏業を成そうとする人物もいる。それが播隆 を僧の世界に導いた椿宗和尚だ。椿宗和尚は、播隆こそ笠ヶ岳再興にふさわしい人物と見込んで白羽の矢を立てる。
播隆は期待に応え、笠ヶ岳再興を成し遂げる。しかし、その偉業はかえって播隆 を、事業僧として奔走する椿宗和尚の影響下から遠ざけてゆく。播隆にとっての救いは、笠ヶ岳山頂でみた御来迎の神々しさ。おはまの形をとった 御来迎に恐れおののく播隆 は、おはまの姿に許しを得たい一心で名号を唱える。
再びおはまの姿をとった御来迎に槍ヶ岳の山頂で出会えるかもしれない。その思いにすがるように播隆 は槍ヶ岳開山に向け邁進する。だが、笠ヶ岳再興を遂げたことで弟子入り希望者が引きも切らぬようになる。一緒に大坂に修行に向かった徳助改め徳念もその一人。また、弥三郎は播隆にめとらせようとした女てると所帯を持つことになるが、その双子の片割れおさとを柏巌尼として強引に播隆の弟子にしてしまう。俗世の邪念を捨て一修行僧でありたいと願う播隆に、次々と俗世のしがらみがまとわりついてくる。
皮肉にも槍ヶ岳開山をやり遂げたことで、仏の世界から俗界に近くなってしまう播隆。そんな彼には、地元有力者の子息を弟子にといった依頼もやってくる。徳念だけを唯一の弟子に置き、俗世から距離を置きたがる播隆は、しつこい依頼に諦めて、弟子を取ることになる。さらには槍ヶ岳開山を盤石にするための鎖の寄進を願ったことから、幕府内の権力闘争にも巻き込まれてしまう。それは、犬山城を犬山藩として独立させようと画策する城主成瀬正寿の思惑。播隆の威光と名声は幕政にまで影響を与えるようになったのだ。播隆本人の意思とは反して。
播隆の運命を見ていると、もはや宗教家にとって静謐な修行の場はこの世に存在しないかに見える。それは、宗教がやがて来る開国とその後の文明開化によって大きく揺さぶられる未来への予兆でもある。宗教界も宗教者もさらに追い詰めて行くのだ。宗教はもはや奇跡でも神秘でもない。科学が容赦なく、宗教から神秘のベールをひきはがしてゆく。例えばたまたま播隆の元に訪問し、足のけがを治療する高野長英。彼は蘭学をおさめた学者でもある。長英は播隆に笠ヶ岳で見た御来迎とは、ドイツでブロッケン現象として科学的に解明された現象である事を教えられる。
本書は聖と俗のはざまでもがく仏教が、次第に俗へと追い詰められて行く様を播隆の仏業を通して冷徹に描いている。まな弟子の徳念さえも柏巌尼 との愛欲に負けて播隆のもとを去って行く。1840年、黒船来航を間近にして播隆は入寂する。その臨終の席で弥三郎がおはまの死の真相やおはまが死に臨んで播隆 に向けたとがめる視線の意味を告白する。全てを知らされても、それは意識の境が曖昧になった播隆には届かない。徳念と柏巌尼が出奔し、俗世に堕ちていったことも知らぬまに。西洋文明が仏教をさらに俗世へと落としてゆく20年前。播隆とは、宗教が神秘的であり得た時代の古き宗教者だったのか。
取材ノートより、という題であとがきが付されている。かなりの人物や寺は実在したようだ。しかしおはまの実在をほのめかすような記述は著者の取材ノートには触れられていない。おそらくおはまは著者の創作なのだろう。だが、播隆が実在の人物に即して書かれているかどうかは問題ではない。本書は仏教の堕ちゆく姿が主題なのだから。獣も登らぬ槍ヶ岳すらも人智は克服した。最後の宗教家、播隆自身の手によって。誤解を恐れずいうなら、播隆以降の仏教とは、葬式仏教との言い方がきつければ、哲学と呼ぶべきではないか。
‘2016/11/15-2016/11/19


