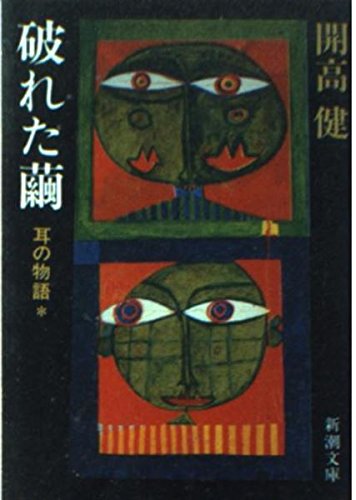
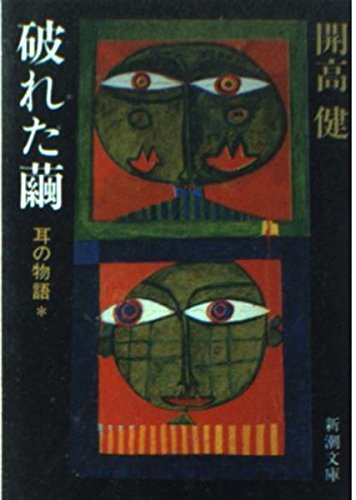
耳の物語と言うサブタイトルは何を意味しているのか。
それは耳から聞こえた世界。日々成長する自分の周りで染みて、流れて、つんざいて、ひびいて、きしむ音。
耳からの知覚を頼りに自らの成長を語ってみる。つまり本書は音で語る自伝だ。
本書は著者の生まれた時から大学を卒業するまでの出来事を耳で描いている。
冒頭にも著者が書いている。過去を描くには何から取り出せばよいのか。香水瓶か、お茶碗か、酒瓶か、タバコか、アヘンか、または性器か。
今までに耳から過去を取り出してみようとした自伝はなかったのではないか。
それが著者の言葉である。
とは言え音だけで自伝を構成するのは不可能だ。本書の最初の文章は、このように視覚に頼っている。
一つの光景がある。
と。
著者は大阪の下町のあちこちを描く。例えば寺町だ。今でも上本町と四天王寺の間にはたくさんの寺が軒を占めている一角がある。そのあたりを寺町と呼ぶ。
幼い頃に著者は、そのあたりで遊んでいたようだ。その記憶を五十一歳の著者は、記憶と戦いながら書き出している。視覚や嗅覚、触覚を駆使した描写の中、徐々に大凧の唸りや子供の叫び声といった聴覚が登場する。
本書で描かれる音で最初に印象に残るのは、ハスの花が弾ける音だ。寺町のどこかの寺の境内で端正に育てられていた蓮の花の音。著者はこれに恐怖を覚えたと語っている。
後年、大阪を訪れた著者は、この寺を探す。だが幼き頃に聞いた音とともに、このハスは消えてしまったようだ。
音はそれほどにも印象に残るが、一方で、その瞬間に消えてしまう。ここまで来ると、著者の意図はなんとなく感じられる。
著者は本書において、かつての光景を蘇らせることを意図していない。むしろ、過去が消えてしまったことを再度確認しようとしているのだ。
著者は、日光の中で感じた泥のつぶやき、草の補給、乙行、魚の探索、虫の羽音など、外で遊んで聞いた音を寝床にまで持ち運ぶ。もちろん、それらの音は二度と聞けない。
昭和初期ののどかな大阪郊外の光景が、描写されていく。それとともに著者の身の回りに起こった出来事も記される。著者の父が亡くなったのは著者が小学校から中学校に進んだ歳だそうだ。
しばらく後に著者は、父の声を誰もいない部屋で聞く。
時代はやがて戦争の音が近づき、あたりは萎縮する。そして配色は濃厚になり、空襲警報や焼夷弾の落下する音や機銃掃射の音や町内の空襲を恐れる声が著者の耳をいたぶる。
ところが本書は、聴覚だけでなく視覚の情報も豊富に描かれている。さらには、著者の心の内にあった思いも描かれている。本書はれっきとした自伝なのだ。
終戦の玉音放送が流れた日の様子は、本書の中でも詳しく描かれている。人々の一挙手一投足や敵機の来ない空の快晴など。著者もその日の記憶は明晰に残っていると書いている。それだけ当時の人々にとって特別な一日だったに違いない。
やがて戦後の混乱が始まり、飢えに翻弄される。聴覚よりも空腹が優先される日々。
そのような中で焼け跡から聞こえるシンバルやトランペットの音。印象的な描写だ。
にぎやかになってからの大阪しか知らない私としては、焼け跡の大阪を音で感じさせてくれるこのシーンは印象に残る。
かつての大阪に、焼けただれた廃虚の時代があったこと。それを、著者は教えてくれる。
この頃の著者の描写は、パン屋で働いていたことや怪しげな酒を出す屋台で働いていたことなど、時代を反映してか、味覚・嗅覚にまつわる記述が目立つ。面白いのは漢方薬の倉庫で働いたエピソードだ。この当時に漢方薬にどれほどの需要があるのかわからないが、著者の物に対する感性の鋭さが感じられる。
学ぶことの目的がつかめず、働くことが優先される時代。学んでいるのか生きているのかよくわからない日々。著者は多様な職に就いた職歴を書いている。本書に取り上げられているだけで20個に迫る職が紹介されている。
著者の世代は昭和の激動と時期を同一にしている。感覚で時代を伝える著者の試みが読み進めるほどに読者にしみてゆく。五感で語る自伝とは、上質な歴史書でもあるのだ。
では、私が著者と同じように自分の時代を描けるだろうか。きっと無理だと思う。
音に対して私たちは鈍感になっていないだろうか。特に印象に残る音だったり、しょっちゅう聞かされた音だったり、メロディーが付属していたりすれば覚えている。だが、本書が描くのはそれ以外の生活音だ。
では、私自身が自らの生活史を振り返り、生活音をどれだけ思い出せるだろう。試してみた。
幼い頃に住んでいた市営住宅に来る牛乳売りのミニトラックが鳴らす歌。豆腐売りの鳴らす鐘の響き。武庫川の鉄橋を渡る国鉄の電車のくぐもった音。
または、特別な出来事の音でよければいくつかの音が思い出せる。阪神・淡路大震災の揺れが落ち着いた後の奇妙な静寂と、それを破る赤ちゃんの鳴き声。または余震の揺れのきしみ。自分の足の骨を削る電気メスの甲高い音など。
普段の忙しさに紛れ、こうした幼い頃に感じたはずの五感を思い出す機会は乏しくなる一方だ。
著者が本書で意図したように、私たちは過去が消えてしまったことを確認することも出来ないのだろうか。それとも無理やり再構築するしかないのだろうか。
五感を総動員して描かれた著者の人生を振り返ってみると、私たちが忘れ去ろうとしているものの豊かさに気づく。
それを読者に気づかせてくれるのが作家だ。
‘2020/04/09-2020/04/12






