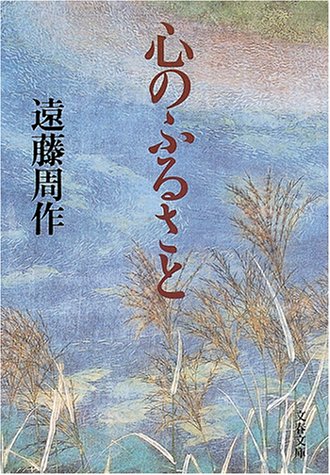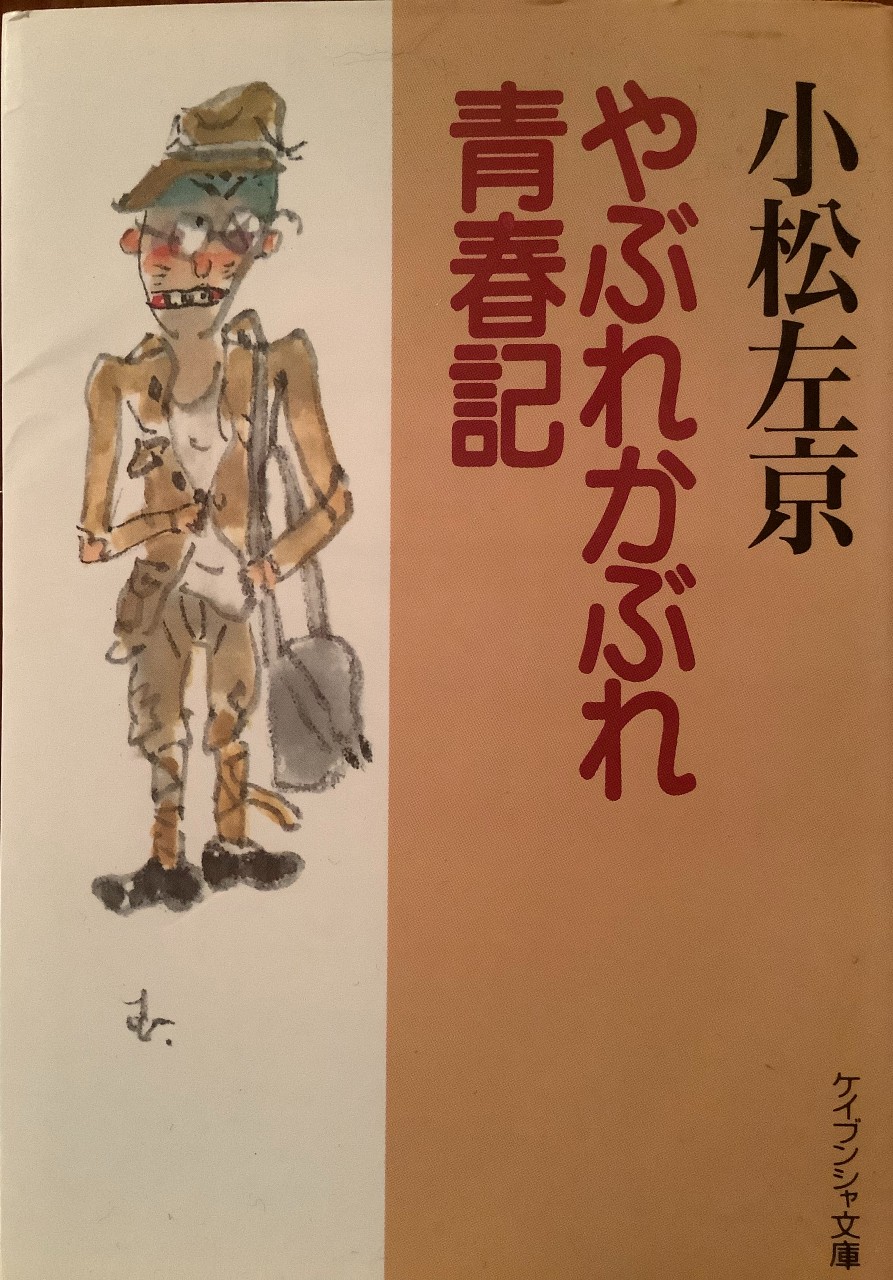
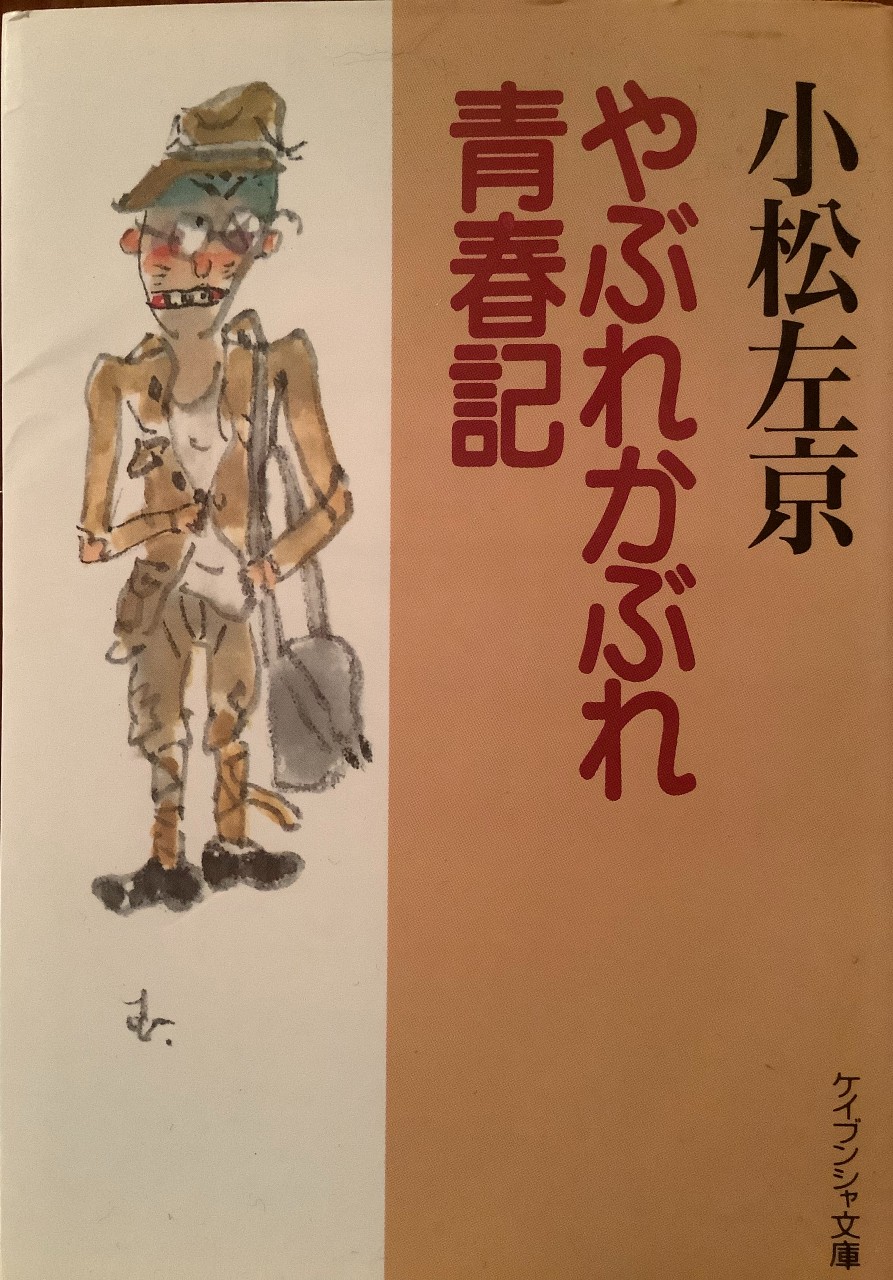
本書も小松左京展をきっかけに読んだ一冊だ。
小松左京展では、著者の生い立ちから死去までが、いくつかの写真や資料とあわせて詳しい年表として紹介されていた。
著者の精力的な活動の数々は、小松左京展でも紹介されていた。あらためて圧倒された。だが、若い時期は苦しみと挫折に満ちた青春時代を送ったそうだ。小松左京展では、それらの若い頃の雌伏についても紹介していた。
だが、業績や著作があまりにも膨大な著者故、著者の若い頃については存分に紹介されていたとはいいがたい。少なくともその時期に焦点を当てた本書に比べれば。
本書は、著者のファンではなくても、自伝としてもと読まれるべきだと思う。それほど素晴らしい。そして勉強になる。何よりも励まされる。
やぶれかぶれ、というのはまさに文字通りだ。
本書の性格や意図については、本書のまえがきで著者自身が書いている。少しだけ長いが引用したい。
「編集部の注文は、大学受験期を中心とした、「明朗な青春小説」というものだった。ーそして、それは私自身の自伝風のものであること、という条件がついている。」(7P)
「まして、私の場合など、この時期と、戦争、戦後という日本の社会の、歴史的異常状況とが重なってしまったから、とても「明朗な青春」などというものではなかった。なにしろ妙な時代に生まれたものである。私の生まれた昭和六年には、満州事変がおっぱじまり、小学校へ上がった十二年には日中戦争がはじまった。五年生の時太平洋戦争がはじまり、中学校にはいった年に学徒動員計画がはじまった。徴兵年齢が一年ひきさげられて、学徒兵の入隊がはじまった。中学二年の時にサイパン玉砕、中学生の工場勤労動員がはじまり、B29の大空襲がはじまる。中学三年の時には大阪、神戸が焼野が原となって終戦、あとは占領下の闇市、食料欠乏の大インフレ、預金凍結、新円切りかえ、中学五年で旧制三高にはいったと思ったら、その年から学制が現在の六三制にかわり、旧制一年だけで新制大学第一期生に入学、その年日本は、大労働攻勢と、大レッドパージの開始で、下山、三鷹、松川事件と国鉄中心に会事件が続発し、翌年朝鮮戦争勃発…。政治、思想、人生などの諸問題、そして何よりも飢餓と貧困にクタクタになって、やっと昭和二十九年、一年おくれで卒業した時、世の中は「もはや戦後でない」という合い言葉とともに「神武景気」「技術革新」の時代に突入しつつあった。その年、家は完全に倒産した。」(12P)
小松左京展でも、著者の戦時体験については一区画が設けられていた。著者の諸作のあちこちに反戦の思いが散見され、著者が心から戦争を嫌っていたことが感じられる。
実際、右傾化した世の中で、著者は相当ひどい目に遭わされたそうだ。そのことが本書にも紹介されている。
鉄拳制裁や教師の無定見からくる差別。理不尽な扱いはしょっちゅう。
何のためにやっているのかわからない勤労奉仕。無意味な作業。
そして戦後になったとたん、戦時中に放っていた勇ましい言葉をすっかり忘れたかのような大人たちの変節。
中学生の時に著者が受けた扱いの数々は、当時の世相や暮らしの実態を知る上でとても興味深い。
戦後、人々がなぜあれほどに左翼思想へと走ったのか。それは戦時中の反動からという説はよく目にする。
実際、著者も大学の頃に共産主義の運動に足を突っ込んだことがあるという。
それもわかるほど、軍国主義に嫌気がさすだけの理由の数々が本書には書かれている。
戦後になって一念発起し、旧制高校にはいった時の著者の喜び。それは本書からもよく感じ取れる。
その無軌道な生活の楽しさと、それが学制改革によって一年で奪われてしまった著者の無念。それも本書からはよく理解できる。
よく昭和一桁世代という。だがその中でも昭和六年生まれの著者が受けた運命の運転や、その不条理な経験は本書を読んでもうんざりさせられる。人を嫌いにさせるには充分だ。
著者の計り知れない執筆量。さらには文壇や論壇の枠からはみ出し、万博への関与や政財界にまで進んだエネルギーが、全てこの時期に培った反発をエネルギーと変えて噴出させたことも本書を読むとよく理解できる。
大学に進んだ著者は、完全に自由なその生活を謳歌する。そしてやぶれかぶれのやりたい放題をする。
その辺の出来事も面白おかしく描かれている。
自伝によくあるのは、ドラマチックなところだけ取れば面白いが、その他の経歴は淡々と読み進める類のものだ。だが、本書は、エピソードの一つ一つが破天荒だ。そしてどれもがとても面白い。そのため、どんな人にとってもスイスイと読めるはずだ。
本書で描かれる大学時代の日々はとても面白い。だが、ある日になって浮かれている著者を置き去りにして周りがフッと醒めていく。周囲の空気の変化を感じた著者が、モラトリアムの終わりを予感するくだり。本書は私にとっても身につまされる描写が多い。
本書に描かれていない出来事は他にもある。そうした情報は小松左京展でも展示されていた。
実家の工場の倒産と、工場長として後始末に駆けずり回る毎日。残された借金を返済するために大量に書きまくる日々。そうした苦しみの数々を小説へのエネルギーに変えたところなど、とても面白い。
おそらくこの時期の著者には面白い出来事をもっと持っていることだろう。そうした体験は著者が別の場所に発表しているはずなので探してみたい。
そして、私にとっては、もう二度と戻ることのない青春時代に、もっとはちゃめちゃな毎日を過ごしておけばよかった、と思うのだ。
私の場合はそれを取り戻そうと、中年になった今でも自由で気ままに生きようと日々を生きているつもりだ。だが、著者のやぶれかぶれで破天荒な青春にはとてもかなわない。
末尾には著者のこの時期を物語る四つの短編が納められている。
「わが青春の野蛮人たち」「わが青春」「わが読書歴」「気ちがい旅行」
これらもあわせて読んでいくと、巨大な著者の存在がより近づく。またはより遠くなってしまう。だが、より親しみを感じられるはずだ。
冒頭にも書いた通り、本書は自伝としてとても推薦できる一冊だ。
‘2019/12/30-2019/12/31