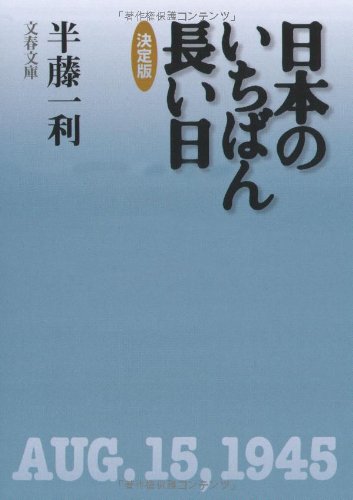
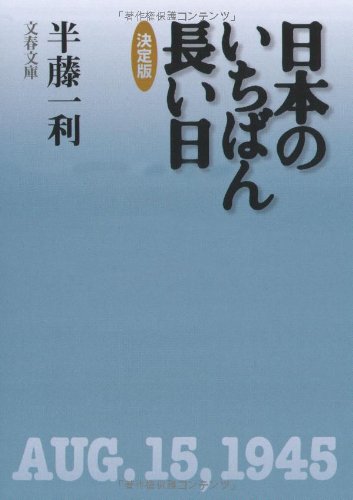
本書を読むのは二度目だ。私が二十年以上前から付けている読書記録によれば、1997年の2月以来、十九年半をへての再読となる。
その間、私は太平洋戦争について書かれた本をたくさん読んできた。それらの本を読んできたにもかかわらず、本書は私の中で不動の位置を占めている。おそらく今後もそうあり続けるはずだ。それは、戦後七十年の節目に本作が再度映画化され、劇場で鑑賞したことで確固となった。(レビュー)
本書は決定版と銘打たれている。前回私が読んだのも決定版だ。私は初版を読んだことがないため、本書から受けた印象は全て決定版から得られた。その印象は十九年半前、初めて本書を読んだ私に鮮烈な影響を与えた。私の中に根付いていた日本陸軍への印象を一変させたのだ。それまでは当時の陸軍すなわち悪という一面だけの見方に縛られていた。ところが、本書によって陸軍にもさまざまな人物がいたことを知ったのだ。それは、陸軍を一括りに断罪することの愚かさを私に教えた。それまで持っていた教科書で習った知識では陸軍によって戦争は始められ、遂行され、終戦までも引き延ばされた、という記憶だけが残っていたのだ。もちろん、紙数の都合上、細かく説明はできなかったのだろう。だが、本書に書かれていた内容は、そんな浅い知識をひっくり返すだけの力があった。まさに私の知識は塗り替えられたのだ。特に阿南陸軍大臣への印象が変わったことは記憶に鮮やかだ。御前会議で戦争継続を一貫して訴えた阿南陸相の姿。その表面だけをみれば、軍人の硬直した思考と捨ててしまうものだ。ところが、本書を読んだ後はそんな通り一遍の批判は慎まねば、と思わせる迫真性がある。前回、読んだ際に感じた印象は今回も変わらなかった。新鮮さこそ薄れたとはいえ、今も変わることがない。
本書は著者にとっての出世作だ。文藝春秋社を定年退職してからの著者は、歴史探偵と名乗って活発な文筆活動を繰り広げている。昭和史だけでなく幕末史にも手を出すほどに。だが、本書は著者にとって出世作というよりも原点だと思う。もともと本書は五十年以上前、著者が三十代の頃に発表されている。それ以来、今もなお出版され続けている。昭和史にとって価値ある一冊との評価をおとしめられることなく。今回の二度目の映画化を劇場で見た後、あらためて本書を読んだ。やはり本書から教えられることは多い。そしてスクリーンの中で当時の様子が映像となって頭にしみ込んだことで、本書がより理解できた気がする。それは私が十九年半の間に積み重ねた経験や知識に相乗りして、本書を理解する上でよき助けとなってくれた。
十九年半の間、私にとって糧となったのは書物だけではない。たとえば、二年ほど前に訪れた鈴木貫太郎記念館での経験もそうだ。この時の訪問は、私の知見を深めてくれた。鈴木貫太郎記念館には白川一郎画伯による「最後の御前会議」の実物が展示されている。厳粛な御前会議の様子が書かれた原画。それを眼前でみたときの私の気持ちは、ただ感無量。その体験は私の中で貴重な思い出として残っている。この記念館には鈴木貫太郎氏の大礼服なども飾ってある。それらを見ると鈴木首相が大将として威厳のあった人物だったことが伺える。 人の訪れることも少ないであろう記念館は、確かに「日本の一番長い日」の余韻を伝えていた。
そういった背景を頭にたたき込んだ上で本書を再読する。すると、鈴木首相の腹のすわった政権運営ぶりに得心がいくのだ。鈴木首相は首相として失敗もした。如才なく立ち回れた政権運営だったとはいえない。それでも見事に終戦に持ち込んだ。在任中、鈴木首相はボケていたわけでも、逃げを打っていたわけでもないのだ。おそらくは軍の圧力をとぼけていなし、はぐらかして交わし続けていたはず。鈴木首相が傑物だったことを記念館の訪問と本書、そして映画によって再確認できたと思う。
阿南陸相もまた同じだ。本書で再現された阿南陸相の言動から読み取れること。それは、阿南陸相が陸軍内の暴発を抑えるためにぎりぎりで綱渡りをしていたことだ。刃の上を裸足で歩くがごとし。足を踏み外せば足だけでなく日本が破滅する。そんな阿南陸相の抱いていたであろう緊迫感が読者の胸に迫ってくる。
一方で神州不滅を信じていた若手将校の焦りもリアルに描かれている。彼らを衝き動かして極限の焦りや危機感。それらに打ち克つには玉音放送を防ぐ以外ない。そのためには玉音盤を奪取するほかすべきことはない。そんな若さゆえの純な気持ち。そこを現代の価値観で測ろうとすれば彼らは理解できない。そして彼らの焦りや危機感は、今のわれわれには決して理解できないのだろう。
この暴走に直面した陸軍の将官がクーデターに同調せず統制を保ったこと。この冷静な態度が宮城事件を不発に終わらせたことも見逃せない。宮城事件が成功していれば、私がこの文書を書くことはおそらくなかっただろう。そもそも日本という国もなかった可能性だってあるのだ。当時の挙国一致の風潮を非難することは簡単だ。国民の多くが軍国主義にあてられ、載せられたことは事実だろう。だが、クーデターに同調しなかった将官たちは、熱に浮かされた若手将校に引きずられなかったのだ。陸軍の将官が若手将校に同調せず、個人としてきちんと対応したこと。それが、暴走する将校たちの企図を頓挫させ、日本を破滅から救ったことは忘れてはならない。
また、本書は私に一つの思い付きを与えてくれた。それは、日本が島国であることだ。それは日本人に島国の心を養った。大陸の端。周りは海に囲まれ逃げ場がない。その地理的条件は日本に守る強さを備わらせたのだ。
今までの我が国の歴史を振り替えると、大陸に攻め込んだ際はことごとく敗れている。白村江の戦い、文禄・慶長の役、シベリア出兵。そして太平洋戦争。日清戦争も勝ったとはいえ、戦局を決定づけたのは海戦だ。日露戦争では多大な犠牲を出してようやく旅順攻略戦に勝利した。が、ロシアに講和を決意させるほどの決定的な勝利は日本海海戦によることに異論はないはず。日清戦争の後は大陸に足掛かりを作ろうとして三国からの干渉で遼東半島の返還を余儀なくされた。日露戦争後は満州で利権を確保し、朝鮮半島への支配権を強化できたが、その支配も太平洋戦争の敗戦で水の泡と消えた。要するに我が国は攻めは不得手であり、本来やるべきではないのだ。
一方で守りに入ると、案外日本は強い。元の侵略を神風で退けたのはよく知られている。薩摩藩や長州藩は、イギリスに完膚なきまでにやっつけられたが占領の憂き目を見ず、逆にそれをばねに倒幕を果たした。幕末には開国を余儀なくされたが、不平等条約を撤廃させ、返す刀で近代化を達成してしまう。徹底的にやられたはずの太平洋戦争も、あまりにも見事な負けっぷりを見せる。それがGHQの占領後に経済大国として世界を驚かせる原動力になった。それでいながらアメリカに国防を任せるというしたたかさを身につけるのだ。要するに我が国は守りに入ってこそ真価を発揮する、とても打たれ強い国なのだ。
それは第二次大戦でのナチス・ドイツの敗北と日本の敗北を比べてみればわかる。ナチス・ドイツが破滅する直前、指揮系統は乱れに乱れた。ヒトラーはじめ著名なナチスの指導者たちは自殺し、さらに膨大な数のナチス戦犯達に逃亡を許してしまった。しかし我が国は違う。一度敗北を受け入れたら、実に従容たる態度を示した。あれだけ完膚なきまでの敗北を喫しながら、昭和天皇の戦争責任は結局不問となった。
日本がこれだけ徹底的に敗北しながら、国としての組織が瓦解しなかった事。その理由とは何だろう。それは、本書で書かれた宮城事件に際しての陸軍指揮官の対応が表わしているのではないだろうか。国の存亡がかかった瀬戸際にあってもなお、統率を旨とする精神。天皇の臣下として統率を聖なるものとして奉じ、若手将校の跳ね返りを抑え込む国民性といえばよいか。現代に生きるわれわれは、当時の重臣たちの終戦の決断までがあまりにも鈍いことにじれったさを感じる。だが、あれだけ国土が蹂躙されてからの降伏だったからこそ軍は暴発せずに軍備を解いたのではないか。そしてかなりの戦力を保持していたにもかかわらず、大本営からの降伏を受け入れた関東軍の態度にも、天皇の威厳がついに保たれ続けた我が国の美徳を見ることができる。仮に若手将校のクーデターが成功していたらどうなっただろう。おそらく日本は戦争を継続していたことだろう。そして天皇制をも危機にさらしていたはずだ。私が習う言葉もアルファベットだけになっていたこともありうる。本書に描かれた若手将校たちの言動を読んでいると、彼らの行動が真剣であること、まかり間違っていればクーデターが成っていた可能性が高いことがわかる。だからこそクーデターを冷静に止めた陸軍の将官たちは賞されるべきなのだ。彼らの冷静な判断があったからこそ、若手将校による暴発は最小限で収まり、日本は国の体裁を保ったまま終戦を迎えられた。こう言っても言い過ぎではないと思うのだが。
本書で逐一書かれた出来事。それは確かに『日本の一番長い日』と呼ぶにふさわしい。だが、それ以上に、「日本の一番堅い日」だったのではないだろうか。日本の底知れぬ堅さを示した日々、という意味で。
ここ数年、日本の国防に不安の声が上がっている。北朝鮮の暴発や中国の膨張、日本の経済不況など不安要素は多い。だが、この期に及んでもまだ我が国の守りに強い本領は発揮されていないように思える。そして前回、我が国の専守の強さが発揮された時こそが、本書に描かれた一日だったのではないか。空襲や原爆など国土が荒廃し、天皇制も未曽有の危機に立たされた終戦時。本当の危機に瀕した時、日本人に何ができたのか。それを確かめるためにも本書は読まれるべきなのだ。そして日本の底力を知るためにものちの世に長く伝えられるべき一冊なのだ。
‘2016/12/29-2016/12/30


