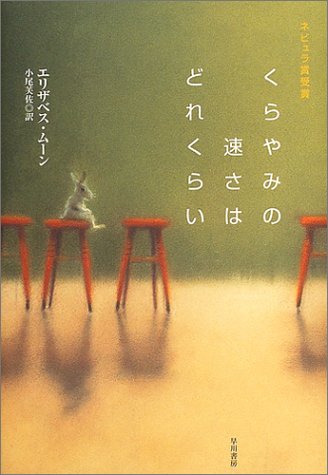令和三年、夏から秋にかけて、私の個人的な境遇に変化がありました。
自分の誕生した病院を訪れたことや、死の恐怖に怯えたこと。そしてその十日後にコロナに感染したこと。山で遭難して野宿したこと。
それらの経験は、私に人生の深さと自分の無知をあらためて教えてくれました。
遡ること8月の20-22日。私は妻と2人で福井、豊川稲荷、久能山東照宮を旅しました。この旅については別のエントリーで詳しく書く予定です。
2日目の朝、私は初めて自分の生まれた病院(福井愛育病院)を訪問できました。48年目で初めてです。
その後、福井市と越前市のあちこちを観光しました。そして夜は豊川稲荷まで移動し、駅のそばにあるホテルに投宿しました。
その夜、私はベッドで自分が死ぬ恐怖に襲われました。
なぜ急に恐怖を感じたのか、わかりません。体調の悪化でしょう。越前市の柳の滝を訪れた際、大きなアブに襲われました。足を三カ所、血が流れるほど噛まれたのですが、それが影響したのかもしれません。
自分の生が終わってしまう。その恐怖は本物でした。自分がいなくなった後、会社はどうなるのか。メンバーの人生は。お客様に依頼された案件は全うできるのか。今自分が死んでも情報共有に不備はないのか。
そして、家族は誰が養うのか。妻や娘に自分の考えや生き方は伝え切れたのか。
そして、自分の人生がこの瞬間に終わってしまうことによって、自分がやりたいことの100,000分の1もできずに死んでゆく未練と無念をどう扱えばいいのか。
かなり煩悶しました。そして、人に比べて人生を積極的に過ごしてきたつもりの自分が、実は全然そうじゃなかったことを痛切に感じました。
自分の人生、このままで終わってしまうのか。そんな諦めと、そうさせてはならじという反抗心。それが私の中でせめぎ合い、朝まで寝られずにベッドの上でのたうちまわっていました。
翌朝、豊川稲荷に妻と訪れました。本堂に参らせてもらった刹那、雨がザーッと降り、そしてすぐに止みました。まさに清めの雨のように。
夫婦で広大な境内を三周ほどしました。最後の一周は、妻が何か思うところがあったのか、私のためにもう一度奥の院などを巡ってくれました。
妻は、少しだけスピリチュアルな能力を持っています。参拝の最後の一周は、豊川稲荷の荼枳尼天が妻の口を通して私に伝えたいことがあると言うので、妻が連れて行ってくれました。荼枳尼天から私への啓示の内容は、その後のドライブの間に妻が教えてくれました。
そこで告げられたのは、私には中身がない。と言うことです。その中身とは、能力や意志や人格を示すのではありません。もっと奥底にある自我やエゴに相当する概念でしょうか。
中核にあるべき中身がない。中身がないため、私は新規なものや新しい概念に目移りし、本を読んで新しい知識を得たいと腐心するようです。
自分の欠落が何かについて、私は自分でもこの数年でうすうすと気づいていました。
一方で、今の私は、スキルや技術がある程度身に付いてきています。商談の場でも立て板に水を流すように言葉が出てきます。ご要望を伺ったその場でシステムの概要がほぼ見えてしまいます。
ですが、それを言わせているのは私自身の自我やエゴではなく、私の職業人のスキルです。ここ数年、商談の技術が上がるごとにその事実に気づき、それとともに新たな疑念が湧いてきました。スキルがアップしていても、魂がこもった商談ができているのだろうか。スキルに乗っかった惰性の商談をしていないか。
それまで仕事だけだった私が、40代になってから急に活発になった事情。そこには、今更ながら自分を探したいとの切実な理由がありました。
妻を通した荼枳尼天の言葉によると、沢庵和尚について調べると良いそうです。
この後、私たちは久能山東照宮に訪れ、1159段の階段を登ったのですが、それは本稿では割愛します。
東京に帰ってから数日後、四谷で商談の機会がありました。良い機会なので、その前の時間を利用して豊川稲荷東京別院に参拝しました。
参拝方法は事前に妻からアドバイスをもらいました。境内を巡る順番やお供え物の供え方など。
この時、私はより深く自我の底から願いを唱え、口にしました。普段から神社仏閣に詣でる時は、いつも自分なりに心で名乗り、感謝して願いを告げていたつもりです。が、より深くより心を込めて。
もし今までの私の祈り方が良くなかったのであれば正さないと。
それとともに、自分なりに励んできた自我の育て方が良くなかったとすれば、今後はそれも直さなければ。
果たして私は、残りの40-50年の余生が尽きる間に自分の中身を満たせるのでしょうか。分かりません。そもそも満たすべき中身が何かすら、今も分かっていませんし。
ただ一つだけ分かるのは、空虚な自分であり続けたくはないということ。
おそらく仕事上のスキルや能力をいくら高めても、それは私の中身の充実とは無関係のはず。
今の私は死ぬ直前にも未練はたらたらで煩悩まみれのままであることは明らかです。では、私が完全に満ち足りた悟りの境地で死ぬにはどうすれば良いのでしょうか。
四谷からの帰り、新宿の紀伊国屋書店により、水上勉さんの「沢庵」を購入しました。そしてその数日後に読破しました。
その本が教えてくれたこと。それは沢庵和尚の権力や名利を求めない生き方でした。清貧の生き方です。禅や武道、茶道といった文化を極めながら、徳川幕府や大寺院、朝廷に媚びへつらわない生き方。
それでいて世を捨てず、朝廷や幕府とは付かず離れずの距離感を保つ。そして、徳川幕府の寺院政策に異論があれば、敢然と意見を開陳する。それが元で流罪になっても。
私は山形の上山にある春雨庵を訪れたことがあります。そこは沢庵和尚が逼塞していた建物です。落ち着いた佇まいでした。その後、三年で流罪を許され、三代将軍家光の帰依と信任を得ても、その境遇に甘んじなかった沢庵和尚の矜持。
私が沢庵を読み終えた次の日、今度は新型コロナウィルスに感染してしまいました。
コロナにかかった経緯はコロナ感染記に書いたので、ここでは繰り返しません。
ですが一つだけ伝えておきたいことがあります。
それは、私の商談のスキルにコロナが悪影響を及ぼした衝撃です。話していてフリーズし、しどろもどろになり、支離滅裂になった自分。自分の空虚な中身を満たす前に、表層の仕事人としてのスキルすら崩れ去ろうとした衝撃がどれほど強かったか。
幸い、コロナはそれ以上重症にならずにすみました。今は若干の咳が残るだけで、商談のスキルにも深刻な後遺症は残りませんでした。
コロナ後、初めてのリアル商談は9/17にありました。
この機会を利用し、私は晩年の沢庵和尚が住職として勤めた東海寺をはじめて訪れました。
かつて東海寺が三代将軍家光から賜った寺領は幕末から明治維新にかけての混乱で大幅に削られてしまいました。今の東海寺の寺領は、かつての塔頭の一つが引き継いでいるだけです。他の寺領は全て運動公園、品川学園、タワーマンションなどに侵食されてしまいました。今の東海寺は表からは分かりにくい場所にあります。
沢庵和尚の没後から360年。年月とは残酷です。
私は東海寺の近くにある沢庵和尚の墓にも詣でました。この大山墓地は、かつては東海寺の境内の一部として隣接していたそうです。
ところが今や、この墓地は新幹線、横須賀線、湘南新宿ライン、京浜東北線、東海道線の線路に囲まれています。ひっきりなしに電車が行き来するこの墓地に静寂さを望むのは不可能です。
地元出身の島倉千代子さんや鉄道の父である井上勝氏は生前に望んで墓地を定めたそうですが、賀茂馬淵や渋川春海、沢庵和尚に至っては今の環境など想像の外だったことでしょう。春雨寺(ここも旧塔頭)と大山墓地の間にある土地では何か大規模な工事の最中でしたし。
そもそも沢庵和尚は、死を前にして墓は建てないことを言いのこしたそうです。それが、ないがしろにされただけでなく、今では騒々しい場所にあります。
ですがここで、「きっとあの世で沢庵和尚は嘆いている」などと思ってはいけません。
あくまでも私見ですが、そもそも沢庵和尚は騒々しい場所に墓を建てられたことを何とも思っていないはずです。なぜなら、死ねば無になるから。沢庵和尚の遺言を読んでみると、沢庵和尚は来世や輪廻など一切考えていなかったのではないかと思うのです。死ねば全ては無に帰す。そのことに大悟していたからこそ、沢庵和尚はあらゆる権力や名利に目もくれなかったのではないでしょうか。
死ねば無になる。かねて私が感じていたことです。いくら本を読んでも、旅をして見聞を深めても死ねば無。
そう分かっているのなら、私の中身が空虚であっても問題ないですよね。
死ねば無になるのなら、生きている間から無であっても何も問題ないわけです。
では、豊川稲荷の荼枳尼天は何を意図して私に沢庵和尚のことを調べるように伝えたのでしょうか。
私は荼枳尼天の真意を考えました。
そして、並行して自らの中身を求めるとしたらどこにあるのかを追い求めました。
まず一つは強烈な目的意識です。今までの私は状況に流されるままに対応し、その都度、好奇心を発揮してスキルを身に着けてきました。
ですが、その経緯に私自身の強い意志はあったのか。なかったはずです。
そもそも私は物事に対して強い意志を持っているのか。本を読みたい、旅がしたい、という欲求は、空虚な私の真空を埋めようとする衝動に過ぎないのでは。
私はその真実が知りたいと思いました。
私が先日、滝子山に登ろうとしたのは、まさに自分の衝動の源を確かめたかったからです。
そして、それが不首尾に終わったことで、私は自分のふがいなさに対して心の底から怒りました。
これは、私にとっては意外なことでした。今まで私が怒ることがあるとすれば、他人からの理不尽な攻撃に対してのみ。自分の不首尾については、あまり怒ることもなく生きてきたのですから。
この怒りはどこから湧いているのでしょう。ようやく空虚な中身を埋めようと私の自我またはエゴが動き始めているのか。
私が無理やりに山を登って達成感を得ようとしたのは、コロナ病原菌からの体力の回復を確かめたかったからではなく、空虚な自分が初めて意志を発揮した表れではないか。
私はその翌週、午後からの時間を利用し、再び山登りにチャレンジしました。ところが登山道が荒れていて、袖平山、鐘撞山、焼山を断念せざるを得ない状況でした。
私はまた自分の不首尾に怒るのか、と思った帰り、三角山を見つけました。標高525メートルと低山ですが、山を一つでも登って達成感を味わえば、何かが変わるのではないか。
その思いだけで199段の階段を登り、そこから藪を漕いで三角山の三角点に到達しました。私は自分に勝ちましたし、意志の力を発揮したのです。
ところが、三角山に登った時点で17時過ぎ。そこから同じ道を帰ったのですが、暗くなってきた道で迷ってしまいました。焦った私は尾根に沿って降りていたつもりでしたが、その時点ですでに誤った谷に迷い込んでいたようなのです。足元は刻一刻と暗くなっていきます。何回も足をとられ、場合によっては沢の水たまりをいとわずに飛び込んだものの、沢の岩が見えなくなりました。そうなると危険度は増します。
そのため、沢に沿った道に復帰しながら里への道を探しました。ところが足元の木や茂みが見えません。歩いているうちにまた滑べり落ち、メガネがどこかに吹っ飛びました。この時に至ってさすがにやばい、と思いました。メガネをなくしたら万事休す。必死になって手あたり次第にあたりを探したところ、奇跡的にメガネは見つかりました。でも、もうこれ以上、沢を下ることは危険だと判断しました。翌朝、確認してみると私が滑べり落ちたのは3メートルほど。一歩間違っていれば骨折やより悲惨な事故もありうる高さでした。
滑落した場所のそばに平地のようなものを見つけ、私はそこに屹立しているスギと思われる木の根元で横になりました。同時に家族にLineを打ちました。帰れない、野宿すると。
娘からは私の父にも連絡が行き、必ず警察や消防に連絡するように激怒の連絡が。妻がその時に一緒にいた友人のご主人も私の身を案じ、近くまで探しに来ようかとまでおっしゃってくださいました。ありがたいことです。

私がこの時、申し出を断った理由を何個か挙げられます。
・着ていたポロシャツに加え、山登りモードでリュックを持ってきており、そこにラガーシャツとポンチョを入れていた。マスクも二つを持っていた。
・私の身体の状況を確認すると、どこにも捻挫や骨折はなさそうだった。
・遭難したのが人里からあまり離れておらず、朝になって道がはっきりすれば必ず人里に戻れる確信があった。また、獣に襲われるほど山奥でなかった。
・少し小雨が降っていたが、事前に記憶していた天気予報では大雨になる兆しはなかった。
・19時の時点でiPadの充電は70%以上あり、節約すれば朝になって連絡ができるはず。そもそも妻とはLine通話や連絡も可能だった。
・そもそも私がどこにいるのか分からず、助けに来てもらってもすぐには見つからず、皆さんに迷惑をかけてしまうことは避けたかった。
そこで私は一晩ビバークを決断しました。
ビバークの間に考えたことは三つ。
一つは、kintone案件で迷っていた構成をまとめることでした。構成は熟知していたので、脳内だけで検証ができました。
一つは、28日に予定のkintone CaféのLTで話す内容。これも決めました。
残りの一つ。それこそ、本稿で書いてきた内容の結論です。空虚な自分を埋める方法。私と沢庵和尚の間にある違いとは何か。
せせらぎと雨音、虫の音がたまに聞こえるだけの世界。そこにいるのは自分だけ。頼れるのも自分だけ。考えるにはうってつけの機会です。むしろ私は、この問題をじっくり考えるためにビバークを選んだのかもしれません。安全が確保できているとはいえ、遭難は異常なこと。その状況で考えた時、結論はより自分の本能を反映するのではないだろうか。
生きたいのか、それとも人生を諦めようとしているのか。
その時に考えたのは、以下のようなことです。
沢庵和尚も自分が死ねば無になることを感じていた。つまり、生きている間も自分の中核にある空虚に気づいていたのではないか。
私も死ねば無になる。そして今の自分の中核は空虚。そう考えると、今の自分が中核の空虚を無理に埋める必要はないのでは。
では沢庵和尚と私の違いは何か。沢庵和尚は話を面白く伝える能力や、禅、武道、茶道などに対する知識を豊富に持っていた。豊かな知識があってこそ話に深みが出る。それが面白く伝える能力の源だった。沢庵和尚の内面の空虚さを補ってありあまるほどに。
私と沢庵和尚を隔てるものとは、この世間に分かりやすく伝えるスキルではないだろうか。
豊川稲荷の荼枳尼天は、そのことを私に伝えたかったのではないだろうか。
私は自分の中に何かをしたいという強い意志を発見しました。そして、その意志を押し通した結果、誰も助けのない世界に一人で横たわって夜を過ごす羽目に陥りました。
その意志の力をこれからも殺さずに生かしていこう。読書、旅、歴史、山、滝、鉄、神社仏閣。意志を強く持ち、自分の興味を満たしていこう。
その一方で当時の仏教界や徳川幕府が帰依した沢庵和尚の発信力を見習おう。それにはきちんとした学識と良識が必要。
今の私がシステム・エンジニアを生業にしているのなら、その方向で発信すればいい。ただし、内容を充実させなければ。発信の裏打ちとなる知識をより深く学び、当代でも指折りの人物にならなければ。
その努力が、きっと自分の空虚な中身を少しでも満たしてくれるはず。
私はそうしたことを朝まで考えました。何度も何度も。
目が覚める5時半。空は白んできました。その時、妻からも連絡が来ました。私は行動を起こし、そこから荒れに荒れた沢を落ちないように進みました。すると、道にたどり着きました。そこは私が駐車した側とは山の反対側でした。私は完全に逆側の沢に迷い込んでいたようです。あらためて夜の山の恐ろしさと、迷ったらみだりに動くなかれという教訓を肝に刻みました。
私の年齢から考えると、次に遭難すると命に係わるはずです。ですから、このようなことは二度とないように自分を律しなければ。
ですが、自分が危地にある状態で考えた思索は、私にとって宝物となりました。孤独と危機が両立した状況で自分だけの時間を持てる機会は二度とないでしょうから。
令和三年の夏から秋にかけてのさまざまな出来事。生まれた場所や死の恐怖やコロナ感染は、私にこれを伝えるためだったはず。
であれば、せっかくの機会は生かしつつこれからも生きていこうと思います。