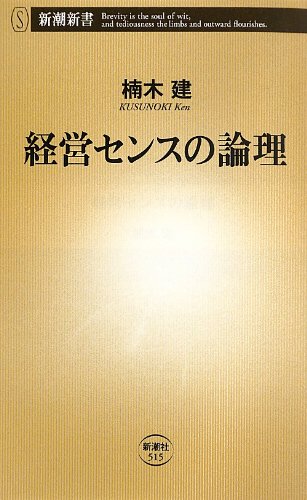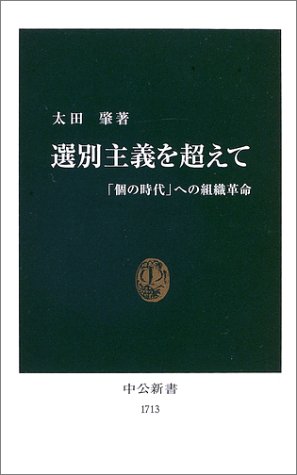
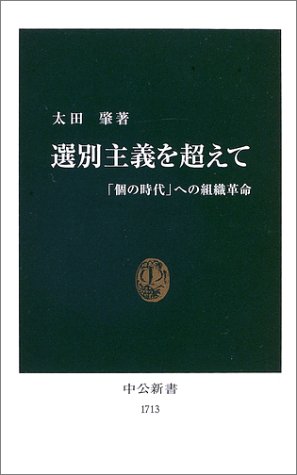
本書は、私が人を雇用し、そろそろ組織を構築しなければ、と思い始めた頃に読んだ。
私の社会人のキャリアは、人とは違う道を歩んだように思う。
新卒で就職する事を諦めた私は、フリーター・ニートの道へ。しばらく、アルバイト生活を転々とした後、就職を決意するもののブラック起業に入ってしまい、揚げ句に皆の面前でクビを宣告され。
そこから、いきなり上京した私は派遣社員の道へと。やがて正社員に登用された私は程なくして転職。そこで個人事業主として会社の立ち上げにスカウトされ、さらにそこを抜けた後は個人事業主として、複数の現場を渡り歩くフリーランサーの稼業へと。やがて、個人事業主を法人にし、雇用に踏み切って今に至った。
このテーマでは、以前鎌倉商工会議所で登壇して話したこともある。
私のキャリアは上に書いたとおりだ。そのため、組織の中で組織の論理に苦しめられた経験が少ない。むしろ、苦しめられたらすぐにそこを離れた。そして、組織の論理に縛られるのを嫌って、その度に自分にとって楽であろうと選択を重ねてきたら今に至った。
本書の後半には、組織の中で自営業のように自由に動く働き方や、フリーランスの形を選ぶ働き方が登場する。ところが、私はだいぶ前にフリーランスの生活を選んだ。すでに本書に書かれている内容は自分の人生で実践していた。つまり、私は本書から学ぶところは本来ならばなかった。
だが、ここに来て私は人を雇用し、組織を作る側になった。すると、本書の内容は私にとってちがう意味を帯びてくる。
組織になじめず、組織から遠ざかっていた私が組織を作る。この皮肉な現実について、本書はいろいろな気づきを与えてくれた。
つまり、私が嫌だったと思う事を個人にしないような組織。それを私が作り上げていけばよいのだ。
しかし、どのように自分に合った組織を作ればよいのだろうか。
例えば経営者としての私が人を雇い、評価し、昇進・昇給させる。その時の基準はどこにおけば良いのだろうか。
私が人を昇進させ、昇給させる営み。それはつまり選別することに等しい。
一方、本書のタイトルは「選別主義を超えて」と題されている。選別がそもそも今の世の中にそぐわなくなり、その次を説いている。
と言う事は、私の中でされて嫌だったことをする必要はない。そのかわり、新たな手法を駆使して組織を運営していかなければならない。ここで私の脳内は堂々巡りを始める。
第一章 席巻する選別主義
この章では、今までのように横並びで入社し、終身雇用の名の下に全ての社員を平等に扱う建前から、早めにエリートを選別し、昇給や昇進にもあからさまな差をつけるやり方が広まっている現状を紹介している。
弊社はまだ零細企業だ。メンバーも少ない。一括で何十人も採用できるような規模になるにはまだ早い。そもそも、働けない社員を雇う余裕はない。そのため、弊社は採用面接の段階で選別をしなければ立ち行かなくなる。
また情報技術を旨とする弊社であるため、昔ながらありえたような単純作業のために人を雇うつもりもない。むしろ、そうした作業は全てシステムに任せてしまうだろう。
第二章 選別主義の限界
この章では、そうした選別主義がもたらす組織の限界について触れている。
社員間に不公平感がはびこること。そもそも選別を行うのは人間である以上、完璧な選別などありえないこと。本章はそうした限界が紹介される。
私も今、経営をしながらそれぞれの社員の適性やスキルや進捗を見極めるようにしている。だが、規模がより広がってくると、私一人ですべての社員の評価をすることは不可能だ。そもそも、私も人の子だ。完璧に客観的な評価ができるか正直自信はない。
第三章 「組織の論理」からの脱却を
ここからは、新たな働き方への転換を紹介している。
組織が人を選別することの限界が来ているのなら、一人一人の社員が個々の立場で自立し、組織に頼らない人間として成長する。そうした道が紹介されている。
この章で書かれているのは、私が組織の中にいながら次の道を模索した試行に通ずる。実際、私はそのような選択を自分の人生に施してきた。今の私は弊社のメンバーにも、自立できるような人になってほしいと望んでいる。
もう、組織に頼りっぱなしで生きる生存戦略は、その本人の一生にとって良くない結果をもたらす。
何も言わず、文句も言わず、ロボットのように働いてくれる社員は果たして経営者にとってありがたいのか。おそらく私はそうした社員の明日は厳しいと感じる。
第四章 適用主義の時代へ
この章で紹介するのは、選別主義に代わる新たなパラダイムである適応主義だ。ある一定の年数がたてば昇給していくのではなく、その都度の会社の業績と個人・部署の業績を社会の状況に照らし合わせ、その都度で評価を行う。それが本書のいう適応主義だ。つまり年功序列は関係ない。
まさに今、社会はこのようになりつつある。
著者は、そのような社会になるためには、学校自体も変わらなければならないと言う。つまり従来のように新卒で大量採用し、といった企業側の要請が変わりつつある以上、学校側も変わらなければならな。企業からも任意のタイミングで社員を学校で学ばせることもある。柔軟で流動的な制度とカリキュラムも必要だとする。
私もこの点は同感だ。
今のような複雑な社会において、企業に入った後は勉強せずに過ごせる訳がない。会社に入っても常に勉強しなければ、これからは社会人としては通用しないと思う。
では、人々は何をどのように学べばよいか。それは企業側では教えにくい。だからこそ大学や専門学校は、常に社会人に対して門戸を開いておかなければならない。
第五章 21世紀の組織像
本書が刊行されたのは2003年。すでに21世紀に突入していた中で21世紀の組織像を語っている。
本書が刊行されてから19年がたち、ますます組織のあり方は多様化している。情報技術の進化がそれを可能にした。
本書で、フリーランスなどの新たな働き方が紹介される。それは、会社や組織を一生の働き場として見ず、スキルアップの場として見る考えだ。キャリアの中で組織に属するのは、あくまでも自らをバージョンアップさせるため。
本章で書かれていることは、私から見ると当たり前の事のように思える。たが、まだまだ組織に依存する働き方を選ぶ人が多いのは事実だ。2022の今でも。まだまだこれは改善の余地はある。そして、企業側でも流動的に働き方を前提に業務を組み立てることが求められる。
終章 日本型システムを見つめ直す
この章では、欧米の最新型の経営手法を安易に持ち込み、日本でまねる事の危険性を述べている。
私もまだ、自分なりの経営手法については試行錯誤の段階だ。
結局、私がいくらあがいたところで、組織としてきちんとした運営ができるようになには、規模が大きくなければ意味がない。
弊社の今の規模であれば、まだ私一人で対応できる。だが、やがては人事担当者を設け、本格的に考えていかなくては。
ただ、そうなったら今度は私個人のくびきを離れ、組織が組織としての自前の論理を備えていく。そうなったとき、個の時代を標榜する本書の意図に反した組織になっていかないか。
そうした段階に達したとき、どこまで経営者の、つまり個を重視する私の考えが評価の中に生かされていくのか。
本書を読むと、そうした課題のあれこれが果てしない未来になるように思える。努力するしかない。
2020/10/21-2020/10/28