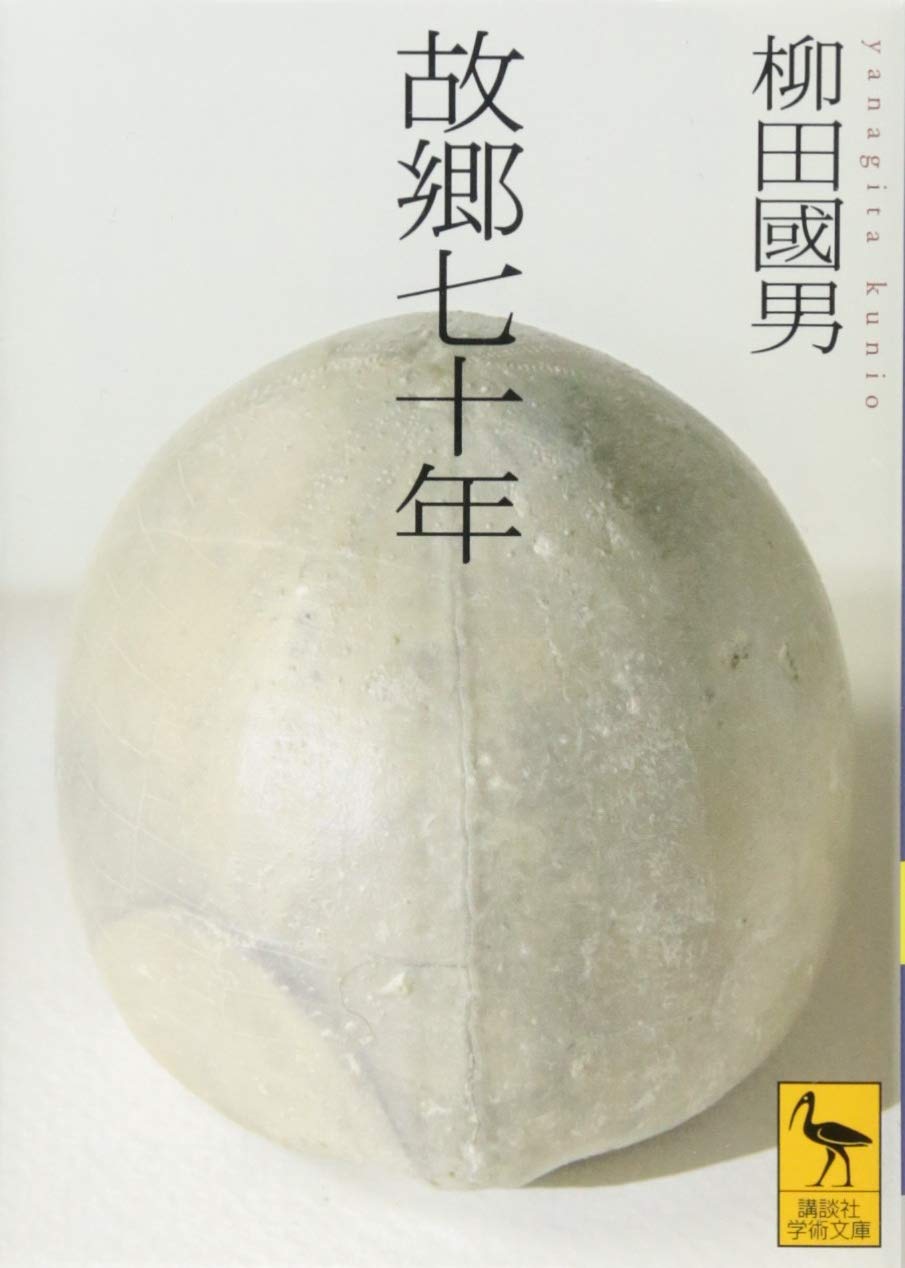
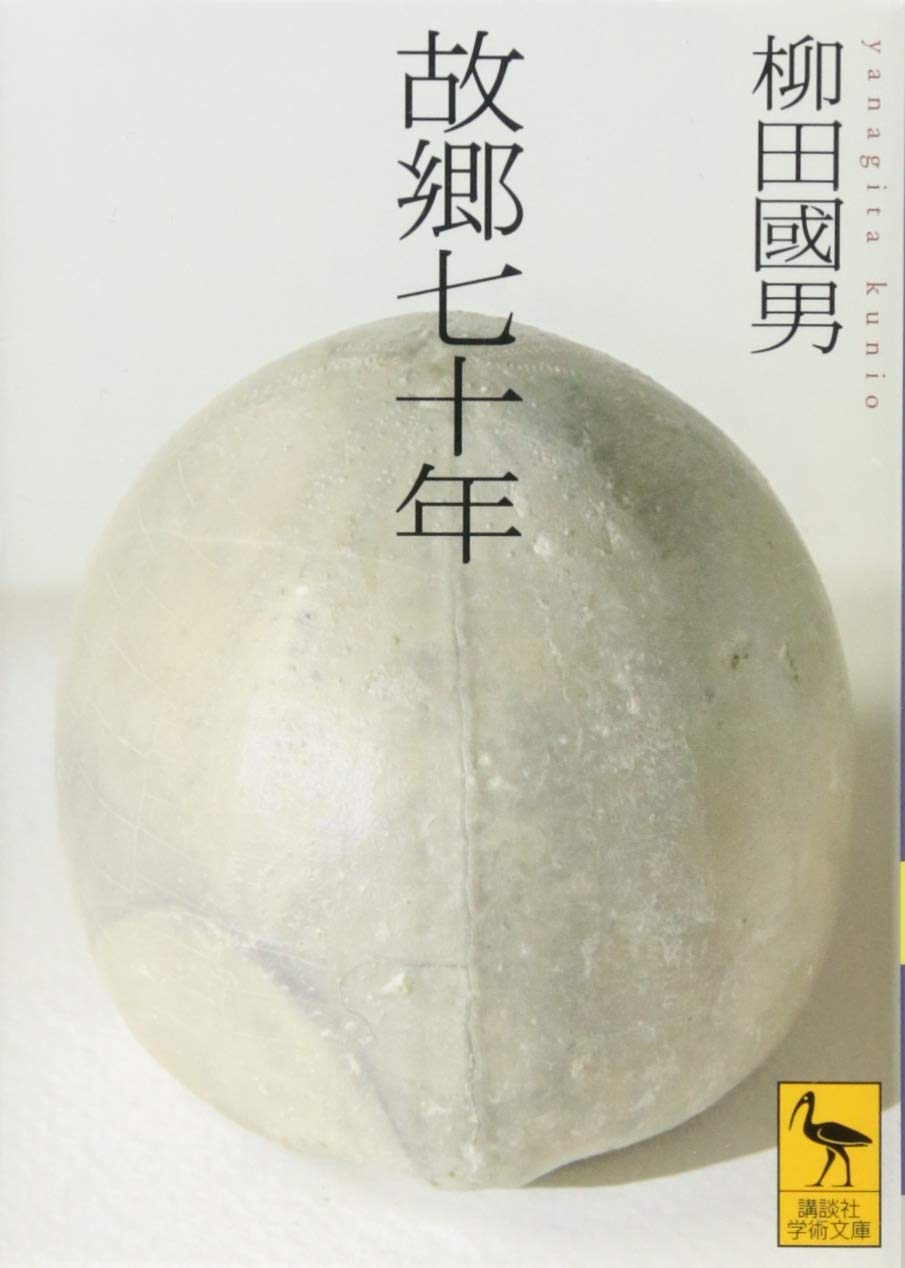
数年前に著者の故郷である福崎を訪れたことがある。
その訪問の記録はこちらのブログにまとめた。
福崎の町に日本民俗学の礎を求めて
訪問する前の秋には、神奈川県立近代文学館で催された「柳田國男展」を見た。展示を見た感想はこちらのブログにまとめている。
生誕140年 柳田國男展 日本人を戦慄せしめよを観て
著者の偉大なる実績と生涯はその二つの経験で十分に学んでいたつもりだ。著者だけでなく、著者の生家である松岡家がとても偉大であったことも含めて。というのも、著者を含めて成長した松岡家の四兄弟の皆が世に出て名を残したのだから。
民俗学という研究分野が、私にとっての関心でもある。どうすればあれだけの成果をあげられたのだろうか。
著者が私に感銘を与えたことは他にもある。著者が博覧強記を誇る民俗学の巨人として実績を積み上げながら、実はキャリアのほとんどを官僚として勤め上げたことだ。
私は展示会において、著者がどのようにして日々の勤めと自らの興味を両立したのかについて強い興味を持った。
そこで展示会を訪れた後、福崎の街を訪れた。
著者が少年時代を過ごした場所を見てみたいと思ったためだ。
私が訪れた福崎の街。今もなお中国自動車道が街を横断し、JR播但線が南北を貫く交通の要衝だ。だが、今の福崎の状況からかつての街道の栄華を想像することは難しい。東西の動脈を擁するとはいえ、かつての往来のあり方とは違ってしまっている。かつての繁栄のよすがを今の福崎から想像することは難しい。
訪れた著者の生家の近くは拓けている。農村風景の余韻もの残っている。が、著者が幼い頃は旅人が頻繁に往来し、家の存在感はさらに顕著だったはずだ。
生家は明治・大正の様子をかろうじて想像させる。そのたたずまいは、著者が小さい家だったと本書でも述べている通りの質素な印象を私に与えた。生家の裏山から受ける印象はからりとして明朗。民俗という言葉からうける暗さやしがらみを感じなかった。
著者は、どういうところから民俗学の関心を得たのだろうか。
まず一つは、本書にも書かれている通りだ。生家近くの三木家の書物から受けた恩恵は大きい。三木家へ預けられている間に、著者は三木家にあった何百、何千冊の書物をあまねく読み込んだようだ。それはは著者の世その冊数は何千冊もあったことだろう。書物の世界をきっかけに、人間の住むこの世界への想像をたくましくしたことは想像がつく。さらに、これも本書に書かれているが、街道に面した著者の家の近くにはありとあらゆる旅の人が行き交い、幼き著者はそうした人々から興味深い地方のよもやま話を聞かされたのだろう。
あともう一つだけ考えられるのは著者が場所による文化の違いを若い頃から知ったことだ。著者は、福崎で生まれ育った。が、長じてのちに茨城の布佐で医師となって診療所を開いた長兄を頼り、茨城へ住み家を移した。つまり著者は幼い頃に兵庫の福崎と茨城の布佐の二カ所で育った。文化が全く違う東西の二カ所で暮らした経験は、地域ごとの風習や民俗の違いとして著者の心に深く刻まれただろう。
私が訪れたのは福崎だけだ。布佐にはまだ訪れたことがない。
もっとも、私が訪れたところで福崎と布佐の違いをつぶさに観察できると思えない。ただ、当時は今よりも訛りや習わしやしきたりの違いも大きく、若き日の著者に大きな影響を与えた事を想像するしかない。
本書で著者は福崎で過ごした日々と、布佐で受けた日々の印象を事細かに書いている。
本書はインタビューを聞き書きし、再構成したものだという。著者はおそらく椅子に座りながら昔を語ったのだろう。昔を記憶だけですらすらと語れること著者の記憶力は驚くべきことだ。
著者の博覧強記の源が、老年になっても幼い頃のことを忘れないその記憶力にあったことは間違いない。
私は本書から、著者のすごさが記憶力にあることを再確認した。
民俗学とは、文献と実地を見聞し、比較する学問である。インターネットのない著者の時代は、文献と文献をつなげる作業はすべて記憶力に頼っていたはずだ。たとえ手帳に書きつけていたとしても、そのつながりを即座に思い出すには記憶の力を借りる必要があった。
各地の伝承や伝説をつなぎ合わせ、人々の営みを一つの物語として再構成する。
誰も手をつけていなかったこの学問の奥深さに気づいた時、著者の目の前には可能性だけがあったことだろう。
ましてや、著者が民俗学を志した頃は江戸時代の風習がようやく文明開化の波に洗われつつあった。まだまだ地域ごとの違いも大きく、その違いは今よりもいっそう興味をそそられるものだったはずだ。
そう考えると今のインターネットや交通が発達した現代において、民俗学の存在意義とはなんだろうか。
私が考えるに、文明が地域ごとの違いを埋めてしまいつつある今だからこそ、その違いを探求する事は意義があるはず。
本書を読み、民俗学に人生をかけようと思った著者の動機と熱意の源を理解したように思う。
最後に本書から感銘を受けたことを記しておきたい。
このこともすでに展示会を訪れて感じ、本稿でも述べた。それは、著者の民俗学の探究が中年に差し掛かって以降に活発になった事だ。
私たちは人生をどう生きれば良いか。
著者のように官吏として勤務につきながら、自分の興味に打ち込むために何をすれば良いか。
本書を読む限りでは、それは幼い頃からの経験や環境にあることを認めるしかない。
幼い頃の環境や経験に加え、天賦の才能が合わさり、著者のような個人が生まれるのだろう。
では、私たちは著者のような才能や実績を前に何をすれば良いのだろうか。
それはもちろん、時代を担う子供たちへ何をすればよいのか、についての答えだ。
子供たちに何をしてあげられるのか。経験・環境・変化・交流。
私たちが著者のようになることは難しいが、子供たちにはそのような環境を与えることはできる。
著者の人生を概観する本書は、著者の残した実績の重さとともに、人が次の世代に何ができるかを教えてくれる。
2020/11/11-2020/11/21


