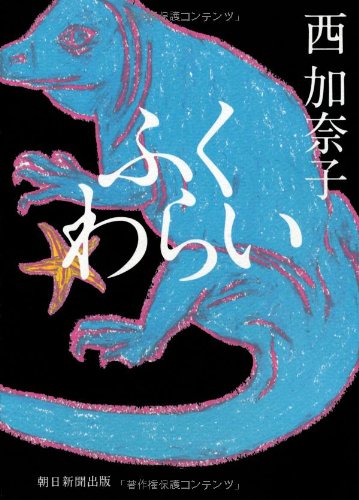本書は乱歩賞を受賞している。
それも選考委員の満票一致で。
私もそれに同意する。本書はまさに傑作だと思う。
そもそも私は、本書を含めて全盲の視覚障害者の視点で描かれた小説を読んだ記憶がない。少なくとも本書のように全編を通して視覚障碍者の視点で描かれた小説は。
巻末の解説で有栖川有栖氏が谷崎潤一郎の「盲目物語」を挙げていたが、私はまだ「盲目物語」を読んだことがない。
視点が闇で閉ざされている場合、人はどう対処するのだろう。おそらく、自分の想像で視野を構成するのではないだろうか。手探りで、あるいは杖や記憶を頼りとして。
それでも、健常者に比べて情報の不足は歴然としている。
私も本書を読んだ後、目を閉じて少し移動してみた。だが、たったそれだけのことが大変だった。
暗闇の視野の中、街を歩くことを想像するだけで、もう無理だと思ってしまう。ましてや、謎解きなどとんでもない。
視覚情報を欠いて生きることは、とても不便なのだ。
本書が描くような闇の中を手探りで行動する描写を読むと、普通の小説がそもそも、正常な視点で語っていることに気づく。その当たり前の描写がどれだけ恵まれていることか。
全盲の人から見た視野で物語を描くことで、著者は健常者に対して明確な問題意識を提示している。
本書は、健常者に視覚障碍者の置かれた困難を教えてくれる意味で、とても有意義な小説だと思う。
もう一つ、本書が提示しているテーマがある。それは、中国残留孤児の問題だ。
太平洋戦争が始まる前、政府の募集に応じて満洲や中国大陸に入植した人々がいた。それらの人々の多くは敗戦時の混乱の中現地に放置された。親とはぐれるなどして、現地に放棄された人もいる。ほとんどが年端のいかぬ子どもだった。彼ら彼女らを指して中国残留孤児という。
彼らは中国人によって育てられた。そして成長してから多くの人は、自らのルーツである日本に帰国を希望した。
私が子どもの頃、中国残留孤児の問題が新聞やニュースで連日のように報じられていた事を思い出す。
彼らが親を見つけられる確率は少ない。DNA鑑定も整っていない1980年初めであればなおのこと。
双方の容貌が似ているか、もしくは肉親が覚えている身体の特徴だけが頼りだった。
当然、間違いも起こり得る。そして、それを逆手に他人に成り済まし、日本に帰国する例もあったという。
幼い頃に比べると顔も変化する。ましてや長年の間を離れているうちに記憶も薄れる。
ましてや、本書の主人公、村上和久のように視覚障碍者の場合、相手の顔を認められない。
そこが本書の筋書きを複雑にし、謎をより魅力的な謎に際立たせている。
視覚障碍者と中国残留孤児の二つを小説の核としただけでも本書はすごい。その着想を思いついた瞬間、本書は賞賛されることが約束されたのかもしれない。
自らの孫が腎臓移植を必要としている。だが孫のドナーになれず、意気消沈していた主人公。さらに、血がつながっているはずの兄は適合検査すらもかたくなに拒む。
なぜだろう。20数年前に中国から帰国した兄。今は年老いた母と二人で住んでいる兄は、本当に兄なのだろうか。
兄が検査を拒むいくつかの理由が考えられる。背景に中国残留孤児の複雑な問題が横たわっているとなおさらだ。その疑心が主人公を縛っていく。兄と自分の間にしがらみがあるのだろうか。それとも、兄には積りに積もった怨念があるのだろうか。
それなのに、村上和久にはそれを確かめる視野がない。すべては暗闇の中。
そもそも、視覚でインプットされる情報と口からのアウトプットの情報との間には圧倒的な断絶がある。
私たち健常者は、そうした断絶を意識せずに日々を暮らしている。
だが、主人公はその断絶を乗り越え、さらに兄の正体を解き明かさねばならない。
なぜなら、孫娘に残された時間は少ないから。
そうした時間的な制約が本書の謎をさらに際立たせる。その設定が、物語の展開上のご都合を感じさせないのもいい。
中国残留孤児のトラブルや思惑が今の主人公にどう絡み合っているのか。そこに主人公はどのように組み込まれているのか。
そうした相関図を健常者の私たちは紙に書き出し、ディスプレイで配置して把握することができる。だが、主人公にはそれすらも困難だ。
そのようなハンディキャップにめげず、主人公は謎の解明に向けて努力する。その展開に破綻や無理な展開はなく、謎が解決するとまた新たな謎が現れる。
目が見えない主人公が頼りにするのは、日々の暮らしで訓練した定位置の情報だ。
だが、それも日々の繰り返しがあってこそ。毎日の繰り返しからほんの少しでも違った出来事があるだけで主人公は異変を察知する。それが謎を解く伏線となる。
主人公の目のかわり、別居していた娘の由香里も担ってくれるようになる。あるいは謎の人物からの点字によるメッセージが主人公に情報を伝える。
白杖の石突きや踏み締める一歩一歩。あるいは手触りや香り。
本書にはそうした描写が続出する。主人公は視覚以外のあらゆる感覚を駆使し、事件の真相の手がかりを求める。
その五感の描き方にも、並々ならぬ労力が感じられる。実に見事だ。
本書の解説でも作家の有栖川有栖氏が、著者の努力を賞賛している。
著者は幾度も新人賞に落選し続け、それでも諦めず努力を続け、本作でついに受賞を勝ち取ったという。
そればかりか、受賞後に発表した作品も軒並み高評価を得ているという。
まさに闇を歩きながら五感を研ぎ澄ませ、小説を著すスキルを磨いてきたのだろう。
それこそ手探りでコツコツと。
あり余る視覚情報に恵まれながら、それに甘えている健常者。私には本書が健常者に対する強烈な叱咤激励に思えた。
ましてや著者は自らの夢を本書で叶えたわけだ。自分のふがいなさを痛感する。
‘2020/02/19-2020/02/20