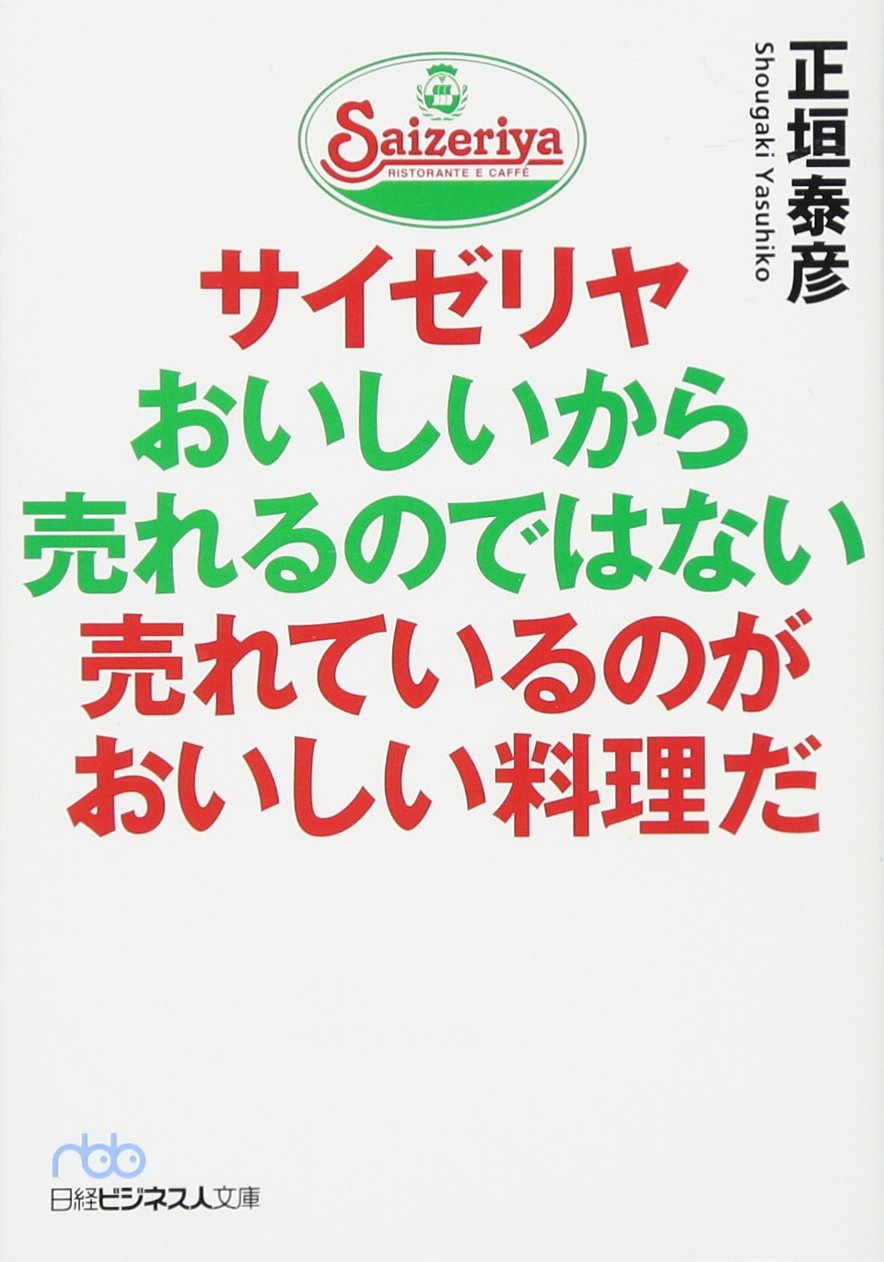
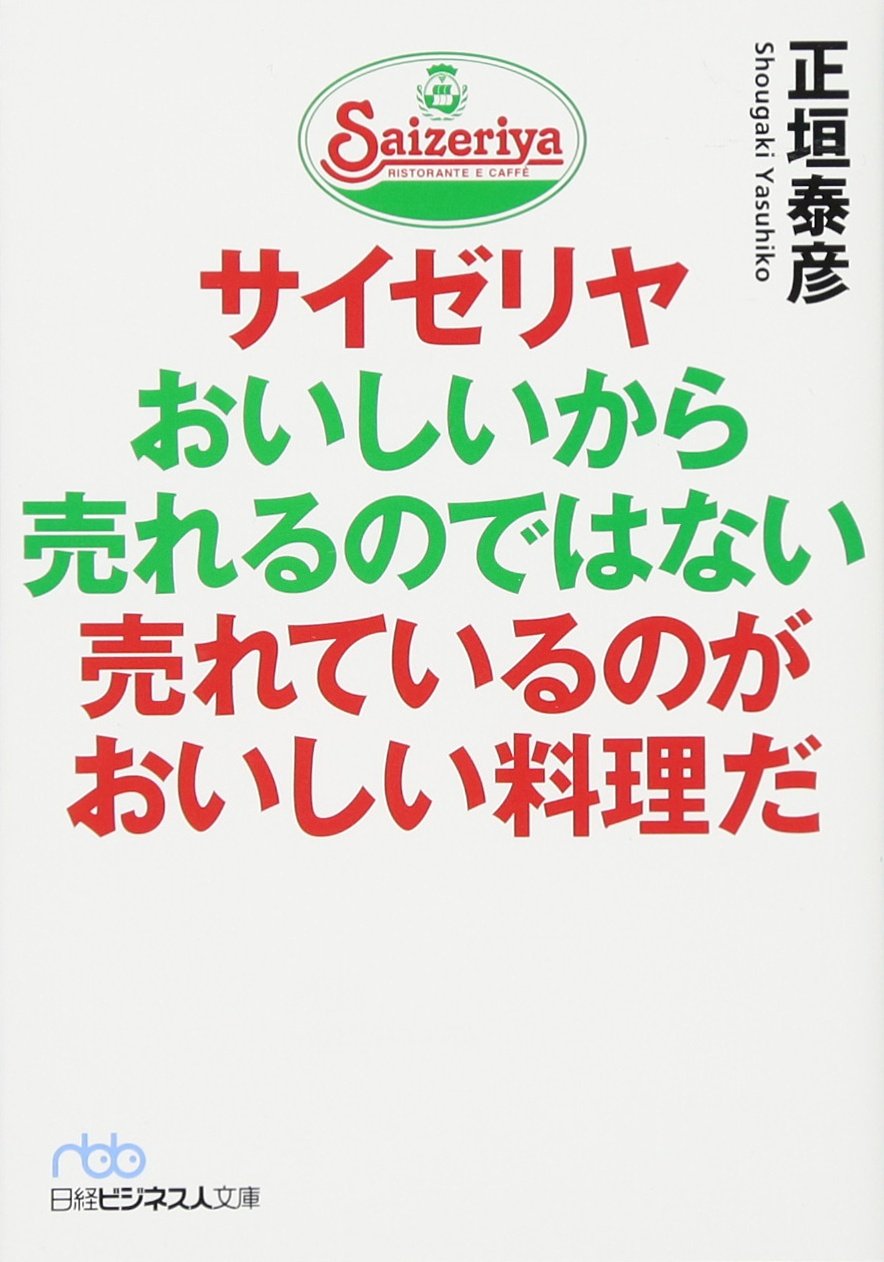
サイゼリヤは私が上京してからよく訪れているレストランだ。さまざまな店舗を合わせると、百回近くは行っているはずだ。
その安さは魅力的だ。そして味も常に一定のレベルの品質が保たれている。
(一度だけ、わが家の近所の店であれ?ということはあったが)
著者はサイゼリヤの創業者であり、今も会長として辣腕を振るっている。
その著者がサイゼリヤを創業し、経営していく中でどのように一大チェーンを築き上げたのか。そのノウハウや哲学を語るのが本書だ。
本書は、レストランの業界誌に連載されていた内容をもとにしているという。そのため、ページ数はさほど多くない。とはいえ、内容がコンパクトにまとめられているので、著者なりの経営の要点が学べる。
私が経営者として感じている壁は無数にある。その一つが、個人からチェーン展開への壁だろう。
個人で全てを回せているうちはまだいい。だが、規模を拡大しようとした途端、個人の能力や時間では賄えなくなってしまう。個人には24時間しか与えられていないからだ。
そこで人を雇う。さらに拠点を増やす。そうなると経営者の目は行き届かなくなる。個人のノウハウをどうやれば伝達できるのか。社員を多く雇い、規模を大きくするには、個人のノウハウを伝達しなければならない。スキル、哲学、規律。それを教えることが最初の壁だ。経営者が自らのビジネスを拡大するためには、まずその壁を乗り越えなければならない。その壁は高く険しい。
それは私自身が今、零細企業の経営者として実感していることだ。
本書は、地に足のついた経営を実践する上で参考になる点が多い。
個人から組織へと規模を拡大するにはどうすればよいか。
本書を読むと、サイゼリヤの成長の軌跡が分かる。サイゼリヤは、資金を調達し、急拡大を遂げてきたのではない。本書から受けるのは、一歩一歩徐々に規模を大きくし、自社でノウハウを積み上げながら経営を進めてきた印象だ。
それは経営の壁にぶつかっている私の立場からは、とても心強い。融資を受けるにはハードルが高いからだ。
著者は市川で開業した一号店で、多くの苦労と失敗をした。そしてそこから多くを学んだ。
著者は状況を打開するため、イタリアに視察に行った。そしてイタリア料理に着目した。当時は高級料理だったイタリア料理に着目したのは著者の先見の明だ。だが、それだけではない。そこから、思い切って金額を下げることで他店との差別化を行った。それらは著者が失敗から学んだことであり、それも著者の明断だといえる。
金額を下げる。それは、いわゆる安売りである。だが、一般に安売りはよくないとされている。私自身、かつては自分の単価を安く設定してしまい、自分の価値を下げてしまった失敗がある。
だが、著者は安く売ることで状況を打開した。私もそこを本書から学びたいと思った。
安売りといっても単に安く売るのではない。安く売るためには、安くてもなお、利益を出せなければ。そのためには利益を出すための体制が欠かせない。
著者は創業の頃から人時単位での生産性を重視してきたという。粗利益÷従業員の1日の総労働時間。この基準を著者は6000円という金額に設定しているそうだ。
また、ROI(Return On Investment)、つまり投資利益率を求める計算式は利益÷投資額×100だ。これも最低基準として20%に設定しているとのこと。
本書を読んでいると、サイゼリヤの成功の秘訣が見えてくる。それは、創業者である著者がどんぶり勘定ではなく、初めから利益と経営への意識をしっかり持っていたことによるのだろう。
だからこそ、継続的に成長を刻みながら、今の規模まで育てられたのだと思う。
もちろん成功の理由はそれだけではない。商品開発や組織開発なども必要だ。本書には財務だけでなく、経営全体に対する著者の努力も書かれている。
財務と組織。その両輪をきちんと押さえていたからこそ今のサイゼリヤがあるのだろう。
翻って私の反省だ。
私は個人で動くことに慣れてしまっていた。一人でやる分には、仕事も十分に回る。私は独立したとはいえ、長い期間を常駐の現場で働いてきた。そのため、私が本当の意味で経営者となったのはごく最近のことだ。常駐から抜け、個人で仕事を請けて回すようになったこの五年。それが私の経営者としての歴史だ。
この五年、個人で仕事を回せるようになってきた。とはいえ、著者の例でいうと、私はまだ、商品開発に没頭している状態だ。組織開発や財務への意識は二の次。
著者を例に例えると、店内で調理をしながら配膳をし、レジ打ちもこなしている。それが私だ。多店舗展開とは程遠い状態にある。
ようやく本書を読んだ数カ月後から、弊社でも人を雇い始めた。ようやく次の壁を乗り越えようとし始めたのだ。
その壁を乗り越えるためにも、経営者としての心の持ち方を養わねばならない。また、失敗を次への教訓として生かさねばならない。また、経験を次代に伝えなければならないし、そのためにも公平な評価を心掛けなければならない。あれもこれも追うのではなく、要となる商品をベースにおき、数値目標は一つに絞る。
ここに書いたことは、どれも本書にも書かれている経営の要諦なのだろう。
そして、経営を行うためには、単なる精神論に頼らない。気持ちを前向きに持ちながらも、押さえておくべき経営のツボはきちんと把握する。その大切さ著者は説いている。
それは例えば在庫回転率や立地の重要性である。著者はそうした観点や指標を例に挙げる。ただ、著者が経営するチェーンストア業界ではなく、それぞれの読者の属する業界によって、その指標は臨機応変に変わるはず。まずはそれを理解すべきだろう。
例えば私のような情報処理業界の場合に置き換えてみる。
例えば、適切な案件が継続的に請けられ、その用意と準備と実装と保守が順調に回る状況。それこそがあるべき姿なのだろう。
そのためには、自社の得意分野を踏まえた上で、正当な商圏を見据える。そして、むやみやたらと広告や営業を打つのではなく、特定の企業に売り上げを依存するのでもなく、適度に分散してリスクを負わない営業チャネルを構築する。そんなところだろうか。
著者は働くことは幸せになることだ、という理念を掲げ、それを常に見直しているという。さらに、経営に失敗という概念はなく、失敗に思えるものはすべて次へつながる成功なのだとも説く。
そして、著者が説くことでもっとも私の心に刺さったことがある。それは、変化に対応するために必要なのが「組織」だと著者はいう。
普通に考えると、機動力と行動力のある一人の方が変化に対応しやすいのではないか。だが、一人だと、対応できるのは一人が動ける時間に限られる。一人の一日の持ち時間は24時間だ。
だが、組織の場合、人数×営業時間が持ち時間として与えられる。分業だ。それぞれが分業をこなし、その能力を磨きつつ、能力を発揮する。それができたとき、組織は一人の時よりも変化に対応できる。
本書で著者が説いている内容は決して難しくない。だからこそ、理屈をこねくり回す必要もない。経営とは複雑なものではなく、本来は単純なものなのかもしれない。だが、そう分かっていても経営は難しい。だが、経営者はそれをやり遂げなければならない。
私は自分の会社をどうしたいのか。経営理念は作り、雇用に踏み切った。失敗もして、ようやく少しずつ組織が形になりつつある。
税理士の先生、社労士の先生に加え、人財コンサルタントの方にもご指導を受けている。
本書で学んだこと、諸先生方のご指導を踏まえ、少しずつ経営の実践と安定に努力しようと思う。
2020/10/5-2020/10/5






