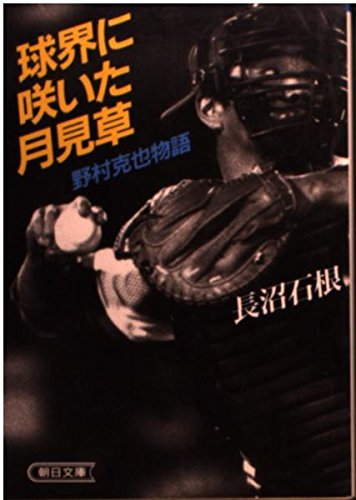
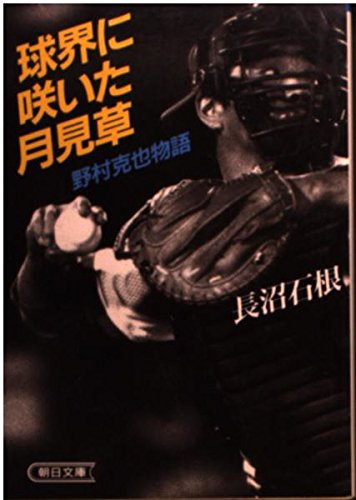
本書を読んだのは、野村克也氏が亡くなって三カ月後のことだ。
もちろん私は野村氏の現役時代を知らない。野村氏は私が7歳の頃に現役を引退しているからだ。
ただ、野村氏が南海ホークスの選手だった頃に住んでいた家が、私の実家から歩いて数分に位置していたと聞いている。ひょっとしたら幼い時にどこかですれ違っていたかもしれない。
現役時代から、解説者として監督として。野村氏の成し遂げた偉大な功績は今更言うまでもない。
また、野村氏は多くの著書を著したことでも知られる。実は私はそれらの著書は読んだことがない。ただ、野村氏の場合はその生涯がそもそも含蓄に富んでいる。
その生涯を一言で表現すると”反骨”の一言に尽きるだろう。本書のタイトルにそれは現れている。月見草。この草は600本の本塁打を打った際、インタビューを受けて語った中に登場する。野村氏の生きざまの体現として知られた。
本書は、野村克也という一人の野球人の生涯を丹念に追った伝記だ。本人も含めて多くの人に証言を得ている。
幼い頃、父が中国で戦死し、母も大病を患うなど貧しさの少年時代を過ごしたこと。高校の野球部長が伝をたどってつないでくれた南海ホークスとのわずかな縁をモノにして入団したものの、一年でクビを告げられたこと。そこから捕手として、打者として努力を重ね、戦後初の三冠王に輝いたこと。選手で一流になるまでにはさまざまな運にも助けられたこと。
南海ホークスでは選手兼任監督として八シーズンの間、捕手と四番と監督の三つの役割を兼任したこと。ささやき戦術や打撃論、キャッチャーのポジションの奥深さ。王選手や張本選手との打撃タイトルや通算成績の熾烈な争い。
南海ホークスから女性問題で解任されたあとも、生涯一捕手としてボロボロになるまでロッテ、西武と移り、45歳まで捕手を務め上げたこと。
その後解説者として腕を磨き、ノムラスコープと言う言葉で野球解説に新風を送り込み、請われて就任したヤクルト・スワローズでは三回の日本一に輝いた。本書の冒頭はその一回目の優勝のシーンで始まっている。
本書には書かれていないが、その後も阪神タイガースや楽天イーグルスの監督を務め、社会人野球の監督まで経験した。
楽天イーグルスの監督時代には、そのキャラクターの魅力が脚光を浴び、スポーツニュースでもコーナーが作られるまでになった。
本書には月見草を語ったインタビューの一節が載っている。
「自分をこれまで支えてきたのは、王や長嶋がいてくれたからだと思う。彼らは常に、人の目の前で華々しい野球をやり、こっちは人の目のふれない場所で寂しくやってきた。悔しい思いもしたが、花の中にだってヒマワリもあれば、人目につかない所でひっそりと咲く月見草もある。自己満足かもしれないが、そんな花もあっていい。月見草の意地に徹し切れたのが、六○○号への積み重ねになった」(230ページ)
長年日の当たらないパ・リーグにいた野村氏。だが、その生涯を通して眺めれば、月見草どころか超一流のヒマワリであったことは間違いない。
ただ、その結果がヒマワリだったからと言って、野村氏のことをあの人は才能があったから、と特別に見てはならない。
確かに、野村氏の生涯は、結果だけ見れば圧倒的な実績に目がくらむ。そして、野村氏のキャラクターには悪く言えばひがみっぽさもある。
たが、そうした境遇を反骨精神として自らのエネルギーに変え、自らを開花させたのも本人の意思と努力があってこそ。
努力を成し遂げられる能力そのものを才能と片付けてしまうのは、あまりにも野村氏に失礼だと思う。
本書の中には、野村氏に師匠がいなかったことを惜しむ声が度々取り上げられる。かの王選手を育てた荒川博氏も本書で語っている。遠回りせずに実績を残せたのに、と。一人の力で野村氏は自らを作り上げてきたのだ。荒川氏はそれが後年の野村氏に役立っているとも述べている。
私が野村氏の生涯でもっとも共感し、目標にできるのは独りで学んだことだ。なぜなら私も独学の人生だから。
一方、私が野村氏の生涯でもっともうらやましいと思うのは、幼い頃に苦難を味わったことだ。私は両親の恩恵を受けて育ち、その恩に強く感謝している。だが、そのために私が試練に立ち向かったのは社会に揉まれてからだ。今になって、子供の頃により強靭な試練に巡り合っていれば、と思う。そう思う最近の自分を逆に残念に感じるのだが。
野村氏がさまざまな書物を著していることは上に書いた。
おそらくそれらの書物には、ビジネスの上で世の中を渡るために役に立つ情報が詰まっているだろう。
私がそれらの本を読んでいないことを承知で言うと、野村氏の反骨の精神がどういう境遇から生み出されたのかを学ぶ方が必要ではないかと思う。あえてその境遇に自分を置かずにビジネスメソッドだけ抽出しても、実践には程遠いのではないか。
今、私も自分の生き方を変えなければならない時期に来ている。ちょうど野村氏が選手を引退してから、評論家として生きていた年齢だ。私は野村氏のような名伯楽になれるだろうか。今、私にはそれが試されている。
くしくも本稿を書き始めた日、日本シリーズでヤクルト・スワローズが20年ぶりに日本一に輝いた。スワローズの高津監督は野村氏の教え子の一人として著名だ。
人が遺すべきものとして金、仕事、人がある。言うまでもなく、最上は人た。
亡くなった野村氏はこの度のスワローズの日本一を通し、人を遺した功績で今もたたえられている。
私も人を遺すことに自分のマインドを変えていかないと。もちろん金もある程度は稼がなければならないが。
それらを実現するためにも、本書は手元に持ち続けたいと思う。そして、本書が少しでも読まれることを願う。
‘2020/05/25-2020/05/25




