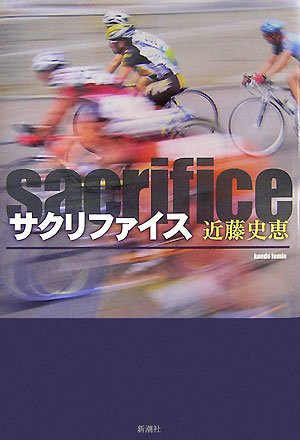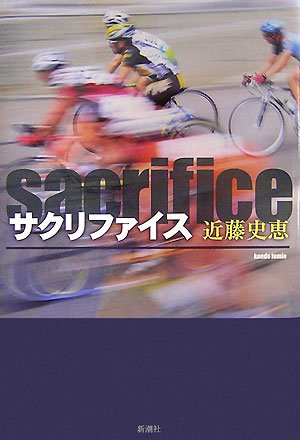
本書は、第5回本屋大賞で二位になったという。と同時に大薮晴彦賞を受賞したそうだ。
その帯の文句にもひかれ、本書を手に取った。
本書が取り上げるのは、自転車ロードレースの世界。
休日に旅先でよくロードレーサーを見かける。数人で列を作り、整然と走る姿は清々しい。
私自身、かつてマウンテンバイクで台湾を一周したことがある。
現地の百貨店で購入した自転車で一周するといういきあたりばったりの旅だったが、なんとか十日ほどで完走した。
もちろん、大学生五人による完全に素人の集まりだったので、この旅で自転車を極めたというつもりは毛頭ない。けれど、なんとなく自転車で長距離を旅する上で気をつけ、心を配るべき勘所はおぼろげに感じたつもりだ。
だが、本書で描かれる自転車ロードレースの世界は、私の理解をはるかに超えて深い。犠牲や駆け引きなど、想像を遥かに超えた複雑な競技のようだ。私はそのことを本書に教えてもらった。
ヨーロッパでは自転車ロードレースはとても人気のある競技である。それは以前から知っていた。本書の中でも言及されているツール・ド・フランスはテレビ中継を視聴したこともある。
だが、私は自転車レースをチーム戦だとあまり考えていなかった。もちろん、チームで参加する以上は団体競技の性格もあるのだろうと思っていたが、ここまでとは。せいぜい、F-1のように二人のチームドライバーがいて、ポイントによっては一方のドライバーがもう一人に勝ちを譲る程度でしか考えていなかった。そもそも、実業団レースと言う認識すら希薄だった。
そうした競技レースの世界に焦点を当てた本書は、一見すると個人競技にも思える自転車ロードレースの競技が、実はチームプレイの性格を強く持っていることを教えてくれる。
似たような競技として、公営ギャンブルである競輪がある。競輪の勝ち負けを決めるのは、単なる速さなどの身体能力だけではないと聞いたことがある。先輩と後輩の関係や、仲の良さ、出身地など、速さ以外の要素が勝敗を分けるため、競輪ファンはそこも含めて予想するそうだ。
ロードレースの世界も、それが当てはまるらしい。チームの中でエースやアシストの役割が設けられる。
各ステージごとの勝利と年間を通しての勝利を目指し、各地の各ステージを転戦する。各ステージは、それぞれ山岳コースや平地のスプリントコースなどの特色がある。選手は自らの得意なコースとそうでない場所を判断し、勝てるところでは全力で勝利を目指す。そうでないコースではポイントを積み上げて年間を通しての勝利のために走る。
だが、ロードレースはチームプレーが求められる。であるが故に、脱輪したエースのためにアシストの選手がその場でタイヤを差し出す事もある。レースを棄権することもあるし、勝てるレースであってもあえてエースに勝ちを譲らなければならないこともある。
自転車ロードレースが持つ密接なチームワークと駆け引き。その世界は、部外者にはわかりづらい。
本書はその人間関係に着目している。各地を連戦する過酷な戦いを描きながら、チームの中で起こる軋轢や葛藤と、そこから生じる人間ドラマを物語に仕立てている。
本書のタイトルのサクリファイスとは、犠牲を意味する。
チームのために犠牲となる選手は、内面にどういう重苦しい思いを宿しているのか。
チームや選手の過去に起こった悲劇。それは犠牲やチーム内の人間関係の葛藤が生んだのかもしれない。
チーム内の疑心とそこから生まれる微妙な人間関係のひだを盛り込みつつ、著者はミステリ仕立てで選手の内面や戦う姿を描ききった。そこに本書の面白さがある。
主人公は、チーム・オッジのチカだ。チカこと、ぼくの視点で本書は物語られる。
チカは、チーム・オッジには入ったばかりの若手だ。チーム・オッジには、同期の伊庭とチームのエースである石尾、それに他のメンバーもいる。各選手たちの互いの協力のもと、スタッフも含めて各地のレースを転々としている。
チカはもともと陸上の選手だったが、速さ故に受ける注目が重荷となった。そのため、チームプレイに徹することもできる自転車ロードレースの世界に飛び込んだ。
だから、もともとアシストの役目に徹することには何の屈託もない。だが、その心はなかなかチームメートには伝わらない。
同期の伊庭は選手としての野心を持ち、それを隠そうともしない。
そんな伊庭に比べ、チカはクライムヒルのコースに強さを発揮し、単なるアシストには終わらない存在感を大会で示し始める。
そんな若い二人の台頭に、エースの石尾はポーカーフェースを貫き、何を考えているのかわからない。
だが、石尾にはかつてレースの中で事故で衝突した仲間が、選手生命を断念した過去を背負っている。その事件については、石尾の地位を脅かそうとしたその選手を石尾が妨害したのではないかとの疑いがささやかれている。
チカは、そんな選手たちの間に漂う空気を感じつつも、選手としてやるべきことを行う。
そんなチカのアシストとしての献身は、海外のチームからも注目され、チームへの誘いもかかる。
日本人選手にとって、海外のチームに参戦する事は見果てぬ夢の一つだ。そこに惹かれるチカ。そうした、選手としての素直な夢とアスリートとしての矜持。そこにチームメートとの駆け引きがうまく絡む。微妙なバランスの上に立つ関係を著者は絶妙に書き分け、物語を進めていく。
かつての石尾が起こした事故の背後にはどういう事情があったのか。
その謎を物語の背後におきながら、本書に陰湿な読後感はない。むしろアスリートとしての気持ちの純粋さを感じさせる余韻。それこそが本書の評価を高めたのだろう。
私はチームプレイがあまり得意ではない。そうした駆け引きが苦手な方だ。だが、また機会があれば数人で近距離の自転車の旅はしてみたいと思う。
‘2020/08/28-2020/08/29