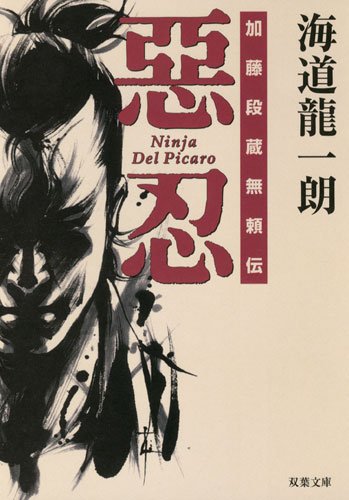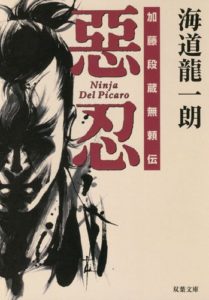本作は「華、散りゆけど 真田幸村 連戦記」から始まった三部作の掉尾を飾る一作だ。「華、散りゆけど 真田幸村 連戦記」で華々しい活躍を見せる真田幸村。著者はその次に幸村の父である昌幸にスポットを当てた。「我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記」は、幼少時から信玄の薫陶を受け、成長していく昌幸の姿を描く。ところが父を失った後、長篠の合戦で二人の兄者を失う悲劇に遭う。昌幸の悲嘆と絶望で幕を閉じる幕切れが印象に残る。
本書はぜひ前作と続けて読んでいただきたい。なぜなら、戦国時代きっての智謀の将と知られ、表裏比興の者と呼ばれた昌幸が培われた基は、幼少期の昌幸にあるからだ。七歳で真田の里から甲斐の武田家に半ば人質としてやってきた昌幸。泣きべそを兄たちからからかわれるほどの少年だった。それが典厩信繁や信玄から目を掛けられ、百足衆の一員として鍛えられ、さらに川中島のすさまじい戦いを目の当たりにして成長する。成長した昌幸は長篠の合戦に敗れ、二人の兄を一挙に喪ったことで世の現実に覚醒する。
本書は真田昌幸という一人の男が、家名と家族、そして領民や部下たちのために奮闘する様子が描かれる。それは子どもから大人へと苦しみを潜り抜け、たくましくなった男の姿だ。苦難とは、かくも人を強くするものか、というテーマ。それはあらゆる人生に欠かせない物語だ。本書はそのテーマを基に、戦国の仮借なき世を生き延びようとあがく男の気迫が全編に満ちている。
本書には前の二冊のように華々しい戦場のシーンはあまり出てこない。だが、川中島の合戦や大坂の陣ほどではないにせよ、上田城を巡って徳川軍と戦った第一次、第二次上田合戦が克明に描かれる。それぞれの戦いで昌幸の息子、信幸、信繁に戦いを教えながら、領民をうまく指導し、徳川軍を鮮やかに撃退する。そうした戦を描かせれば著者の筆は魔法を帯びる。実に素晴らしい。それ以外にも、調略で名胡桃城や沼田城を奪取した知略にも光るものがある。本書は昌幸の智謀を前面に出して描いている。
それほどまでに昌幸が守りたかったものは何か。それが本書の随所に登場する。それは長篠の合戦で兄二人を相次いで失い、兄を差し置いて真田家の棟梁となった昌幸の気負いであり、心の空洞を埋めるための奮起だ。もちろん、真田家を安泰に導かねば父や兄にあの世で顔向けできないと覚悟を持っていたこともあるだろう。
その覚悟のままに、昌幸は沼田領を巡っての北条氏との争いに忙殺される。その一方では、武田氏の遺領を巡って徳川軍、上杉軍、北条軍が争いが勃発する。昌幸は真田氏を守るため、上杉家に次男信繁を人質として送り、徳川家と和睦すると見せかけ、その条件として上田城をせしめる。それでも真田家の維持は厳しくなってきたため、豊臣家に臣従することで、家名と領地を守り抜く。
そうした目まぐるしい移り変わりを、著者は丁寧に描いてゆく。戦闘シーンはあまり登場しない本書だが、智謀だけで戦国時代という戦場を戦い抜く昌幸の気迫が生き生きと描かれている。
昌幸にとっては、上杉家に預けた次男信繁を無断で豊臣家に送り出すという義理を欠く振る舞いも辞さない。一方で、信義を一方的に破り、沼田城を断りもなしに北条家との条件のかたにした徳川家康には怒りを示す。
そのあたりの昌幸の心の動きは読み手の解釈に委ねられる。どっちもどっちじゃね?と思う人もいれば、沼田城の場合と、切羽詰まった状況を打破するために上杉家への義理を欠いた行いは同義ではないと擁護する人もいるだろう。ただ、昌幸は上杉家へ後ろめたさを感じなかったわけではない。本書でも、後ろめたさを感じる昌幸の心の動きが何度か書かれる。表裏比興の者とそしられた昌幸であっても、道を外れた恥知らずとは書きたくない作者の思いが透けて見える。
実際、本書で描かれる昌幸のふるまいのうち、失敗だと思うのは上杉家から信繁を引き抜き、豊臣家に送り出した一件だけに思える。それだけ、その時の真田家が危機に瀕していた証だったのだろう。
では犬伏の別れで、真田を二つに分け、あえて息子とともに西軍に付いた判断はどうだろう? もちろん、それは結果論に過ぎない。本書では、犬伏の別れを描くにあたり、二人の息子に自分の思う判断を述べさせている。長男は家康の四天王本田忠勝の娘小松姫をめとっているので、徳川方にくみすると述べた。次男は西軍についた大谷吉継の娘を妻にしている以上、石田方に参戦するという。二人の思いを確かめた上で、昌幸は真田を二つに割った責任を取り、隠居すると述べる。もし、昌幸がそれを実行していたら、昌幸の生涯は筋を通したままで終わったはず。
ところが、徳川方が上田城を見逃してくれず、攻め寄せる意図を見せる。それによって昌幸の堪忍袋が破れる。沼田城に続いてまた、真田を愚弄するか、という怒り。犬伏の別れで決めたのは徳川に恭順の意志を示すこと。ところが昌幸はそこで徳川に弓を引いてしまう。そうした解釈を著者は取っているようだ。それはそれで納得ができる。昌幸は見事に秀忠軍を撃退したばかりか、結果的に秀忠軍を関ケ原に参陣できなくした。
最終章で、昌幸が信繁あらため幸村に詫びを入れるシーンが描かれる。上田城の戦いは自らのわがままで起こした戦だったと。めっきり弱った昌幸は、幸村への形見として信玄から譲り受けた碁盤と碁石を渡す。これは前作でも印象深い場面で登場した小道具だ。そしてこのシーンは幸村が大坂で名をあげるシリーズの第一作につながっている。
「家康を敵にしたことが、間違いであったのか?」このセリフを独白するのが昌幸ではなく幸村であること。それは三部作の冒頭を飾る「華、散りゆけど 真田幸村 連戦記」につながっており、三部作が全体で円環の構造になっている。つまり、見事な大団円を成しているのだ。
なお、本書では信繁が幸村に名乗りを変えたことを次のように解釈している。兄信幸が徳川家に帰順した証として通字である「幸」を「之」に変えたこと。兄者にそのような処置をとらせてしまったことで、自分が、せめて信繁から「幸」の字を受け継ごうとした、という筋立てだ。それで好白斎幸村と道号を名乗ったと解釈している。それが書簡の形では後世に伝わっておらず、それが史実なのか著者の解釈なのかはわからない。だが、その解釈も受け入れられる。なぜなら本書は小説だから。
戦国の世を精一杯生きたある親子の生きざま。それが劇的であればあるほど、そうした情のこもった解釈が読者の心にすっと染み込む。
‘2018/10/23-2018/10/23