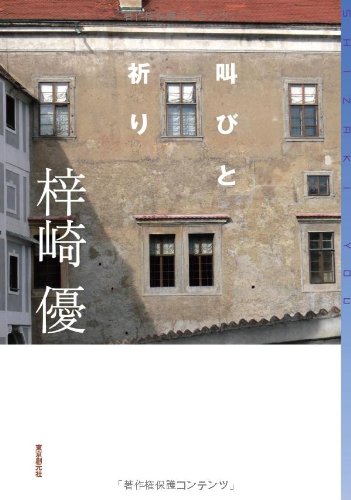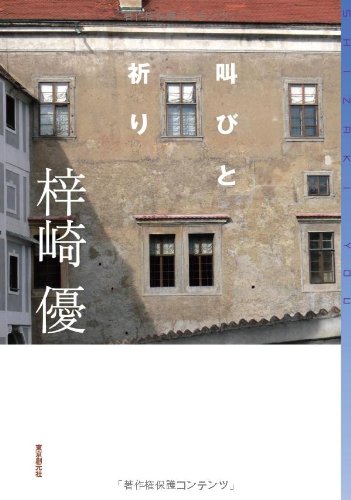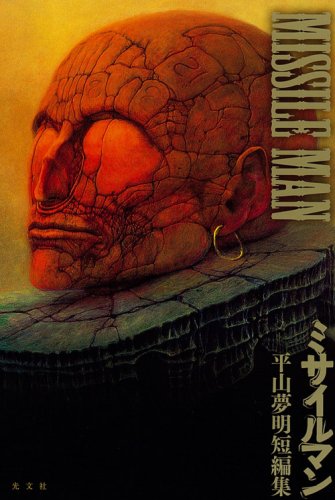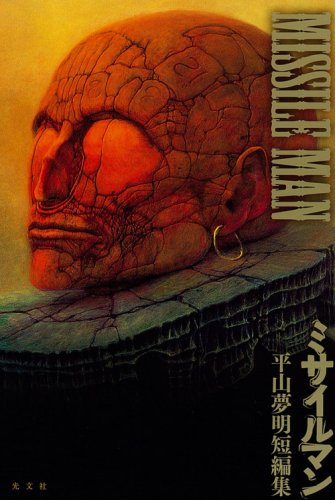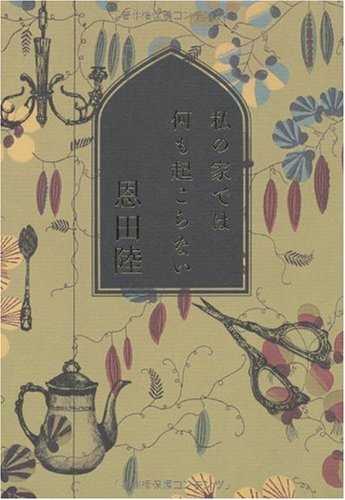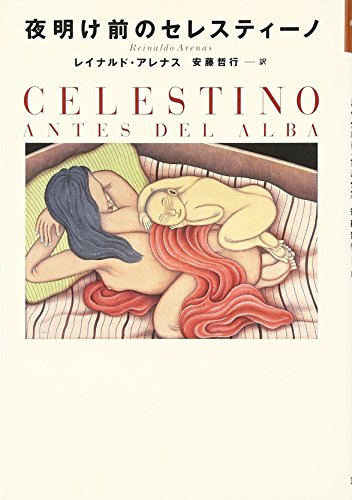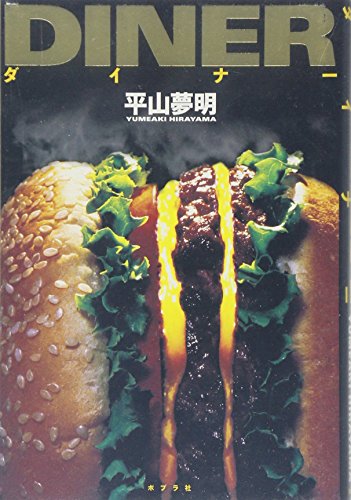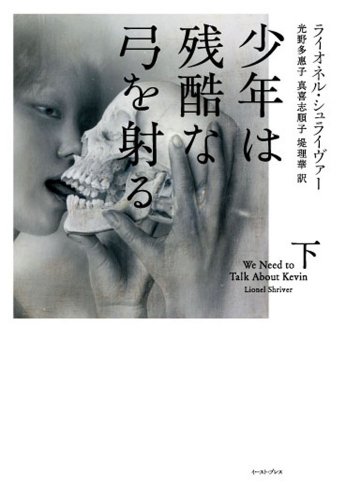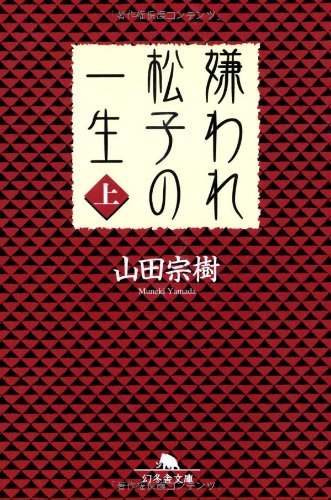本作を見てとても心が痛くなった。試写が終わった後、パネリストの方が仰った「この現実は日本でもおきている」事実が、同じ年ごろの娘を持つ身として私の心を刺した。この鋭さこそがドキュメンタリー。映像の持つメッセージの力をあらためて認識させられた。それが本作だ。
私にとってサイボウズさんとのご縁はもう6,7年になる。今までにもさまざまなイベントにお招きいただき、参加する度に多くの勉強をさせていただいた。もともと、働き方改革や柔軟な人事制度など、サイボウズさんの社風には賛同するところが多い。だから展開するサービスにも惹かれる点があり、私もkintoneやチーム応援ライセンスなどでお世話になっている。私のキャリアにとってもサイボウズさんは飛躍へのステップを作ってくださった会社。本当に感謝しているし、これからも続くべき会社だと思っている。
ところが、私が今までに参加したサイボウズさんのイベントは、そのほとんどがITに関係している。それはサイボウズさんがIT企業である以上、当然のことだ。
そんな私が今回、参加させていただいたのは、本作の特別試写会。まったくITには関係がない。なぜ、このような社会的なメッセージの強い作品の試写会を開催したのか。それは、サイボウズさんが児童虐待防止特別プランを展開されていることと密に関係しているはずだ。
子どもの虐待プロジェクト2018
南丹市、児童虐待防止の地域連携にkintoneを導入
この試写会のご担当者様は、サイボウズさんがチーム応援ライセンスを開始するにあたっての記念セミナーでもお世話になった方。私はそのセミナーで登壇させていただき、その時も今も、私が自分にできる社会貢献とは何か、について考え続けていた。そのため、お誘いを受けてすぐに参加を決めた。
本作は、2019/11/2から岩波ホールで公開予定だとか。
岩波ホールの告知サイト
公式サイト
それにしても、私が今回のような純然たる社会派の映画を見るのは久しぶりのことだ。
冒頭にも書いた通り、本作はとても心を痛める映画だ。描かれた現実そのものが発する痛みもそうだが、その痛みの一部は、私自身の無知ゆえの恥からも来ている。
そもそも私はイランのことをほとんど知らない。世界史の教科書から得た知識ぐらいのもの。「風土は?」と聞かれても、吹きすさぶ砂嵐の中に土づくりの家が集まっている、というお粗末な答えしか持っていなかった。日本をハラキリゲイシャのイメージで想像する国外の方を笑えない。
だから、本書の冒頭で一面の雪景色が登場するだけで意表をつかれてしまう。イランにも雪がふる事実。そして、普通に舗装された道路を車が走る描写。それだけで、私の認識は簡単に揺さぶられてしまう。
さらに、その雪をぶつけ合い、はしゃぐ少女たちが、とても楽しそうなのをみて、私の思いはさらに意外な方向に向かう。彼女たちは保護施設に収容された犯罪者ではなかったのか。
だが、少女たちが歌う内容を知ると、私の認識は一変する。字幕には「幸せだからって不幸せな私たちを笑わないで」という文字が。少女たちが悪事を犯した罪人という見え方が変わる瞬間だ。
本作を上映する前振りで本作の宣伝スタッフの方の言葉や、リーフレットを見ていた私は、彼女たちを単なる犯罪者だとくくっていたように思う。だが、彼女たちは犯罪者の前に一人の人間なのだ。彼女たちの多くは私の娘たちと同じ年ごろであり、本来ならば芳紀を謳歌しているはずのかわいらしい少女なのだ、という事実に思い至る。
その事実に気づくと同時に、心から楽しんでいるように見える彼女たちの笑いの裏には、想像を絶するほどの痛みがあることが感じられる。そもそも、楽しげな雪合戦も高くそびえる塀に囲まれなければできない。また、本作のあらゆるシーンには、曇り空しか登場しない。本作を通して、一瞬たりとも晴れ間は見えない。それは本作が12月から新年までの20日しかロケしておらず、季節がたまたまだったことも関係あるだろうが、監督も晴れ渡った空は撮るつもりもなかっただろう。
あえて平板なイントネーションで少女たちにインタビューしているのは本作のメヘルダード・オスコウイ監督だろうか。一切の感情を交えず、施設に入った理由を娘たちのそれぞれに聞く監督。その中立的な声音につられるように、娘たちはそれぞれの境遇を述べる。
18歳の娘は、14歳で結婚し、15歳で子どもを産んだ。だが、クスリの売人になることを強いられ、7カ月も娘には会っていないという。その子の名前がハスティ(存在)というのも、痛々しい。この世に自分がある理由。それは娘が存在しているから。だが、施設に入っている以上、娘と会うことは叶わない。名前と境遇の落差の激しさ。
昔はいい子だったというが、周りの環境に合わせて不良のように振る舞っているという少女。自分を名無しと名乗っている。面会に来るおばあさんに対しては満面の笑みを見せるのに、釈放にあたっておばあさんが来てくれないことに泣き叫ぶ。そして朝方、世間に戻されても生きていけないと絶望にすすり泣く。性的虐待を受けた自分の帰る場所は父でも母でもなくおばあさんだけ。
なりたい職業が弁護士か警官。理由は同じ境遇の子供を助けてあげたいから。と語る直後に今の夢はと聞かれ「死ぬこと」と答える少女。その矛盾した答えを発する顔は、疲れて希望を失っている。彼女は性的虐待を加えた叔父のうそを信じる家族に絶望していた。だが、家族が実は叔父のうそを見抜き、自分を信じ、愛していたことを知った途端、輝きを取り戻す。満面の笑顔で施設を出る顔に憂いはない。
娘が生まれたら「殺す」と即答し、息子は?との問いに息子は母の宝だから、と答える少女。それは母への愛憎の裏返しであることはすぐに理解できる。だが、普段は陽気なムードメーカー役を担っているにもかかわらず、そこには絶望が感じられる。強盗の子は強盗にしかならないとあきらめ、肉親に対して何も差し入れをしてくれないことを電話口で泣きながら訴える。
そんな少女がいる一方で、息子が生まれれば「殺す」と即答する少女もいる。娘の名前はすでに付けているというのに。
釈放を申し渡されても、それに対して「お悔やみを」と返す少女。鎖につながれ、虐待される日々に戻るだけという絶望。決して自分に明るい未来があると信じず、そもそも明るい未来のあることを知らない少女。
651と名乗る少女は、クスリを651グラム所持していたからそう名乗っているという。本作に登場する少女たちにとってクスリは日常。それが正しくないとわかっていても、生活のため、肉親から求められれば扱うしかない。そんな切っても切れないのがクスリ。
実の父を母や姉とはかって殺した少女。「ここは痛みだらけだね」という監督に、四方の壁から染み出すほどだと返す。その少女は物静かに見えるが、実はもっとも矛盾と怒りを抱いている存在かもしれない。イスラム教の導師に対し、世の矛盾を一番熱く語っていたのも彼女。
本作には何人ものインタビューと、釈放されるシーンが挟まれる。BGMなどほとんどない本作において、目立つのは乗り込んだ車が発車するシーンで流れる不協和音のBGMだ。彼女たちの釈放後の生活を暗示するかのような。
彼女たちに共通する認識は、罰とは生きる事そのものであり、その罪は生まれてきた事そのものだという。なんという苦しく胸の痛む人生観だろうか。私は少女たちの全てに私の娘たちの生活を重ね合わせ、その間に存在する闇の深さに胸が痛んだ。いったい、私の娘たちと彼女たちの間には何の差があるのだろう。国や民族、宗教、文化が違うだけでこうなってしまうのだろうか?
施設の職員がAidsの知識を授けようとする。塀に囲まれた庭でバレーボールをする。収容者の乳飲み子のお世話をする機会が与えられる。新しいオーディオ機器で音楽も聴くことができる。人形劇を演じる事だってできる。それだけだと平和な日常だ。少女たちは施設の中にあって、平和に生きているようにも見える。だが、本作にあって、一切塀の外の世界は映し出されない。だからこそ、その矛盾と暴力に満ちた世界の無慈悲さがあぶりだされる。施設の人がとある少女を突き放すように、ここを出たら何が何でも外の世界で生きねばならないこと。たとえ自殺しても知ったこっちゃないと言い放つ。少女たちの笑顔や会話は、施設の中だからこそ許されるかりそめのもの。
女性だけが集まる場だと派閥やグループが陰険な争いを繰り広げる。そんな偏見が頭をもたげる。だが、本作の少女たちにそのようなものは見当たらない。泣く相手には胸を貸し、出ていく者にはもう戻ってくるなと励ましの声をかける。少女たちは下らない派閥争いなどにうつつを抜かす暇はないのだ。ここに収容されているのはみな同じく苦しむ仲間。だからこそ支えない、慰め合う。その事実にさらに胸が締め付けられる。
イスラム教の導師が少女たちに道を説こうとし、逆に少女たちからなぜ男と女の命の重みは違うのか、という切実な問いを投げかけられる。男と女の命の重みに差があるかなんて、少なくとも最近の日本では感じることはない。少女たちの真摯な問いに導師は「社会を平穏にしなければ」という言葉でお茶を濁す。
何が少女たちをこうしてしまったのか。イランにもイスラム教にも詳しくない私にはわからない。少女たちは決して犯罪者になるべくして生まれてきたのではない。それが証拠に、収容者の乳飲み子が登場し、その無垢な姿を観客の私たちに見せる。その表情からは、この子が将来強盗や殺人や誘拐や売春や薬物に手を染める予兆は全く見えない。
少女たちもまた、違う時空に生まれていたら輝かしい毎日を送っていたはず。少女たちの多くは顔立ちも整っており、化粧したら女優にだってなれるのでは、という子もいる。ただ、環境が。肉親との暮らしが少女たちをこのような境遇に追い込んでいるのだ。
彼女たちの境遇は、社会に潤沢な金を流通させればいなくなるのだろうか。それとも文化や宗教の違いは、今後も彼女たちのような存在を生み続けるのだろうか。監督はそこは描かない。あるがものをあるがままに。ただ、これがイランの現実だと監督は現実を提示する。7年の準備期間はダテではなく、本作に監督の私情は不要だとわきまえているのだろう。
心を痛めたまま、エンドクレジットが流れる。続いてトークイベントへ。
虐待被害を受けたお子さんがいるご家庭や里親家庭で養育支援をしているバディチームの代表岡田さん、妊娠相談、漂流妊婦の居場所づくりにとりくむピッコラーレ代表中島さんによるトークは、こうした現実を送る少女が日本にもいることを語ってくださった。最近の自販機は暖かくないという、普段の生活では気づかない事実。そうした経験から受ける視点は新鮮だ。わが国にも野宿し、その揚げ句に売春に走る少女はいるとか。
本作を見た後、日本にも同様の生活を送る少女がいることは衝撃だ。生活の確立に失敗し、放浪に走る少女たち。援助交際とは交際じゃない。ただの性的搾取だ、という言葉ももっともだし、売春を取り締まるとは売る側を取り締まる話であり、そうした行為を強いられている少女たちを救うことにならない、という指摘にもうなずける。春を買った側を取り締まる法律がない現状にも目を向けなければ、という指摘も納得がいく。同じ年ごろの娘を持つ私は、娘たちの将来だけを考えればよいのか。否。そうではないはずだ。
本書をただ観劇しただけなら、文化も宗教も違う場所の悲劇、として片付けてしまっていたかもしれない。だが、こうしてトークイベントが催されたことによって、本作への理解がさらに深みを増した。もちろん、映画館で観ることで、本作が伝えるメッセージの鋭さは痛みをもって伝わるはず。
私たちが何をすればよいのか。私は経営者として何をすればよいのか。その答えはまだ出ていない。ただ、トークイベントの中では、ボランティアの道もご紹介いただいた。あらためて自分の時間を見据えてみたいと思う。とても貴重な時間だった。
今回の催しを企画してくださり、当日も動いてくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました。
‘2019/10/17 サイボウズ社本社