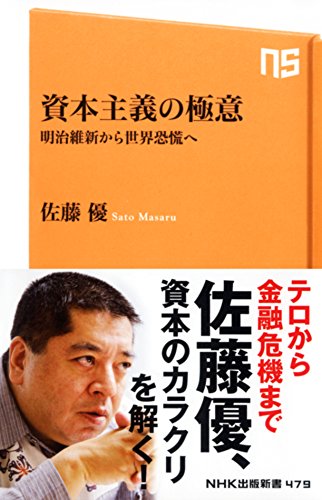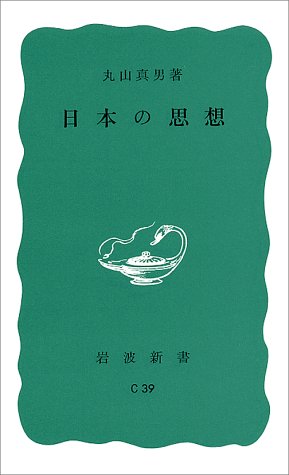
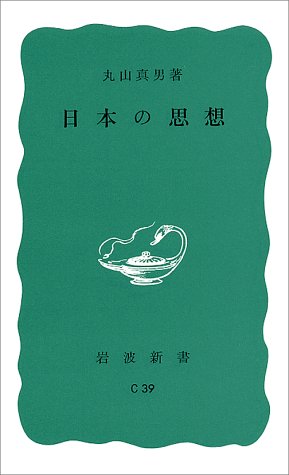
著者の高名は以前から認識していた。いずれは著作を読まねばとも思っていた。戦後知識人の巨星として。日本思想史の泰斗として。
だが、私はここで告白しておかねばならない。戦中に活躍した知識人にたいし、どこか軽んじる気持ちをもっていた事を。なぜかというと、当時の知識人たちが軍部の専横に対して無力であったからだ。もちろん、当時の世相にあって無力であったことを非難するのは、あまりに厳しい見方だというのはわかっている。多分、私自身もあの風潮の中では何も言えなかったはずだ。当時を批判できるのは当時を生きた人々だけ。私は常々そう思っている。だからあの時代に知識人であったことは、巡り合った時代が悪かっただけなのかもしれない。ただ、それは分かっていてもなお、戦中に無力であった人々が発言する論説に対し、素直にうなづけない気分がどうしても残る。
だが、そうも言っていられない。著者をはじめとした知識人が戦後の日本をどう導こうとしたのか。そして彼らの思想が廃虚の日本をどうやって先進国へと導いたのか。そして、その繁栄からの停滞の不安が国を覆う今、わが国はどう進むべきなのか。私はそれを本書で知りたかった。もちろんその理由は国を思う気持ちだけではない。私自身のこれから、弊社自身のこれからを占う参考になればという計算もある。
だが、本書は実に難解だった。特に出だしの「Ⅰ.日本の思想」を読み通すのにとても難儀した。本書を読んだ当時、とても仕事が忙しかったこともあったが、それを考慮してもなお、本書は私を難渋させた。結果、本章を含め、本書を読破するのに三週間近くかかってしまった。そのうち「Ⅰ.日本の思想」に費やしたのは二週間。仕事に気がとられ、本書の論旨を理解するだけの集中力が取れなかったことも事実。だが、著者の筆致にも理由がある。なにしろ一文ごとが長い。そして一文の中に複数の文が句読点でつながっている。また、~的といった抽象的な表現も頻出する。そのため、文章が表す主体や論旨がつかみにくい。要するにとても読みにくいのだ。段落ごとの論旨を理解するため、かなりの集中が求められた。
もう一つ、本章は注釈も挟まっている。それがまた長く難解だ。本文よりも注釈のほうが長いのではと思える箇所も数カ所見られる。注釈によって本文の理解が途切れ、そのことも私の読解の手を焼いた。
ただ、それにもかかわらず本書は名著としての評価を不動にしているようだ。「Ⅰ.日本の思想」は難解だが、勉強になる論考は多い。
神道が絶対的な神をもうけず、八百万の神を設定したこと。それによって日本に規範となる道が示されなかったこと。その結果、諸外国から流入する思想に無防備であったこと。その視点は多少は知っていたため、目新しさは感じない。だが、本章を何度も繰り返し読む中で、理解がより深まった。完全にはらに落ちたと思えるほどに。
また、わが国の国体を巡る一連の論考が試みられているのも興味深い。そもそも国体が意識されたのは、明治政府が大日本帝国憲法の制定に当たり、国とは何かを考えはじめてからのこと。大日本帝国憲法の制定に際しては伊藤博文の尽力が大きい。伊藤博文は、大日本帝国憲法の背骨をどこに求めるかを考える前に、まずわが国の機軸がどこにあるかを考えねばならなかった。いみじくも、伊藤博文が憲法制定の根本精神について披瀝した所信が残されている。それは本書にも抜粋(33p)されている。その中で伊藤博文は、仏教も神道も我が国の機軸にするには足りないと認めた上で「我国二在テ機軸トスヘキハ、独リ皇室アルノミ」という。ところが、そこで定まった国体は明らかに防御の体質を持っていた。国体を侵そうとする対象には滅法強い。だが、国体を積極的に定義しようと試みても、茫洋として捉えられない。本書の中でも指摘されている通り、太平洋戦争も土壇場の御前会議の場においてさえ、国体が何を指すのかについて誰一人として明確に答えを出せない。その膠着状態を打破するため、鈴木貫太郎首相が昭和天皇の御聖断を仰ぐくだりは誰もが知っているとおりだ。
そして、著者の究明は日本が官僚化する原因にまで及ぶ。権力の所在は極めて明確に記された大日本帝国憲法。でありながら責任の所在が甚だ曖昧だったこと。大日本帝国憲法に内在したそのような性質は、一方で日本を官僚化に進めてゆき、他方ではイエ的な土着的価値観を温存させたと著者はいう。それによって日本の近代史は二極化に向かった。著者はその二極を相克することこそが近代日本文学のテーマだった事を喝破する。著者は59pの括弧書きで森鴎外はべつにして、と書いている。著者の指摘から、森鴎外の『舞姫』が西洋の考えを取り入れた画期的な作品だったことにあらためて気づかされる。
また、著者はマルクス主義が日本の思想史に与えた影響を重く見ている。マルクス主義によって初めて日本の思想史に理論や体系が生まれたこと。ところが、一部の人がマルクス主義を浅く理解したこと。そして理論と現実を安易に調和させようとしたこと。それらが左翼運動に関する諸事件となって表れたことを著者は指摘する。
結局のところ著者が言いたいのは、まだ真の意味で日本の思想は確立していないことに尽きると思う。そして、著者は本書の第三部で日本の思想がタコつぼ型になっており、真の意味でお互いが交流し合っていない事情を憂う。雑種型の思想でありながら、相互が真に交わっていない。そんなわが国の思想はこれからどうあるべきか。著者は日本の文学者にそのかじ取りを託しているかに読み取れる。
「Ⅱ.近代文学の思想と文学」で著者は、日本の思想が文学に与えた影響を論じている。上にも書いたが、著者にとって森鴎外とは評価に値する文学者のようだ。「むしろ天皇制の虚構をあれほど鋭く鮮やかに表現した点で、鴎外は「特殊」な知識人のなかでも特殊であった」(80P)。ということは、著者にとって明治から大正にかけての文壇とは、自然主義や私小説のような、政治と乖離した独自の世界の話にすぎなかったということだろうか。
著者は、マルクス主義が文壇にも嵐を巻き起こしたことも忘れずに書く。マルクス主義が日本の思想に理論と体系をもたらしたことで、文学も無縁ではいられなくなった。今までは文学と政治は別の世界の出来事として安んじていられた。ところがマルクス主義という体系が両者を包括してしまったため、文学者は意識を見直さざるをえなくなった。というのが私の解釈した著者の論だ。
「Ⅱ.近代文学の思想と文学」は解説によると昭和34年に発表されたらしい。つまりマルクス主義を吸収したプロレタリア文学が挫折や転向を余儀なくされ、さらに戦時体制に組み込まれる一連のいきさつを振り返るには十分な時間があった。著者はその悲劇においてプロレタリア文学が何を生み、何を目指そうとしたのかを克明に描こうと苦心する。著者はマルクス主義にはかなり同情的だ。だが、その思想をうまく御しきれなかった当時の文壇には厳しい。ただし、その中で小林秀雄氏に対してはある種畏敬の念がみられるのが面白い。
もう一つ言えば、本書はいわゆる”第三の新人”については全く触れられていない。それは気になる。昭和34年といえばまさに”第三の新人”たちが盛んに作品を発表していた時期のはず。文学に何ができるのかを読み解くのに、当時の潮流を読むのが一番ふさわしい。ところが本書には当時の文学の最新が登場しない。これは著者の関心の偏りなのか、それとも第三の新人とはいえ、しょせんは新人、深く顧みられなかったのだろうか。いま、平成から令和をまたごうとする私たちにとって、”第三の新人”の発表した作品群はすでに古典となりつつある。泉下の著者の目にその後の日本の文学はどう映っているのだろうか。ぜひ聞いてみたいものだ。
「Ⅲ.思想のあり方について」については、上にも軽く触れた。西洋の思想は一つの根っ子から分かれたササラ型なので、ある共通項がみられる。それに対し、日本の思想はタコつぼ型であり、相互に何の関連性もない、というのが著者の思想だ。
本章は講演を書き起こししており、前の二部に比べると格段に読みやすい。それもあってか、日本の思想には相互に共通の言語がなく、それぞれに独自の言語から獲得した思想の影響のもと、相互に閉じこもってしまっているという論旨がすんなりと理解できる。本章から学べる事は多い。例えば私にしてみれば、情報処理業界の用語を乱発してはいないか、という反省に生かせる。
業界ごとの共通言語のなさ。その罠から抜け出すのは容易ではない。私は30代になってから、寺社仏閣の中に日本を貫く共通言語を見つけ出そうとしている。が、なかなか難しい。特に情報処理の分野では、ロジックが幅を利かせる情報処理に共通言語が根付いていない。そんな貧弱な言語体系でお客様へ提案する場合、お客様のお作法に追随するしかない。ところが、その作業も往々にしてうまくいかない。このタコつぼの考え方を反面教師とし、システム導入のノウハウにいかせないものだろうか。
「Ⅳ.「である」ことと「する」こと」も講演の書き起こしだ。これは日本に見られる集団の形式の違いを論じている。「である」とはすでにその地位に安住するものだ。既得権益とでもいおうか。血脈や人種や身分に縛られた組織と本書でいっている。一方で「する」とはそういう先天的な属性よりも、人の役割に応じた組織をいう。つまり会社組織は「する」組織に近い。我が国の場合、「である」から「する」への組織が進んでいるようには見えるが、社会の考え方が「である」を引きずっているところに問題がある。それを著者は「「である」価値と「する」価値の倒錯」(198)と表現している。著者は第四部をこのような言葉で締めくくる。「現代日本の知的世界に切実に不足し、もっとも要求されるのは、ラディカル(根底的)な精神的貴族主義がラディカルな民主主義と内面的に結びつくことではないかと」(198-199P)
著者はまえがきで日本には全ての分野をつないだ思想史がなく、本書がそれを担えれば、と願う。一方、あとがきでは本書の成立事情を釈明しながら、本書の視点の偏りを弁解する。私は不勉強なので、同様の書を知らない。今の日本をこうした視点で描いた本はあるのだろうか。おそらくはあるのだろう。そこから学ぶべき点は多いはずだ。そしてその元祖として本書はますます不朽の立場を保ち続けるに違いない。
‘2018/06/03-2018/06/21