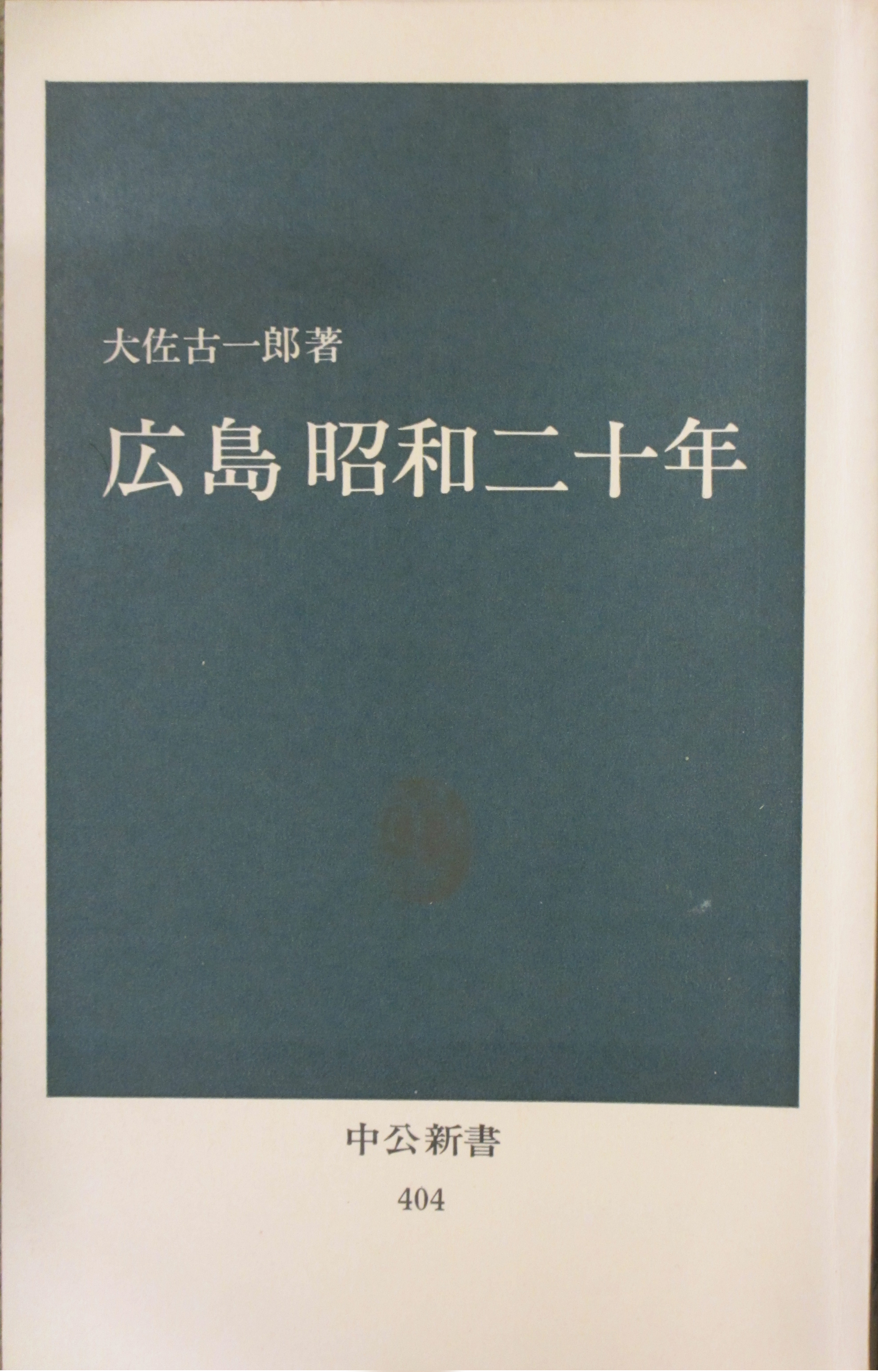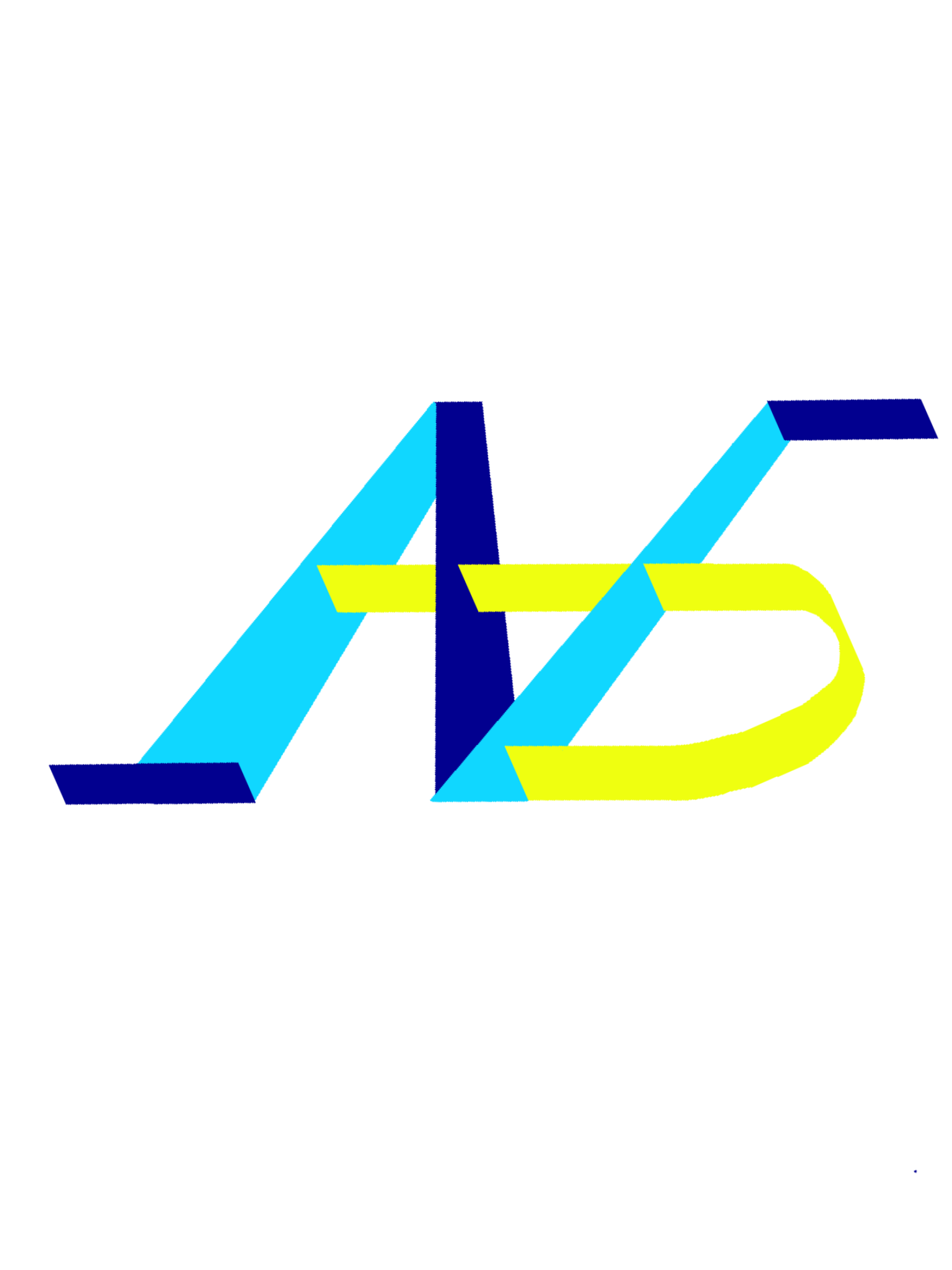本書は、お客様にお勧めとして貸していただいた一冊だ。
本書はいわゆるノート術を扱っている。いろいろなノート術は世の中に出回っている。だが、そうしたやり方とは一線を画している、と著者は主張する。
それは、著者がダイエットに成功した実績があるからだ。その時に使った実際のノウハウをノートとして置き換えたものが本書に惜しみなく書かれている。
タイトルにある天才、とは受け狙いのネーミングにも見えるが、そうではない。
著者は天才を、発想力、表現力、論理力の三つを兼ね備えた人物だと定義する。この三要素を持ち合わせた人となると、人類の中でも一握りだ、とも。
著者はその人物を例に挙げ、スティーブ・ジョブズ、北野武、レオナルド・ダヴィンチだとする。あいまいな天才という概念で終わらせず、三つの能力を持ち出したのが本書の良い点だ。私たちに目指すべき目標をまず明確に提示しているからだ。
著者は本書において、手書きのノートの効用を強調する。そして、自らのノートの実例を何例もそのまま掲載する。
私が普段実践している方法は、著者が本書で推奨する方法のいくつかに近い。だが、取り入れていないことはまだまだあると思っている。
私が既にやっていることは、日々の反省を必ずSNSにアップすることだ。これは七年ほど毎日、欠かさず行っている習慣だ。
だが、私がSNSに書く内容は著者の勧める内容とは少しだけ違う。書く内容が雑多だからだ。日記に近い。
著者はより踏み込んだ記述を勧めている。その記述とは、良かったことと悪かったことを明確にリストアップし、記す。そしてその内容は積極的に忘れる。著者が打ち出す姿勢はその二つだ。
この姿勢は、著者の意見に全く同意だ。私がSNSにアップする理由の一つは、忘れるためだからだ。
一方でメモを取る人間と取らない人間の差についても著者は触れている。それは人間の記憶容量と加齢による衰えだ。脳内で処理する人は、それができるうちはメモが不要だが、やがてその能力に衰えが兆した時、メモを取っていたものが優位になる。
著者も元来はノートが不要と考える論者だったが、今はノートの効用を確信しているという。
著者は続いて、日々の良かった点と悪かった点に六段階で評価することも勧めている。点をつけることによって、自分を客観視することができる。自分の中で区切りをつけられる効果も見越しているのだろう。これもまた、忘れるための一つの通過点だ。
著者は忘れることの効果を説く。ところが、積極的に忘れているつもりでも、無意識では自分の中に日々の言動が確実に蓄積されてゆく。それが著者のいう効果だ。
私の場合、SNSにアップした記事の数々によって、パブリックイメージも間違いなく蓄積されていると思う。
著者の勧めるメソッドで最も目をみはらされたのが、余白の効用だ。
著者は一日の記述を見開き左右ページで使うことを強く推奨する。
右にその日の出来事を書いたら、左ページは雑感、所感、なんでも好きなことを書くために空けておく。書かなくてもいい。数日間空白でもいい。ただし、左は何でも書けるように確保しておく。
これが本書で著者が勧めるメソッドの肝だ。
それはあえて心に余白を意識させることだと思う。余白とは余裕であり、遊びだ。
それを左ページの余白として日々意識することで、心はそれを埋めよう、活かそうと作用する。
私がSNSに書き込むのとはそこが違う。
SNSは書き込んだ後、余白はトリミングされて表示される。
いくら自由に編集もでき、ツイッターのように字数制限がないとしても、入力欄には余白がない。
つまり、SNSは余白を意識しにくいツールなのだ。
だが、著者の勧めるスマートノートは常に左一面を余白として用意する。その余白を意識させることで、今の自分の可能性を意識させ、器を広げる。
なるほど。
ただし、余白を意識するにはノートと筆記具が必要だ。スマホやパソコンではそれが難しい。
私にとってそれが大きなハードルだ。
今までも手帳を持ち歩く習慣を身につけようと頑張ってみたが、予定を管理する機能においてスマホやパソコンにかなわない。また、予定を簡単に共有できる利点も捨てがたい。そもそも、毎回カバンから出すのが面倒だからだ。
デジタルな私は本書を読んだあと、著者のスマートノートのメソッドがアプリとして存在しているのではないかと探してみた。ところが見つけられなかった。
自分で作ろうかと思ったぐらいだ。
ここで大切なのは、著者がデジタルを否定していないことだ。著者はアナログを礼賛し、デジタルを否定してはいない。
ただ、現状ではまだデジタルは紙の利便性に到達していないといっている。本書は2011年に出版された。だが、それから10年近くがたった今でも、デジタルは余白を意識させる設計にはなっていない。背後には広大なハードディスクの空き容量があるにもかかわらず。
デジタルの余白の問題は、デバイスの画面サイズという問題としてもついて回る。
著者はデジタルを頭から否定するわけではなく、デジタルが著者の構想を再現できるようになればデジタルを厭わないと書いている。
私もせっかく貸していただいたので、これを機会にノートへの記述を始めてみようと思う。
本書をお客様に返す日が、年の後半の開始という切りの良さもあるし。
何より、私が自分の弱点であるビジネスの発想力を養ってくれるかもしれないからだ。
衰えていく一方の脳に刺激を与える意味でも。
最後に著者はオタキングexというFREE ex組織についても紹介している。
これは面白い。著者は自らがもらうべき印税その他の報酬を0円にしているという。その代わり、オタキングexの社員から一人あたり12万円を受け取っているという。
社員は著者の印税で収入を得て、それと同時に著者に給料を払う。
それによって著者は定期収入を確保するというしくみだ。
いわゆるサブスクリプションの考えを会社の運営に当てはめた試みだ。
これは面白い。
私も今後の生き方について大いに参考になった。
もっとも私の場合、著者の持つ知名度の足元にも及ばないが。
そのためにもスマートノートを試し、飛躍したいと思う。
上の文章は、お借りした当時に記した文章だ。だが、実は私の中にスマートノートの習慣は根付いていない。
ノートを取り出すのがどうしても億劫だったのだ。
Evernoteをより頻繁に利用するようにした。
そして、これからの展望を書くようにもした。
確実に本書を読んだ成果はどこかで身についているようだ。
著者と貸してくださったお客様には感謝だ。
‘2020/06/01-2020/06/02