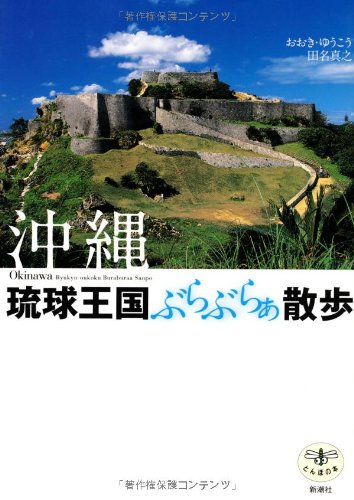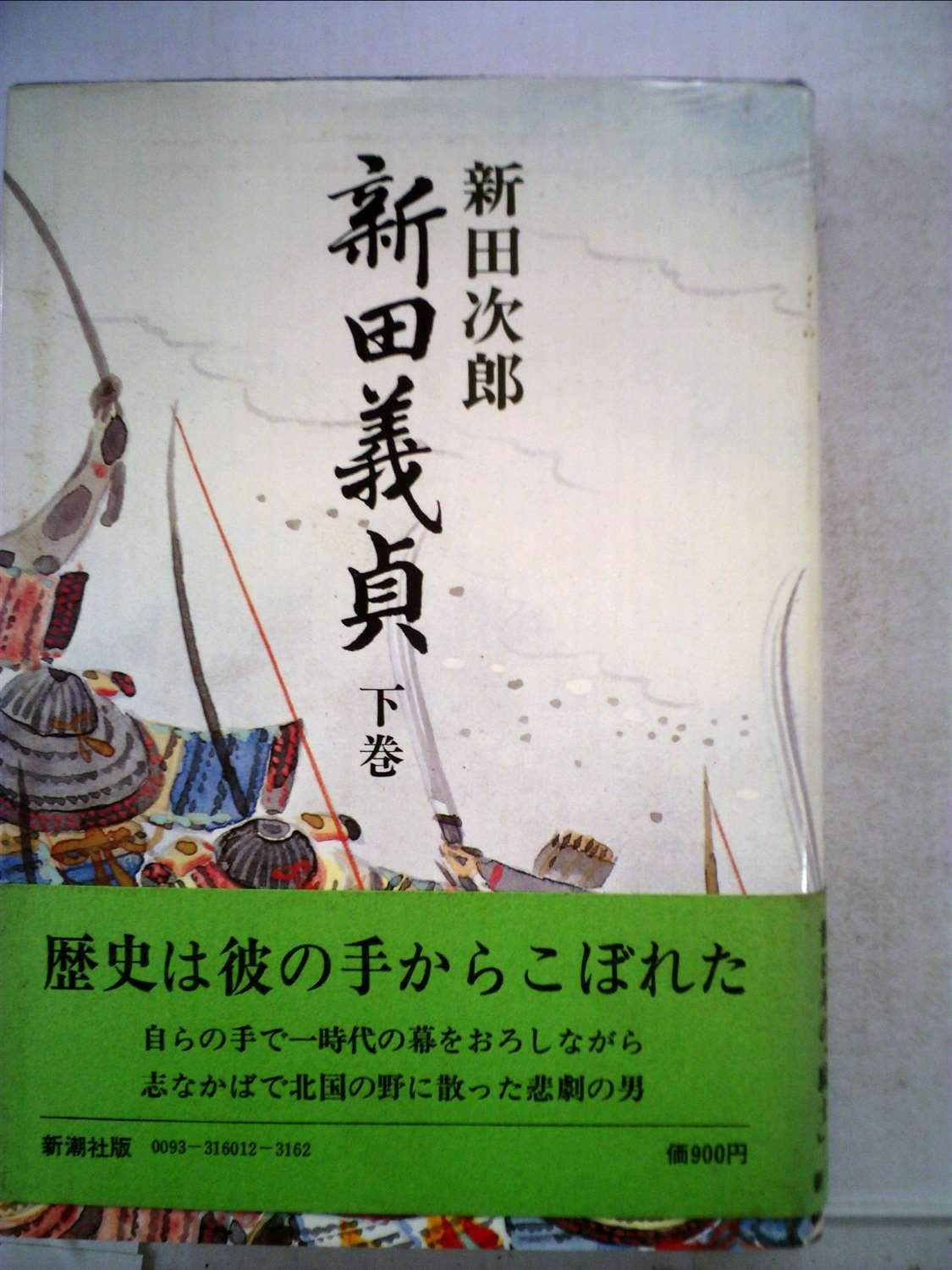
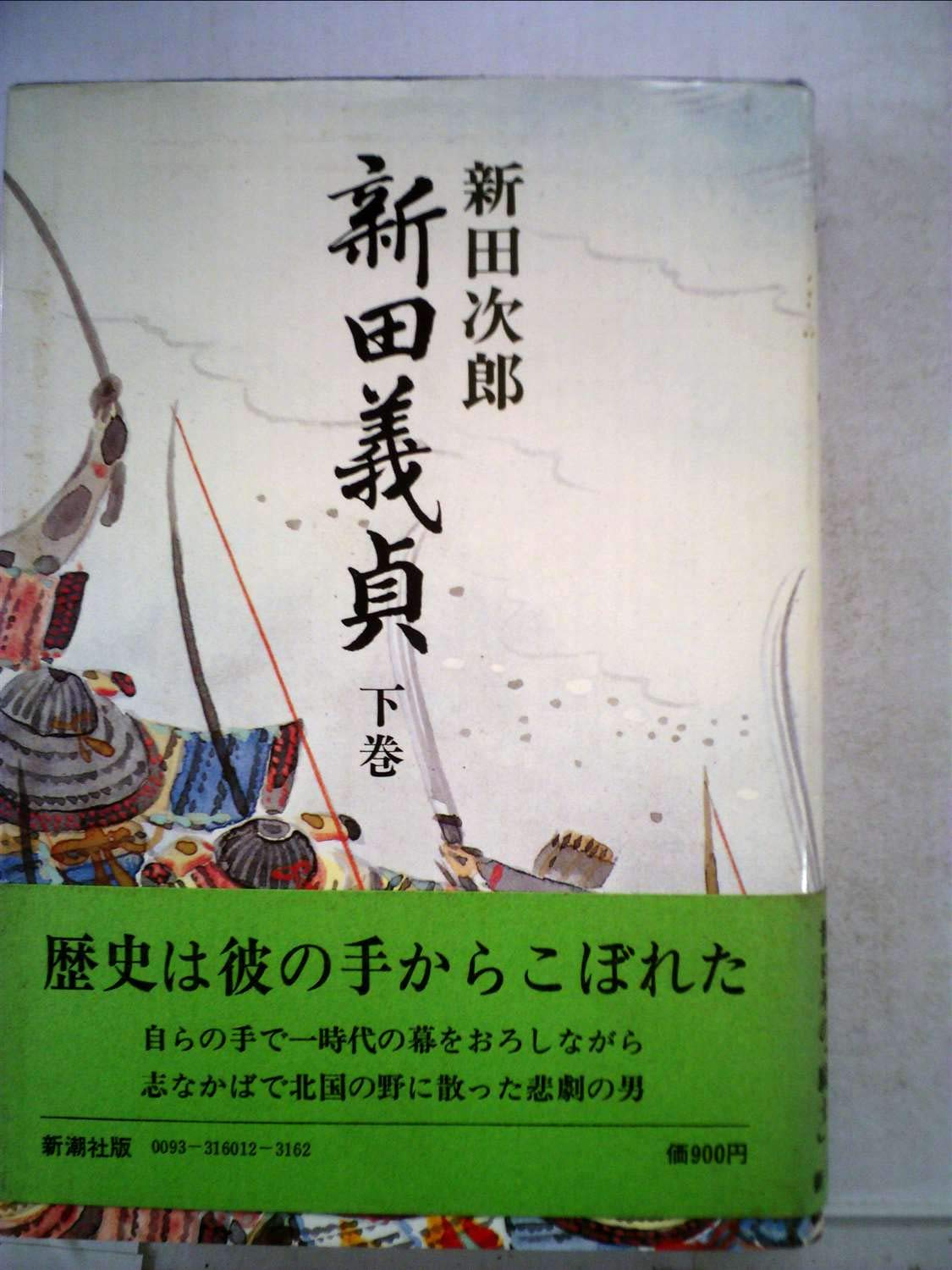
上巻は、日野俊基が鎌倉幕府によって処刑される場面で幕を閉じる。
数度の失敗にもくじけず沸き上がる後醍醐天皇による倒幕の動き。それに対抗する幕府の対応。
新田義貞公はその合間に立ち、どちらとも決めかね、事態を静観していた。
そんな義貞公に近づいてきたのが、朝廷からの密使である刀屋三郎四郎。三郎四郎は武器商人としての利益を確保するため双方を焚き付けようと暗躍していた。
双方の思惑が風雲を巻き起こす中、義貞公は朝廷に睨みを利かせるための京都大番役に抜擢される。そして、幕府の役人として京に赴く。
それが義貞公にとっての波乱の人生の幕開けであった。
幕府の朝廷への圧力は強さを増し、ついには後醍醐天皇を隠岐の島へ流すまでに至る。
ところが、その時期に足利尊氏が幕府に反旗を翻す。そして、足利直義や高師直らによる陰謀で、足利家の下に属するような指令を義貞公にだす。
それによって穏やかならぬ義貞公。源氏を率いるべきは新田氏と足利氏のどちらなのか。足利尊氏に属することはすなわち源氏の棟梁が足利氏であることを認めることに等しい。
義貞公は足利尊氏が鎌倉を落とす前に、自分が先に鎌倉を落とさねば、と決意する。そしてついに上野の新田庄を出立する。
上巻では、お互いが鎌倉幕府の有力御家人だった頃からの足利尊氏と義貞公の関係を描いている。義貞公に対してひたすら丁重に接する足利尊氏。刺激を与えまいと配慮する中で、お互いの力を測る用心深さものぞかせている。
北条家の本拠に近く、朝廷の働きかけも盛んでないこの時期、源氏の主流を争うことは得策ではない。それよりまず、北条氏との関係をどうするか。
朝廷からの密書が届くようになってからも、下手に動いては墓穴を掘る。誰に忠君を励むのかはっきりさせるのは利口とはいえない時期だった。
その時期、足利尊氏も義貞公もお互いが敵になるとは毛頭も考えていなかったことは、本書でも何度か強調されている。
両雄が雌雄を決するにはまだ長い日数がある。
義貞公が立ち上がってからの本書は、私にとってなじみのある場面や戦いが続く。私の家の近くも登場する。
小手指ヶ原の戦いから、分倍河原の合戦へと戦場は移る。さらに関戸の戦場へと。
それらの戦いの中では、私の家の近くでも激しい戦闘も行われた事だろう。だが、本書はそうした些事には触れない。
それよりも、どうやって新田軍が足利軍を打ち破ったのか。分倍河原の戦いの全容に興味が向く。個々の先頭よりも高い視野から活写される戦いの数々。義貞公が最も冴えていたのもこの時期だったはず。
敵と味方が頻繁に入れ替わり、戦場も日本全土に及んだ太平記の時代。
鎌倉から南北朝への目まぐるしい時代を描くには、本書のボリュームでは足りない。
義貞公だけをとり上げても語るべきことはまだあるように思える。
例えば鎌倉包囲戦や、稲村ヶ崎の海を干潮時に渡って鎌倉への攻め口を開く戦いなど、北条家と新田家の戦いだけでも語るべき挿話はまだまだあるだろう。
もちろん、太刀を海に投げ入れて稲村ケ崎からの突破を祈願したことや、そもそも稲村ヶ崎を渡るために苦戦したことなどは描かれている。
だが、鎌倉への攻めこそが義貞公の人生を描くうえで最大の見せ場である以上、もう少し紙数を割いても良かった気がする。
とはいえ、義貞公が稲村ケ崎を抜いたことで、鎌倉を落とし、歴史に名を轟かせたことにかわりはない。
ところがそれ以降の義貞公の動きはあまりさえない。
後醍醐天皇に気に入られ、京の守りを申し付けられた義貞公。ところがその隙に、足利直義が鎌倉に入り、実権を握ってしまう。
そんな中、足利尊氏は建武の新政の現状に見切りをつけ、ついに天皇に反旗を翻す。
ここに至っても義貞公の動きは曖昧で、どちらに付くか旗幟を鮮明にしないまま。そのため、ついに足利尊氏との対立が避けられない情勢まで陥ってしまう。
現代に至るまで、新田義貞公の評価は芳しくない。
足利尊氏が戦後になって復権し、楠木正成は今も皇居に像が立てられているほど、尊王の士としての名声をほしいままにしている。ところが義貞公はそうした評価とは無縁だ。
なぜか。
それは時代の流れにうまく立ち回われず、時代を超えた構想を描けなかったからではないか。
例えば足利尊氏を京都から追い出す戦い。
そこでも著者は軍功があったのは楠木正成の方だとしている。
そして足利尊氏は勢力を立て直すため、九州まで兵を引き再び勢力を盛り返そうとする。
尊氏と同じように鎌倉に帰って勢力を立て直したいとする義貞公の意見は、公家によってことごとく握りつぶされる。義貞公を鎌倉に帰らせてしまうと、関東に覇をとなえ、朝廷に反旗を翻すのではないかと疑われてしまう。
北条家の後継としての野心があるのでは、と公家に曲解された義貞公。
それが足利尊氏への戦いに半端な対応を示した理由だろう。
義貞公は、本書を通じて公家に振り回されている。毅然たる態度をとらず、自分の意見を押し通さなかったこと。確固たる態度をとらず、相手の立場を忖度してしまったこと。
だからこそ、新田義貞公は時代の流れに乗れなかったのであろう。
本書で著者は、なるべく新田義貞公の立場に立って書こうとしている。だが、本書を読んでいると、義貞公は負けるべくして負けた人物に思えてくる。おそらく天下を取る器ではなかったのだろうと思うほかない。
九州から大群を率いて上京してきた足利尊氏を打ち破るにも、公家の横車が頻繁に入り、命令系統に支障をきたしてしまう。
その結果、赤松軍に大回りされて包囲された楠木正成は全滅し、義貞公は京都に逃げ帰る。逃げ帰った後で、後醍醐天皇の次に天皇となった光厳天皇を奉じ、越前で再起をかけようとする。
南北朝時代や義貞公に対する知識が疎い私は、なぜ義貞公が越前で再起を図ろうとしたのかよくわかっていなかった。
本書を通し、新田一族は上野だけでなく、越後にも地盤を広げていたことが描かれる。つまり越前の背後は新田一族の所領であった。だからこそ新田義貞公は越前を再挙の地として選んだのだろう。
ところが、燈明寺畷において義貞公は戦死を遂げてしまう。
その最後は、日本史上に名を残した武将にしてはあまりにも残念なものだった。
油断した義貞公は、少年時代の心に帰り、馬で遠掛けしようとした。
その情報が敵に筒抜けとなり、敵軍の待ち伏せに会い、死に至る。
義貞公の死によって、新田幕府が打ち立てられることはついになくなった。新田庄に残した愛妾や妻子に会うこともついに叶わなかった。
結果だけ見れば、義貞公の一生はついに負けておわった。それだけでしかない。
だが、義貞公をそれだけで片付けてよいのだろうか。
そもそも、歴史の上で勝ち続けた人はいない。勝ち続けた人物とはもちろん最終的な勝者として歴史に名を残す。歴史に名を残すことができた最終的な勝者とは、以下のような人物たちがそうだろう。
中大兄皇子、大海人皇子、藤原道長、後白河院、源頼朝、足利尊氏、豊臣秀吉、徳川家康。
だが、彼らの生涯には起伏があった。ここに挙げていない織田信長や平清盛も一時は天下を確かにつかんだ。
徳川家康もようやく晩年にチャンスをつかんだのであって、それまでは苦しい負けを乗り越えた人生だった。
歴史上を生きた数多くの人物は、勝って負けてを繰り返した。それが実情だろう。
ところが、最後に勝利したことで歴史に名を残した。そのほかの歴史を生きた無数の人々は、名を残すことすらなく死んでいった。
それを考えると、歴史に名を残すとは最後に敗れたとはいえ、とても評価されるべき業績とはいえないだろうか。
そして、義貞公の残した業績は、評価が芳しくないにも関わらず、歴史に名を残さずに死んでいったほとんどの人物よりも際立っている。
それを踏まえると、私たちが義貞公の生き方から学ぶべきことは大いにあると思う。
それだけの実績を残した義貞公だからこそ、人生から教訓とすべきこともわかりやすいように思える。
例えば、将たる者として対外的に毅然とした態度を貫くこと。その判断に権威への盲従を含めてはならないこと。刀屋三郎四郎がもたらす情報だけではなく、より自主的な情報を取りに行くべきこと。
そうしたことは、今のせわしない世の中を生きるためにも活かせる教訓だ。
将ともなれば出る杭として打たれ、率いる身としての重圧は大きい。
だからこそ、全てを丸くおさめ、調整しようとした義貞公の試みが破綻したのだろう。
どこかで調整者としての立場を打ち捨て、自分の意志を強く打ち出さねば。新田庄を出立した時のように。
私も小さいながらも組織の上に立つ身だ。本書から学んだ義貞公の生涯から、自らの判断や身の処し方について活かせることは多かった。
だからこそ、義貞公を私たちが参考にできる人物として評価したいと思う。
偉大な勝者ではなく、私たちが参考とすべき歴史上の偉人として。
今度、小手指が原の合戦地、上野の新田庄、そして最期の地となった灯明寺畷にも訪れたいと思っている。
‘2019/7/6-2019/7/10