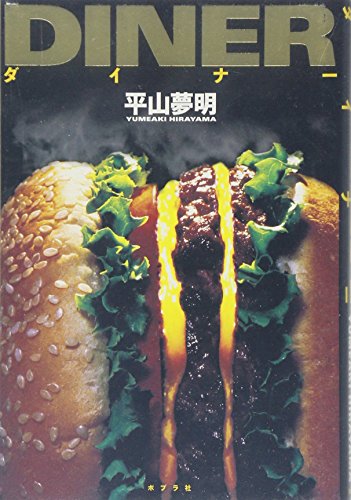7/26に「kintone Café Metaverse Vol.4」に参加しました。
告知サイト
こちら、私も四回とも参加しています。
そのうちの二回はメタバース上で登壇も果たしています。皆勤です。
そんな私だから、日常でもVRゴーグルが欠かさず、しょっちゅうメタバース世界にのめり込んでいる?そう思われた方。答えは否、です。
日常で私はまったくVRゴーグルを使っていません。なんなら、私がVRゴーグルを掛けるのは、三カ月おきの「kintone Café Metaverse」だけかもしれません。
私がVRゴーグルを使わず、メタバースも利用しない理由は列挙できます。が、私の場合、デバイスの問題が大きいでしょう。メガネをかけ、コンタクトレンズをしない私は、裸眼でも使用可能な度付きのアタッチメントレンズを購入したのですが、それがいまいちしっくり来てません。頭のバンドが緩むため、しょっちゅう視界がぼやけるのです。
あと、もう一つの深刻な問題はキーボードと連携できないことです。
これは、若干の説明が必要でしょう。
私にとって、メタバースの可能性とは、自分の仕事環境を決定的に拡張してくれることです。目の前の広大な空間に無数のディスプレイを並べ、マルチタスクを文字通り実現する。これは現実世界ではまず無理です。
ところが、パソコンのモニターはいくらでも連動が可能だと思うのですが、肝心のキーボードが私のノートパソコンと連動しないため、仕事ができません。
となると、残るのはエンタメ系かコミュニティ系しかないのですが、これがまだ成熟に至っておらず、お粗末なのです。
今ここにあげた理由。おそらく私だけでなくメタバース経験者のうちかなりの方が感じていることだと思います。
だからこそ、あれほどもてはやされたメタバースがオワコンとして扱われているのです。
この辺りは以下の記事の中でも書いています。「kintone Café Metaverse Vol.1」と「kintone Café Metaverse Vol.3」の記事です。
私は上のVol.3の記事の中で書きました。
「新しい会社が発表する革新的な次世代のデバイス。
あと数年もすれば出てくると思うのです。いや、すでに出ています。
簡単にメガネのように装着するだけで、VRの世界が体験できるデバイスが。そのデバイスの値段をさらに下げ、人々が手に取りやすくする。」
と。
前回の「kintone Café Metaverse」のあと、革新的と称されるデバイスが発売されました。AppleのVision Proです。
製品サイト
私はまだ実際にそれを経験したことはなく、見たことすらありません。ただし、価格があまりにも高く、Oculus Quest、あらためMeta Questの見た目とあまり変わらないことから、重さや首の疲れ、そして近眼の方にとって同じ課題があるのではないかと考えました。また、キーボードの問題もあります。
ただ、こうしてApple社も出してきたということは、まだメタバース、つまり仮想空間の可能性はついえたわけではないのです。ただ、デバイスとコンテンツの問題だけです。
各社とも、革新的なデバイスが出たら、コンテンツを整備し、ユーザーを囲い込む。その機会を虎視眈々と狙っているように思います。
私が「kintone Café Metaverse」に関わり続けるのもその可能性を感じているためです。
インプットとアウトプットの可能性が根本的に変わるはず。その可能性がある限り、またメタバースをオワコンとするのは早いように思うのです。
今回の「kintone Café Metaverse」は、soracomugとの共催です。
soracomugの皆さんとは、昨年9月に鎌倉でkintone Café 神奈川 Vol.13を共催して以来です。IoTの雄として、kintoneとは親和性が高く、弊社も昨年秋のCybozu Daysのブースにおいて、kintoneと soracomと組み合わせでさまざまな展示を出しました。
今回はIoTとkintoneの組み合わせだけでなく、そこに仮想のメタバースが絡みます。私としても興味深い内容です。
今回の司会はなっちゃんこと、藤田なつみさん。soracomugではおなじみですし、最近はkintone界隈でも名を知られています。
そのなっちゃんから、kintone Caféやsoracomugのご紹介から。
続いては、藤村さんによる「IoTxkintone意外と相性が良い」です。
まずは、kinotneとsoracomの相性の良さをご紹介いただきました。
実際、昨年6月の高知から始まったkintone Caféとsoracomugのご縁は、鎌倉や福岡や広島、そしてこの夏に岡山でも開催を控えているそう。
私も引き続きsoracomさんとは関わりたいですし、そうなるでしょう。

続いては、古里さんによる「kintoneでIoTデータを収集してみた」です。
古里さんとはまだオフライン/オンラインも含めてお会いできていなかったように思います。とても活発に各種のコミュニティで活動しておられる様子。
めんツナかんかんエバンジェリストを名乗っておられるのもユニークだし、その個数をIoTと組み合わせておられるのも素晴らしい。
また、連携にあたってYoomを使っておられるところもポイントが高いです。また、Sens’itというデバイスも初めて教わったので、今度、試してみたいと思います。
8月末の「kintone Café 岡山」とsoracomugのコラボイベントにお誘いされたので、検討してみたいと思います。

続いてはなかじさんによる「ヒトとセカイをツナグもの」です。
視聴覚などの感覚とIoTやkintoneのデータを絡めた視点はとても興味深いです。
私の弱点は、感覚をシステム構築に持ち込まないことです。特に視覚効果はあまり重視していません。つまり見た目です。
ですが、メタバースを扱う際は、単なるデータだけで取り組むとその良さが生かせません。なかじさんの発表を聞いていて、私の弱点をあらためて感じました。

続いてはMaxによる「3D空間内にIoTデータをマッピングする方法」です。
ソラコム社は社内でニックネームで呼び合う文化があり、松下さんはMaxと名乗っておられます。以前、Maxさんはやめてほしいと言われたので、Maxと呼びますね。
さて、Maxの発表によるこれらの知見は私にはありません。3D空間のパースもモデリングも私にとっては未知の領域です。デジタルツインも最近よく聞くワードですが、私がそれを案件で実装したことはありません。
以前、リアルタイム3D制作ツールであるUnreal Engineもインストールしてみたことがありますが、私がマスターするには時間がなさすぎてモノになっていません。
ただ、IoTのデータを活かすには二次元ではだめです。最低でも奥行きを含めた三次元で確認できることが必要です。さらには時間も含めて四次元であればなおよいです。
kintoneは行列二次元による管理なので、IoTのデータを視覚的に確認するには限界があります。そこで、今回Maxが紹介してくれたAWS IoT TwinMakerやAzure Digital Twins、さらにはBabylon.jsやThree.jsのようなツールを習得しておくと、3Dバース上でIoTのデータを確認したいニーズも満たせるのです。
素晴らしい!
 皆さんの発表の後は、ふりかえりセッションが挟まれていました。メタバースの良さである臨場感を感じながらの振り返りは、kintone Café メタバースの最大の魅力です。
皆さんの発表の後は、ふりかえりセッションが挟まれていました。メタバースの良さである臨場感を感じながらの振り返りは、kintone Café メタバースの最大の魅力です。
Zoomで入ってくださったkintoneコミュニティ界では著名なはっしーさんや大野さんも。
コロナが落ち着いたことによって、リアルのkintone Caféは増えました。おそらくオンラインセミナ―は減っていくことでしょう。オンラインセミナーはどうしても没入度に劣りますし、そもそもその場で次の交流につながっていきません。
本稿の冒頭で触れたようなデバイスの問題が解消し、安価でかつメタバースに参加しやすい形になれば、遠方の方もオンラインで参加するしきいがぐっと減るはず。
今後もデバイスの進化には引き続き期待しつつ、私もkintoneの拡張できる余地について学びたいと思います。
今回登壇された皆様、ご参加してくださった皆様、ありがとうございました。