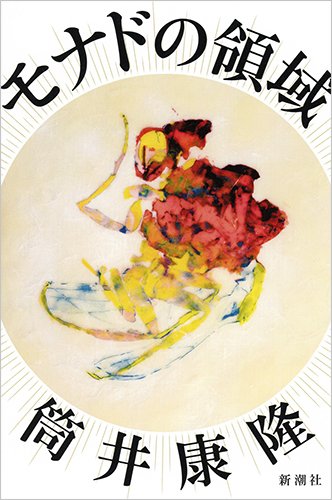ハードSFは読んでいる間は楽しく読めるのだが、読み終えるとなぜか中身を忘れてしまうことが多い。本書も同じだった。
設定や頻出する英文字略語、登場人物などは真っ先に忘れる。それらが失われると、筋の運びすらバラバラに解けていく。
本書については、あらすじすらもあやふやになっていた。
そのため、本稿を書くに当たって改めてざっと読み直してみた。
本書のあらすじはこんな感じだ。
突如として水星の地中から高く噴き出した柱。それを発見したのは高校の天文部の部長である白石亜紀。その柱は水星を構成する鉱物資源であり、それは太陽の引力に引かれ、直径8000万キロのリングとなって太陽を取り巻いた。
それによって地球に届くべき太陽エネルギーは激減し、地球は寒冷の星と化した。収穫は減り、それによって多くの産業が衰えていた。大量の人が死んでいき、既存の経済に頼ったあらゆる体制は崩壊していく。
リングがなぜできたのか、リングをどうすればなくせるのか。
長じて科学者となった亜紀は、長きにわたってリングの謎に関わっていく。
本書は異星人とのファースト・コンタクトを描いている。
リングの正体については、本書の中盤あたりで描かれる。だから本稿がネタバレを含んでいても許してほしい。
このリングは、正体の不明な異星人がどこかの星系から次の星系へ船団ごと移動するための手段だ。
リングの構築にあたって、地球と人類に甚大な損害を与えた異星人。異星人を糾弾し、彼らを撃退する迎撃体制が組まれる。そうした風潮に対し、白石亜紀はその異星人が地球に知的生物がいると知らずにリングを設定したのではないかと仮定する。そして、異星人を迎撃しないよう必死に訴える。異星人とのファースト・コンタクトに臨んだクルーは、そこで何を見るのか。
著者は、本書を書くにあたって、異星人とのファースト・コンタクトにおける可能性を熟慮したのだろう。本書を読めばそのことが感じられる。
実際、私たちがファースト・コンタクトを経験する日は来るのだろうか。
私はこの広大な宇宙のどこかに人間と同じような知的生物は存在すると思っている。その存在と遭遇するのはいつか、またはどういう形で遭遇するのか。私にはわからない。そもそも、その存在に確たる証拠がない以上、私がそう思っていることは、もはや信仰に近いのかもしれない。
人類と異星人が遭遇するケースはさまざまに考えられる。例えば、SETI(地球外知的生命体探査)が検出した信号をもとに何かしらの交信が始まることもあるだろう。パイオニア・ボイジャー探査機に取り付けられた銘板を見た異星人が地球を訪問する可能性もゼロではない。逆に、人類の発したメッセージとは無関係に異星人が地球を発見する可能性もありえる。
人類と異星人の遭遇のあり方についてはあらゆるケースを考えた方がいいし、SF作家にとってはテーマとしては使い古されていても、あらゆる書き方が可能である。著者がその一つとして描いたのが本書だ。
異星人の文明が地球よりも相当進化している場合、そもそも遭遇の実際は、人類が想像することすら難しいかもしれない。著者のようなSF作家が知恵を絞っても思い付かないような。
では仮に、私たちの思いもよらない方法で遭遇が実現したとする。
その時、人類は国や民族、宗教の違いによって殺し合うよう段階から、一つ成長できるのではないかと思っている。
異星人は思考回路や思考パターンも人類と違うだろう。そもそも知的水準すら今の人類を凌駕しているとすれば、人類は彼らの思考パターンの片鱗さえも読み取れないはずだ。その時、異星人の容姿や思考回路の違いなど、人類が悩む暇などないはずだ。マスコミが面白おかしく取り上げるとしても。
容姿や思考パターンの違いなど、本書で書かれたようにほとんどの人は触れずに終わってしまうだろう。
ただ、遭遇して初めて人類は知るだろう。それぞれの個人が持つ考え方の違いなど、異星人と人類の違いに比べたら、比較にならないことを。
自分たちが仕事や宗教や文化、価値観の違いに悩んでいることなどちっぽけであることを。それを争いのタネとすることの愚かさを。
そこから人類はどのような道を選んでいくのだろうか。
そもそも今の人類のあり方は、生命として能率的な形なのだろうか。今の生命体としてのあり方は絶対の普遍なのだろうか。
もし、生命のあり方から変えた方がよりよい未来が望めるのなら、どのような生命へと変わっていくのか最適なのか。
なぜそう思うのか。それは、本書に出てくる異星人が、生物としてのあり方を根本から変革しているからだ。
われわれの存在と違う形で発展した異星人の姿が描かれた本書は、今の人類のあり方に問いを投げかける。
今の人類は、それぞれの個体がそれぞれの思惑や欲求をばらばらに抱えている。だから、生まれた民族や文化や宗教や土地に縛られた思考しか巡らせられない。
そのあり方のままで果たして、種族としての進化は可能なのだろうか。
そうした思索からは、根源的な疑問すら湧き上がる。私たちの存在のあり方が理想の形なのだろうかという。
全ての思考の型が今までに人類の発展する中で設けられた枠から抜けられないとすれば、人類が次の段階に進むことは到底無理だろう。
もし人類が次の段階に進みたいのであれば、私たちは徹底的に自らを客観的に考える訓練をしなければならない。自己の思考の道筋を客観的に考え、その思考の道筋を自分の主観から自由にする。それはまさに哲学が今まで苦闘してきた道そのものだ。
SFとはサイエンス・フィクションの略であることは誰でも知っている。だが、フィクションだからといって、その内容を自己の思索の材料にしないのはもったいない。たとえ壮大な時間軸であっても。
‘2020/05/22-2020/05/23