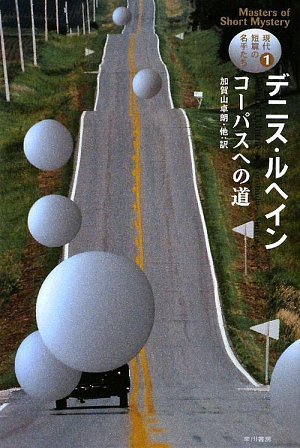著者の作風に変化を感じたのは「夢幻花」だったと思う。その変化についてはレビューにも書いた。私が感じた変化をまとめると、謎や解決のプロセスを本筋できちっと書き込み、なおかつ、それとは並行する別の筋に作者の想いや主張を込める離れ業を見せるようになったことだ。作風の変化というより作家として新たなレベルへ進化したというべきか。
「夢幻花」はシリーズものではなく単発作品だった。普通は安定のシリーズものではなく単発作品で実験的な手法を試すのが常道だと思う。
だが、著者はガリレオシリーズの一冊である本書で新たな手法を試す。今までガリレオの活躍を読まれてきた方にはお分かりだが、ガリレオシリーズは新しい科学的知見がトリックに惜しみ無く投入される。ガリレオこと湯川学が物理学者としての知見で謎を解くのがお決まりの構成だ。決して理論だけに凝り固まらず、謎や犯人との対峙の中で、ガリレオの人としての温かみが垣間見える。そんなところがガリレオシリーズの魅力である。
本書でもガリレオの前に科学的な装置を駆使した犯罪が立ちふさがる。その装置を使って一線を越えようとする人物の素性も序盤で読者に明かされる。それはガリレオのかつてのまな弟子。師は果たして不肖の弟子の暴走を止められるのか。それがあらすじだ。
もちろん著者は本筋をおろそかにしない。読者は、著者が安定のレベルで紡ぎだす謎解きの醍醐味を味わうことになる。いまや熟練の推理作家である著者にとって、謎の提示と解決までの筋書きを用意するのはさほど難しくないのだろう。
著者が用意した本書の裏の筋は、ここでは書かない。本筋にも関係のあることだからだ。表の謎が解かれた後に明かされる裏の事情。それは正直にいうと「夢幻花」で受けたインパクトよりも弱い。
でも、それはガリレオというキャラクターを語る上では欠かせないピースである。それをあえて本筋の後に持ってきたことにより、著者の新たな挑戦のあとがみえるのである。
あえて難癖をつけるとすれば、犯人の意図を挫くためにガリレオがとった行動にある。うーむ、さすがにそれは間抜けすぎでは、と思った。
‘2016/08/20-2016/08/20